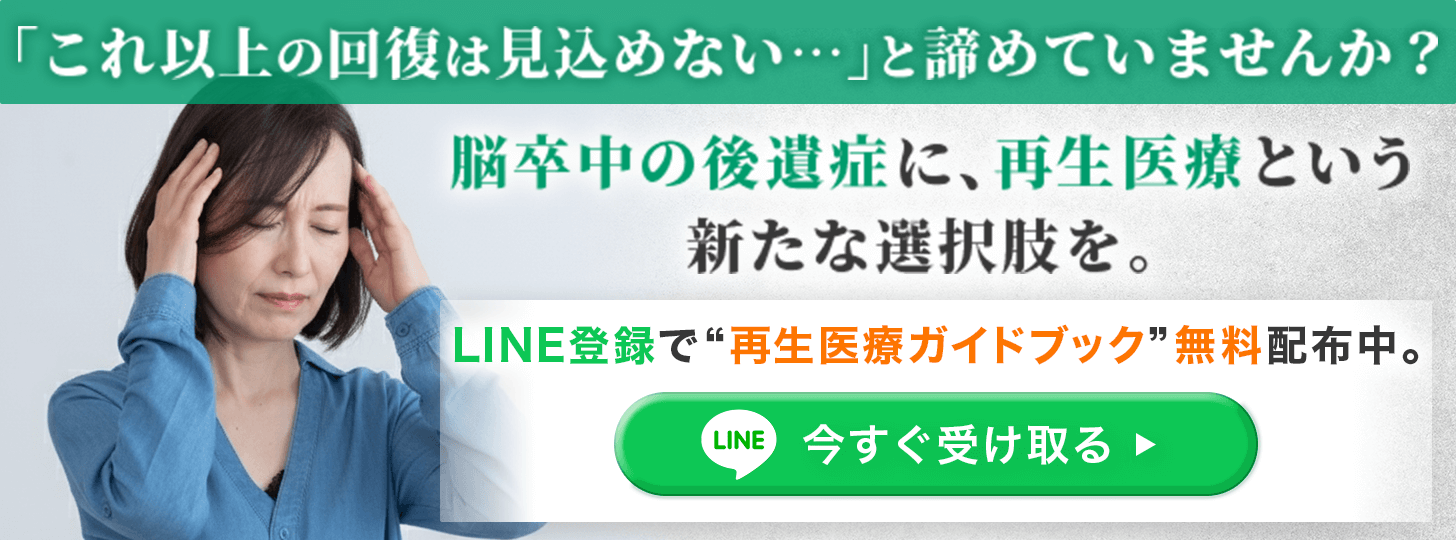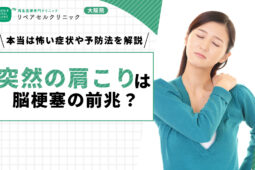- 脳卒中
- 再生治療
体幹失調とは?後遺症によるふらつきを改善するためのアプローチ方法も紹介

歩行中にふらつきを感じたり、立っているだけで体が揺れたりといった体幹失調による不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
体幹失調とは、姿勢や歩行のバランスをコントロールする力がうまく働かず、日常生活の動作が不安定になる状態を指します。
この記事では、体幹失調の概要や原因、リハビリなどについて解説します。
また、近年では体幹失調の主な原因とされる脳梗塞や脳出血の後遺症の改善が期待できる再生医療も注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を向上させて、損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、脳梗塞や脳出血の後遺症に対する再生医療の治療法や症例を公開しています。
歩行や姿勢のふらつきを改善したい方や、従来のリハビリだけでは効果が不十分と感じている方はぜひ参考にしてください。
目次
体幹失調とは|体幹のバランスが崩れ、姿勢の安定が難しくなる状態
体幹失調とは、胴体のバランスを保つ機能が低下し姿勢や歩行が不安定になる状態です。
運動失調の一種で、歩行や座位保持が不安定になるのが特徴です。
体幹失調の歩き方には、次のような傾向が見られます。
- 左右に揺れながら歩く
- まっすぐ歩けない
- 足を左右に開いて歩く
- 足を大きく持ち上げ、踏み出しが大きくなる
- 目を閉じて歩くと症状が悪化する
体幹失調は、バランスを調整する小脳や脳幹・耳の奥でバランスを感じ取る前庭・背骨の中を通る脊髄などの異常によって起こります。
そのため、主な原因は脳から筋肉への指令がうまく伝わらないことであり、単なる筋力低下や麻痺とは異なる場合があります。※
※出典:JSTAGE「運動失調を呈した脳卒中患者の小脳または脳幹障害による身体機能・動作能力の相違」
筋力はあるのに座れない・歩けない際は、体幹失調を疑ってみましょう。
体幹失調の主な原因
体幹失調の主な原因は、以下の通りです。
体幹失調は、小脳・脳幹・脊髄・前庭など体のバランスを司る複数の部位が関わるため、原因を見極めるには医師の診察が必要です。
症状に不安がある場合は専門医による診察を受け、必要に応じてリハビリを取り入れましょう。
脳の障害(小脳疾患・脳梗塞・脳出血など)
体幹失調の原因の一つに、脳の障害が挙げられます。
主な例は、以下の通りです。
- 脳梗塞や脳出血などの脳血管障害
- 小脳の病気(小脳梗塞・小脳出血など)
- 前庭脳幹の障害
小脳は、手足や体幹の微細な動作を調整する役割を持ち、小脳失調は体幹失調の代表的なタイプです。
脳梗塞や脳出血の後遺症としても現れることがあり、麻痺が軽くても体幹のバランスが崩れる場合があります。
また、前庭(耳の奥でバランスを感じ取る場所)や脳幹も、体幹の安定に関わる重要な部位です。
脊髄の障害
脊髄の障害も、体幹失調の原因の一つです。
脊髄は背骨の中を通る神経の束で、脳と体をつなぐ役割があります。
異常が起こると体を動かす指令や感覚の情報が正しく伝わらず、体のバランスが崩れる場合があります。
主な原因は、以下の通りです。
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 脊髄損傷など
脊髄小脳変性症や多系統萎縮症は進行に伴って体幹失調が徐々に現れ、日常生活動作に支障をきたすことがあります。
外傷や圧迫によって脊髄が損傷されると、感覚と運動の情報伝達が乱れ、バランスを取るのが難しくなることがあります。
脊髄の障害では、筋力がある場合でも座る・立つ・歩くといった動作が不安定になりやすいため、日常生活での転倒やふらつきに注意が必要です。
症状が気になる場合は、早めに専門医や理学療法士に相談し、適切なリハビリやサポートを検討しましょう。
その他の原因
体幹失調は、神経の障害だけでなく筋力や生活習慣などの要因でも起こることがあります。
主な要因は、以下の通りです。
- 筋力低下
- 運動不足
- 不良姿勢
- ウイルス性脳炎
- アルコール性小脳障害
- ビタミン不足など
神経以外の要因でも体幹のバランスが崩れることがあるため、原因が一つとは限らない点に注意しましょう。
体幹失調の改善に役立つリハビリ・トレーニング方法
体幹失調の改善に役立つリハビリ・トレーニング方法は、以下の通りです。
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
フレンケル運動
フレンケル運動は、小脳性失調(小脳出血や脊髄小脳変性症など)のリハビリに用いられる運動療法です。
動作をゆっくり丁寧に繰り返すと手足の位置や動きを感じる感覚が強化され、歩行や日常動作のふらつき軽減に役立ちます。
身体を動かしながら自分の手足の動きを目で確認して、身体のバランスを整えましょう。
具体的な運動の例は、以下の通りです。
- 仰向けになって、かかとを床につけたまま片方の膝を滑らせるようにゆっくり曲げ伸ばしする
- 両膝をそろえて椅子に座り、立ち上がってから再び座る
- 立ったまま体重を左右の足に交互にかける
体操の際は無理のない範囲で動かし、転倒に注意しましょう。
運動学習
運動学習とは、練習を繰り返すことで体の動かし方が上達していく仕組みです。
日常生活での運動学習の一例として、自転車の乗り方や箸の使い方を練習して身につける過程が挙げられます。
運動学習は以下の段階で進行します。
- 認知段階:どんな動きをするのか理解する段階で、ぎこちない動きが多い
- 連合段階:動きの練習を重ねて徐々に動きの正確さや安定性が向上する
- 自動化段階:日常生活の中で無意識にスムーズに動けるようになる
リハビリでは、同じ動作を繰り返したり、鏡や動画で自分の動きを確認したり、専門家からアドバイスを受けたりすると正しい動作を習得しやすくなります。
弾性緊縛帯
弾性緊縛帯とは、ゴムのように伸び縮みする素材でできた包帯で、患部を適度に圧迫しながら優しく支える医療用補助具です。
腰や股関節、膝など体の中心に近い部分に巻いて体幹や関節の動きを安定させ、座位や歩行時のふらつきを抑える効果が見込めます。
リハビリの際に弾性緊縛帯を使用すると、ふらつきを心配せずに体を動かしながら正しい動きを覚えるのに役立ちます。
重り荷運動
小脳性の運動失調に対して、重り荷運動は体幹失調や腕の動きの乱れに有効であると示唆されています。※
※出典:J-STAGE「小脳性運動失調患者に対する上肢への重錘負荷が重心動揺に与える影響」
重り荷運動は、腕や足に軽い重りを装着して行うリハビリ方法です。
手首や足首に軽い重りをつけると、関節や筋肉がどのくらい動いているか・どちらの方向に力が入っているかといった感覚(固有感覚)がわかりやすくなります。
固有感覚が強まると手足の動きを自分で調整しやすくなり、正しい動き方の習得につながります。
最初は軽い重りから始め、個人の症状に応じて徐々に重さを上げていくのが一般的です。
自己判断で行うとケガのリスクがあるため、必ず医師や理学療法士など専門家の指導を受けましょう。
体幹失調改善にはリハビリが重要!改善が見られない場合は再生医療も選択肢の一つ
体幹失調を改善するには、原因を正しく把握し継続的なリハビリを行うのが重要です。
リハビリでは、体幹のバランスや協調性を高める運動学習やフレンケル運動などが取り入れられます。
従来のリハビリだけでは十分な改善が得られない方や、脳梗塞や脳出血など脳の障害における後遺症にお悩みの方は、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療は、患者さまから幹細胞を採取・培養して注射や点滴にて患部に届ける治療法で、以下の特徴があります。
- 損傷した神経や細胞、血管などの根本的な改善を目指せる
- 手術や入院せずに、早期復帰が目指せる
- 自身の細胞を利用するため体への負担が少ない
体幹失調の治療や回復方法について前向きに情報を探している方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長