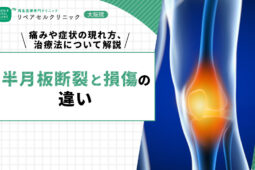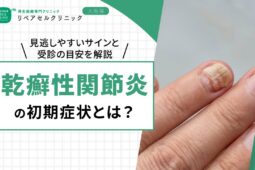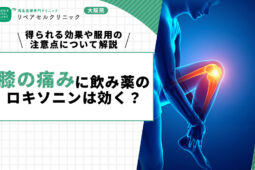- 変形性膝関節症
- 靭帯損傷
- 半月板損傷
- 膝部、その他疾患
- ひざ関節
膝の水を抜いた後の注意点|処置後のリスクや水がたまる原因について解説
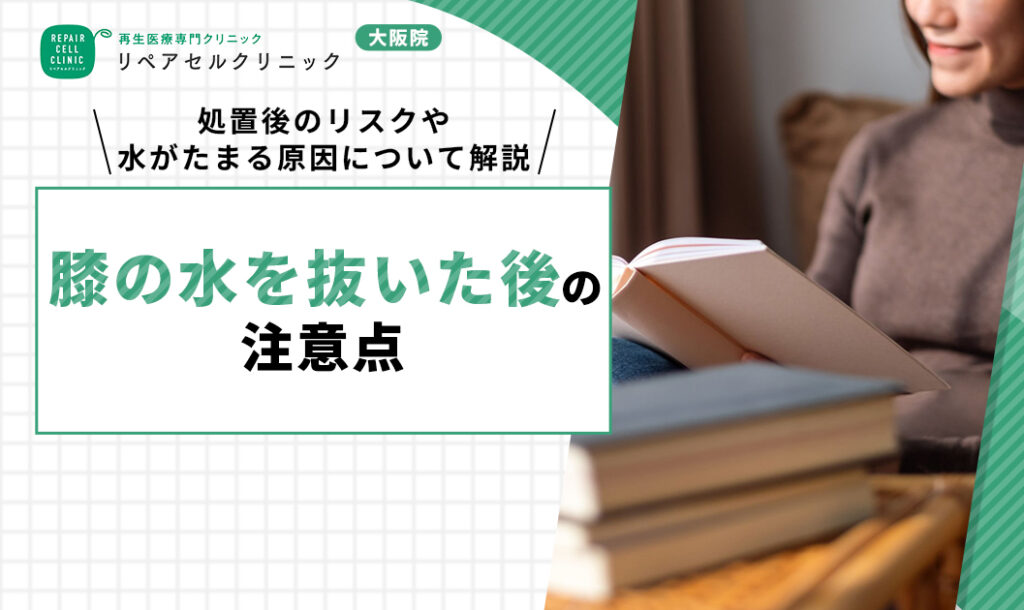
「膝の水を抜いた後に注意すべきことは?」
「水を抜くと癖になるのでは?」
膝に水がたまってしまい、処置を検討している方の中には、上記のような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実際、処置後の過ごし方やケアを誤ると、炎症が再燃したり、稀に感染症を引き起こしたりする可能性もゼロではありません。
本記事では、膝の水を抜いた後に守るべき正しい注意点、考えられるリスクについて詳しく解説します。
膝にたまった水にお悩みの方は、症状改善のためにもぜひ本記事を参考にしてください。
また、膝に水がたまる根本原因を治療したい方は、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
「繰り返す膝の腫れや痛みを早く治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。
目次
膝の水を抜いた後の注意点
膝の水を抜いた後は、処置当日の過ごし方と再発防止のための根本治療という2つの側面で注意すべき点があります。
処置後に守るべき主な注意点は、以下のとおりです。
関節穿刺によって膝にたまった水を抜くことはできますが、水がたまる原因が解決したわけではありません。
以下では、それぞれの注意点について詳しく解説します。
処置直後は患部を安静にする
膝の水を抜く処置は、関節に針を刺して行うため、処置直後は注射した膝をできるだけ安静に保つことが優先されます。
処置直後に歩き回ったり、膝に負担をかけたりすると、関節内が刺激され、再び炎症が起きる可能性があります。
また、注射の針穴からの出血や感染のリスクもゼロではありません。
基本的に処置後24〜48時間の安静が推奨されますが、医師の指示に従い、帰宅後は無理をせず安静に過ごしましょう。
激しい運動や入浴は避ける
処置当日は、激しい運動や長時間の入浴(湯船につかること)は控えてください。
ランニングやスポーツ、重いものを持つ作業などは、膝関節に強い負担をかけ、再び炎症が起きる原因となります。
また、湯船につかる入浴は、血行が良くなることで炎症を悪化させたり、注射の針穴から細菌が侵入したりするリスクを高めます。
処置当日はシャワーで軽く済ませるなど、医師の指示に従って生活することが重要です。
膝に水がたまる原因を治す必要がある
膝の水は、抜いたら終わりではなく、「水がたまる根本原因の治療」を受けることが重要です。
膝に水がたまるのは、変形性膝関節症や半月板損傷などによって関節内に炎症が起きている「結果」に過ぎません。
水を抜くのは一時的に症状を和らげる対症療法のため、水がたまる原因が治ったわけではないことを理解しておきましょう。
また、「水を抜くと癖になる」と言われることがありますが、癖になるのではなく、根本原因の炎症が治まっていないために繰り返し水がたまってしまうのです。
ヒアルロン酸注射やリハビリ、生活習慣の見直しなど、医師と相談しながら根本原因の治療に取り組みましょう。
膝の水を抜いた後に考えられるリスク
膝の水を抜く処置(関節穿刺)は、医療機関で一般的に行われる安全性の高い手技ですが、針を刺す以上、リスクが全くゼロというわけではありません。
処置後に考えられる主なリスクとして、以下の点が挙げられます。
これらのリスクは頻繁に起こるものではありませんが、万が一の事態に備えて理解しておきましょう。
感染症のリスク
処置(関節穿刺)に伴うリスクの中でも、とくに注意すべきなのは細菌による感染症です。
頻度は非常に稀ですが、注射針を刺す際、皮膚の細菌が関節内に入り込むことで「化膿性関節炎」を引き起こす可能性があります。
医療機関では皮膚を厳重に消毒して行いますが、処置後に針穴を不潔にしたり、医師の指示(入浴禁止など)を守らなかったりするとリスクが高まる可能性があります。
処置後に、通常とは異なる激しい痛み、熱感、赤み、または発熱が見られた場合は、早期に医療機関を受診してください。
出血のリスク
膝の水を抜く際に針を刺すため、皮膚の下や関節内部で軽度の出血(内出血)が起こる可能性があります。
通常は数日で自然に吸収されますが、処置後に膝が異常に腫れあがったり、痛みが続いたりする場合は注意が必要です。
とくに、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬や抗血小板薬)を服用している方は、出血のリスクが通常より高まります。
抗凝固薬や抗血小板薬を服用中の方は、処置を受ける前に必ず医師に申告してください。
アレルギー反応のリスク
処置に使用する薬剤に対してアレルギー反応が起きる可能性もゼロではありません。
具体的には、皮膚の消毒薬(ヨードなど)や、処置の痛みを和らげるための局所麻酔薬が原因となることがあります。
また、水を抜いた後に関節の炎症を抑えるためにステロイド剤やヒアルロン酸を注入した場合、それらの薬剤が体質に合わないことも考えられます。
過去に薬剤アレルギーの経験がある方は、必ず事前に医師に伝えてください。
神経や靭帯損傷のリスク
関節穿刺の際に、注射針が周囲の神経や血管、靭帯などを傷つけてしまうリスクも考えられます。
これは非常に稀なケースであり、医師は解剖学的な知識に基づいて安全な部位を選んで針を刺します。
しかし、万が一、処置後に膝や足先にしびれが残る、力が入らない、激しい痛みが続くといった異常を感じた場合は、すぐに医師に相談することが重要です。
膝に水がたまる原因として考えられる疾患
膝に水がたまるのは、膝関節の内部で何らかの異常が起き、炎症が発生しているサインです。
水を抜く処置は一時的に症状を楽にしますが、炎症の原因となる疾患を解決しない限り、水は再びたまってしまいます。
膝に水がたまる原因として考えられる疾患や症状について解説します。
以下では、それぞれの疾患や症状について詳しく解説します。
変形性膝関節症
膝に水がたまる原因疾患として主に考えられるのは、変形性膝関節症です。
加齢や体重の増加、筋力の低下、過去の怪我などが要因となり、膝関節のクッションである軟骨がすり減ってしまう疾患です。
軟骨がすり減ると、その破片が関節を包む滑膜を刺激し、炎症を引き起こします。
この炎症反応の結果として、関節液が過剰に分泌され、膝に水がたまって腫れや痛みが生じます。
とくに中高年の方で、明らかな怪我のきっかけがないにもかかわらず膝が腫れる場合、この疾患が強く疑われます。
半月板や靭帯の損傷
スポーツや事故、転倒などによる外傷で半月板や靭帯など膝の組織を痛めることも、水がたまる大きな原因となります。
代表的なものとして、膝のクッションの役割を果たす「半月板」の損傷や、関節を安定させる「靭帯(前十字靭帯など)」の損傷が挙げられます。
これらの組織が損傷すると、関節内部に強い炎症が起こり、関節が不安定になります。
その結果、滑膜が刺激されて急激に関節液が分泌されることで膝に水がたまり、膝が腫れ上がります。
変形性膝関節症とは異なり、若い世代でもスポーツ活動中などに発生することが多いのが特徴です。
その他に考えられる疾患
変形性膝関節症や半月板などの損傷以外にも、さまざまな疾患が膝の炎症と水腫(水がたまること)を引き起こす可能性があります。
代表的なものには、以下のような疾患があります。
| 疾患名 | 概要 |
|---|---|
| 関節リウマチ | 免疫の異常により、自身の関節を攻撃して炎症を起こす自己免疫疾患の一つ |
| 痛風・偽痛風 | 尿酸やピロリン酸カルシウムといった結晶が関節内にたまり、激しい炎症(発作)を引き起こす |
| 感染症(化膿性関節炎) | 細菌が関節内に侵入して炎症を起こすもので、緊急の治療が必要 |
これらの疾患は原因が全く異なるため、治療法も変わってきます。
水がたまる原因を正確に突き止めるためにも、医療機関による適切な診断が不可欠です。
膝の水を抜いた後の注意点についてよくある質問
膝の水を抜いた後の安静期間や同時に行われることの多いヒアルロン酸注射の効果について、疑問を持つ方は少なくありません。
本章では、膝の水を抜いた後の注意点についてよくある質問を紹介します。
以下では、それぞれの質問に対して詳しく回答していきます。
膝の水を抜いた後の安静期間はどのくらい?
膝の水を抜いた後の安静期間は、一般的に処置直後から24〜48時間の安静が推奨されます。
関節穿刺(水を抜く処置)は関節に針を刺すため、処置直後に激しい運動をしたり、湯船につかって体を温めすぎたりすることは避けましょう。
これらは炎症を再燃させたり、針穴から細菌が感染したりするリスクを高める可能性があります。
医師から特別な指示がない限り、処置当日はシャワー程度で済ませ、長距離の歩行やスポーツは控えましょう。
翌日以降の活動については、膝の状態や膝に水がたまる原因によって異なるため、必ず医師の指示に従ってください。
膝の水を抜いた後にヒアルロン酸を注射するとどうなる?
ヒアルロン酸を注射することで、関節内の炎症抑制や膝の動きを滑らかにする効果が期待できます。
膝にたまる炎症性の水を抜いた後に、正常な関節液に近い性質を持つヒアルロン酸を注入することは、標準的な治療法の一つです。
ヒアルロン酸には、関節の「潤滑油」としての役割を果たし、動きをスムーズにする効果があります。
関節の潤滑性を高めることで軟骨への負担を和らげ、炎症を抑える働きも期待できます。
膝に水がたまる原因を治療したい方は再生医療をご検討ください
本記事では、膝の水を抜いた後の注意点や、水がたまる原因について解説しました。
重要なのは、水を抜く処置(関節穿刺)は、あくまで腫れや痛みを和らげる一時的な対症療法であるということです。
膝にたまった水を抜いただけでは、水がたまる原因となっている疾患や症状が解決したわけではありません。
そのため、膝に水がたまるのを繰り返さないためには、根本原因の治療が不可欠です。
膝に水がたまる根本原因の治療を目指す場合、「再生医療」をご検討ください。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
繰り返す膝の腫れや痛みにお悩みで、根本的な治療を検討したい方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。
>当院の再生医療による膝関節の症例はこちら

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設