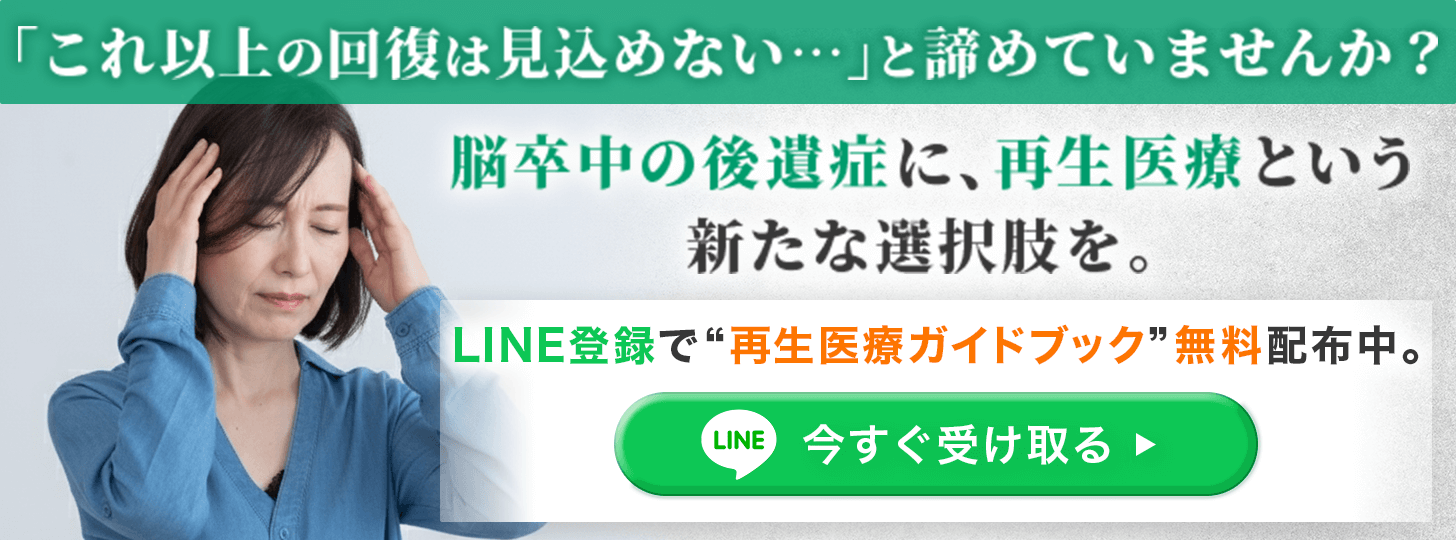- 脳卒中
- 再生治療
脳出血の予後はどこまで回復できる?後遺症と改善の可能性を紹介
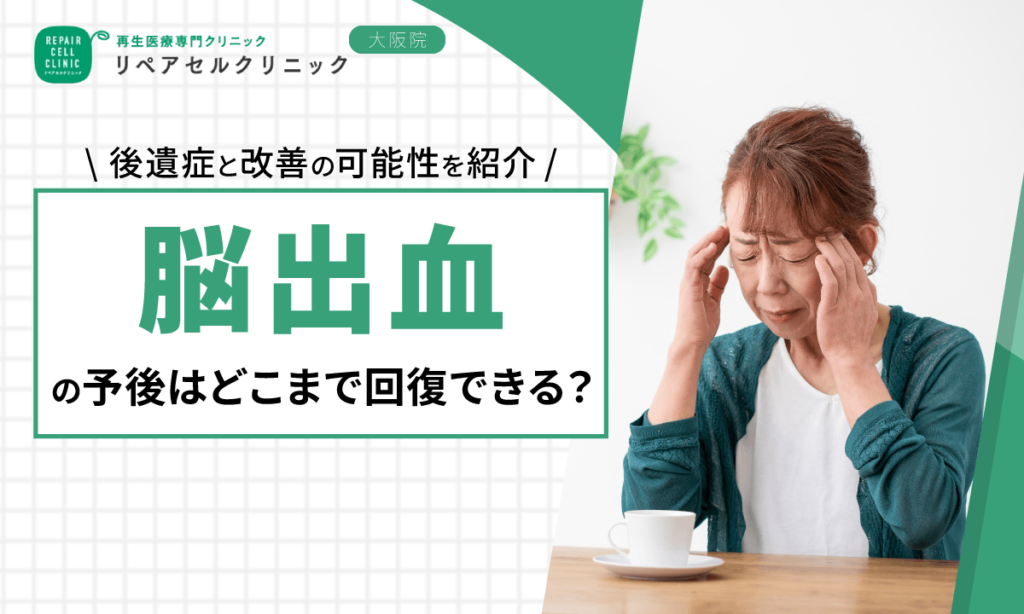
「脳出血」は突然発症し、多くの後遺症を引き起こす病気です。
命が助かったとしても出血による脳の損傷で、四肢麻痺や運動障害などの後遺症が発症する可能性があります。
それにより日常生活に支障をきたし、「今後の生活はどうなるんだろう」「脳出血の予後はどこまで回復できる?」と不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
インターネットでは脳出血の後遺症は治らないとの情報も多くみられますが、実は変えられる部分も多く存在します。
そこでこの記事では、脳出血の予後や対処方法、再生医療の可能性について解説します。
目次
脳出血の「予後」とは?
脳出血の「予後(よご)」とは、脳出血が発症した後の回復の見込みや後遺症の程度、生活への影響のことを指します。
予後を正確に予測することは、具体的な治療計画を立てるうえで必要不可欠です。
また、患者や家族としても今後の生活や人生計画を立てていくうえで正確な予後の予測が重要になります。
脳出血の予後(回復の見通し)を左右する要因
日本脳卒中学会※によると、脳出血の予後は以下に挙げる要因によって左右されます。
| 予後を左右する要因 | 理由 |
|---|---|
| 出血量と部位 |
・出血量が多いほど脳が圧迫され、脳浮腫や脳ヘルニア(脳が押し出される状態)を起こしやすく、死亡率が高まる ・出血部位によって障害される脳機能が異なるため、生命予後や後遺症の重さも変わる |
| 年齢 |
・高齢者は脳血管の弾力が低下し、出血による損傷が広がりやすいほか、自己修復力・神経可塑性(回復力)が低下する ・高血圧や糖尿病などの基礎疾患の有無も予後不良に直結する。 |
| 意識レベル(GCSスコア) |
・意識レベルが低いほど脳全体への圧迫や脳幹障害が強く、致命的なダメージを受けていることを意味する ・スコアが低いと予後が悪い可能性が高まる。 |
| 脳室穿破(のうしつせんぱ)の有無 |
・脳室穿破(のうしつせんぱ)は脳室に血液が流れ込む状態 ・脳室穿破は水頭症や脳圧上昇・意識障害が悪化の要因となりうる |
| 治療・リハビリ開始までの時間 |
発症24~48時間以内にリハビリを開始することで、廃用症候群(筋力低下や拘縮)を防ぎ、日常生活動作の改善率が上昇する 治療・リハビリの遅れは、回復機会の損失につながりやすい |
脳出血はこのような要因で予後が左右されるため、迅速な対応が必要です。
脳出血が疑われる場合には迷わず119番で救急車を要請するか、迷った場合には7119番に連絡して専門家の助言を受けましょう。
※参考文献:脳卒中ガイドライン2021[改訂2025]
予後の流れ
脳出血の予後は、大きく分けて以下の3段階で経過します。
- 発症直後(急性期):命の危険と合併症リスク
- 1~3か月:リハビリで回復が進む時期
- 6か月以降:回復の“壁”が見え始める
脳出血が発症した直後は、命の危険が高い時期です。
とくに、脳浮腫や再出血を予防しつつ、水頭症や肺炎・深部静脈血栓症などの合併症に注意しなければいけません。
命の危険を脱した後は、リハビリを進め身体機能の回復を図りますが、発症から3ヶ月が重要です。
過去の研究※から発症から3ヶ月は神経機能の回復が盛んなことがわかっていて、この時期のリハビリは機能を回復するうえで不可欠といえます。
しかし、6ヶ月を過ぎると徐々に神経の回復が止まってしまい、機能回復の壁を感じる方も多い傾向にあります。
脳出血後に起こりやすい後遺症と回復の目安
ここからは、脳出血後に起こりやすい後遺症と回復の目安について、以下の3項目を解説します。
これらは脳出血の予後を考えるうえで重要な知識です。
脳出血でお悩みの方は、ぜひ最後までチェックしてください。
主な後遺症の種類と頻度
脳出血でみられる主な後遺症は以下のとおりです。
| 主な後遺症の種類と頻度 | |
|---|---|
| 片麻痺(運動麻痺) | 約70〜80%の患者で、体の片側(右または左)の手足が動かしにくくなる。 |
| 構音障害・失語症 | うまく発音できない、言葉が出てこない・理解しづらいといった症状が約30〜40%に出現。 |
| 嚥下障害(飲み込みづらさ) | 食べ物や水が飲み込みにくい、むせる、誤嚥性肺炎を起こしやすいといった症状が約40〜50%で一時的または持続的に出現。 |
| 認知障害・感情変化 | 記憶力・注意力低下、感情の起伏が激しくなるといった症状が約30〜50%に出現。 |
これらの後遺症はすべての脳出血患者に発症するわけではありませんが、脳出血後遺症として問題になりやすい症状です。
しかしリハビリで改善する可能性もあるため、専門家による早期治療が重要となります。
リハビリで回復する機能・しにくい機能
リハビリで回復する機能と回復しにくい機能は、以下の表のように分類されます。
| 回復しやすい機能 | 運動障害 | 少しでも神経回路が生き残っていれば、リハビリによって再生しやすい。 |
| 感覚障害 | 神経の再生による回復は時間がかかるが、視覚や運動感覚による代償が効きやすい | |
| 回復しにくい機能 | 高次脳機能障害 | 高次脳機能障害を引き起こす部位は神経の回復が難しいため、回復しにくい |
| 言語障害 |
言語機能は脳の左半球に多く依存しているため、左半球を損傷すると代償が効きにくい |
このように、運動障害や感覚障害は神経が回復したり他の機能により代償が効いたりするために、回復しやすいといえます。
逆に高次脳機能障害や言語障害は神経が回復しにくいうえに代償が効きにくいため、回復しにくい機能です。
回復を左右する「神経可塑性」とは
神経可塑性とは、脳神経が損傷した後に構造や機能を再編成する能力です。
言い換えれば、壊れた神経回路を別の経路で補う「脳の柔軟性」ともいえます。
具体的には、損傷した部位の周囲や反対側の脳が機能を補う能力です。
この神経可塑性があることで、脳出血後遺症は回復していきます。
予後を良くするために重要なポイント
脳出血後の予後を良くするために重要なポイントは、以下の3点です。
- 迅速な治療開始
- 集中的で質の高いリハビリ
- 家族・社会的なサポート
脳出血は、「時間との戦い」です。
迅速に治療を開始することで脳のダメージを軽減でき、後遺症の重症度軽減が期待できます。
また、「ゴールデンタイム」と呼ばれる脳出血発症後数ヶ月で集中的なリハビリを行えば、前述した神経の可塑性も最大限に高められるでしょう。
一方で、脳出血では家族や社会的なサポートも欠かせません。
脳出血は身体機能だけでなく、認知機能や感情・社会的な能力も損なわれる可能性があるためです。
とくにうつ・意欲低下・社会的孤立は、回復意欲を損ない、再発や寝たきりリスクを高めます。
そのため、家族や社会的なサポートが再発予防・生活の質(QOL)向上のために不可欠といえるでしょう。
このような迅速で質の高い身体的な治療や家族・社会的なサポートは、脳出血の予後を良くするために重要です。
リハビリで限界を感じた方向けの再生医療という新たな選択肢
脳出血は発症後、6ヶ月後までは機能の回復が得られる可能性があります。
しかし、6ヶ月を経過して以降はあまり機能の回復が望めないため、装具を使用するなどの代替手段が検討されてきました。
しかし、近年では再生医療が発達してきたことにより、6ヶ月経過した後でも神経の回復が期待できる可能性があります。
実際に当院リペアセルクリニック大阪院でも、脳出血後遺症に対して再生医療が功を奏したケースを経験してきました。
脳出血以外の脳梗塞などの後遺症にも効果が期待できる可能性はありますので、興味がある方はぜひ以下のリンクをご参照ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳出血の予後を良くするためには、早期のリハビリと専門医への相談が重要
脳出血の予後にみられる後遺症や、予後を良くするためのポイントを解説しました。
ポイントは以下のとおりです。
- 脳出血後迅速な治療が予後の重症度に関わる
- 早期のリハビリによって後遺症が改善する可能性がある
- リハビリの限界がきても再生医療なら改善する可能性がある
脳出血は迅速な治療が重要です。
神経が回復できる期間も決まっているため、早期のリハビリ介入も大切といわれています。
そのため、脳出血が疑われる場合には速やかに専門医に相談し、可能な限り早くリハビリを開始しましょう。
なお、リハビリの効果を感じない時期に差し掛かった場合でも、再生医療であれば神経機能が回復する可能性があります。
当院でも多数の症例を経験しているため、興味がある方はお気軽にご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長