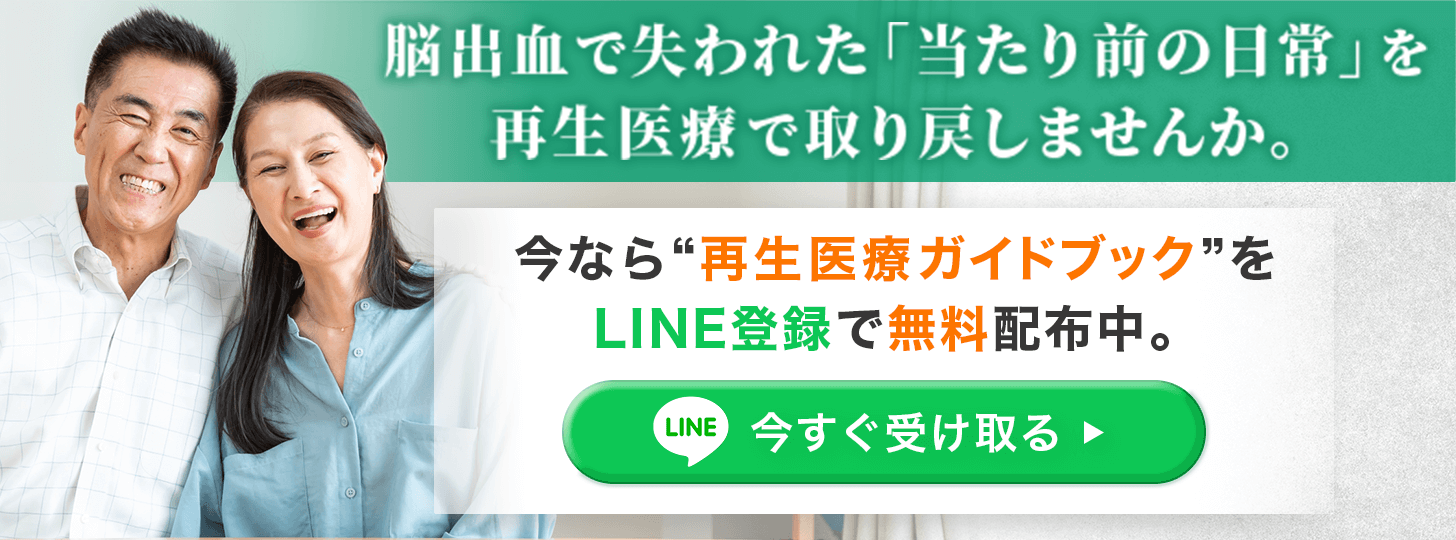- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
- 再生治療
脳幹出血に回復見込みはある?早期にリハビリを行う重要性を再生医療専門医が解説
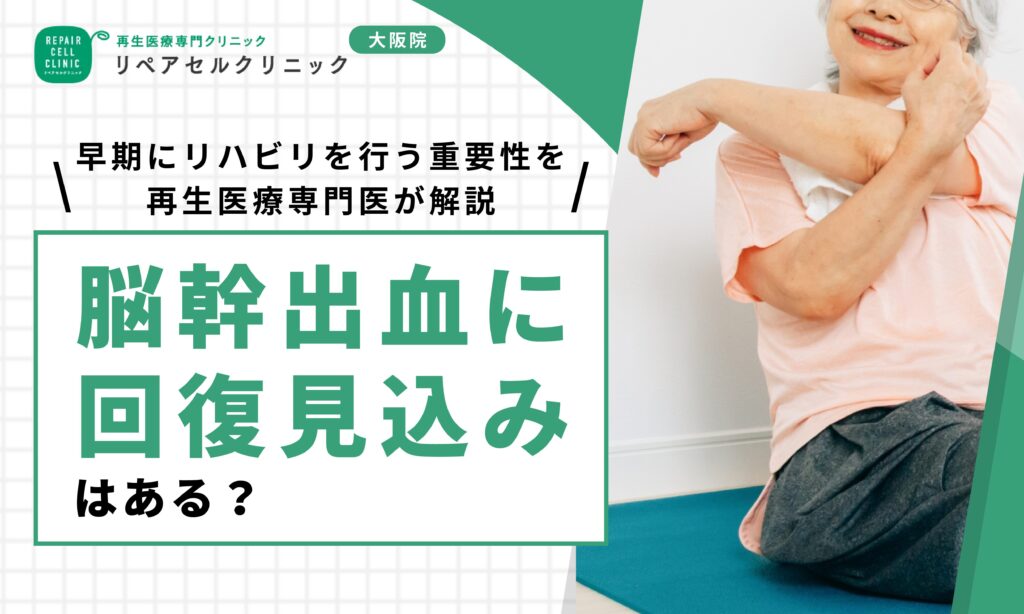
脳の中でも生命維持に関わる重要な部位である脳幹での出血は特に深刻とされています。
脳幹出血を経験した患者さまやご家族は、回復の見込みはあるのか?不安を抱えていることでしょう。
この記事では、脳幹出血の回復見込みについて複数の医学論文のデータも合わせて解説します。
脳幹出血は重篤な疾患ですが、適切な治療と早期からのリハビリによって機能回復の可能性を高められることがわかります。
目次
脳幹出血に回復の見込みはあるのか【論文データについても解説】
脳幹出血に回復見込みはどの程度あるのでしょうか?
ここでは複数の医学論文のデータも合わせて脳幹出血後の回復率や死亡率、また回復に影響する要因について解説します。
意識状態や年齢といった要素が予後にどう関わるのか、また発症初期の状態から将来の機能回復をどの程度予測できるのかについても解説します。
脳幹出血から良好回復した方は約6.1%
脳幹出血患者を対象とした研究※では、発症から3ヶ月後の転帰として「良好な回復」が得られたのは全体の6.1%でした。
※出典:ScienceDirect
その他の転帰としては「中等度障害」12.7%、「重度障害」12.7%、「植物状態」10.8%、そして「死亡」が57.5%となっています。
ただし、脳幹出血の死亡率は研究によって幅があり、対象患者の状態や年齢層、医療体制などの違いが影響していると考えられます。
上記から脳幹出血は重篤性がありますが、良好な回復を遂げる可能性もあることがわかります。
患者の予後は61%が死亡例というデータも
国立病院機構災害医療センターによる脳幹出血患者を対象とした研究では、退院時の予後として死亡例が61%、生存例が39%※という結果が報告されています。
※出典: 脳幹出血患者の予後に関する臨床的検討
また、生存例の詳細は以下のようになっています。
- 良好な回復:3%
- 中等度障害:9%
- 重度障害:13%
- 植物状態:14%
この研究では年齢層による死亡率の差も分析されており、70歳以上の患者の死亡率は79%、70歳未満では57%と高齢なほど死亡率が高い傾向が見られましたが、統計学的な有意差は認められていません。
つまり、年齢と死亡率の間に明確な相関関係があるとは言えないものの、数値としては高齢者ほど予後不良となる可能性が高いことがわかります。
脳幹出血を発症した時の意識状態が予後に影響
脳幹出血患者の予後を左右する重要な因子として、発症時の意識状態が挙げられます。
国立病院機構災害医療センターの研究では、来院時の運動機能スコア(M1~M6)と予後の関係について詳細な分析※が行われました。
※出典: 脳幹出血患者の予後に関する臨床的検討
結果として、M1(全く動かない)の患者21例の死亡率は86%、M2(痛み刺激に対して除脳硬直)の患者25例の死亡率は76%と非常に高い割合でした。
脳幹出血発症時の意識レベルは患者の予後を予測する上で非常に重要な指標であり、特に重度の意識障害を伴う場合は、死亡リスクが著しく高まるということがわかります。
発症1か月時点で半年後の歩行能力が予測可能
脳幹出血患者の半年後の歩行能力は、発症1ヶ月時点での評価で高い精度で予測できる※ことが明らかになりました。
※出典: 脳幹出血患者の予後予測. 脳卒中の外科
17例の脳幹出血患者を観察した研究では、1ヶ月時点で以下の条件を満たす患者は半年後に歩行能力を獲得できる可能性が高いことが示されています。
特に、端座位保持能力と歩行機能の間には強い関連があり、1ヶ月以内に端座位を自力保持できた患者はほぼ全例が半年後に歩行可能となっています。
脳幹出血の改善には早期のリハビリが重要
脳幹出血は重篤な後遺症をもたらす可能性が高いため、機能回復に向けた計画的なリハビリテーションが重要です。
リハビリは以下の3段階に分けて進められます。
本章では、各時期のリハビリの特徴と重要なポイントについて詳しく解説します。
急性期のリハビリ
急性期(発症直後2週間〜1ヶ月程度)のリハビリテーションは、二次的合併症の予防と早期の機能回復に重点を置きます。
急性期は全身状態に注意した上で主に以下のリハビリを行います。
- 関節可動域訓練(関節が固まるのを防ぐ)
- ベッド上での寝返り訓練
- 座位訓練(上体を起こす練習)
- 嚥下(えんげ)訓練
- 車いすへの移乗訓練
- 立位・歩行訓練(状態に応じて)
- 言語機能の回復訓練
- ストレッチ運動
近年の研究では、早期からリハビリを開始した患者の方が、長期的な予後や後遺症の改善に良い効果が見られています。
回復期のリハビリ
回復期(3〜6ヶ月程度)のリハビリテーションでは、急性期で回復しなかった機能や後遺症の改善を目指します。
回復期には、主に以下のリハビリを行います。
- 生活に必要な基本動作訓練(立つ、座る、歩くなど)
- 日常生活動作(ADL)訓練(食事、着替え、トイレなど)
- 麻痺の改善訓練(促通訓練)
- 筋力増強訓練
- 痙縮(けいしゅく)対策(ストレッチや薬物療法)
- 高次脳機能訓練
- 嚥下・構音訓練
- 装具の使用訓練
この時期には一般的に回復期リハビリテーション病棟へ転院し、集中的なリハビリを行います。
維持期のリハビリ
維持期(発症6ヶ月以降)は「生活期」とも呼ばれ、回復した機能の維持と社会生活への復帰を目指す時期です。
この時期は在宅で生活しながら、以下のようなリハビリを継続します。
- 物理療法(病院で実施)
- 自宅でのストレッチや筋力訓練
- 散歩やラジオ体操などの日常運動
- 生活に必要な動作の確認と練習
- 装具の調整とメンテナンス
- デイケアや訪問リハビリの活用
- 社会参加を促す活動
- 再発予防のための生活習慣指導
継続的なリハビリと生活習慣の改善により、機能維持と再発予防を両立させることが重要です。
脳幹出血にはどのような後遺症がある?
脳幹出血には、主に以下の後遺症が出る場合があります。
| 後遺症の種類 | 主な症状 |
|---|---|
| 運動麻痺 | 手足が思うように動かせない |
| 感覚障害 | 触覚や痛覚の異常、しびれ |
| 嚥下障害 | 飲食物の飲み込みが困難 |
| 構音障害 | 発音がうまくできない、呂律が回らない |
| 眼球運動障害 | 物が二重に見える、まぶたが開かない |
| 自律神経障害 | 体温調節障害、発汗異常、血圧変動 |
| 運動失調 | ふらつき、体のバランスが取りにくい |
| 高次脳機能障害 | 記憶障害、注意障害、判断力低下 |
脳幹出血の後遺症は、適切なリハビリによって改善する可能性があります。
脳幹出血の再発防止・後遺症からの回復には「再生医療」が注目されている
脳幹出血の再発防止・後遺症に対して、再生医療という治療方法があります。
再生医療は、人間が持っている再生能力を活かした医療技術の一つです。
当院「リペアセルクリニック」では、自己脂肪由来の幹細胞治療を実施しています。
手術や入院を必要としない治療方法です。
再生医療の詳細については、無料のメール相談やオンラインカウンセリングからお問い合わせください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
脳幹出血の回復見込みに関してよくある質問
脳幹出血の回復見込みに関してよくある質問を紹介します。
出血の程度や部位、患者さまの年齢や既往歴によって回復の見込みや予後は異なるため、あくまで参考としてごらんください。
脳幹出血の回復率は?
脳幹出血の発症から3ヶ月後の回復率は以下の通りです。
- 良好な回復:6.1%(13名)
- 中等度障害:12.7%(27名)
- 重度障害:12.7%(27名)
- 植物状態:10.8%(23名)
- 死亡:57.5%(122名)
※出典:ScienceDirect
何らかの障害を抱えながら生存される方が約36%、亡くなる方が半数以上を占めるため回復率は低いといえるでしょう。
脳幹出血の余命はどのくらい?
脳幹出血を含む脳出血患者の余命は、約12年程度とされています。
その他、生存率に関する調査では以下のような結果が報告されています。
- 10年生存率は約24.1%
- 5年生存率は24%
- 1年生存率は38%、
- 若年層(50歳以下)は高齢者(70歳以上)よりも5年生存率が高い
特に意識障害が強い場合や出血量が多い場合は、発症後数時間から数日で急激に状態が悪化するケースもあり、注意が必要です。
脳幹出血を予防する方法は?
脳幹出血の主な原因は高血圧や動脈硬化であるため、予防は基本的に生活習慣の改善によって行います。
- 減塩する
- 大量飲酒・喫煙を控える
- 肥満を解消する
- ストレスを溜めない
- 定期的な健康診断を受ける
- 適切な血圧管理
これらの予防法を継続的に実践することで、脳幹出血のリスクを減らすことができます。
【まとめ】脳幹出血は程度によって回復の見込みもある!早期のリハビリテーションが重要
脳幹出血は重篤な疾患ですが、出血の程度によっては回復の見込みがあります。
ある研究では良好回復は約6.1%※と低いものの、予後を左右する重要な因子として、発症時の意識状態や出血量、年齢などが挙げられます。
※出典: 脳幹出血患者の予後予測. 脳卒中の外科
回復のためには早期からの適切なリハビリテーションが非常に重要であり、急性期・回復期・維持期の各段階に応じた計画的なアプローチが求められます。
また、再発予防のためには減塩や禁煙、適切な血圧管理などの生活習慣改善が不可欠です。
他にも脳幹出血の再発予防や後遺症には、再生医療の選択肢があります。
>>実際の症例はこちらから
以下の動画では、実際に再生医療の治療を受け、脳幹出血による麻痺が改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
再生医療に興味がある方は、お気軽にご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
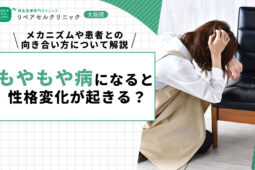
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介