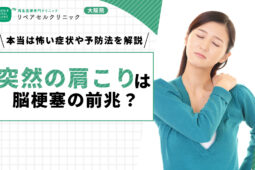- 頭部
- 脳梗塞
- 脳卒中
脳梗塞の後遺症によるふらつきの原因は?めまいの特徴や改善に重要なリハビリについて
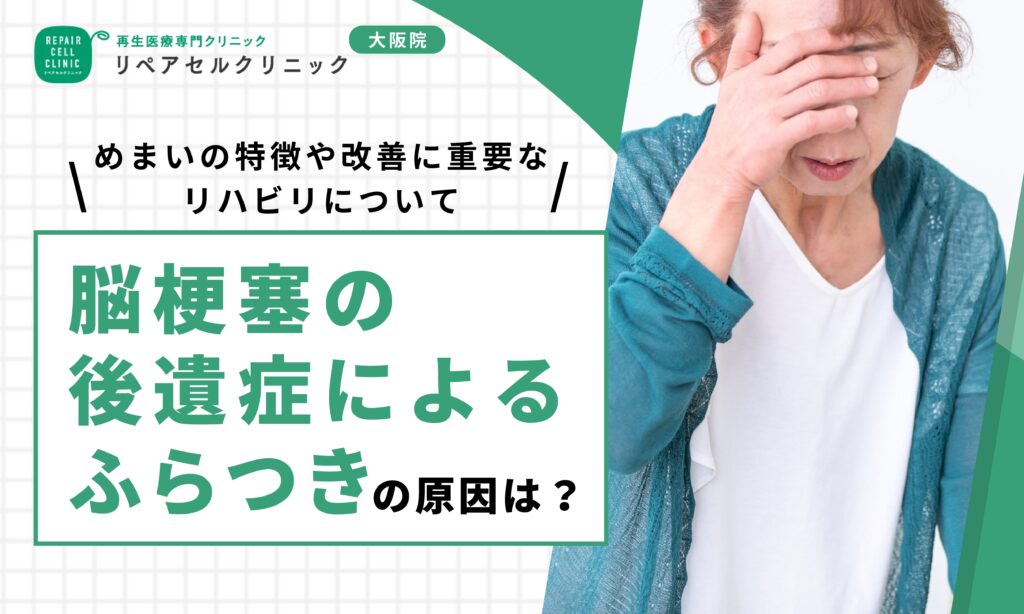
脳梗塞の後遺症でふらつきやめまいが出現し、お困りの方はいませんか。
脳梗塞は、血の塊(血栓)が脳血管をふさぎ、発症部位より先の血流が滞ることで脳細胞が壊死する疾患です。
後遺症で出現するふらつきは、体幹失調が原因の可能性があります。体幹失調は、胴体のバランスが取りづらく、スムーズに身体を動かせない状態です。
本記事では、脳梗塞の後遺症によってふらつきが出現する原因や、めまいの特徴について詳しくご紹介します。
ふらつきやめまいは発症からの日数によって、症状の特徴が異なります。経過に合ったリハビリテーションを行い、脳梗塞によるふらつきを改善しましょう。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。
併せて参考にしてください。
目次
脳梗塞の後遺症でふらつく原因
脳梗塞の後遺症でふらつく原因は、小脳や脳幹の損傷によって体幹失調が起こっている可能性が高いです。
体幹失調とは、脳と胴体の連携が十分にできず、バランスを取ることが困難になる状態です。
脳梗塞は血の塊(血栓)が脳血管で詰まる疾患で、梗塞部位より先の血流が滞り脳細胞が壊死します。
小脳梗塞を引き起こすと、脳は身体を動かす指令を伝達できなくなる恐れがあるため注意が必要です。
体幹失調とは
体幹失調とは、脳梗塞の後遺症で起こる可能性がある運動失調の一種で、以下の特徴が現れます。
- 座っているときにグラグラする
- 足を大きく開いて歩く
- 手足の動きがバラバラになる
- 千鳥足のような歩き方になる
- 起き上がりや寝返りが困難になる
体幹失調は歩行時に症状が目立ちますが、身体のバランスが悪くなるため座っているときにも症状が現れる場合があります。
脳梗塞で体幹失調が起こるメカニズム
脳梗塞によって脳幹や特定部位が損傷すると、体幹失調が起こる可能性があります。体幹失調のメカニズムは、以下のとおりです。
- 脳幹に血栓が詰まり、発症部位より先の血流が遮断される
- 血流が減少し脳細胞が壊死する
- 身体へ指令を出す脳幹やバランスを取るための小脳や前庭迷路が機能しづらくなくなる
- 歩行時にふらつき症状やめまいが出現する
脳は、神経に身体を動かす指令を送る役割を担っています。
脳血管の一部の血流が遮断されると、身体をスムーズに動かせなくなり、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。
脳梗塞の後遺症による「めまい」の特徴
脳梗塞の後遺症による「めまい」は、大きく以下の3つに分けられます。
| めまいの種類 | 特徴 |
|---|---|
| 回転性めまい | ぐるぐると回っているように感じる |
|
浮遊性めまい |
ふわふわと宙に浮いているように感じる |
| 前失神性めまい | 立ちくらみ同様、目の前が突然真っ暗になったように感じる |
めまいが起こると、自分自身が動いていなくても動いているように感じ、周囲からはふらついている状態に見えます。
脳梗塞によるふらつき・めまいの症状の変化
脳梗塞によるふらつきやめまいでは、発症してからの日数によって症状が変化します。
症状に合わせて、適切な治療やリハビリテーションを受け、ふらつきを改善していくことが重要です。
発症直後
脳梗塞の発症直後は、ぐるぐると回っているように感じる「回転性めまい」が出現しやすく、重いふらつき症状が現れます。
発症直後の回転性めまいは重度で、自分自身で立位を保つことは困難です。
以下の脳梗塞の初期症状(一過性脳虚血発作)がみられた場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
- 口が閉まりにくい
- ろれつが回らない
- 言葉が出ない
- 片麻痺
- めまいやふらつきがある
- 視野が狭くなる
治療せずに放置すると重い後遺症が出る恐れがあるため、早期発見・早期治療を行うことが大切です。
脳梗塞の初期症状や発症原因については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
数日〜数週間経過後
脳梗塞の発症から数日~数週間経過すると、回転性めまいの症状が軽減する場合があります。
しかし、平衡感覚障害やふらつきが残る場合があるため、リハビリが重要です。
歩行時のふらつきやめまいがあるときは、無理に動かず、医療者の指示に従いましょう。
治療後
脳梗塞の治療後は、後遺症としてふらつきやめまいが出る場合があります。
後遺症でめまいやふらつきがある方は、治療やリハビリテーションを継続し、転倒リスクの軽減を図ることが大切です。
脳梗塞の後遺症によるふらつき改善に重要なリハビリテーション
脳梗塞の後遺症によるふらつきを改善するには、以下のリハビリテーションを行うことが重要です。
リハビリテーションで効果を得られるように、適切なリハビリ方法を確認しましょう。
フレンケル体操
脳梗塞の後遺症によるふらつきに効果的なリハビリテーションの1つに、フレンケル体操があります。
フレンケル体操は、小脳を原因とした運動失調に有用なリハビリテーションで、身体の位置感覚や運動バランスを改善するために行われます。
体操の運動項目は120種類以上あり、後遺症の程度や病状に合わせて選択するのが一般的です。
仰向けで行う方法
- 両足のかかとを床につける
- 片足をすべらせるように動かし、膝の曲げ伸ばしを行う
- かかとを床につけたまま、片膝を曲げた状態で股関節を内外に動かす
- 片膝を立てた状態で股関節を内外へ動かす
椅子に座って行う方法
- 椅子に座り、数分間姿勢を保持する
- 足の前に目印を置き、片方のつま先でタッチして元の姿勢に戻る
- 足を閉じて立ち上がり、再度椅子に座る
無理のない範囲でフレンケル体操を実施し、身体の平衡感覚の改善を目指しましょう。
前庭リハビリテーション
脳梗塞の後遺症でふらつきがみられる場合に、前庭リハビリテーションを行う方法があります。
前庭リハビリテーションは、歩行や姿勢の保持など、日常生活動作の改善を目的として行われる反復訓練です。
リハビリテーションを行うことで、平衡感覚をつかさどる前庭の機能を改善し、ふらつき症状やめまいの軽減が期待できます。
椅子に座って行う方法
- 体の正面で腕を伸ばし、親指を目の高さに持ってくる
- 親指を見ながら頭を左右・上下に動かす
立って行う方法
-
- 目を開けたまま足を閉じて立ち、前後左右に身体を傾ける
- 1ができたら、目を閉じて立ち、前後左右に身体を傾ける
椅子に座って行う方法や、立って実施する訓練ができたら、歩行訓練を行います。
歩行時は身体を静止しているときと比べて転倒リスクが高いため、注意して実施しましょう。
脳梗塞の後遺症によるふらつきにお困りの方は再生医療をご検討ください
脳梗塞の後遺症によるふらつきにお困りの方は、後遺症の根本的な治療を目指せる再生医療を検討してみましょう。
再生医療とは、体が持つ再生能力を利用して一度壊死した脳細胞を再生させる医療技術のことで、脳機能の回復が期待できます。
また、リハビリと並行して再生医療を行うことで身体機能の回復効果を高め、治療期間の短縮にもつながります。
リペアセルクリニックでは、患者さまの症状に適したリハビリの訓練や指導が行えるよう、医師の他に理学療法士や柔道整復師などの専門資格を持つチーム体制が整っています。
脳梗塞の後遺症でお悩みの方は、ぜひ当院(リペアセルクリニック)にご相談ください。
【まとめ】脳梗塞の後遺症によるふらつき改善にはリハビリが重要
脳梗塞の後遺症によるふらつき改善には、症状に合ったリハビリが重要です。
適切なリハビリテーションを行うことで、ふらつきが改善され、転倒リスクが低減します。
後遺症のめまいやふらつきが改善せずお困りの場合は、リハビリテーションと並行して再生医療による治療も検討しましょう。
当院(リペアセルクリニック)の再生医療は、厚生労働省に受理された治療法で、後遺症の改善だけでなく脳梗塞の再発予防も期待できます。
脳梗塞の後遺症によるふらつきにお悩みの方は 、当院(リペアセルクリニック)へお気軽にお問い合わせください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長