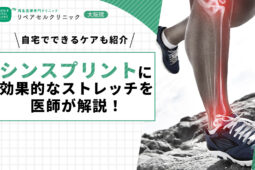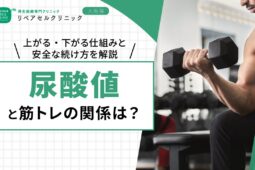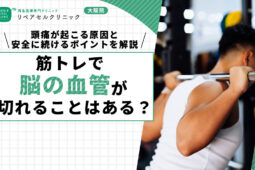- スポーツ医療
- 再生治療
疲労骨折は自然治癒する?早く治す方法や治癒するまでの期間を解説【医師監修】
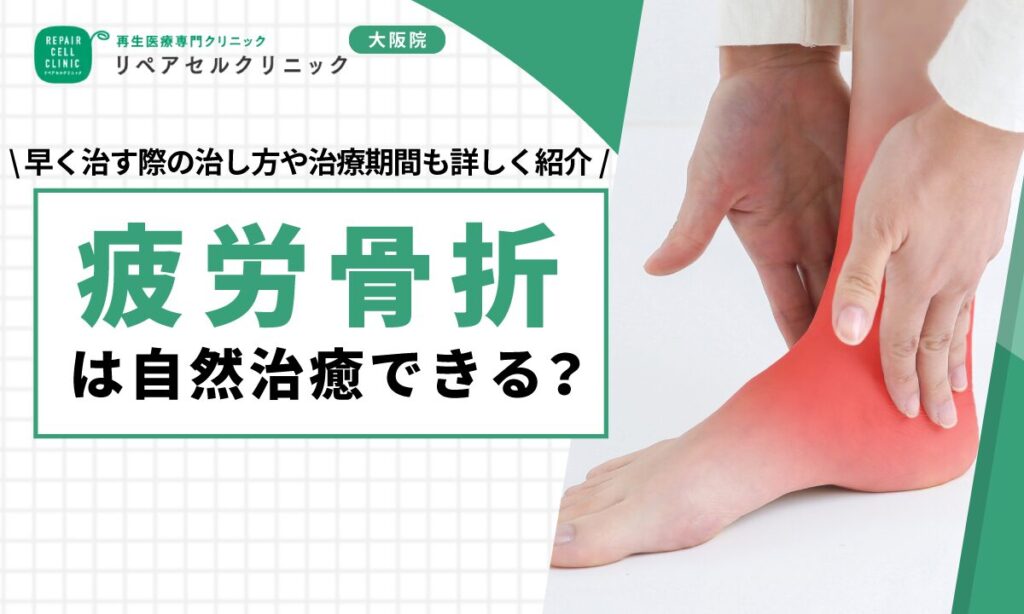
疲労骨折してしまった場合「病院で治療を受けた方がいいのか」「自然治癒するのか」気になる方も多いでしょう。
結論、疲労骨折は、骨折部位の負担を避けて安静にしておくことで自然治癒を目指せるケガです。
しかし、早く治すためには症状に応じて適切なケアが必要であり、自己判断で自然治癒を目指すのはリスクがあるといえます。
この記事では、疲労骨折が起こりやすい部位や、自然治癒で早く治す方法、治療にかかる期間などを解説しています。
「疲労骨折が疑われる方」や「疲労骨折を早く治したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
疲労骨折は自然治癒が期待できる
疲労骨折は、骨折部位に負担をかけないように安静すれば、基本的に自然治癒が期待できます。
しかし、時間の経過とともに自然に治癒していきますが、放置してしまうと治りが遅くなる可能性があるため注意が必要です。
疲労骨折の痛みの特徴や、起こりやすい部位を理解して、適切な対応を取ることが大切です。
痛みが長引く場合は、医療機関を受診することも選択肢の一つとして検討しましょう。
疲労骨折はどんな痛み?
疲労骨折の痛みは、運動時や特定の動作時にズキズキとした痛みを感じるのが特徴です。
完全に骨折した場合と異なり、大きな腫れや出血を伴う強い痛みはないため、痛みを我慢しながら日常生活や運動を続けられる場合があります。
しかし、痛みを我慢して運動を続けることで完全な骨折に至る可能性があるので注意しましょう。
疲労骨折が起こりやすい部位
一般的に疲労骨折が起こりやすい部位は、以下の通りです。
- 足の甲(中足骨)
- すねの内側(脛骨)
- 脛の外側(腓骨)
- かかと
- 肋骨
- 大腿骨
- 腕の前腕(尺骨)
骨に負担がかかりすぎることによって発生する疲労骨折は、身体を支える際に負荷がかかる下肢に起こりやすいものです。
疲労骨折が起こりやすい部位を把握して、負担をかけすぎないように心がけましょう。
疲労骨折が自然治癒するまでの期間
疲労骨折の自然治癒に取り組む場合、一般的には2~3か月が休息期間として設定されています。
部位や重症度によって休息期間は異なりますが、設定された期間中は疲労骨折の原因となった運動は禁止されます。
疲労骨折した部位と、自然治癒までにかかる一般的な期間は以下のとおりです。
- 脛骨…4~8週間
- 中足骨…6~8週間
- 腰椎…6~12週間
- 大腿骨頸部…8~12週間
あくまで目安であるため、治癒までの期間は個人差が生じることに留意しておきましょう。
疲労骨折を自然治癒で早く治す方法
疲労骨折を自然治癒で早く治す方法を解説します。
疲労骨折を早く治したい方は、ぜひ参考にしてください。
6〜8週間は安静にする
疲労骨折を早く治すためには、骨折部位に負担をかけないように6〜8週間は安静にしましょう。
骨折部位別の安静期間の目安は、以下の通りです。
| 骨折部位 | 安静期間の目安 |
|---|---|
| 脛骨(すねの骨) | 4〜8週間 |
| 中足骨 | 6〜8週間 |
| 腰椎 | 6〜12週間 |
| 大腿骨頸部 | 8〜12週間 |
骨折部位や症状によって適切な安静期間には個人差があるため、まずは医療機関の受診が推奨されます。
また、安静にするだけではなく、以下で解説している方法も合わせて実践してみましょう。
カルシウムやたんぱく質を摂取する
疲労骨折を早く治すには、カルシウムやたんぱく質などの自然治癒を助けるために必要な栄養素を積極的に摂取しましょう。
| 必要な栄養素 | 主な食品 |
|---|---|
| カルシウム | ・乳製品 ・大豆製品 ・緑黄色野菜 など |
| たんぱく質 | ・肉類 ・魚介類 ・大豆製品 ・卵 など |
| ビタミンD | ・魚類 ・きのこ類 ・卵黄 など |
上記のような栄養素を摂取できる食べ物をバランスよく取り入れることが、疲労骨折を早く治すために重要です。
適切なリハビリを行う
疲労骨折を早く治すためには、適切なリハビリを行うことも重要です。
優先すべきは骨折部位に負担をかけないことですが、運動不足によって筋力や柔軟性が低下すると、治った後にケガをするリスクが高まる可能性があります。
骨折部位に注意しつつ、以下のような運動を取り入れましょう。
- 骨折部位周辺の筋力トレーニング
- 骨折部位周辺のストレッチ
- 片足立ちなどのバランス感覚の訓練
また、上記のようなリハビリを取り入れることは重要ですが、自己判断で行うと思わぬケガや症状の悪化につながる可能性があるため注意が必要です。
理学療法士の指導を受けるなど、専門家と相談しながらリハビリを行いましょう。
自然治癒を補助する治療を検討する
疲労骨折を早く治すには、医師や理学療法士と相談して自然治癒を補助する治療を検討してみましょう。
自然治癒を補助する治療方法の種類と、期待できる効果は以下のとおりです。
| 治療方法 | 期待できる効果 |
|---|---|
| アイシング | 痛みと腫れの緩和 |
| 電気刺激療法 | 痛みの軽減/筋肉の緊張緩和 |
| 超音波療法 | 骨治癒の促進 |
| マッサージ療法 | 血行促進/筋肉の緊張緩和 |
| ストレッチング | 関節可動域の維持/筋力低下の予防 |
| 運動療法 | 筋力強化/関節機能の回復 |
アイシングや電気刺激療法をはじめとする物理療法は、痛みの緩和や、炎症を抑えることが期待されている治療方法です。
効果には個人差がありますが、早期回復を目指す場合は医師と相談の上で採用してもよい方法でしょう。
スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
自然治癒後に疲労骨折を再発させない予防法
疲労骨折は自然治癒したあとも、再発させないことが大切です。
ここからは疲労骨折を再発させないための予防方法や、予防に有効な食べ物を紹介します。
運動前のウォーミングアップ
一度治った疲労骨折を再発させないためにも、運動前のウォーミングアップを徹底しましょう。
ウォーミングアップは、単なる準備運動ではなく、体温を高めることで筋肉への酸素・血液量を増加させ、筋肉を柔らかくする目的があります。
また、関節の可動域を広げ、柔軟性を高めることでケガを防ぐことも可能です。
自分に合った負荷のトレーニング
疲労骨折を再発させないためにも、自分に合った負荷のトレーニングを心がけましょう。
急激に大きな負荷をかけないよう注意し、トレーニングの負荷は段階的に増やすことが重要です。
定期的に休息日を設けながらトレーニングするのも良いでしょう。
また、トレーニングを行う際は、足のサイズに合った靴やクッション性のある靴を使用するなど、運動に向けたコンディションを整えることも大切です。
規則正しい生活習慣
疲労骨折を予防するためにも、規則正しい生活習慣を身につけることも大切です。
- バランスの取れた食生活を意識する
- 適度な運動習慣を身につける
- 睡眠時間を確保する
- 禁煙・禁酒をする
上記のような生活習慣への改善によって、骨を十分に休息させる規則正しい生活を送りましょう。
また、定期的に骨密度の検査を受け、骨の健康状態を管理することも重要です。
疲労骨折の自然治癒についてよくある質問
最後に疲労骨折と自然治癒に関してよくある質問を紹介します。
疑問がある方はここで解消しておきましょう。
疲労骨折になりかけの前兆は?
疲労骨折になりかけている場合、以下のような前兆が出ると考えられます。
- 特定の動作をすると痛い
- 安静にすると痛みが和らぐ
- 明らかなケガはしていないのに痛む
通常の骨折は、明らかに衝撃が加わるようなケガをしており、患部が腫れたり安静にしていても痛むなどの症状が出るという点で異なります。
疲労骨折になりやすい人の特徴は?
疲労骨折になりやすい人の傾向として、以下のような特徴が挙げられます。
- 急にトレーニング量を増やした
- ランニングのフォームが揃っていない
- 地面が硬い/柔らかい
- 靴が足に合っていない
- 筋力・柔軟性不足
- 技術不足
- 加齢
- 体重増加
- 偏平足
- 栄養不足
- 骨密度の低下
- O脚またはX脚
骨に対する過度な負荷をかけ続けることで疲労骨折につながるため、無理のない運動負荷に収めることが大切です。
疲労骨折しても歩ける?
通常の骨折とは異なり、疲労骨折は骨のズレが生じないため、骨折部位によっては歩くことが可能です。
しかし、歩けるからといって無理して歩いてしまうと、さらに状態が悪化する恐れがあるため、できる限り安静に過ごす必要があります。
痛みや違和感があるなど、疲労骨折が疑われる場合は、早めに病院で診察してもらいましょう。
疲労骨折が自然治癒しない場合は再生医療をご検討ください
疲労骨折した場合、自然治癒だけでは完全回復には至らない可能性があります。
自然治癒に取り組み、経過観察をしても回復の兆しが見えなかったり悪化したりした場合は、手術が必要となるおそれがあるため注意が必要です。
もし疲労骨折が慢性化していたり、再発が多い、既存の手術治療で完治しなかったなどの場合は、当院(リペアセルクリニック)の再生医療をご検討ください。
再生医療を活用することで、治療期間を大幅に短縮し、日常生活や競技への早期回復が見込めるようになります。
自然治癒では完治しきらず手術が必要となる場合でも、手術をせずに済ませられるのも再生医療の特徴です。
手術後の悪影響や後遺症の心配をする必要がなくなるため、興味がある方は再生医療の活用を検討してみてください。
再生医療の詳しい治療法やプラン、料金などを知りたい方は、無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設