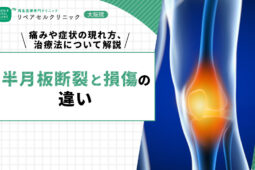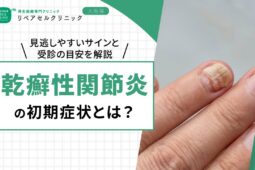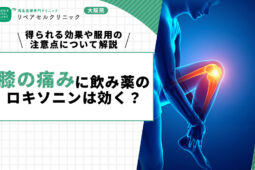- ひざ関節
しゃがむと膝がポキポキ鳴るけど痛みがないのはなぜ?音がする主な原因・疾患を紹介

「しゃがむときに膝からポキポキ音がする」
「ポキポキ音は異常のサイン?」
膝の痛みはないものの、頻繁に音がなる現象に不安を抱いている方も多いことでしょう。
結論、膝からポキポキ音がするときは、関節や筋肉の問題が潜んでいる可能性があります。
この記事では、膝の音が鳴るメカニズム、関連する疾患、そして症状への対処法を詳しく解説します。
- しゃがむと膝がポキポキと鳴る理由
- しゃがむと膝が鳴るときの対処法
痛みを伴う場合はとくに注意が必要になるので、本記事を参考にして早めに医療機関を受診しましょう。
目次
しゃがむと膝がポキポキとなる鳴る理由
膝を曲げたときにポキポキ音が鳴る理由は、以下の通りです。
- 膝関節内の気泡が破裂している
- 変形性膝関節症で関節間の骨同士が接触している
- 半月板が損傷している
- 靭帯が損傷している
膝を動かすと関節液の中で気泡が移動して破裂音が鳴る場合がありますが、基本的に問題ありません。
しかし、痛みを感じる場合は半月板や靭帯の損傷が考えられます。
長期間の放置は症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。
痛くないけど膝が鳴るのは異常?
痛みを伴わずしゃがむと膝が鳴る場合は関節液の中で気泡が破裂しており、問題ないとされています。
しかし、痛みがなくても変形性膝関節症の兆候として音が鳴っているかもしれません。
とくにミシミシとした音や、ジャリッとした音が鳴った場合は、半月板や軟骨に異常をきたしている可能性があります。
痛みの有無にかかわらず、膝に違和感を覚えたら医療機関を受診するよう心がけましょう。
しゃがむと膝が鳴る主な原因・疾患
しゃがむと膝が鳴る主な原因・疾患として、以下が考えられます。
しゃがむと膝が鳴る主な原因・疾患についてそれぞれ詳しくみていきましょう。
膝の筋力が弱っている
外傷や病気がなくても、膝周辺の筋力低下が膝の痛みや音が鳴る原因になります。
膝を動かす筋肉には、大腿四頭筋やハムストリングス、縫工筋や半腱様筋などがあり、筋肉が弱ると、膝関節の動きにズレが生じやすくなります。
筋力低下を防ぐためには、軽いウォーキングや自転車など、負担の少ない運動を継続的に行うことが大切です。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、長期間にわたり少しずつ膝関節が変形する疾患です。
大きな衝撃で急に膝が動かなくなるわけではありませんが、以前は気にならなかった膝の曲げ伸ばし時の痛みや音が徐々に強まります。
- 初期段階:体重がかかった状態で膝を曲げる動作を行うと痛みを感じる
- 進行後:非荷重の状態でも痛みを感じる
そのまま放置してしまうと、痛みが慢性化し、歩行や階段の昇り降りに支障が出ることもあります。
年齢のせいと思わず、違和感を感じた時点で早めに整形外科を受診し、進行を防ぐ適切な治療やリハビリを始めることが大切です。
タナ障害
タナ障害は、膝関節内の滑膜(タナ)が厚くなり、膝を曲げ伸ばしする際に膝蓋骨との摩擦が生じる障害です。
以下のような原因で発症することが多いとされています。
- スポーツによる膝の酷使(ジャンプ、ダッシュ、急停止など)
- 外傷(打撲や転倒による膝の衝撃)
- オーバーユース(使いすぎ):反復動作や長時間の練習など
中学生や高校生は、部活動やクラブ活動で膝を酷使しやすく、かつ成長期で関節が未発達なため、タナ障害のリスクが高いといえます。
治療は、休息や消炎鎮痛薬の使用、ストレッチや筋力トレーニングなどの保存療法が基本です。
軽度の場合はこれらの方法で改善することが多いですが、効果が見られない場合は関節鏡手術で肥厚した滑膜ヒダを切除することもあります。
気になる症状がある方は、無理をせず整形外科など専門医への相談をおすすめします。
半月板損傷
半月板損傷は、膝を深く曲げたりひねったりした際に、膝関節内で半月板が損傷して発生します。
半月板は衝撃吸収の役割を担っている組織です。
半月板の損傷によって膝の不安定感や痛みが生じ、しゃがんだときにポキポキという音が鳴る場合があります。
半月板は衝撃吸収の役割を担っていますが、加齢やスポーツによる負荷が原因で劣化するケースもあります。
痛みが続く場合は、早期に医師の診断と適切なリハビリが必要です。
腸脛靭帯炎
腸脛靭帯炎はランナーズニーとも呼ばれる疾患です。
大殿筋から始まる腸脛靭帯が大腿骨外側を通り下腿まで伸びる中で、外側顆と摩擦が生じて発症します。
腸脛靭帯炎になると、屈曲や伸展運動の際に腸脛靭帯と外側顆が擦れるので、当然膝を曲げると痛みが出ます。
腸脛靭帯炎になってしまう原因は、オーバーユース(使いすぎ)です。
大殿筋や大腿部の筋肉に負担がかかるような長距離ランナーに多くみられます。
疼痛部を守ろうとするあまり、周りの筋肉は自然と硬くなります。その結果、膝関節が硬くなり、痛みに加えて音が鳴るのです。
しゃがむと膝が鳴るときの対処法
しゃがむと膝が鳴るときの対処法は以下の通りです。
すぐに実施できる方法を以下で詳しく紹介するので、できることから取り組んでみましょう。
大腿四頭筋のストレッチをする
膝を動かす筋肉の緊張は不調の原因になります。とくに大腿四頭筋の緊張が強まると、膝の障害リスクが高まります。
対策として、大腿四頭筋のストレッチを日常的に行いましょう。
ストレッチでは、膝関節をしっかりと曲げるのがポイントです。
また、股関節が曲がってしまうと効果が半減するので、股関節を伸ばしながら膝を曲げるように心がけましょう。
- 椅子や壁などにつかまり直立の姿勢を保つ
- 伸ばす側の足首を持ち、後ろから臀部(お尻側)に引きつける
- 大腿四頭筋が伸びていることを確認し20秒キープ
※反動をつけずに無理なく実施しましょう。
内転筋のトレーニングをする
日常生活の中で最も筋力が落ちやすい部位が内転筋です。
膝の内側にある内転筋と、大殿筋などの股関節外転筋のバランスが崩れると、膝の安定性が低下します。
筋力低下により、O脚や変形性膝関節症の進行リスクが高まるので内転筋を意識したトレーニングを取り入れましょう。
内転筋を鍛えると、膝関節の運動がスムーズになり、安定性が増して痛みが軽減していきます。
| チューブを使うトレーニング | ゴムチューブを足に巻き付けて、股関節の内転方向に力を入れる |
|---|---|
| 椅子を使うトレーニング | 座った状態で足を浮かせ、膝を前にまっすぐ伸ばす ※膝の内側にボールやクッションを挟むとより効果的 |
足首をよく回す
お風呂上がりなどに足首を手で回すと、膝を曲げたときの痛みや音が軽減できます。
足首を定期的に回すことで足関節の曲げ伸ばしがスムーズになると同時に、歩行時の推進力が向上するため、間接的に膝への負担が軽減されるのです。
変形性膝関節症の進行や腸脛靭帯炎のリスクも抑えられるため、積極的に実施しておきたい対処法のひとつです。
整形外科で精査してもらう
原因不明の膝の痛みや音が非荷重時・歩行時に発生する場合は、整形外科を受診しましょう。
整形外科ではレントゲンやMRIを用いた診断が可能です。
転倒や打撲の事実がないのに膝関節の腫れや屈曲時の音や痛みが続く場合は、変形性膝関節症が進行しているかもしれません。
原因を特定し、適切な治療を行うためにも、早めに専門医にみてもらいましょう。
接骨院で治療する
筋緊張の緩和や筋力強化を目的とした保存治療を受ける際は接骨院の通院が適しています。
薬物療法や画像診断はおこなえませんが、膝の痛みに対して専門的な治療が受けられるだけでなく、症状を和らげるとともに、再発予防に関する指導もしてくれます。
整形外科で痛みや音の原因を精査した後に、接骨院で治療を受けることも視野に入れてみましょう。
痛みを伴う膝の異常は専門医に相談しよう
膝を曲げたときの痛みは、原因に関係なく膝になんらかの異常が起きているサインです。
痛みを放置すると手術が必要な症状に発展する可能性もあるため、早めに専門医へ相談しましょう。
音が鳴るだけであれば直ちに問題になるケースは多くありませんが、疾患の兆候の可能性も考えられます。
日頃からストレッチや軽めのトレーニングを実施し、あらかじめ対処しておきましょう。
また、膝に関するお悩みは当院でも受け付けておりますので、お問い合わせください。
以下のページでは、膝関節に対する再生医療の症例を公開しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療による膝関節の症例はこちら

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設