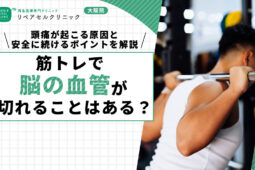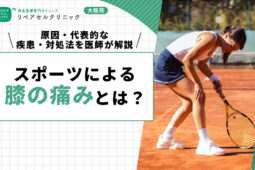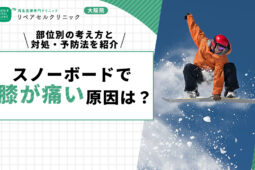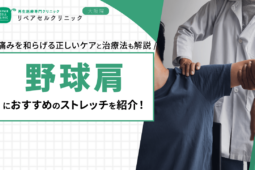- スポーツ医療
- その他
足の甲が疲労骨折する原因|どのくらいで治る?症状の見分け方と治し方を解説

歩行や運動時に感じる足の甲の痛みは、日常生活に支障をきたすだけでなく、「もしかして骨折?」という大きな不安材料となるでしょう。
特にスポーツをされている方や、立ち仕事が多い方にとって、足の甲の痛みは見過ごせないサインです。
本記事では、足の甲が疲労骨折してしまう原因や、見逃してはいけない症状の特徴について詳しく解説します。
- 足の甲が疲労骨折する原因
- 足の甲が疲労骨折したときの症状
- 疲労骨折の症状の見分け方【チェックリスト】
- 足の甲の疲労骨折の治療法・予防法
足の甲の痛みを正しく理解し、適切な処置への第一歩を踏み出しましょう。
また、保存療法で改善が見られない疲労骨折では、再生医療が選択肢となる場合があります
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、炎症抑制や損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
当院リペアセルクリニックでは、具体的な治療について無料カウンセリングを実施しておりますので、ぜひご相談ください。
目次
足の甲が疲労骨折する原因
足の甲に疲労骨折が生じる大きな原因は、骨の強度を超える負荷が、繰り返し同じ場所に加わり続けることです。
足の甲に過度なストレスがかかる主な要因は、以下のとおりです。
- オーバーユース(使いすぎ)
- 急激なトレーニング量の増加
- 下半身の筋力不足と柔軟性の低下
- 足に合っていないシューズの着用
- コンクリートなどの硬い路面での運動
- フォームや身体の使い方の癖
- 偏平足・ハイアーチなどの骨格的な問題
- 骨密度の低下
ランニングやジャンプを繰り返すスポーツなど、足への衝撃を伴う動作の繰り返しによって骨への負担が蓄積されます。
急激にトレーニング量を増やした時期などは、特に疲労骨折のリスクが高まります。
また、下半身の筋力・柔軟性不足やクッション性のないシューズの着用、コンクリートなどの硬い路面での運動も、足の甲への負担を増大させる要因です。
骨への負荷を減らすには、運動量の調整だけでなく、シューズの見直しやストレッチによる柔軟性の確保など、多角的なアプローチが有効です。
足の甲が疲労骨折したときの症状
足の甲が疲労骨折している場合、痛みは突然激しくなるのではなく、徐々に強まっていくことが多いため、初期段階での発見と対処が重要です。
本章では、足の甲が疲労骨折したときの具体的な症状や見分け方について解説します。
ご自分の足の状態と照らし合わせながら、疲労骨折かどうか判断するための参考にしてください。
疲労骨折の主な症状
足の甲の疲労骨折は、特に第2・第3中足骨(足部の中央に位置し、体重負荷を最も受けやすい部位)に好発します。
第2・第3中足骨が疲労骨折した場合、以下のような症状が現れます。
- 歩行時・運動時の足の甲に鈍い痛みがある
- 安静にしていても足の甲が痛い
- 患部を指で押すと特定の一点に圧痛を感じる
- 患部に腫れや熱感がある
上記のような症状を無視して生活や運動を続けると、完全な骨折に至り、長期の安静期間が必要になる可能性があります。
疲労骨折が疑われる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な対処を心がけましょう。
また、小指側にある第5中足骨を疲労骨折した状態を「ジョーンズ骨折」と呼び、通常の疲労骨折とは予後が異なるため、注意が必要です。
疲労骨折の症状の見分け方
足の甲の痛みは、疲労骨折以外にも「腱炎」や「捻挫」などの可能性があります。
これらを見分けるためには、以下のチェックリストを参考に、痛みの広がり方や、特定の動作による反応などを確認しましょう。
| チェック項目 | 疲労骨折の疑い | 腱炎や捻挫の疑い |
|---|---|---|
| 痛みの範囲 | ピンポイントの痛み | ぼんやりとした広範囲の痛み |
| 圧痛部位 | 骨の上を押すと痛む | 筋(スジ)や関節を押すと痛む |
| 腫れ方 | 患部周辺の全体的な腫れ | 筋に沿った腫れ、または関節周辺の腫れ |
| 発症パターン | 数日~数週間かけて徐々に悪化 | 急性発症、運動後すぐ |
| 安静時の痛み | 症状悪化によって痛む | 軽度、またはなし |
ただし、上記のチェック項目はあくまで目安程度に捉えましょう。
自己判断で処置を遅らせるリスクを避けるため、疑わしい場合は整形外科でのレントゲンやMRI検査を受けることが、確実な回復への近道です。
また、初期段階の疲労骨折ではレントゲンに写らないこともあるため、他の検査を受けることも検討する必要があります。
足の甲の疲労骨折はどのくらいで治る?主な治し方
足の甲の疲労骨折は、多くの場合、手術を行わずに「保存療法」と呼ばれる治療法で自然治癒を目指すことができます。
ただし、これは「何もしないで放置すれば治る」という意味ではなく、骨が修復される環境を整え、適切な管理を行うことが前提です。
疲労骨折の治療プロセスは、主に以下の2つの段階に分けて進められます。
骨折の程度や場所によっては手術が検討されるケースもありますが、基本的には患部への負担を取り除くことから治療が始まります。
早期復帰を目指すためにも、各段階でどのような処置が行われるのかを理解しておきましょう。
安静と固定
疲労骨折の治療で優先すべきことは、骨の修復を妨げないよう患部を固定して安静にすることです。
固定期間は重症度によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
- 軽度:4~8週間
- 中等度:8~12週間
- 重度:12週間以上
完全に骨が治っていない状態で固定を外したり、運動を再開したりすると、再骨折や難治化(骨がつかなくなること)を招く恐れがあります。
骨の癒合が確認されるまでは、焦らず安静を保つことが、早期改善の近道です。
リハビリテーション
骨の癒合が確認され、医師の許可が出た後は、少しずつ元の生活やスポーツ活動に戻るためのリハビリテーションを開始します。
リハビリテーションは、以下のようなメニューを段階的に実施します。
- 荷重訓練
- 可動域訓練
- ストレッチ
- 筋力トレーニング
- 動作やフォーム改善
安静期間中に低下してしまった筋力や柔軟性を取り戻し、再発を防ぐ身体作りが目的となります。
無理に頻度や負荷を上げてしまうと再骨折や難治化につながるため、注意が必要です。
「痛みが出ないか」を常に確認しながら、医師や理学療法士の指導のもと、慎重にステップアップしていきましょう。
足の甲の疲労骨折を予防する方法
疲労骨折は、日々のトレーニング習慣や生活環境を見直すことで予防できる怪我です。
「一度治ったから安心」と考えるのではなく、骨への負担をコントロールし続ける意識を持つことが、長くスポーツや歩行を楽しむための鍵となります。
疲労骨折で実践したい具体的な予防法は、以下の5つです。
以下では、それぞれの予防法とポイントについて、詳しく見ていきましょう。
運動量は段階的に増やす
疲労骨折の主なリスク要因は、オーバーユース(使いすぎ)や急激なトレーニング量の増加のため、運動量は段階的に増やすことが重要です。
運動時間や走行距離を増やす際は、前週比で1.1倍以内に抑える「10%ルール」を意識しましょう。
また、週に1〜2日は完全休養日を設け、骨の微細な損傷を修復させるための休息時間を確保することも不可欠です。
「もう少しやりたい」と思う段階で止める勇気が怪我を防ぎ、結果として長期的なパフォーマンス向上につながります。
運動前後のセルフケア
ふくらはぎや足裏が硬くなると、その衝撃が骨に直接伝わりやすくなるため、運動前後のセルフケアが欠かせません。
筋肉の柔軟性は、地面からの衝撃を和らげる重要な「クッション機能」を果たします。
運動前には関節を温める動的ストレッチを、運動後にはアイシングや静的ストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。
また、入浴やマッサージで血流を促すことも有効です。
自分の身体の状態を確認する習慣が、疲労の蓄積や異変の早期発見につながります。
下半身の筋力トレーニング
足の甲への負担を物理的に軽減するためには、衝撃を受け止めるための筋力強化が重要です。
特に、足のアーチ(土踏まず)を支える足裏や、着地を安定させるふくらはぎの筋肉を鍛えることで、衝撃分散能力が高まります。
自宅でも手軽にできる「タオルギャザー(足指でタオルを寄せる運動)」や「カーフレイズ(つま先立ち)」がおすすめです。
地道なトレーニングを継続して足の筋力を強化することが、疲労骨折を再発しにくい「強い足」を作る土台となります。
体重管理や食生活の改善
骨の健康を守り、疲労骨折を予防するためには、適正体重の維持と栄養バランスの取れた食事が不可欠です。
急激な体重増加は足への物理的負荷を増大させ、過度な減量による栄養不足は骨の修復を妨げます。
骨の主成分となるカルシウムに加え、吸収を助けるビタミンD、定着を促すビタミンK、骨の基礎を作るタンパク質を積極的に摂取しましょう。
身体の内側から骨折しにくい丈夫な骨を作っていく意識が大切です。
適切なシューズを着用する
疲労骨折の予防のためには、衝撃吸収性と安定性に優れ、サイズ感が適切なシューズを選ぶことが重要です。
サイズの合わないシューズや、クッション性が低下したシューズでの運動は、骨への負担を増大させる大きな要因となります。
また、靴底がすり減っていたり、クッション部分にシワが寄っていたりする場合は機能が低下しているサインなので、早めの交換を検討しましょう。
路面や体重、走行フォームにより劣化速度は異なりますが、一般的なランニングシューズの場合、500km程度使用した時点で交換することが推奨されています。
扁平足などの特徴がある場合は、インソールを活用して足のアーチ機能をサポートすることも有効な手段です。
足の甲が疲労骨折したら安静にして早期改善を目指そう
足の甲の疲労骨折は、繰り返す負荷によって徐々に進行するため、初期段階での発見と適切な対処を行うことが重要です。
痛みや違和感を「ただの疲れ」と放置せず、足からのサインに耳を傾けることが、重症化を防ぐ第一歩となります。
足の甲(第2・第3中足骨)を疲労骨折した場合、以下のような症状が現れます。
- 歩行時・運動時の足の甲に鈍い痛みがある
- 安静にしていても足の甲が痛い
- 患部を指で押すと特定の一点に圧痛を感じる
- 患部に腫れや熱感がある
上記のような症状を無視して生活や運動を続けると症状悪化につながったり、完治が遅れたりする可能性があるため、早期に医療機関を受診しましょう。
早期に適切な診断と治療を受けることが、スポーツや快適な日常生活への一番の近道となります。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設