- 再生治療
- その他
骨を強く(丈夫)にする食べ物・飲み物を解説!年齢別におすすめの食品も紹介

「最近、骨密度が気になる」「将来、骨折しやすくなるのが不安」といった悩みを抱えていませんか?
骨は年齢とともに少しずつ弱くなり、もろくなると転んだだけで骨折しやすくなるほか、背骨がつぶれて姿勢が崩れる(圧迫骨折)、慢性的な痛みにつながることもあります。
しかし、日々の食事を工夫するだけでも、骨の強さは大きく変わります。
特にカルシウム・ビタミンD・タンパク質などの栄養素は、骨をつくり、維持するために欠かせません。
本記事では、骨を強くするために積極的に摂りたい食べ物・飲み物について解説しています。
年齢別の食事ポイント、控えるべき食品、食事以外で骨を強くする方法まで紹介していますので、ぜひ参考にして今日から実践できる対策を見つけましょう。
目次
骨を強くする食べ物・飲み物
骨を強くするためには、骨の材料となる栄養素をバランスよく摂取することが大切です。
とくに重要な栄養素として以下の4つがあります。
それぞれの栄養素の働きと、含まれる食品を確認しましょう。
カルシウムを含む食品
カルシウムは骨の主成分であり、骨を強くするうえで最も基本となる栄養素です。
カルシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)
- 小魚(しらす、いわし、ししゃもなど骨ごと食べられる魚)
- 大豆製品(豆腐、納豆、厚揚げ)
- 緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜)
- 海藻類(ひじき、わかめ、昆布)
乳製品が苦手な方は、小魚や大豆製品、野菜など複数の食品から摂取することをおすすめします。
ビタミンDを含む食品
ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を助け、骨へのカルシウムの沈着を促進する栄養素です。
ビタミンDを多く含む食品は以下のとおりです。
- 魚類(サケ、サンマ、イワシ、シラス、サバ)
- きのこ類(干ししいたけ、まいたけ、エリンギ)
- 卵(とくに卵黄)
またビタミンDは食事からの摂取だけでなく、日光を浴びることで皮膚でも生成されます。
ビタミンKを含む食品
ビタミンKは骨にカルシウムを定着させるタンパク質(オステオカルシン)を活性化する働きがあります。
ビタミンKを多く含む食品は以下のとおりです。
- 納豆
- 緑黄色野菜(小松菜、ブロッコリー、ほうれん草、キャベツ)
- 海藻類(わかめ、のり)
とくに納豆はビタミンKの含有量が非常に高く、1パック(約50g)で1日の推奨量を十分に摂取できます。
マグネシウムを含む食品
マグネシウムは骨の構成成分として骨の強度維持に関わり、カルシウムの代謝を調整する役割も担っています。
マグネシウムを多く含む食品は以下のとおりです。
- 海藻類(わかめ、ひじき)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)
- 大豆製品(豆腐、納豆)
- 魚介類(あさり、牡蠣)
カルシウムを意識して摂る際には、マグネシウムも一緒に摂ることを心がけましょう。
タンパク質を含む食品
骨を強くするためには、カルシウムなどのミネラルに加えてタンパク質も重要な栄養素です。
タンパク質を多く含む食品は以下のとおりです。
- 肉類(鶏むね肉、豚肉、牛肉)
- 魚類(サバ、アジ、マグロ)
- 卵
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)
1日3食でそれぞれ手のひらサイズの肉や魚、または豆腐半丁程度を目安に摂取しましょう。
年齢と性別で変わる骨を強くするための食事ポイント
骨を強くするための食事は、年齢や性別によってとくに意識すべきポイントが異なります。
以下のライフステージに合わせた栄養摂取を心がけることで、より効果的に骨の健康を守れます。
以下では、成長期、更年期、高齢期それぞれの食事ポイントを解説します。
成長期の子どもが摂りたい栄養と食材
成長期の子どもにとくに意識してほしい栄養素と食材は以下のとおりです。
| 栄養素 | おすすめの食材と摂取のポイント |
|---|---|
| カルシウム | 牛乳、ヨーグルト、小魚、小松菜を毎日の食事に取り入れる |
| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品を毎食バランスよく摂取する |
| ビタミンD | 魚料理を週に3回以上取り入れ、外遊びで日光浴も行う |
スポーツをしている子どもはとくに、運動後のタンパク質補給を意識しましょう。
更年期以降に意識したい食事
骨密度が低下しやすい更年期以降に意識したい栄養素と食材は以下のとおりです。
| 栄養素 | おすすめの食材と摂取のポイント |
|---|---|
| カルシウム | 1日あたり男性750mg / 女性650mgを目標に乳製品と小魚、野菜から摂取 |
| ビタミンD・K | 魚料理と納豆を積極的に食べる |
| 大豆イソフラボン | 豆腐、納豆、豆乳など大豆製品を毎日摂取 |
毎日の食事に大豆製品を取り入れることを心がけましょう。
高齢者
食事量の減少や消化吸収機能の低下により、栄養不足に陥りやすい高齢者が意識したい栄養摂取のポイントは以下のとおりです。
| ポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 少量でも栄養価の高い食品を選ぶ | 牛乳、チーズ、卵、しらすなど |
| タンパク質を毎食摂る | 筋力低下を防ぎ、転倒予防にもつながる |
| ビタミンDを意識して摂取 | 魚料理、きのこ類、必要に応じてサプリメント |
食が細くなっている場合は、無理なくカルシウムを摂取できる工夫をしましょう。
骨粗しょう症の人が控えたい食品・食習慣
骨を強くするためには、必要な栄養素を摂るだけでなく、骨に悪影響を与える食品や食習慣を避けることも大切です。
以下の食品・食習慣は、カルシウムの吸収を妨げたり、骨からカルシウムを排出させたりする作用があるため、摂りすぎに注意が必要です。
| 控えたい食品・習慣 | 骨への影響 |
|---|---|
| 塩分の多い食品 | カルシウムの尿中排泄を増加させる |
| カフェインの摂りすぎ | カルシウムの吸収を妨げる |
| アルコールの過剰摂取 | 骨形成を抑制し、カルシウムの吸収も低下させる |
| リンの摂りすぎ | 加工食品やスナック菓子に多く含まれ、カルシウムの吸収を阻害する |
| 極端なダイエット | 栄養不足により骨形成に必要な栄養素が不足する |
これらを完全に避ける必要はありませんが、日常的に摂りすぎていないか意識しましょう。
骨にいい食べ物以外で骨を強くする方法|運動する習慣を付けよう
骨を強くするためには、食事だけでなく適度な運動や生活習慣の改善も欠かせません。
ここでは、骨を強くするために効果的な運動と生活習慣について解説します。
骨を強くする運動
骨に適度な負荷をかける運動が骨密度の維持・向上に効果的です。
| 運動の種類 | ポイント |
|---|---|
| ウォーキング・ジョギング | 1日30分程度、週に3〜5回を推奨 |
| 筋力トレーニング | スクワットや踵上げなど、下半身を中心とした運動が効果的 |
| 階段の上り下り | 日常生活の中で無理なく取り入れる |
いずれも無理は禁物です。最初は軽めに始めて、問題なければ徐々に負荷を増やしていきましょう。
骨を強くする生活習慣
運動以外にも、以下の生活習慣が骨の健康維持に重要です。
| 生活習慣 | 骨への効果 |
|---|---|
| 十分な睡眠 | 成長ホルモンは睡眠中に分泌され、骨の形成を促進します |
| 日光浴 | 1日15〜30分程度の日光浴で皮膚でビタミンDが生成されます |
| 禁煙 | 喫煙は骨密度を低下させ、骨折リスクを高めます |
とくに日光浴は食事だけでは不足しがちなビタミンDを体内で生成できるため、積極的に取り入れましょう。
骨を強くするには食事と生活習慣が重要!
骨を強くするためには、栄養素をバランスよく摂取し、適度な運動や日光浴を組み合わせることが大切です。
とくに中高年以降は骨密度が低下しやすいため、骨粗しょう症の予防のために食事や運動習慣を改善しましょう。
しかし、「すでに骨密度が大きく低下している」「生活習慣だけでは改善が追いつかない」といったケースでは、食事や運動に加えて医療によるアプローチが選択肢になる場合もあります。
リペアセルクリニックでは、骨や関節のお悩みに対して、再生医療による治療を提供しています。
詳しい治療内容や症例については、公式LINEで情報発信しておりますので、お気軽にご登録ください。

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師
あわせて読みたいトピックス
-

ジョーンズ骨折に効果的なテーピング方法|注意点や主な治療法について解説
-
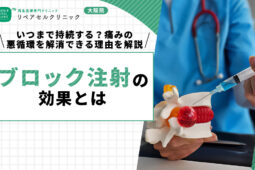
ブロック注射の効果とは|いつまで持続する?痛みの悪循環を解消できる理由について解説
-
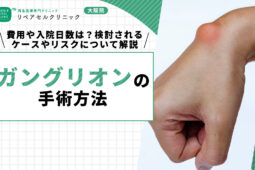
ガングリオンの手術方法|費用や入院日数は?検討されるケースやリスクについて解説
-
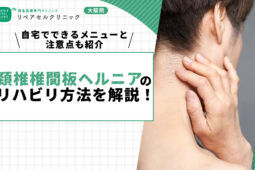
頚椎椎間板ヘルニアのリハビリ方法を解説!自宅でできるメニューと注意点も紹介
-
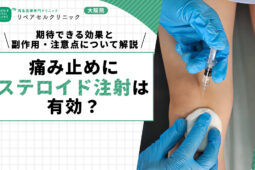
痛み止めにステロイド注射は有効?期待できる効果と副作用・注意点について解説
-
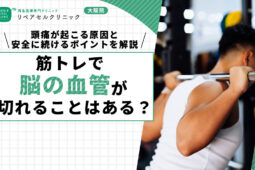
筋トレで脳の血管が切れることはある?頭痛が起こる原因と安全に続けるポイントを解説
-

セロトニン欠乏脳のセルフチェック方法を紹介!不足している人の特徴・症状と対策法も解説
-
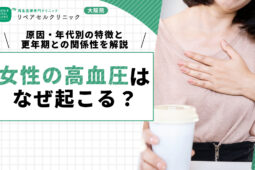
女性の高血圧はなぜ起こる?原因・年代別の特徴と更年期との関係性を解説
















