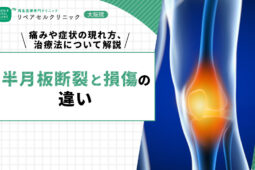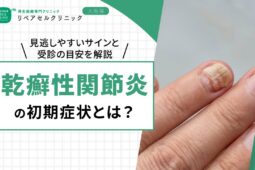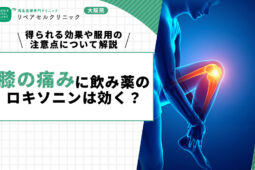- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
膝棚障害とは|どうやって治す?治し方や原因について詳しく解説【医師監修】
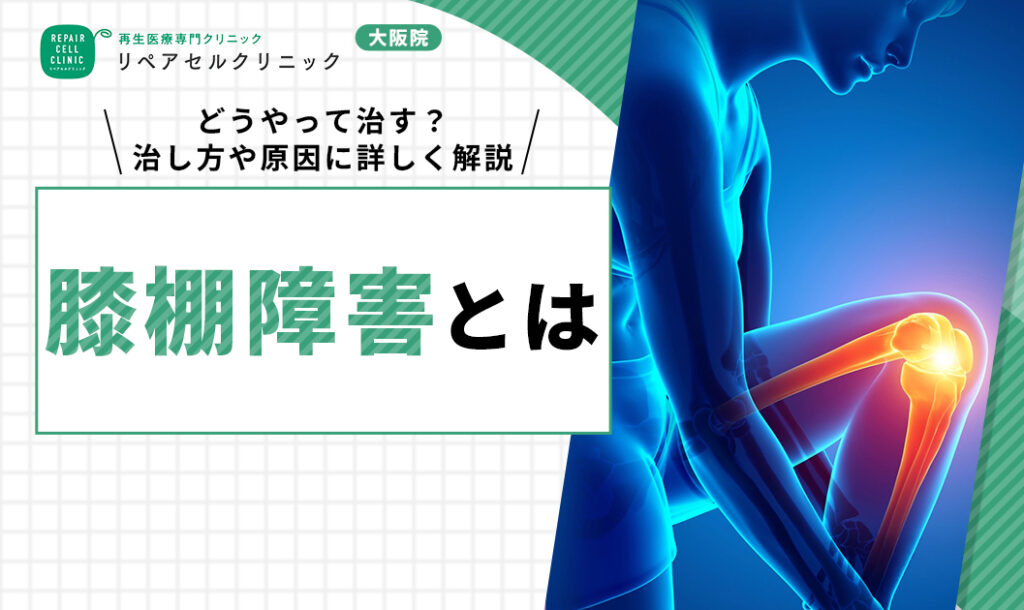
「棚障害はどんな病気?」
「棚障害を治すにはどんな治療法がある?」
膝棚障害(タナ障害)とは、膝関節の「骨膜ひだ」が炎症を起こす疾患です。
膝を曲げ伸ばしするときに痛みが出たり、「ポキポキ」と音が鳴ったりする棚障害の原因や治し方を知りたいという方も多いでしょう。
本記事では、膝棚障害の具体的な症状や原因、治療法までを詳しく解説します。
ご自身の膝の状態を理解し、適切な対処法を見つけるために、ぜひ参考にしてください。
また、長引く膝の痛みには、再生医療も選択肢の一つです。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、再生医療に関する情報を無料で配信しています。
「膝の痛みを早く治したい」という方は、合わせてご覧ください。
目次
膝棚障害(タナ障害)とはどのような病気?
膝棚障害(タナ障害)とは、膝関節を覆っている「滑膜ひだ」が炎症を起こし、痛みを引き起こす疾患です。
本章では、膝棚障害の主な症状や原因について解説します。
まずは、どのような症状が現れるのか、その原因は何か、そしてどう診断されるのかを詳しく解説します。
膝棚障害の主な症状
膝棚障害の主な症状は、以下のとおりです。
- 膝を曲げ伸ばししたときの痛み
- 引っかかり感(キャッチング)
- 動作時に「ポキポキ」「コキコキ」のような音が鳴る
炎症が起きている滑膜ひだが、膝の動きによって骨や軟骨に擦れたり挟まったりすることで、上記のような症状が現れます。
しかし、これらの症状は半月板損傷の初期症状でも見られるため、疑われる場合は医療機関を受診しましょう。
膝棚障害の主な原因
膝棚障害の主な原因は、以下のとおりです。
- スポーツなどによる使いすぎ
- 膝への直接的な打撃
ランニング、ジャンプ、水泳など膝の曲げ伸ばしを繰り返し行うスポーツでは、反復的な摩擦が滑膜ひだの炎症を招く可能性があります。
上記のような負担が継続的に加わることで滑膜ひだが刺激され、炎症を起こすと痛みが生じます。
膝棚障害の診断方法
膝棚障害の診断は、主に医師による診察(問診や触診)と、MRIなどの画像検査を組み合わせて行われます。
診断プロセスは、一般的に以下の流れで進められます。
【問診・触診】
- いつからどのような動作で痛むか、スポーツ歴などを確認
- 膝のお皿の内側など、痛みがある場所を押して確認(圧痛)
- 膝を動かして引っかかりやクリック音を再現するテスト
| 画像検査 | 詳細 |
|---|---|
| X線(レントゲン) | ・骨の異常(骨折や変形)がないかを確認する ・滑膜ひだそのものは写らない |
| MRI検査 | ・炎症を起こして厚くなった滑膜ひだや、関節内の水(関節水腫)の状態を確認する ・半月板や靭帯など、他の軟部組織の損傷がないかを確認するためにも用いる |
| 超音波(エコー)検査 | ・MRIと同様に、炎症を起こした滑膜ひだの状態を観察するために用いる |
上記のように症状や膝の状態から膝棚障害が疑われるかを確認し、他の疾患(半月板損傷や軟骨損傷など)との見極めを行います。
これらの検査結果を総合的に判断し、他の疾患の可能性を排除した上で、膝棚障害として診断されます。
膝棚障害(タナ障害)かどうかセルフチェック
ご自身の膝の痛みが膝棚障害によるものか、いくつかの症状を通じて確認する目安があります。
以下の項目に当てはまるものがないか、ご自身の膝の状態と照らし合わせてみてください。
- 膝のお皿(膝蓋骨)の内側を押すと痛みがある
- 階段の昇り降りなど膝の曲げ伸ばしをすると痛みがある
- 膝に引っかかり感がある
これらの項目に複数当てはまる場合、膝棚障害の可能性が考えられます。
ただし、これはあくまで簡易的なチェックであり、正確な診断は医療機関で受けることが前提です。
似た症状の半月板損傷など他の疾患との見極めも必要になるため、気になる点があれば専門医に相談しましょう。
膝棚障害(タナ障害)の治し方|手術しない保存療法
膝棚障害の治療は、まず炎症を抑え、痛みの原因となっている膝への負担を減らす「保存療法」が基本です。
具体的な保存療法には、以下のようなアプローチが組み合わせて用いられます。
手術を選択する前に、これらの方法で症状の改善を目指します。
具体的にどのような治療法があるのか、詳しく見ていきましょう。
安静
膝棚障害の保存療法において基本となるのは、膝を安静に保つことです。
スポーツ活動や膝の曲げ伸ばしを多用する動作を一時的に中断し、膝にかかる負担を減らします。
日常生活でも、階段を避けてエレベーターを使用するなど、膝に負担がかかる動きを避ける工夫が必要です。
炎症が鎮まるまでの間、膝を休ませることが回復への第一歩となります。
物理療法
物理療法は、温熱や電気刺激などを利用して、膝の痛みや炎症を和らげる治療法です。
患部を温めるホットパック(温熱療法)や超音波治療、低周波治療(電気刺激)などが用いられます。
これらのアプローチは、膝周辺の血流を促し、硬くなった筋肉の緊張をほぐすことで、痛みの軽減を図ります。
リハビリテーションと並行して行われることもあります。
薬物療法
薬物療法では、痛みや炎症を抑えるために、飲み薬や貼り薬、塗り薬などが用いられます。
主に「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」が処方されるのが一般的です。
これにより、滑膜ひだの炎症を鎮め、膝の痛みを軽減させる効果が期待できます。
症状が強い時期には、他の治療と組み合わせて活用されます。
関節内注射
関節内注射は、痛みが強い場合や、他の保存療法で改善しない場合に行われる治療法です。
主に、強力な抗炎症作用を持つステロイド剤や、関節の滑りを良くし軟骨を保護するヒアルロン酸ナトリウムなどが用いられます。
炎症を起こしている患部に注射することで、痛みを迅速に抑える効果が見込めます。
ただし、ステロイド注射は頻繁に行うと組織に影響を与える可能性もあるため、医師の判断のもと適切に行われます。
リハビリテーション
リハビリテーションは、痛みが落ち着いた後の再発予防や、膝への負担を根本から見直すために行われます。
膝棚障害は、太ももの筋肉(大腿四頭筋)や股関節周りの柔軟性低下が原因で、滑膜ひだが膝に挟まりやすくなっているケースが少なくありません。
リハビリテーションでは、主に以下の2点に取り組みます。
| リハビリテーション内容 | 目的 |
|---|---|
| ストレッチング | 太ももや股関節周りの筋肉の柔軟性を高め、膝がスムーズに動くようにする目的 |
| 筋力トレーニング | 膝関節を支える筋肉(特に大腿四頭筋の内側)を鍛え、膝の動きを安定させる目的 |
これらの運動を通じて、滑膜ひだが骨と擦れにくい身体の使い方を習得し、膝への負担を軽減させていきます。
膝棚障害(タナ障害)で手術が検討されるケース
膝棚障害の手術は、数ヶ月にわたる保存療法を続けても痛みが改善せず、日常生活やスポーツ活動に大きな支障が出ている場合に検討されます。
具体的には、以下のようなケースで手術が選択肢となります。
- 保存療法を3〜6ヶ月継続しても効果がない
- 膝の痛みで歩行や階段の昇り降りが困難
手術は関節鏡と呼ばれる細いカメラを用いて、炎症を起こして厚くなった滑膜ひだを切除するのが一般的です。
傷も小さく治療できるため、身体への負担は比較的小さいとされています。
しかし、術後のリハビリや手術リスクから、「できるだけ手術を避けたい」という方も少なくありません。
近年の治療では、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した組織の修復・再生を促す再生医療が注目されています。
手術や入院不要で治療を行えるため、早期復帰を目指したい方は、ぜひ再生医療をご検討ください。
膝棚障害(タナ障害)に関するよくある質問
膝棚障害と診断された方や、その疑いがある方からよく寄せられる質問にお答えします。
ここでは、以下の2つの質問について解説します。
それぞれの疑問について、詳しく見ていきましょう。
膝棚障害はストレッチで治る?
膝棚障害はストレッチだけで完治するわけではありません。
しかし、適切なストレッチを行うことで、症状の改善と再発予防において重要な役割を果たします。
膝棚障害の原因の一つとして、太ももの筋肉(大腿四頭筋)の柔軟性が低下していることで、膝のお皿の動きが悪くなり、滑膜ひだが挟まれやすくなることが挙げられます。
そのため、ストレッチによって太もも周りの筋肉の柔軟性を高めて、滑膜ひだが骨や軟骨と擦れることを減らすことが重要です。
治療中や痛みが引いた後のリハビリとして、継続的に行うと良いでしょう。
膝棚障害にサポーターは有効?
膝サポーターの活用は、膝棚障害の症状を和らげるうえで有効な場合があります。
サポーターの主な役割は、膝関節の安定性を高め、膝のお皿(膝蓋骨)の動きを適切にサポートすることです。
炎症が起きている時期にサポーターを装着すると、膝が不安定になるのを防ぎ、滑膜ひだへの不要な刺激を減らす助けになります。
また、運動を再開する際にも、膝への負担や不安感を軽減する効果が期待できるでしょう。
ただし、サポーターはあくまで補助的なものであり、炎症そのものを治すわけではないため、他の治療と組み合わせて使用することが大切です。
膝棚障害(タナ障害)を治すには再生医療も選択肢の一つ
膝棚障害(タナ障害)は、膝関節の内部にある滑膜ひだが炎症を起こし、痛みや引っかかり感を引き起こす疾患です。
治療は、まず安静を保ち、ストレッチなどのリハビリテーション、薬物療法、関節内注射といった「保存療法」で炎症を鎮めるのが基本となります。
多くの場合、これらの保存療法で症状の改善が期待できるでしょう。
しかし、数ヶ月にわたり保存療法を続けても痛みが改善しない場合や、日常生活への支障が続く場合には、関節鏡を使った滑膜ひだの切除手術が検討されます。
近年の治療では、従来の手術や保存療法に加え、手術を避けたい方や、なかなか改善しない方のためのアプローチとして「再生医療」という選択肢も注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した組織の修復・再生を促す医療技術です。
長引く膝の痛みを治したい方は、ぜひ再生医療専門クリニックである当院(リペアセルクリニック)にご相談ください。
>当院の再生医療による膝関節の症例はこちら

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設