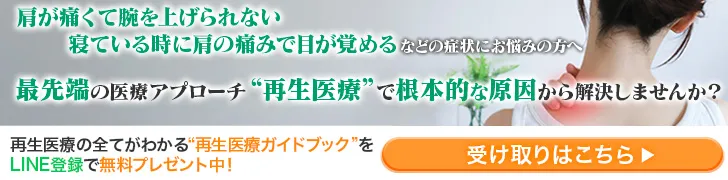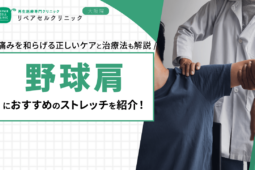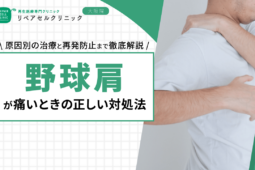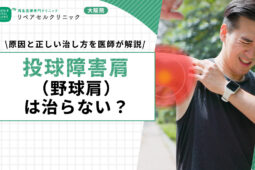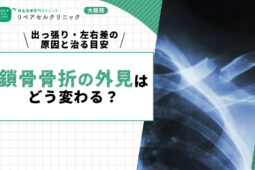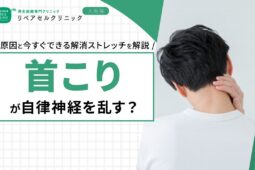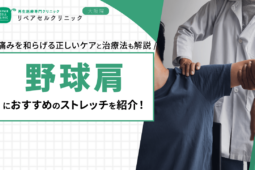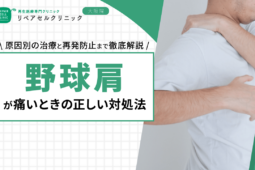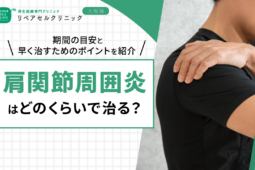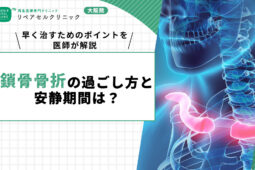- 肩
野球肩に適応される手術療法|費用の目安や競技復帰までの流れについて解説

野球肩(投球障害肩)は、投球動作の繰り返しによって肩関節に過剰な負荷がかかり、痛みが生じる障害です。
野球肩の症状が発生して、リハビリテーションなど保存療法でも改善が見られない場合、手術を行う必要があります。
この記事では手術の症例や回復するまでの期間、費用の目安などを紹介しますので、参考にしてください。
また、野球肩の手術以外での治療方法も紹介します。手術を避けたい方も本記事をご覧ください。
目次
野球肩に適応される手術の種類
野球肩の手術方法は以下の通りです。
損傷や炎症の程度によって、適した手術方法が選択されます。
それぞれの手術方法を解説していきますので、参考にしてください。
関節鏡手術|低侵襲で回復が早い
関節鏡手術は、関節鏡で肩関節の内部を観察し、損傷部位を特定して組織の除去や修復を行う手術療法です。
小さな切開からカメラや器具を挿入し、モニターを見ながら手術を行うのが一般的です。
野球肩の主な症状として、肩の痛みや可動域の制限や肩の不安定感(外れそうな感覚)がありますが、関節鏡手術は傷が小さいため、体への負担も少なく早期の回復が期待できます。
ただし、手術後は安静にする必要があり、医師の指導のもと適切なリハビリテーションを行うことが重要です。
直視下手術|重度症例に適した手術
直視下手術は、関節鏡手術では対応が難しい重症度が高い場合に検討される手術方法で、肩関節を大きく切開して手術が行われます。
関節鏡手術と比べて皮膚切開が大きく、また身体への負担が大きいため、肩の不安定性が大きい場合(繰り返し脱臼する状態)や骨移植を伴うような、重度で複雑なケース・骨の処置が必要な場合に検討されます。
筋肉などの軟部組織への侵襲が大きい傾向があり、術後の痛みや回復に時間がかかる可能性があるため、直視下手術をする場合は専門医とよく相談するようにしましょう。
手術後は過度な運動を避け、装具などで安定した状態を保ち、医師の指導のもとリハビリテーションを行います。
野球肩の手術にかかる費用目安
野球肩の手術にかかる費用の目安は以下の通りです。
| 手術名 | 適応病名 | 入院期間 | 概算費用 |
| 関節鏡下腱板断裂手術 | 肩腱板断裂 | 5~6日間 | 25~39万円 |
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | 肩関節脱臼、反復性肩関節脱臼 | 4日間 | 22~34万円 |
| 関節鏡下関節授動術 | 肩関節拘縮 | 4日間 | 15~23万円 |
上記の入院期間や費用はあくまでも目安のため、医療機関によって異なる場合もあります。
野球肩が治る期間は?手術後から競技復帰まで流れ
野球肩には、腱板損傷、肩関節唇損傷(SLAP損傷)、インピンジメント症候群など複数の病態があります。
本章では、これらの手術治療後の一般的な復帰の流れを解説します。ただし、具体的な期間は病態や手術方法により異なります。
手術後の競技復帰までの期間には個人差もありますが、1年ほどかかるケースもあります。
術後数週間~3カ月
手術直後は痛みや炎症があるため、手術内容に応じて適切な期間は安静にします。
術後の固定期間が終了したら、肩の可動域を徐々に広げるトレーニングや、段階的に筋力を戻していくためのトレーニングが行われます。
リハビリを始めるタイミングや運動の強度については、医師の指示に従い無理のない範囲で行ってください。
過度に安静にしすぎると肩関節が拘縮(固まる)する恐れがありますが、一方で早すぎるリハビリ開始は修復組織を損傷するリスクがあります。
特に肩に負担のかかる動作や競技復帰のためのリハビリは、回復状態を見ながら慎重に判断しましょう。
術後3カ月~6カ月
術後3カ月~6カ月ほど経過すると多くの場合、肩の力や関節可動域がある程度戻り、日常動作での痛みが軽減します。
この期間では医師の許可を得て段階的に仕事やスポーツに復帰できます。ただし、完全にスポーツに復帰するのは一般的に6カ月以降になるケースが多いです。
リハビリを怠ると肩が固まって可動域が戻らなくなる可能性があるため、可動域拡大のトレーニングを継続する必要があります。
また、過度な負荷をかけると再断裂するリスクがあるので、無理な動きをしないよう注意してください。
術後6カ月~1年
術後6カ月~1年では、適切なリハビリを継続することで、肩関節の可動域はほぼ正常範囲まで改善します。
この期間になると競技に必要な筋力トレーニングや運動機能の改善など、競技復帰に向けたリハビリメニューが行われます。
野球肩の手術から1年経過すると、本格的に競技に復帰できる可能性が高いです。
ただし、回復の早さには個人差があるほか、投球など肩を酷使する動作が多い場合にはさらに時間がかかるケースがあります。
野球肩の手術以外の治し方
野球肩は手術での治療が行われるケースが多いですが、手術以外での治し方を紹介します。
それぞれの治療法について、特徴などを詳しく説明します。
保存療法
保存療法は、主に初期の野球肩の方に適応される、手術を伴わない治療法です。
患部に負担をかけないように安静にし、薬物療法や理学療法を用いて症状の改善、または軽減を図ります。
痛みが強いときは、炎症を抑制するために抗炎症薬やステロイド注射が行われるケースもありますが、間隔を空ける必要があったり、回数に制限があったりします。
また、保存療法は対症療法となるため、野球肩の根本的な改善にはいたらない点に注意しましょう。
再生医療
野球肩からスポーツへの早期復帰を目指す方には、メジャーリーガーの⼤⾕翔平選手も受けた「再生医療」という選択肢があります。
再生医療とは、患者さま自身から採取した幹細胞や血小板を活用し、損傷した組織の再生・修復を促す治療法のことです。
自己細胞のみを用いるため、アレルギー反応や拒絶反応などの副作用リスクの心配も少ないことが特徴です。
以下ページでは、再生医療によって手術しても治らなかった肩関節の痛みや可動域制限が改善した症例を紹介しているため、併せてご覧ください。
>再生医療によって肩関節の痛みや可動域制限が改善した症例(40代男性)はこちら
野球肩の治療に悩んでいる方で、身体への負担を軽くしたい方や早期復帰を目指される方は、リペアセルクリニックまでご相談ください。
野球肩の手術についてよくある質問
野球肩の手術を検討している患者さまからの、よくある質問にお答えします。
野球で肩を壊した場合の、手術の必要性などについて解説します。
野球で肩を壊したら手術は必要?
野球で肩を壊した場合、保存療法で症状が改善されるなら手術は必須ではありません。
しかし、保存療法を行っても痛みや炎症が緩和されないケースや、靭帯や腱の損傷が重度のケースでは手術が必要です。
手術を行うか否かについては、医師と相談のうえ慎重に決定しましょう。
野球肩がなかなか治らない理由は?
野球肩がなかなか治らない理由として、以下のような原因が挙げられます。
- 適切な安静期間を設けていない
- 不適切なフォームで肩に過度な負荷がかかっている
- 肩周辺の筋力や柔軟性が不足している
- 疲労が蓄積されて回復できていない
野球肩による痛みが強いときは、専門医と相談したうえで適切な安静期間を設けることが大切です。
リハビリが始まったら、肩周辺の筋力や柔軟性を向上させましょう。
競技復帰に向けたリハビリでは、肩に負荷のかかりやすい不適切なフォームを改善することも重要です。
野球肩からの早期回復を目指すなら再生医療をご検討ください
野球肩の手術には主に2種類あり、傷が小さい場合は関節鏡手術、腱板断裂など重症度が高い場合は直視下手術が行われます。
手術後は、治療からリハビリテーションを経て競技復帰まで、一般的に6カ月から1年程度の期間を要します。
早期治療、復帰を目指す方には、患者さま自身から採取した幹細胞や血小板を活用し、損傷した組織の再生・修復を促す治療法のことです。
再生医療では入院や手術を必要とせず、早期にリハビリへ移行できます。
以前のようなパフォーマンスを早期に取り戻したい方や、手術後に思ったように回復せず別の手段を考えている方は、当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設