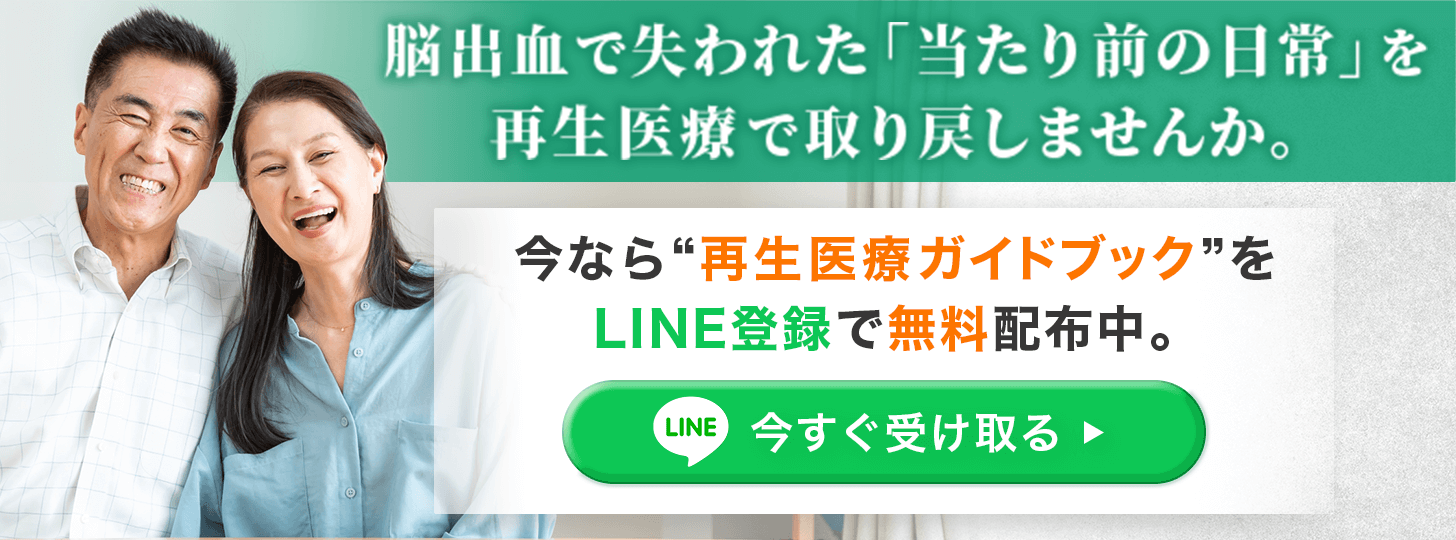- 脳卒中
- 頭部
- 脳出血
- 再生治療
脳幹出血の主な後遺症|効果的なリハビリテーションや治療法について解説【医師監修】

「脳幹出血の後遺症や、効果的なリハビリについて知りたい」
ご家族が脳幹出血を発症された方は、これからの治療や生活について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
脳幹出血の後遺症は、早期からのリハビリ開始と継続によって改善の可能性があります。
この記事では、脳幹出血の主な後遺症とその症状、治療・リハビリ方法について詳しく解説します。
近年の治療では、脳幹出血による後遺症の改善を目指す「再生医療」が注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した脳細胞を再生・修復を促す治療法です。
当院リペアセルクリニックでは、再生医療の治療法や適応症例について無料カウンセリングを実施しているため、ぜひご相談ください。
目次
脳幹出血の主な後遺症
出血した部位によって後遺症の症状は変わりますが、脳幹出血の後遺症は主に以下の5つがあります。
それぞれの後遺症の詳しい症状について解説します。
運動・感覚障害
運動・感覚麻痺の症状は以下のように分類されます。
- 不全麻痺(運動機能や感覚機能が完全に失われず、手足の動きが少し残る)
- 完全麻痺(自分の意志で手足をまったく動かせない状態)
- 弛緩性麻痺(筋肉の緊張が低下して力が入らない状態)
- 痙性麻痺(筋肉が硬く緊張した状態で、スムーズに動かせない)
- 痛覚の低下または過敏(痛みを感じにくい、あるいはわずかな刺激でも痛みを感じる)
- 温度感覚の低下(熱い・冷たいの区別がつきにくい)
- 深部感覚の低下(体の動きや位置の認識が難しい)
- しびれ、ふるえ
脳幹出血で運動障害が起こる理由は、出血によって脳の運動を制御する神経細胞や神経回路(主に錐体路)が損傷・圧迫されて、脳からの指令が筋肉に伝わりにくくなるからです。
また、しびれや感覚障害は脳幹内を通過する感覚神経路(内側毛帯など)の損傷が原因で発生します。
脳幹は左右の神経経路が近接して走行しているため、出血の範囲によっては両側の手足に後遺症が現れる可能性があります。
言語・嚥下障害
言語障害は、舌や口唇、声帯の動きに異常が生じる後遺症です。
また、嚥下障害は飲食物を飲み込む動作に異常が生じます。
- はっきり発音できなくなる(ろれつが回らない)
- 声がかすれやすくなる
- 声の大きさをコントロールしにくくなる
- 言葉に抑揚がなくなる
- 食事中にむせる・咳をする頻度が増える
- 食事に時間がかかるようになる
- よだれが増える
脳幹出血後の言語障害では、ろれつが回らない(構音障害)といった症状が起こる可能性があります。
出血した部位によって後遺症は異なりますが、脳幹の一部である「橋」や、脳からの指令を筋肉に伝える役割を持つ神経線維(錐体路)などが損傷すると構音障害が発生します。
また、嚥下障害は嚥下をコントロールする舌咽神経や迷走神経が損傷することによって引き起こされます。
嚥下に関する神経は脳幹に集中しているため、脳幹出血の後遺症で嚥下障害を発症する患者さまが多いです。
嚥下機能の低下によって誤嚥のリスクが高まり、誤嚥を繰り返すと誤嚥性肺炎になる可能性があります。
視覚障害
脳幹出血により、視覚障害が起きる可能性があります。目の見え方に異常をきたすほか、まぶたも影響を受ける可能性があるのです。
- 眼球運動障害
- 眼瞼下垂(まぶたが垂れ下がってくる)
眼球運動障害は、眼球を動かす神経が損傷することによって起こる後遺症です。
具体的な症状として、物が二重に見える(複視)や、眼振(自分の意志とは関係なく眼球が左右に揺れる)などの症状があります。
他にも、片方の目だけ動かない、視界が揺れてしまうなど、症状は多岐にわたります。
視覚障害は、歩行や読書などの日常生活に大きな影響を及ぼすため、早期のリハビリ開始が重要です。
意識障害
脳幹出血の後遺症として、意識障害を発症するケースがあります。
脳幹は意識の中枢を担っているため重篤化しやすく、症状が重い場合は昏睡状態や回復不能な状態になってしまう可能性があります。
神経の損傷が重度だと回復が難しく、何らかの症状が残ってしまう可能性が否定できません。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、脳幹の損傷によって日常生活や社会生活に大きな影響を与える後遺症です。
主な症状は、以下の通りです。
- 記憶障害(新しいことが覚えられない)
- 注意障害(集中力の低下、注意が散漫になる)
- 社会的行動障害(感情のコントロールが難しい)
- 遂行機能障害(計画を立てて行動するのが難しい)
- 意欲が低下する
高次脳機能障害は、出血が広範囲に及ぶ場合は、麻痺や意識障害と複合的に発症する可能性があります。
高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため「見えない障害」とも呼ばれます。
本人が気付きにくいからこそ、家族や周囲の人の理解が必要です。
脳幹出血の後遺症に対するリハビリテーションと治療法
脳幹出血は重篤な症状を引き起こす疾患であり、後遺症の回復には適切な治療とリハビリテーションが欠かせません。
治療とリハビリは病期によって大きく内容が変わります。
脳幹出血の後遺症に対するアプローチは、上記の3段階に分けて行われ、それぞれの段階で必要な治療とリハビリ方法が選択されます。
急性期のリハビリテーションと治療
発症から約2週間〜1カ月程度の急性期は、命を守り、状態を安定させることが最優先される時期です。
急性期の治療は主に次のように行われます。
| 治療方法 | 内容 |
|---|---|
| 降圧療法 | 出血の拡大を防ぐため血圧を適切にコントロール |
| 脳浮腫治療 | マンニトールやグリセオールなど薬剤を用いて脳浮腫(脳の腫れ)を軽減 |
| ドレナージ手術 | 水頭症が見られる場合にチューブで脳脊髄液を体外に排出 |
| 人工呼吸器管理 | 呼吸機能低下時に実施 |
| 気管切開 | 長期的な呼吸管理が必要な場合に実施 |
脳幹出血は他の脳出血と異なり、手術の負担が大きいという理由から血腫除去手術はあまり適応されません。
治療の主な目的は出血の拡大防止と全身状態の安定化です。
急性期には、全身状態に注意した上で以下のリハビリが実施されます
- ベッドでの関節可動域訓練
- 早期離床訓練(座位訓練)
- 嚥下機能評価と訓練
- 呼吸リハビリ
- 基本動作訓練
急性期のリハビリは、可能な限り早期から開始することが推奨されています。長期間のベッド上安静は筋力低下や関節拘縮、褥瘡などの二次的合併症のリスクを高めるためです。
ただし、脳幹出血の場合は他の脳血管疾患よりも安静度が高く設定されることが多いため、医師の判断のもとで状態に合わせた適切なリハビリを進めていきます。
回復期のリハビリテーションと治療
回復期(発症後約3~6カ月)は、失われた機能の回復に集中的に取り組む時期です。
急性期を過ぎても症状や後遺症に応じて以下のような治療が行われます。
| 治療方法 | 内容 |
|---|---|
| 薬物療法 | 痙縮に対する筋弛緩薬の投与 |
| ボツリヌス療法 | 強い痙縮に対しボツリヌス毒素を注射し筋緊張を緩和 |
| ITB療法 | 重度痙縮に対しバクロフェンを脊髄腔内に持続投与 |
| 電気刺激療法 | 筋肉に電気刺激を与え運動機能回復を促進 |
回復期ではとくに痙縮(けいしゅく)と呼ばれる手足の筋肉が緊張して突っ張る症状に対する治療が重要です。
回復期には、症状や後遺症に応じて以下のリハビリが実施されます。
- 歩行訓練
- ADL(日常生活動作)訓練
- 上肢機能訓練
- 高次脳機能障害へのアプローチ
- 嚥下・構音訓練
- 筋力増強訓練
脳幹出血患者の場合、リハビリ専門病院への入院期間は150日間(高次脳機能障害を伴う場合は180日間)までと決まっています。
この時期は機能回復が期待できる時期であり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など多職種によるリハビリが行われます。
維持期のリハビリテーションと治療
維持期(発症後6カ月以降)は、回復した機能の維持と、残された症状に適応した生活の再構築を目指す時期です。
維持期には、以下の治療が行われます。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 継続的な薬物療法 | 痙縮、高血圧、脳卒中再発予防のための薬物治療 |
| 定期的な検査 | 合併症の早期発見のための検査(血液検査やCT・MRIなど) |
| 再発予防治療 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患管理 |
| 二次的合併症対応 | 関節拘縮、排尿障害、うつなどへの治療 |
| 補助具・福祉機器の処方 | 日常生活の自立度を高めるための支援機器提供と調整 |
維持期の治療では再発予防がとくに重要です。脳幹出血は再発すると症状がさらに重篤化することが多いため、基礎疾患の管理と定期的な健康チェックが欠かせません。
また、維持期には、以下のリハビリが実施されます。
- 外来リハビリテーション
- 訪問リハビリテーション
- デイケア・デイサービスでのリハビリ
- 自主トレーニング
- 環境調整と生活支援
維持期のリハビリは在宅で行われることが一般的で、介護保険サービスを活用しながら継続的に実施します。
リハビリを継続することで生活の質を向上させることができます。
脳幹出血の後遺症に関してよくある質問
脳幹出血の後遺症に関してよくある質問を紹介します。
それぞれ詳しくみていきましょう。
脳幹出血の後遺症から回復する見込みはある?
脳幹出血の後遺症からの回復見込みは、出血の重症度によって大きく異なります。
軽度から中程度の場合は回復が期待できることもありますが、重度の場合は回復が難しい可能性が高いです。
調査では、脳幹出血患者の※約6.1%が良好な回復、25.4%が中〜重度の障害を残すという結果が報告されています。
※参考:PubMed|Five-year survival-after first-ever stroke
発症時の意識レベルや出血量が大きな予後因子となります。
脳出血で後遺症になったら余命はどのくらい?
脳幹出血に限らず脳出血で後遺症が残った場合の余命については、研究データによると、脳内出血全体の10年生存率は※約24%とされています。
※参考:AHAJIA JOURNALS|Incidence and 10-Year Survival of Intracerebral Hemorrhage in a Population-Based Registry
具体的には、深部出血で31.6%、脳葉出血で23.8%、後頭蓋窩(脳幹や小脳を含む部位)出血では34.3%の10年生存率が報告されています。
脳幹出血の前兆・サインはある?
脳幹出血の発症前に現れる前兆やサインとして、主に以下の症状が挙げられます。
- 突然の激しいめまい
- 大きないびき
- 視覚の異常(視野が狭くなる・二重に見えるなど)
以上の症状を感じた場合は、早急に医療機関を受診することが重要です。
脳幹出血の後遺症にお悩みの方は再生医療をご検討ください
脳幹出血は運動麻痺や高次脳機能障害などの日常生活に大きな影響を与える後遺症が出ることがあり、生活の質が著しく下がる可能性が否定できません。
しかし、脳幹出血の後遺症は、早期から適切なリハビリテーションを継続することによって改善される可能性があります。
また、近年の脳幹出血の後遺症治療には、損傷した脳細胞の再生・修復を促す「再生医療」も選択肢の一つです。
再生医療は患者さまご自身の細胞を利用するため、拒否反応などの副作用リスクが少なく、リハビリ期間の短縮や後遺症の改善・緩和が期待できます。
以下の動画では、実際に再生医療の治療を受け、脳出血(脳卒中)による後遺症が改善した患者さまの症例を紹介しているため、併せて参考にしてください。
また、当院「リペアセルクリニック」では、脳幹出血の後遺症に対する再生医療について無料カウンセリングを実施しています。
脳幹出血の後遺症でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
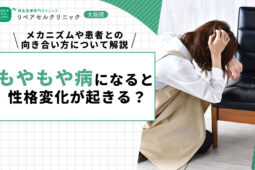
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介