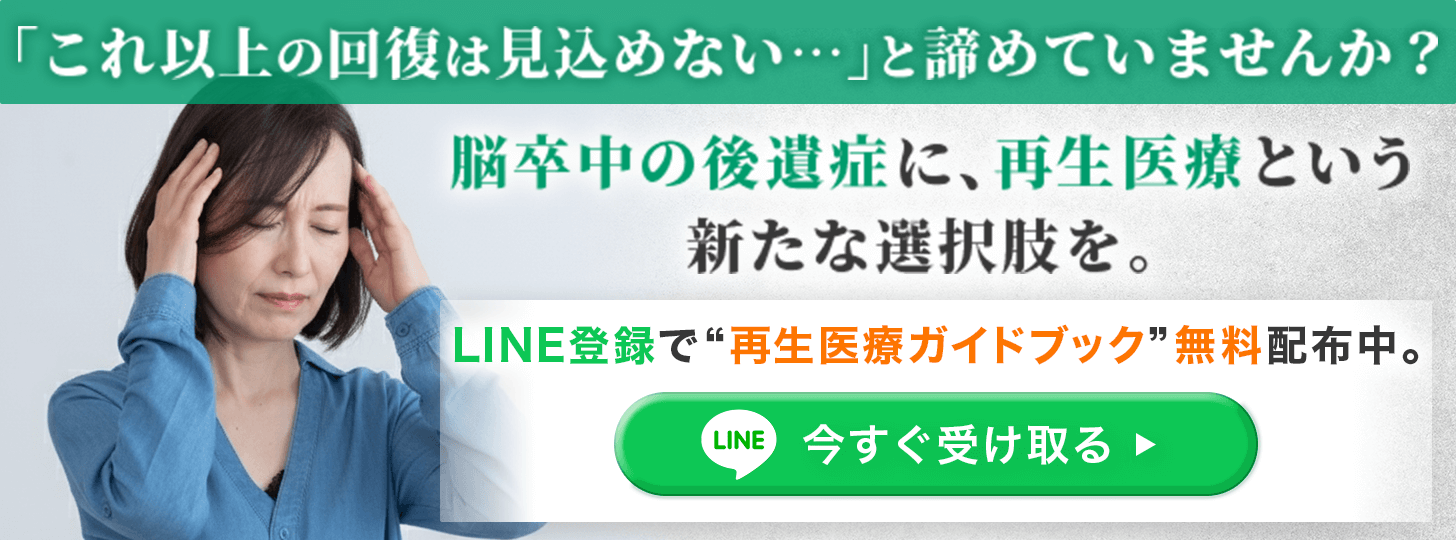- 脳卒中
- 頭部
高次脳機能障害は治る?回復過程やリハビリ方法、治療法を解説【医師監修】
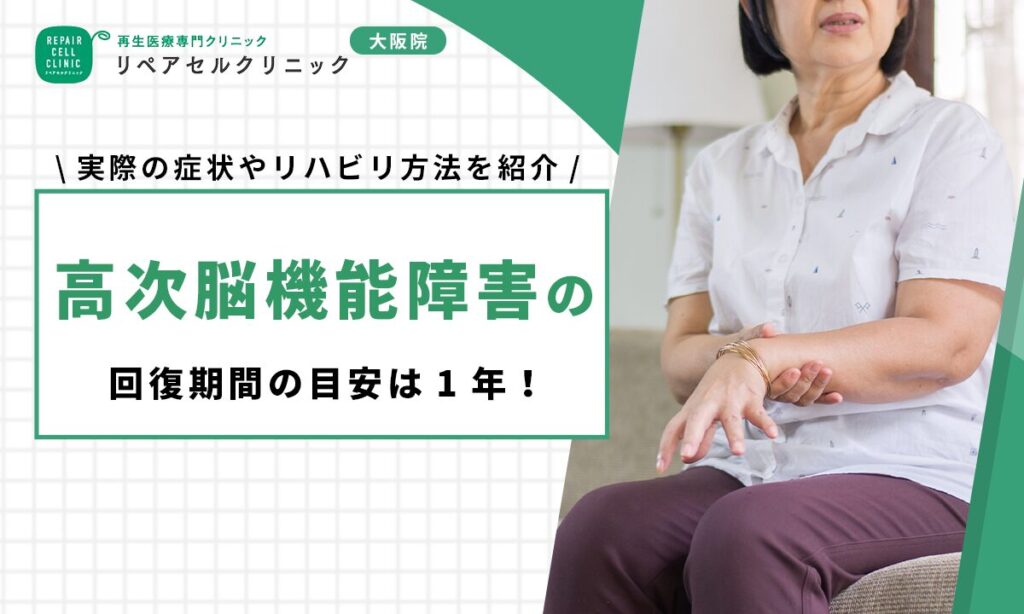
「高次脳機能障害は治るか知りたい」と不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
高次脳機能障害とは、脳の一部がダメージを受けたことで思うような行動が取れなくなったり、注意力や記憶力に問題が生じたりする脳卒中の後遺症の一つです。
高次脳機能障害は完治が難しいと考えられていますが、リハビリを受けることで症状の緩和・改善が見込めます。
この記事では、高次脳機能障害の回復過程やリハビリ方法について解説しています。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、高次脳機能障害が改善された患者様の症例を紹介しています。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでも、脳卒中の治療として注目されている再生医療に関する内容や症例を公開中ですので、併せて参考にしてください。
目次
高次脳機能障害が治る見込みはある?
高次脳機能障害はリハビリを継続することで改善の見込みがあります。
脳は損傷を受けても残っている神経の働きを活用したり、新しい神経経路を作り出したりする可塑性(かそせい)と呼ばれる力があります。
そのため、早期に適切なリハビリを始め、継続的に取り組むことが重要です。
ただし、リハビリの効果があらわれるスピードや程度は個人差があります。
症状が軽度の方は比較的早く改善が見られることもありますが、重度の場合は回復に時間がかかることもあります。
専門医と相談しながら、患者さまに合ったリハビリを継続しましょう。
高次脳機能障害の回復過程|期間は1年が目安
高次脳機能障害とは、脳の損傷により記憶力・注意力・思考力・言語能力・感情などに障害が起こる後遺症です。
主な原因は脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)や、交通事故による頭部の外傷とされています。
高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、周囲の方や患者さまも障害に気づきにくいのが特徴です。
適切なリハビリを受けると、症状が回復する可能性があります。
この項目では、高次脳機能障害の具体的な回復期間について解説します。
リハビリ後1年で約97%の方に改善がみられる
高次脳機能障害のリハビリを受けた方のうち、症状の改善がみられた割合は以下の通りです。※
※出典:高次脳機能障害者支援の手引き(改訂第2版)
- 発症から半年:74%
- 発症から1年:97%
高次脳機能障害は、発症早期に適切な訓練を受けるのが重要です。
多様な種類のリハビリがあるので医療機関や福祉施設など、さまざまなサービスと連携して行います。
リハビリの効果には個人差がありますが、合計1年を目安とした訓練を受けるのが望ましいです。
回復には発症から早期のリハビリ開始が重要
高次脳機能障害は、発症からリハビリ開始までの期間が短いほど、改善に期待ができます。
発症からリハビリ開始までの期間別に、症状が改善した患者の割合をまとめました。※
※出典:平成13年度高次脳機能障害支援モデル事業年次報告 (北海道・札幌市)
- 発症から6カ月以内に訓練開始:46%が改善
- 6か月から1年以内に訓練開始:32%が改善
- 1年以上経ってから訓練開始:14%が改善
高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、患者さま本人やご家族も障害に気づかない場合や気付くのが遅れる場合もあります。
上記のデータでは、発症から時間が経ってしまうと十分な効果を得にくい傾向があることがわかります。
リハビリは医療機関やリハビリテーションセンターで受けられるので、心配な方は受診を検討してください。
【症状別】高次脳機能障害のリハビリ方法
高次脳機能障害のリハビリは、主に病院や診療所などで行います。
以下では、高次脳機能障害の症状とリハビリの内容をまとめました。
一つずつみていきましょう。
記憶障害のリハビリ方法
高次脳機能障害の症状の一つに記憶障害があります。
記憶障害とは、新しい情報を覚えにくくなったり、過去の出来事や約束を忘れやすくなったりする状態※を指します。
※出典「:医学的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター」
また、新しいことを覚えるのに時間がかかることも少なくありません。
記憶障害のリハビリでは、どの種類の記憶に問題があるのか、どの程度の期間情報を保持できるのかを確認しながら個々に合った訓練を行うことが重要です。
具体的なリハビリ方法は、主に以下の2つに分けられます。
| リハビリ方法 | 内容 |
|---|---|
| 内的記憶戦略法 |
|
| 外的補助手段 |
|
いずれの方法も、訓練を繰り返し行います。
また、思い出しやすい環境を整えることも効果的です。
ご家族が声かけやメモの補助を行うことで、リハビリの効果をさらに高められます。
注意障害のリハビリ方法
高次脳機能障害の症状の一つに注意障害があります。
注意障害とは物事に集中する力が低下したり、周囲の状況をうまく判断できなかったりする状態※です。
※出典:「医学的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター」
たとえば、長時間の作業が続かず途中で止めてしまったり、複数の作業を同時にこなすのが難しかったりする場合があります。
注意障害のリハビリでは、集中しやすい環境を整えることが大切です。
具体的には、個室や静かな場所で決まった支援者と一緒に訓練を行うことで、注意力を高めやすくなります。
また、課題は簡単なものから少しずつステップアップしていくことが効果的です。
主なリハビリの内容は、以下の通りです。
- パズル
- まちがい探し
- 教育関連のテキスト
- 電卓の計算
- 校正作業
- 辞書調べ
- 入力作業
訓練を繰り返すと注意を持続させる力が徐々に改善され、日常生活や仕事でのミス軽減につながります。
ご家族がそばで声かけや環境の調整を行うことも、リハビリの効果を高めるポイントです。
遂行機能障害のリハビリ方法
高次脳機能障害の一つに遂行機能障害があります。
遂行機能は物事を計画・段取りする力で、障害があると予定に遅れやすくなったり、作業を途中でやめたりします。※
※出典:「医学的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター」
記憶障害や注意障害が影響している場合もあり、どの能力に問題があるのかを見極めることが重要です。
遂行機能障害のリハビリでは日常生活や作業に近い課題を通して、計画性や行動の管理能力を段階的に訓練します。
個々の特性に応じて、習慣化しやすい方法を取り入れることもポイントです。
主なリハビリの内容は、以下の通りです。
- 日常生活で必要な動作や作業を繰り返し行って習慣化し、手順を体で覚える
- 作業やスケジュールの順序を支援者と一緒に考え、段取りの立て方や優先順位を身につける
- ワークブックや組み立てキットなどマニュアルに沿って作業を行い、計画性の改善と作業の安定につなげる
リハビリを繰り返すことで、遂行機能障害の影響を受けにくい生活の習慣や作業手順を作れます。
ご家族が日常生活で声かけや作業の補助を行うと、より効果的にリハビリを進められます。
社会的行動障害のリハビリ方法
高次脳機能障害の一つに社会的行動障害があります。
社会的行動障害は欲求や感情のコントロールが難しくなり、他者との関わりで問題が生じやすくなる症状※です。
※出典:「医学的リハビリテーションプログラム | 国立障害者リハビリテーションセンター」
たとえば、興奮して大声を出したり、自傷行為に至ったり、自分中心の行動で満足感を得ようとしたりする場合があります。
社会的行動障害のリハビリでは、まず刺激の少ない静かな環境を整えることが重要です。
どのような状況やきっかけで症状が現れるのかを把握し、患者さまと一緒に対処法を考えていきます。
主なリハビリの内容は、以下の通りです。
- 症状が出やすい場面や行動のパターンを観察し、どの刺激が問題を引き起こすかを整理する
- 落ち着く方法や感情の切り替え方、声かけや環境調整など、症状が出たときに取る対応を練習する
- 簡単なゲームやロールプレイを通じて他者との関わり方やマナーを学ぶ
リハビリを繰り返すことで感情や行動のコントロールが少しずつ身につき、日常生活や人間関係の安定につながります。
ご家族の理解や支援も、リハビリ効果を高める大切なポイントです。
高次脳機能障害へ家族ができる接し方と対応方法
高次脳機能障害のある方を支える際、ご家族の関わり方は回復や日常生活の安定に大きく影響します。
接し方や対応方法を知ることで、本人もご家族も負担を軽くしながら生活しやすくなります。
症状を理解する
高次脳機能障害に対応する際は、まず症状を正しく理解することが大切です。
症状の現れ方は患者さまによって異なり、たとえば物事をすぐに忘れてしまう、集中が続かない、決められた行動がとれない、感情の起伏が激しいなど多岐に渡るためです。
対応の基本的な考え方は、以下の通りです。
- どのようなときに問題が現れるのか観察する
- 問題が現れた際の状況を整理する(時間や場所、相手、話題など)
- 整理した状況を元に、単純な対策を立てて実行する(人の多い場所を避ける、手帳やメモなどの補助ツールを活用する)
※出典:厚生労働科学研究「障害福祉サービス等事業者向け高次脳機能障害支援マニュアル」
高次脳機能障害の方自身も感情のコントロールが難しい場合があるため、ご家族が症状を把握しておくことで無用な摩擦を避けられます。
症状を理解できれば、患者さまもご家族も余計なストレスを減らせ、日常生活のサポートがよりスムーズになります。
生活環境を整備する
高次脳機能障害のある方を支える上で、生活環境の整備は有効な対処法です。
環境を工夫できれば日常生活のしやすさが増し、症状の悪化を防ぎ改善を助ける可能性があります。
環境整備の具体例は、以下の通りです。
| 症状 | 環境整備の具体例 |
|---|---|
| 作業のミスが多い | 作業後のチェック方法を話し合って決める |
| 外出のたびに家の鍵が見つからない | 鍵の保管場所を決める |
| 家電の操作方法が覚えられない | 操作方法の図や写真を家電の近くに貼る |
| 浴室に入っても体を洗わずに座っている | 最初の動作を補助する |
| ギャンブルにお金を使い込む | 不安や他の問題の回避のためにギャンブルに依存している可能性があるため、代替え方法を探してみる |
※出典:厚生労働科学研究「障害福祉サービス等事業者向け高次脳機能障害支援マニュアル」
上記の工夫により本人は安心して生活でき、ご家族もサポートしやすくなります。
専門機関の利用を検討する
高次脳機能障害の症状に長期的に対応するために、医療や介護・福祉の専門サービスを活用しましょう。
主な障害福祉サービスの一例は、下記の通りです。
| 障害者福祉サービス | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練(生活訓練) | 通所や自宅の訪問、施設での宿泊などを通じて日常生活に必要な能力を高めるための支援を行う |
| 共同生活援助(グループホーム) | 少人数での共同生活にて孤立の防止や身体・精神状態の安定を目指す |
| 施設入所支援 | 施設に入所した方に入浴や食事の介護、日常生活の支援を行う |
※出典:厚生労働科学研究「障害福祉サービス等事業者向け高次脳機能障害支援マニュアル」
また、高次脳機能障害の方が受けられる支援の一例は、下記の通りです。
- 身体障害者手帳を取得すると、医療費の自己負担が軽くなったり、公共料金が割引かれたりする
- 介護保険を利用して訪問介護やヘルパーサービスを受け、本人やサポートするご家族の負担を軽減する
- 医療機関やリハビリ施設では、症状に応じたリハビリプログラムを提供してもらえる
患者さまとご家族が安心して生活するために、制度やサービスを上手に活用しましょう。
高次脳機能障害の社会復帰を目指す生活訓練プログラムについて
生活訓練プログラムとは、日常生活を安定させ、積極的な社会参加ができるようになることを目指します。
患者さま本人だけでなく、ご家族にも働きかけます。
以下では、生活訓練プログラムの内容をまとめました。
順番に紹介します。
生活リズムの確立
生活訓練プログラムでは、生活リズムを整えるのが重要です。
高次脳機能障害では、記憶力や意欲の低下によって、日課を組み立てて行動するのが難しい場合があるためです。
施設に入所して規則正しい生活を身につけ、日中の訓練と訓練の空き時間を少なくすると安定する傾向にあります。
生活で必要な管理能力の向上
生活管理能力の向上も生活訓練プログラムの一つに挙げられます。
患者さま自身が進んで日課をこなすために、施設では以下の訓練を行います。
- スケジュール帳の活用
- 目印や案内の表示に沿って行動する
- その日のスケジュールを確認する時間をとる
- チェック表や薬ボックスを使用して服薬を管理する
- 小遣い帳を使用して金銭を管理する
スケジュール帳や薬ボックスなど、シンプルでわかりやすいものを使用して、自己管理の習慣化を図ります。
社会生活技能の獲得
社会生活技能では、地域での生活や患者さまの目標に沿って外出や生活体験の実習を行います。
具体的な内容は買い物や交通機関の利用、調理などです。
支援者から実習の場で評価や助言があるので、次回に活かせるようにしましょう。
社会的コミュニケーション能力の向上
社会的なコミュニケーション能力を向上するために、施設の患者さま同士でグループワークを行います。
意見の交換や役割分担などは、コミュニケーション能力の向上に効果的です。
グループワークでは、福祉制度を学んだり、外出の計画をしたりします。
また、他の施設の患者さまと共に日課をこなし、交流するのも重要な訓練です。
障害の自己認識と現実的な目標設定
生活訓練プログラムでは、障害の認識を深め、現実的な目標が設定できるようになる支援も行っています。
具体的な内容は以下の通りです。
- 外出や課題の訓練のフィードバックを受ける
- 患者さま同士のトラブルがあった際、支援者による客観的なフィードバックを受ける
- 一般企業や就労継続支援事業所にて実習する
実習の結果は、職員から直接本人に伝えてもらうとより高い効果が期待できます。
必要とする支援の明確化
必要とする支援の明確化も生活訓練プログラムの一つです。
患者さま本人の希望と支援者が提案する支援内容や方向性の間にギャップが生じる場合があるためです。
現在は何が必要かを考え、支援者の提案に患者さまが消極的でも実際に試してみましょう。
スムーズに適応する可能性があります。
家族への支援体制
生活訓練プログラムでは、ご家族の支援も重要です。
患者さまが障害を負ったことへのショックは大きく、受け止めるまでには時間がかかるでしょう。
主な内容は以下の通りです。
- ご家族の不安や負担の軽減を図る
- 患者さまの障害について理解してもらう
- 相談を受ける
- サポートや介護の情報提供
- 家族懇談会の開催
ご家族が孤立しないよう、継続的に支援を受けられます。
就労移行支援プログラム
就労移行支援プログラムは、一般企業や在宅で働きたいとお考えの患者さまを対象に、障害者支援施設が行います。
- 必要な知識や能力を高めるトレーニングを行う
- 施設内外で職場実習を行い、さまざまな職業の体験
- 患者さまの能力にあった仕事探し
- 職場や患者さまに連絡をとり、就職後も長く働けるような支援を行う
日頃の生活リズムや訓練を通じて、適性を見極めるのが重要です。
希望と現実の間にギャップがある場合は、長期的な目標と短期的な目標を設定し、段階的にステップアップしていくことが一般的です。
高次脳機能障害の根本的な回復を目指す「再生医療」とは
再生医療は損傷した組織にアプローチし、後遺症の改善や脳卒中の再発予防につながる可能性がある治療法です。
患者さま自身から組織の修復や再生のベースとなる幹細胞を採取・培養し、幹部に投与することで失われた機能の改善を目指します。
副作用のリスクが低く手術や入院の必要もないため、高齢の方や体力に不安がある方でも取り組みやすい治療です。
当院「リペアセルクリニック」では、高次脳機能障害の患者さまに再生医療をご提供しています。
高次脳機能障害の回復を不安に感じているご家族や患者さまは、まずはお気軽にご相談ください。
脳卒中のお悩みに対する新しい治療法があります。
高次脳機能障害の回復期間は1年が目安!早期のリハビリ開始が重要
高次脳機能障害の回復期間は、適切な治療・リハビリを継続することで1年を目安に症状の改善がみられます。
また、治療の開始は発症から早いほど症状の改善に期待できます。
高次脳機能障害リハビリプログラムは、発症後すぐに行う医学的リハビリテーションプログラムから始め、症状に合わせて日常生活や就労の訓練を行います。
ご自身の症状や目標に合わせて適切なプログラムを選択し、継続的にリハビリに取り組むことが大切です。
また、高次脳機能障害の根本的な改善を目指し、リハビリ効果を高める方法として、再生医療をご検討ください。
- 後遺症によってうまく話せない
- 痺れや麻痺をなんとかしたい
- これ以上の機能回復が見込めないといわれた
- 現在のリハビリで効果を実感できていない
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)の再発を予防したい
再生医療の治療効果は、脳卒中の発症後から早ければ早いほど改善が期待できます。
>>実際の症例はこちらからもご確認いただけます。
高次脳機能障害を治療したいとお考えの方は、当院「リペアセルクリニック」の再生医療をご検討ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳卒中における二木の予後予測とは|回復期リハビリテーションの重要性と注意点を解説
-
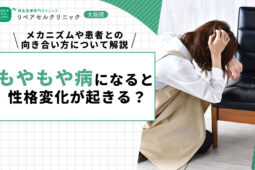
もやもや病になると性格変化が起きる?メカニズムや患者との向き合い方について解説
-

くも膜下出血は後遺症がなくても再発するリスクがある!注意点を解説
-

橋梗塞の症状とリハビリの進め方|具体的なプログラムとポイントについて解説
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の回復事例を紹介!経過や治療・リハビリが大切な理由も解説
-

高次脳機能障害患者の家族が抱えるストレスとは?つらさの理由と無理をしない接し方を紹介