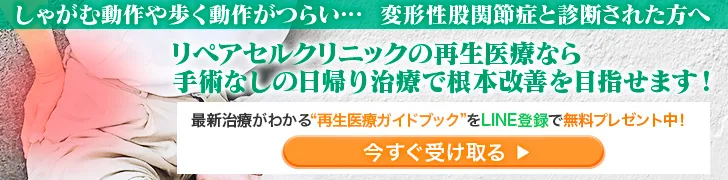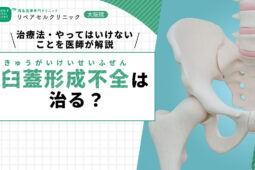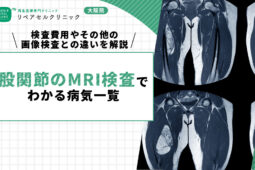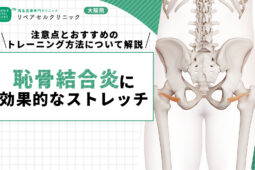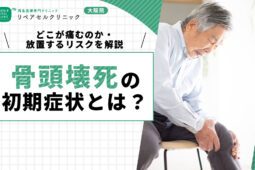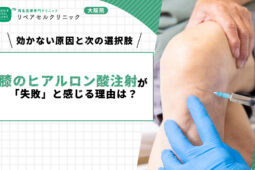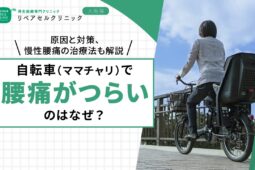- 股関節
人工股関節にならないためにできることは?置換するデメリット再生医療による治療についても解説

股関節に何らかの問題があり、保存療法などの治療で改善が見込めない場合は、人工股関節への置換が選択されるケースもあります。
メリットが多い人工関節ですが、デメリットもあります。また、人工関節にしたくない方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、人工股関節が必要になる原因から人工股関節にならないためにできることについて解説します。
人工股関節にした後に日常生活で注意することについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
人工股関節置換術とは?
人工股関節置換術とは、病気などで傷ついた股関節を、人工の股関節に置き換える手術を指します。
- 1.変形した骨を切除する
- 2.骨の中に人工の股関節を埋め込む
- 3.人工関節を固定する
手術後は、なるべく早期から自分の足で歩き始めることが重要です。
人工股関節置換術が必要になる主な原因
人工股関節置換術が必要になる原因は、主に以下の疾患によるものです。
それぞれの疾患でどのような症状がみられるのか、詳しく解説していきます。
変形性股関節症
変形性膝関節症とは、股関節の関節軟骨が変形することによって、痛みや可動域が制限される疾患です。
発症の原因は、「加齢による筋力の低下」、「股関節への過剰な負担」、「スポーツ外傷」などさまざまです。
変形した股関節をもとに戻すことはできないため、症状が悪化した場合は、人工股関節置換の手術が検討されるケースがあります。
大腿骨頭壊死症
大腿骨頭から関節内に流れる血流が悪くなることで、大腿骨頭の骨組織が壊死していく疾患です。
骨壊死だけでは痛みがない場合もありますが、進行すると壊死した骨が潰れ、体重がかかることによって痛みが生じます。
大腿骨壊死症の発症と関連する因子は解明されつつありますが、原因は未だ不明とされています。
大腿骨頭壊死症は見つかり次第すぐに人工股関節置換術を行うわけではなく、経過観察されるケースもあります。
関節リウマチ
関節リウマチは、免疫の働きに異常が生じ、健康な細胞を攻撃してしまうことで関節が炎症を起こす疾患です。
関節の痛みや腫れだけでなく、関節の変形や機能障害を引き起こす可能性もあります。
股関節の変形などの症状が悪化し、日常動作に大きな影響を及ぼしている場合は人工股関節置換術が適用されることがあります。
股関節の痛みに対する人工股関節置換術以外の治療方法
人工股関節置換術以外の治療法についても解説します。主に以下の3つが挙げられます。
ご自身の症状などを鑑みて、最適な治療法を検討してください。
保存療法
保存療法では、主に以下の方法を用いて症状・痛みの緩和が期待できます。
|
温熱療法は温めているときは痛みが軽減されますが、効果が持続しないことに注意が必要です。
運動療法を受ける際には、無理のない範囲で続けることが大切です。医師のアドバイスを受けながらトレーニングしましょう。
また、保存療法は痛みを和らげることが目的で、疾患の完治が期待できる治療法ではありません。
骨切り術
股関節の骨切り術は、「関節温存術」とも呼ばれています。
股関節がそれほど損傷していない場合、股関節周辺の骨を切って関節の向きなどを矯正する手術を行う場合があります。
状況に応じて、大腿骨側の骨を切る方法と骨盤側の骨を切る方法があります。
自分の組織や関節が残るメリットがありますが、完全に回復するまでに時間がかかるなどのデメリットがあります。
再生医療
保存療法で効果が得られなかった場合や人工関節を避けたい方は、再生医療の選択肢もあります。
再生医療とは、機能障害や機能不全になった組織に対して、体が持つ再生能力を利用して損なわれた機能を再生させる医療技術のことです。
当院(リペアセルクリニック)では、患者さまご自身の細胞を用いて治療するため、アレルギーや拒絶反応の危険性が少ないです。
また、手術や入院も不要なので、現在注目されている治療法です。
人工股関節置換術による治療も増えてきている
股関節の痛みに対して、人工股関節置換術による治療を選択する方も増えてきています。
その理由は、人工関節の性能が向上し、耐久 耐用年数が長くなったためです。
一般的に高齢の方に多い治療法ですが、運動習慣や症状の程度によっては40代や50代で人工股関節置換術が選択される場合もあります。
人工股関節のデメリット・注意点
人工股関節には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点もあります。以下では、その注意点についてお伝えします。
人工股関節に置換し、日常生活が送れるようになったあとも、注意しなければならないことはいくつかあります。
脱臼する可能性がある
脱臼を防ぐために、日常生活の中で以下の動作を避けるようにしましょう。
|
股関節が深く曲がりこむ姿勢は脱臼の可能性が高まります。日常生活でも頻繁にとる姿勢ですので、術後は安静にし、股関節に負担をかけない姿勢を意識してください。
このような姿勢は日常生活の中で無意識にしてしまうことが多いので、手術後は過度な屈曲や伸展、外旋に注意しましょう。
長期的なリハビリが必要
多くの場合は人工股関節にするまでに、日常生活に影響を与えるほどの痛みと向き合ってきているでしょう。
したがって、筋力が大幅に落ちています。筋力を元通りに戻すのには時間がかかります。
どのくらいの生活レベルを目指すかにもよりますが、リハビリは長いスパンで計画する必要があります。
耐久年数が決まっている
人工股関節には耐久年数があります。
運動の習慣や生活にもよりますが、一般的に20年程度が人工股関節の耐久年数といわれています。
そのため、若い世代の方が人工股関節置換術を受けた場合は、再度手術を行い人工関節の置き換えが必要になる可能性があります。
人工股関節の性能が向上し耐久年数も長くなってきているため、再手術が必要かどうかは医師に相談しましょう。
感染症リスクがある
人工股関節には、合併症として感染症リスクがあることも注意が必要です。
人工関節周囲感染(PJI)と呼ばれ、手術中だけでなく、術後にも歯周病や虫歯などの菌が血液を介して感染する場合があります。
- 腫れ
- 痛み
- 発熱
- 人工関節のゆるみ
症状によっては再手術の可能性もありますので、違和感がある場合はすぐに医師に相談してください。
人工股関節にならないためにできること
人工股関節にならないためには、日常生活の動作に気を付けましょう。
股関節の負担を減らす生活について、具体的に解説します。
股関節の負担を減らす生活を意識する
日常生活では、意外と股関節に負担がかかっています。以下のことを意識して生活してみてください。
|
低い場所に座ってかがんで靴を履く、ずっと座って頭を洗うなどの動作が股関節に負担をかけている場合があります。
日常生活を見直し、股関節への負担を和らげましょう。
適度な運動やストレッチを行う
股関節に負担をかけたくないからといって、一切運動をしないのは逆効果です。
適度な運動をすることにより股関節周辺の筋力が上がり、股関節にかかる負担が減ります。自宅での簡単なトレーニングもで筋力が上がりますので、無理のない範囲で継続して運動しましょう。
また、水中でのトレーニングや固定式バイクは股関節に負担をかけずに足の筋力を鍛えられます。
股関節に痛みがある場合は再生医療による治療を検討する
股関節の治療で人工股関節を入れたくない場合は、再生医療による治療を検討しましょう。
再生医療とは、機能障害や機能不全になった組織に対して、体が持つ再生能力を利用して損なわれた機能を再生させる医療技術のことです。
患者さまの幹細胞を採取・培養し、損傷した股関節を再生できる場合があります。手術や入院も必要ないため、注目されている治療方法です。
再生医療を検討している方は、当院(リペアセルクリニック)にご相談ください。
以下のページでは、股関節に対する再生医療の症例を公開しているため、併せて参考にしてください。
>再生医療による股関節の症例はこちら
【まとめ】人工股関節にならないためには股関節の負担を減らすことが重要
人工股関節置換術や、それ以外の治療法について解説しました。
人工股関節にならないためには、日常生活のなかで股関節に負担をかける動作を避けることが大切です。
人工股関節置換術は元通りの生活が送れるようになる半面、注意点も多くあります。ご自身の年齢や症状に合わせて適切な治療法を検討してください。
また、適度な運動によって股関節周辺の負担を和らげましょう。
どうしても股関節の痛みがおさまらない場合は、再生医療もご検討ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設