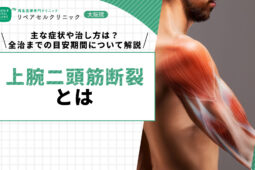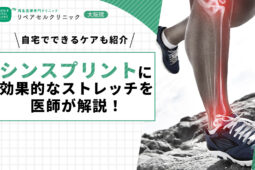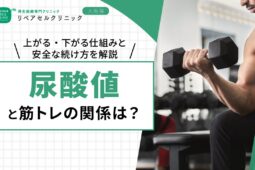- 肘
- スポーツ医療
- 再生治療
野球肘の痛みを悪化させないストレッチとは?安全に可動域を取り戻す方法を紹介
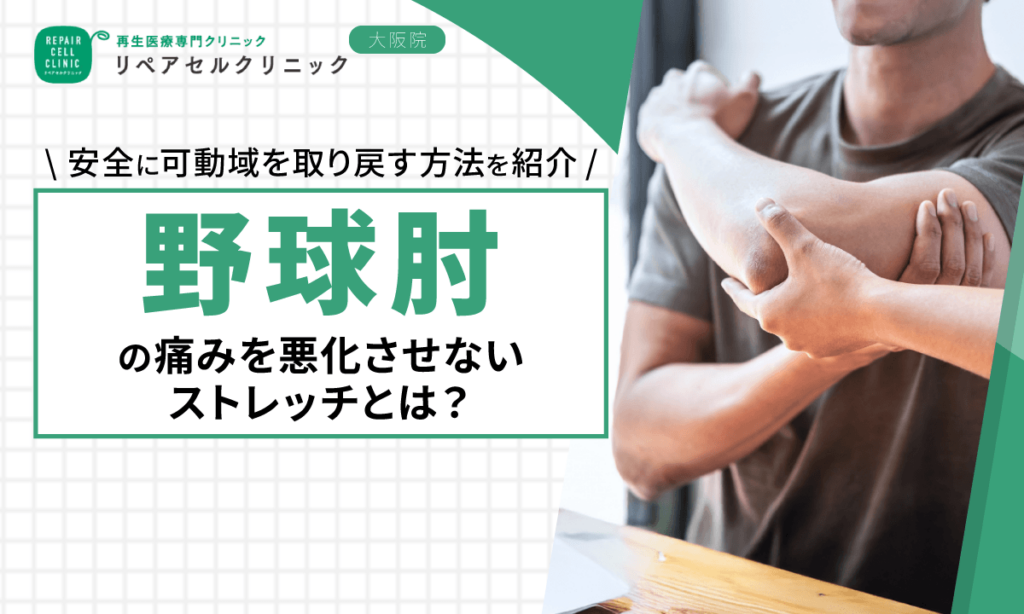
野球肘におけるストレッチは、「痛みを我慢して伸ばす」ことが悪化の原因になるため注意が必要です。
特に、投球による炎症や筋腱損傷を抱えた状態では、間違ったストレッチが組織をさらに傷つけることがあります。
本記事では、野球肘を悪化させない安全なストレッチ方法と、ストレッチだけでは回復しない場合の治療選択肢について解説します。
- 野球肘ストレッチを安全に行うための基本ポイント
- 時期別(急性期・亜急性期)の正しいケア方法
- ストレッチで悪化する危険動作の例
- 再生医療による根本的な肘の修復法
目次
安全に行う野球肘ストレッチのポイント
野球肘のストレッチで最も大切なのは、「炎症の時期を見極めて無理をしない」ことです。
炎症が強い時期にストレッチを行うと、靭帯や腱への微細損傷が広がり、回復が遅れてしまいます。
症状の進行段階に合わせて、段階的にストレッチの強度を変えることが重要です。
急性期は無理に伸ばさない
結論として、痛みや腫れがある急性期にはストレッチをしてはいけません。
この時期は上腕骨内側上顆(ないそくじょうか)付近の筋肉や靱帯に炎症が起こり、組織が非常に脆い状態です。
無理に動かすと再損傷のリスクが高まります。
- 患部を冷やして炎症を抑える(アイシングは1回15分まで)
- 安静を保ち、肘を軽く曲げた姿勢で固定する
- 医師の許可が出るまでストレッチは控える
炎症が治まるまでは、肘関節を動かすよりも「安静+冷却+圧迫+挙上(RICE処置)」を優先します。
再発を防ぐ第一歩は、焦らないことです。
急性期に無理なストレッチを行うと、骨端線損傷(こったんせんそんしょう)や靱帯断裂など、重症化する例もあります。
亜急性期は軽いストレッチを行う
急性期を過ぎて痛みや腫れが落ち着いた、亜急性期(2〜4週)では軽いストレッチを再開できます。
ただし「気持ちいい程度」で止めるのが原則です。
肘の柔軟性を少しずつ取り戻すためには、周囲筋(前腕屈筋群・伸筋群)のストレッチを中心に行います。
- 手首を反らして前腕の筋肉を軽く伸ばす(10秒×3セット)
- 反対の手で肘を支えながら、曲げ伸ばしを小さく繰り返す
- 肩甲骨まわり(肩甲下筋や僧帽筋)のストレッチも併用
ストレッチの際は、「痛みが出る一歩手前」で止めることが大切です。
可動域を広げる目的で勢いをつけたり、長時間続けたりすると、治りかけの腱に再び炎症が起きる場合があります。
特に成長期の選手は骨端線が閉じていないため、慎重に進めましょう。
危険なストレッチの例
野球肘の改善目的で行われがちなストレッチの中には、実際には症状を悪化させるものもあります。
特に、肘の過伸展や強制的な回内・回外運動は靭帯や骨を痛める原因になります。
- 肘を完全に伸ばしたまま手首を強く反らせる
- ボールを握って力を入れながら肘を回す
- 痛みを我慢して関節を押し込む
一見「柔軟性を高める」ように見えるこれらの動作は、実際には損傷部位に負担をかけます。
ストレッチは筋肉に対して行うものであり、関節や靭帯を無理に動かすものではないことを理解しましょう。
痛みを感じる動作を繰り返す場合、軽度の炎症が慢性化し、最終的には投球障害へ発展することもあります。
ストレッチで改善しない場合のサインと治療の選択肢
ストレッチを数週間続けても改善しない場合、単なる筋緊張ではなく腱・軟骨・骨端への損傷が関与している可能性があります。
そのまま放置すると変形性肘関節症などの慢性障害に移行するため、早期の診断が重要です。
下記では受診の必要な症状について詳しく解説しているので、治療の選択肢を把握するためにもぜひ参考にしてみてください。
要受診のサイン
結論として、次のような症状がある場合は自己判断でストレッチを続けず整形外科を受診しましょう。
- ストレッチ後も痛みや腫れが長引く(1週間以上)
- 肘の曲げ伸ばしに「引っかかり」や「音」がある
- 安静時や夜間に痛みが出る
- 投球時の痛みが再発する
これらの症状が続く場合、靱帯損傷や剥離骨折、軟骨障害などが潜んでいることがあります。
早期にMRIや超音波検査を受けることで、再発や重症化を防ぐことができます。
治療の選択肢
野球肘の治療には、保存療法・注射・再生医療など複数の選択肢があります。
症状の程度や競技レベルに応じて、段階的に治療を組み合わせることが推奨されます。
| 治療法 | 概要 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 保存療法 | 安静・冷却・ストレッチ制限・リハビリ | 炎症軽減、痛みの抑制 |
| 注射治療 | ヒアルロン酸やステロイドの局所注射 | 短期的な疼痛緩和 |
| 再生医療 | 自分の血液や幹細胞を利用して修復を促進 | 組織の再生、再発予防 |
特に再生医療は、損傷した腱や靭帯の修復を促すことが報告されており、手術に抵抗のある方にも有効な選択肢となります。
リペアセルクリニック大阪院の再生医療で、肘の根本回復を目指す
リペアセルクリニック大阪院では、野球肘のような投球障害に対して、脂肪由来幹細胞(ADRCs)やPRP(多血小板血漿)を用いた再生医療を行っています。
自分自身の細胞を利用して炎症を鎮め、損傷した組織の修復を促すため、副作用リスクが少なく安全性が高いのが特徴です。
- 手術不要・ダウンタイムが短い
- 自然治癒力を活かして根本的な修復を促進
- 再発を防ぎ、競技への早期復帰をサポート
スポーツ選手のように肘を酷使する方にとって、再生医療は「早く・安全に回復したい」という要望に応える新しい選択肢です。
炎症の抑制と組織再生を同時に進めることで、再発しにくい肘を目指せます。
以下では、肘関節に関するリペアセルクリニック大阪院の症例紹介を行っているので、ぜひ参考にしてみてください。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
野球肘はストレッチだけに頼らず、根本的なケアが重要
野球肘の回復には、ストレッチだけでなく、炎症のコントロールと組織修復の両立が不可欠です。
急性期は安静を守り、亜急性期以降は軽いストレッチで柔軟性を戻ことを意識しましょう。
さらに、再生医療などの治療を取り入れることで、痛みを抑えながら根本改善を図ることができます。
- 急性期は「安静+冷却」で悪化を防ぐ
- 亜急性期は「軽いストレッチ+リハビリ」で柔軟性を戻す
- 再生医療で「組織修復+再発予防」を行う
痛みを我慢してストレッチを続けることは、治療を遠ざける原因になりかねません。
専門医の診断と正しいケアで、肘の機能を取り戻しましょう。
リペアセルクリニック大阪院では丁寧なカウンセリングを行い、一人一人の症状に合わせた、治療が可能です。
スポーツ復帰を目指す方に、最適な治療プランをご提案し、回復まで寄り添います。
肘関節の根本的な回復のために、ぜひ無料カウンセリングを活用してみてください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設