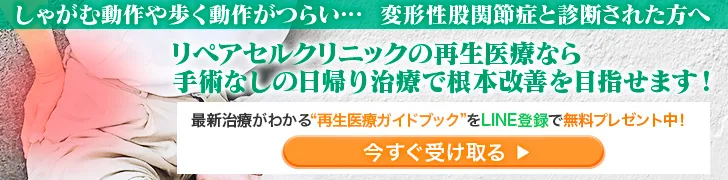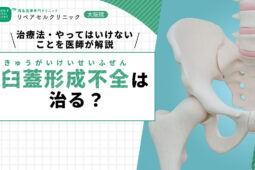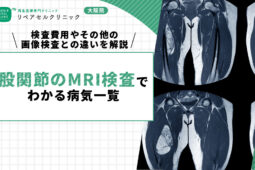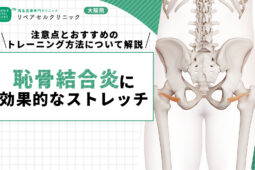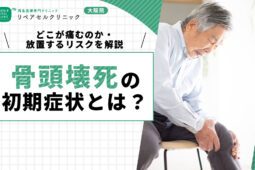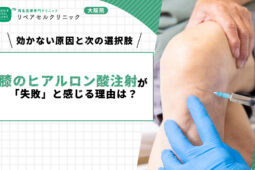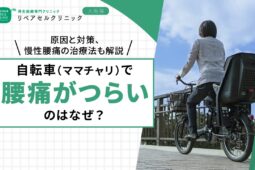- 股関節
恥骨結合炎(恥骨炎)とは|どこが痛い?症状や原因、何科を受診すべきか解説
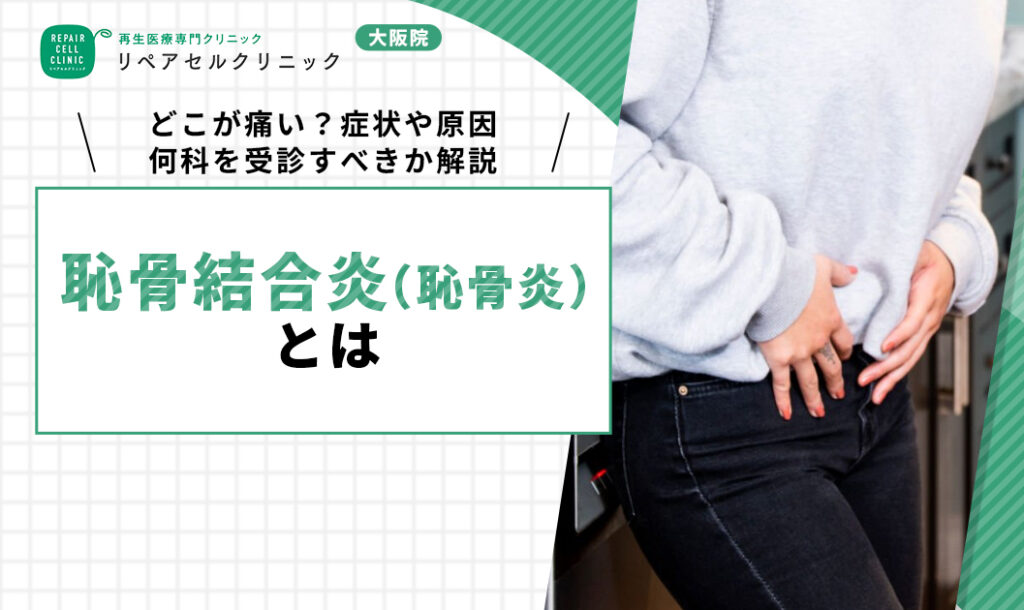
ランニングやサッカーの後、あるいは妊娠・出産後に足の付け根や下腹部に原因のわからない痛みを感じていませんか。
上記のような恥骨周辺の痛みや違和感は、「恥骨結合炎」が疑われます。
恥骨結合炎は、悪化すると歩くのもつらくなるなど、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早期に治療を受けることが重要です。
本記事では、恥骨結合炎の主な症状や原因、受診すべき診療科について詳しく解説しています。
- 恥骨結合炎の主な症状や原因
- 受診すべき診療科
- 主な治療法とセルフケアの方法
従来の治療法に加えて、近年では炎症抑制や損傷した組織の再生・修復を促す「再生医療」も選択肢の一つです。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の治療法や症例について配信しているので、ぜひご登録ください。
目次
恥骨結合炎(恥骨炎)とは|主な症状
恥骨結合炎とは、骨盤の前方で左右の恥骨をつないでいる軟骨組織「恥骨結合」に炎症が起きる疾患です。
主な症状は、以下のとおりです。
恥骨結合炎の主な症状
- 恥骨部、鼠径部、下腹部の痛み
- 立ち上がりや歩行など、動作時の痛み
- 太ももや背中など、患部とは異なる部位への放散痛
- まれに細菌感染による発熱
初期症状は運動後の違和感や鈍い痛みですが、悪化すると歩くのもつらくなるなど、日常生活に支障をきたす可能性があります。
上記のような症状が見られた場合、恥骨結合炎が疑われるため、早期に医療機関を受診しましょう。
恥骨結合炎(恥骨炎)の原因3つ
恥骨結合炎を引き起こす原因は、主に以下の3つです。
以下では、それぞれの原因について詳しく解説します。
妊娠・出産
妊娠・出産は、女性が恥骨結合炎を発症する要因の一つです。
妊娠後期になると、出産準備のために骨盤の靭帯の伸展性が高まる「リラキシン」というホルモンが分泌されます。
その影響で恥骨結合も緩んで不安定になり、大きくなった子宮の重みで負担がかかります。
特に出産の際に赤ちゃんが産道を通るとき、恥骨結合が大きく引き伸ばされて炎症を起こすことで、強い痛みを感じる場合があります。
産後、骨盤が不安定な状態での育児も、症状を悪化させる一因です。
激しい運動の繰り返し
恥骨結合炎は、スポーツ選手に多く見られるスポーツ障害の一種です。
ランニングやジャンプ、サッカーのキック動作など、同じ動きを繰り返すことで恥骨結合に過度な負担がかかるのが原因です。
また、股関節周辺の筋力や柔軟性の不足、急激なトレーニング量の増加によって、恥骨結合への負担が増大するため注意しましょう。
初めは運動後の違和感だけでも、無理に運動を続けると慢性的な痛みに変わる可能性があります。
外傷や手術後の合併症
頻度は低いですが、ケガや手術が原因で恥骨結合炎になる場合もあります。
例えば、転倒や事故で骨盤に強い衝撃が加わり、恥骨結合を直接損傷してしまうケースです。
また、まれな原因として、婦人科や泌尿器科などの手術後の細菌感染によって発症する「化膿性恥骨結合炎」もあります。
この場合は、恥骨周辺の痛みに加えて発熱するのが特徴で、速やかに医療機関を受診する必要があります。
【何科に行く?】恥骨結合炎(恥骨炎)の診断方法
恥骨結合炎が疑われるときは、症状に合わせて適切な診療科を選ぶのが早期回復への第一歩です。
受診すべき診療科
- 整形外科:運動や歩行など、体を動かすと痛む場合
- 泌尿器科:発熱+排尿時痛
- 婦人科:妊娠中・産後の骨盤痛
基本的には、骨や筋肉の専門である整形外科を受診しましょう。
また、主な診断方法は、問診、触診、画像検査を組み合わせて総合的に行います。
| 検査の種類 | 内容 |
|---|---|
| 触診 | 医師が恥骨周辺を直接触れて、痛みの場所や程度、どのような動きで痛むかを確認 |
| MRI検査 | 骨やその周りの筋肉の炎症を詳しく見ることができ、恥骨結合炎の診断に欠かせない検査 |
| レントゲン・CT検査 | 骨の変形やズレがないかを確認 |
これらの検査結果をもとに、医師が恥骨結合炎かどうかを正確に診断します。
運動時の恥骨周辺の痛みが長引いている方や発熱を伴う恥骨痛が見られる方は、早期に医療機関を受診しましょう。
恥骨結合炎(恥骨炎)による痛みの対処法
恥骨結合炎の痛みに対処するには、炎症の程度や時期に合わせたセルフケアが有効です。
まずは炎症を抑えることから始め、回復期には再発を防ぐための体づくりへと移っていきます。
負担を避けて安静にする
恥骨結合炎の治療で基本となるのは、患部に負担をかけず安静にすることです。
ランニングやジャンプ動作を繰り返し、股関節への負担が大きいスポーツは完全に中止しましょう。
日常生活でも、足を大きく開いたり、片足立ちになったりする動作は、症状悪化を招くため避けるべきです。
しかし、完全安静は筋力低下につながるため、推奨されていません。
痛みを悪化させる活動を避けつつ、日常生活は可能な範囲で継続することが重要です。
骨盤ベルトを装着する
骨盤ベルトの装着は、痛みを和らげるための有効な手段の一つで、妊娠・出産後などで骨盤が不安定になっている場合に推奨されます。
骨盤ベルトは、緩んだ骨盤を外側から支えて安定させる役割を持ちます。
装着すると、歩いたり立ち上がったりする際に恥骨結合にかかる負担が軽減され、痛みが和らぐ効果が期待できます。
ただし、強く締めすぎると血行不良の原因になるため、適切な位置に正しい強さで装着しましょう。
以下の記事では、股関節と骨盤の関係性について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
ストレッチや筋トレを行う
痛みが落ち着いてきたら、再発予防のためにストレッチや筋力トレーニングを行うことも重要です。
| ケアの種類 | 詳細 |
|---|---|
| ストレッチ | ・硬くなった筋肉の柔軟性を取り戻すのが目的 ・股関節周辺だけでなく、お腹や太ももの内側の筋肉を伸ばす |
| 筋力トレーニング | ・骨盤の安定性を高めるのが目的 ・お尻の筋肉や体幹を鍛えるトレーニングが有効 ・体への負荷が少ない水中ウォーキングもおすすめ |
これらのケアで骨盤周りの筋肉のバランスを整えることで、恥骨結合にかかる負担が分散され、症状の改善と再発予防につながります。
しかし、発症直後の炎症が強い時期に行うと逆効果になる可能性があるため、必ず痛みのない範囲で始めてください。
恥骨結合炎(恥骨炎)の治し方|主な治療法
恥骨結合炎の治療は、症状の重さや原因に応じて、「非外科的治療」と「外科的治療」の2つが検討されます。
ほとんどの場合、まずは非外科的治療から開始されます。
非外科的治療
非外科的治療は、恥骨結合炎の治療で最初に選択される治療法です。
主な治療目的は、患部の炎症を鎮めて痛みを和らげ、再発を防ぐための体の機能を取り戻すことです。
以下のような保存療法を組み合わせて治療を行います。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 安静・活動制限 | 痛みの原因となるスポーツ活動などを中止し、患部に負担をかけないようにする |
| 薬物療法 | 痛みや炎症を抑えるために、飲み薬や湿布薬を使用する |
| 物理療法 | 痛みが強い急性期に、患部を冷やして(アイシング)炎症を抑える |
| リハビリテーション | 痛みが落ち着いたら、ストレッチや筋トレで骨盤周りの筋肉の柔軟性を高め、安定させる |
| 装具療法(骨盤ベルト) | 骨盤を固定して恥骨結合への負担を減らし、痛みを和らげる |
適切な治療により、約8割の方が3〜6ヶ月程度で日常生活だけでなく、スポーツ復帰も可能なレベルまで改善します。
しかし、治療を継続しても症状が長引くケースや、再発するリスクもあるため、焦らずに治療を続ける姿勢が求められます。
外科的治療
非外科的治療を3〜6ヶ月継続しても症状が改善しない場合や、重症例では外科的治療が検討されます。
主な治療法は、以下のとおりです。
主な外科的治療
- 運動器カテーテル治療(血管塞栓術):慢性的な痛みの原因となる異常血管を塞ぐ
- 内視鏡的恥骨結合掻爬術:内視鏡を用いて、炎症を起こしている組織を取り除く手術
- その他の手術:筋肉の腱を切り離す手術や、恥骨結合部を削る手術など
従来の治療では重症例に対して、お腹を切る開腹手術が一般的でしたが、近年では内視鏡を用いてお腹を切らずに手術を行う方法もあります。
症状や重症度に応じて適切なアプローチが異なるため、医療機関と相談したうえで納得できる治療法を選択しましょう。
恥骨結合炎(恥骨炎)に関してよくある質問
本章では、恥骨結合炎について多くの方が疑問に思う点にお答えします。
痛みの具体的な場所や、治るまでにかかる期間について正しく理解し、不安を解消しましょう。
恥骨結合炎はどこが痛い?
恥骨結合炎の痛みは、主に骨盤の前方中央、おへその下あたりにある「恥骨結合」という部分に生じます。
この部分を指で押すと強い痛みを感じるのが、恥骨結合炎の特徴です。
痛みは中心部だけでなく、その周辺にも広がります。
痛みが広がりやすい場所
- 鼠径部(そけいぶ)
- 下腹部
- 太ももの内側
- 会陰部(えいんぶ)
人によっては背中やすねにまで痛みが及ぶ場合もあります。
とくに、ランニングやキック動作、寝返りを打つときなど、恥骨結合に負担がかかる動きで痛みは悪化する傾向があります。
恥骨結合炎はどのくらいで治る?
恥骨結合炎の治癒までにかかる期間は、症状や治療法によって異なるため、一概に「この期間で治る」とは言えません。
治療期間の目安は、以下を参考にしてください。
| 症状の重さ | 治癒期間の目安 |
|---|---|
| 軽症 | 適切な治療により、6〜12週間で日常生活への復帰が可能 |
| 中等度 | 約8割の方が3〜6ヶ月の治療期間を経て、日常生活およびスポーツ復帰が可能 |
| 重症・慢性化 | 治療期間は長引く傾向にあり、6ヶ月以上かかるケースもある |
痛みが改善した後でも筋力や柔軟性を取り戻すためのリハビリ期間が必要です。
上記の治療期間はあくまで参考程度に捉え、焦らずに治療を続けることが重要です。
つらい恥骨結合炎(恥骨炎)には再生医療をご検討ください
恥骨結合炎はスポーツや妊娠・出産をきっかけに発症します。
適切な治療を受けずに放置してしまうと、症状が長引いたり、再発を繰り返したりするケースも少なくありません。
症状の重さや原因に応じて、「非外科的治療」と「外科的治療」の2つの治療法があるため、医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。
また、近年の治療では、手術せずに根本的な改善を目指せる「再生医療」も選択肢の一つです。
再生医療は、患者さま自身の血液や細胞を用いて、炎症抑制や損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
長引く痛みにお悩みの方は、根本的な改善を目指せる可能性がありますので、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設