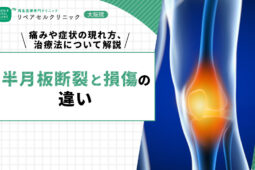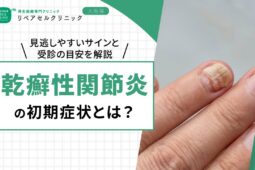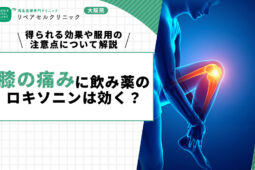- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
ジャンパー膝の症状チェック|有効なストレッチや治し方について解説【医師監修】
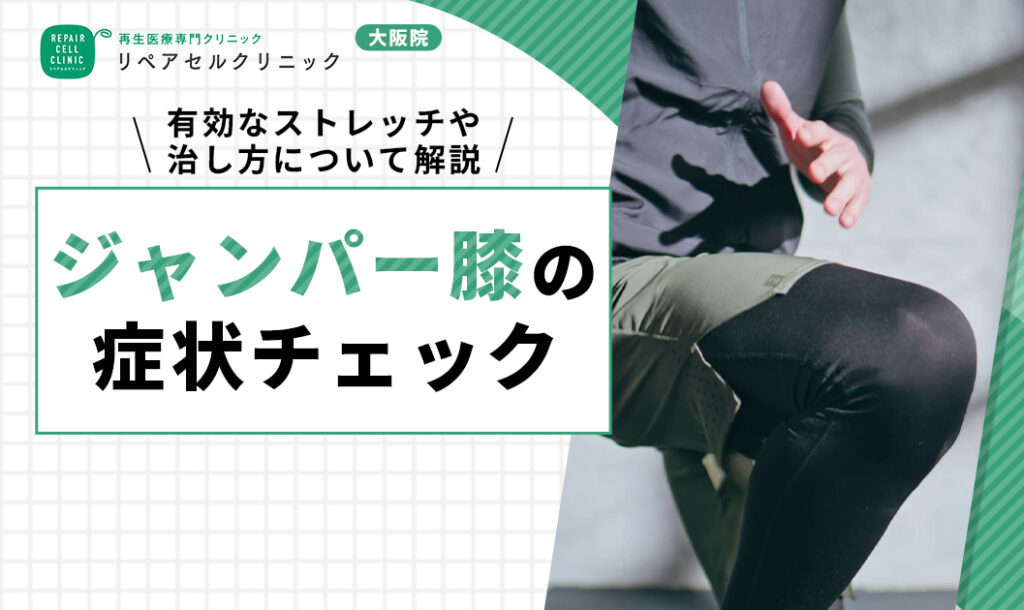
ジャンプや着地、階段の利用時に膝下の痛みや違和感がある方は「この症状はジャンパー膝?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
ジャンパー膝かどうかチェックするには、ジャンプの着地や膝を深く曲げる動作で膝に痛みがあるか確認しましょう。
本記事では、ジャンパー膝の症状チェック方法や自宅でできるストレッチ、治療法について詳しく解説します。
膝の痛みや違和感を正しく理解し、日常生活での負担軽減や受診のタイミングの判断にお役立てください。
また、当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、再生医療の情報や症例も公開しています。
慢性化に不安を抱える方や、手術以外の治療法を検討している方は参考にしてください。
目次
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)とは|基礎知識をチェック
ジャンパー膝とは、膝のお皿(膝蓋骨)とすねの骨をつなぐ膝蓋腱に負担がかかり炎症が起こる状態です。
ジャンプやダッシュなど、膝に繰り返し負荷のかかる動作で発症しやすいとされています。
まずは自分の膝にどんな違和感や痛みがあるか、日常動作を通してチェックしてみましょう。
ジャンパー膝の症状
ジャンパー膝の症状は、以下の通りです。
- 膝のお皿の下や上がズキズキと痛む
- 膝のお皿の下や上を押すと痛い
- 膝のお皿周囲が熱をもったり腫れたりする
- ジャンプやランニングの着地、階段の上り下りで痛みが強くなる
ジャンパー膝の初期は、運動中や運動直後に痛みを感じるのが一般的です。
痛みが軽いからと放置すると、膝蓋腱へのダメージが進行し、最悪の場合は腱の断裂につながる恐れもあります。
自己判断で対処せず、早めに整形外科で適切な診断と治療を受けましょう。
なお、膝の前面に痛みを生じるスポーツ障害にはオスグッド病も挙げられます。
ジャンパー膝は膝のお皿(膝蓋骨)のすぐ下あたりが痛むのに対し、オスグッド病はさらに下部であるすねの骨(脛骨)の少し出っ張った部分が痛むのが特徴です。
以下の記事は、ジャンパー膝とオスグッド病の違いについて解説しているので参考にしてください。
ジャンパー膝の原因
ジャンパー膝の主な原因は、膝蓋腱への繰り返しの負担(オーバーユース)です。
膝蓋腱は膝のお皿の下にある腱で、膝の曲げ伸ばしをサポートしています。
ジャンプやダッシュ、急な方向転換など膝に負荷がかかる動作を繰り返すことで、膝蓋腱に微細な損傷が生じ炎症が起こります。
とくに症状が現れやすいスポーツは以下の通りです。
- バレーボール
- バスケットボール
- 走高跳
- サッカー
- 長距離走
- スキー
- 野球
膝に繰り返し負荷がかかっていたり、運動時のフォームが乱れていたりすると、膝蓋腱に過度な負担をかけてしまいます。
日常生活やトレーニングで膝の使い方を意識して、ジャンパー膝の予防につなげましょう。
また、ジャンパー膝は成長期に急激に身長が伸びている子どもに多くみられる傾向があります。
以下の記事では、成長期におけるジャンパー膝の原因について解説していますので参考にしてください。
ジャンパー膝の症状チェック|自分でできる方法
自宅で簡単にできるジャンパー膝のチェック方法は、以下の通りです。
動作時の痛みや、膝のお皿の上下を押したときの痛みを確認することで、おおよその状態を把握できます。
無理のない範囲で試し、強い痛みがある場合はすぐに中止して整形外科で医師の診察を受けましょう。
動作時の痛みチェック
ジャンパー膝かどうか確かめるには、膝に負担がかかる動作をした際に、どのような痛みが出るかチェックしてみましょう。
| 動作 | 詳細 |
|---|---|
| 階段の上り下り | 膝を深く曲げたときに膝のお皿の下あたりが痛む場合は、膝蓋腱に負担がかかっている可能性がある |
| しゃがみ動作 | |
| 軽くジャンプして着地 | 着地の瞬間や直後に膝の前面に痛みや違和感があれば、ジャンパー膝が疑われる |
| うつぶせの状態で膝を曲げ、かかとをお尻に近づける | 股関節まわりが浮く場合、膝周囲に強い緊張が生じている恐れがある |
いずれのチェックでも、強い痛みを感じたらすぐに中止してください。
セルフチェックはあくまで目安であり、痛みが続く・膝に力が入りにくいなどの症状がある際は早めに整形外科を受診しましょう。
患部の圧痛テスト
ジャンパー膝の確認方法の一つに、膝のお皿(膝蓋骨)の下にある腱部分を指で軽く押してみる圧痛テストがあります。
膝のお皿の下を押すと痛みを感じる場合は、膝蓋腱に炎症が起きている可能性があります。
膝を曲げた状態や伸ばした状態の両方で試すと、痛みの出方をより確認しやすいでしょう。
ただし、強く押したり何度も繰り返したりすると、炎症を悪化させる恐れがあります。
違和感や痛みを感じた際は、整形外科で専門的な診断を受けましょう。
ジャンパー膝の症状を和らげるストレッチ
ジャンパー膝の症状を和らげる代表的なストレッチは、以下の通りです。
自宅で無理なくできるストレッチを紹介します。
いずれも「痛気持ち良い」と感じる程度にとどめ、強く伸ばしすぎないことがポイントです。
ストレッチを習慣にして、膝の違和感の軽減や再発予防につなげましょう。
大腿四頭筋のストレッチ(立位)
立ったままできる大腿四頭筋ストレッチの手順は、以下の通りです。
- 1.立った状態で壁や椅子に手を添え、片脚を後ろに曲げる
- 2.曲げた足首を同じ側の手でつかみ、かかとをお尻に近づける
- 3.腰を反らさずお腹に軽く力を入れ、体が前に傾かないようにする
- 4.膝を後ろに引き、太ももの前側が伸びているのを感じながら30秒ほどキープする
ストレッチの際は、腰を反らせすぎると腰に負担がかかるため、注意が必要です。
また、股関節が十分に動かせていないとストレッチの効果は低くなるため、太ももの前側だけでなく股関節周りも伸びているか確認しましょう。
大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)はジャンパー膝で炎症を起こしやすい膝蓋腱と深い関係があり、筋肉が硬くなると膝蓋腱に過度な負担がかかり、痛みが長引く原因になります。
ストレッチで大腿四頭筋の柔軟性を高めて膝への負担を軽減し、症状の緩和や再発予防につなげましょう。
大腿四頭筋のストレッチ(座位)
床に座ってできる大腿四頭筋ストレッチの手順は、以下の通りです。
- 1.膝を伸ばして床に座る
- 2.痛む側の足のかかとをお尻に近づける
- 3.両手を後方につき、太もも前面の伸びを感じる
- 4.膝が浮かないように意識する
- 5.さらに伸ばしたい場合は肘をつき、太ももを床に押し付ける
- 6.膝が浮いたら元に戻す
- 7.余裕があれば背中を床につけ、30秒ほどキープする
大腿前面の筋肉をほぐして膝のストレスを減らし、ジャンパー膝の症状の悪化を防ぎましょう。
腰を反ったり膝が浮いたりすると大腿四頭筋が十分に伸びないため、姿勢が崩れない範囲で伸ばすのが重要です。
痛みが強い場合は無理せず中止してください。
ハムストリングスのストレッチ
ハムストリングスストレッチの手順は以下の通りです。
- 1.膝立ちの姿勢になる
- 2.片方のかかとを床につけ、膝は軽く曲げる
- 3.両手を床につき、体を支える
- 4.胸を太ももにできるだけ近づける
- 5.気持ち良いくらいの強さで、30秒ほどキープする
- 6.深呼吸を意識しながら、体の力を抜いて伸ばす
ハムストリングス(太ももの裏の筋肉)の柔軟性を高めると、膝の曲げ伸ばし動作がスムーズになり、大腿四頭筋にかかる負担軽減が見込めます。
ストレッチを行う際は、背中や腰が反らないよう姿勢を正しく保つように意識しましょう。
殿筋(おしり)のストレッチ
殿筋のストレッチ手順は、以下の通りです。
- 1.両足を伸ばして床に座る
- 2.左膝を立てる
- 3.左膝に右肘を当て、体を右に振り向く
- 4.右肘で左膝を軽く押す
- 5.30秒ほどキープする
- 6.足を組み替えて反対も行う
おしりの筋肉をほぐすと、ジャンプやダッシュなど膝に負担のかかる動作時の力の分散に役立ちます。
ストレッチを行う際は、背中や腰が丸まったり反ったりしないよう注意しましょう。
ジャンパー膝の治し方|主な治療法
ジャンパー膝の主な治療法は、以下の通りです。
| 治療方法 | 内容 |
|---|---|
| 物理療法 | 電気や超音波などの機器を使って患部を刺激し、炎症を抑えて回復を促す 痛みや腫れが強い場合は、消炎鎮痛薬や湿布を使用する |
| 薬物療法 | 痛みや腫れが強い場合は、消炎鎮痛薬や湿布を使用する |
| リハビリ | ストレッチで太ももや股関節の筋肉の柔軟性を高め、膝蓋腱の負荷軽減を目指す |
| 再生医療 | 自身の血液や脂肪から採取した成分を患部に注射し、損傷した組織にアプローチする |
ジャンパー膝の治療では、患部を安静にしつつ痛みや炎症の抑制を目指します。
さらに、再生医療も治療の選択肢の一つです。
再生医療とは、患者さま自身の細胞や血液を活用し、傷ついた組織にアプローチする治療法です。
入院や手術が不要なので、ジャンパー膝の痛みが長引いている方やスポーツの早期復帰を目指す方に選ばれています。
具体的な治療法については、当院「リペアセルクリニック」の無料カウンセリングをご活用ください。
ジャンパー膝の症状チェックに関するよくある質問
ジャンパー膝の症状チェックに関するよくある疑問は、以下の通りです。
気になるポイントを確認しながら、自身の状態を見直してみましょう。
ジャンパー膝の初期症状は?
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)の初期には、運動後や階段の上り下りの際に、お皿の下(膝蓋骨の下部)に痛みや違和感が出るのが特徴です。
初期段階で適切なケアを行わないと、炎症が進行して安静時にも痛みが続く慢性化につながる恐れがあります。
痛みが軽くても、「運動の後にお皿の下がズキッとする」「階段の昇りで違和感がある」と感じたら、ストレッチやアイシングなどのセルフケアを行い医療機関の受診を検討しましょう。
ジャンパー膝でやってはいけないことは?
ジャンパー膝でやってはいけないことは、以下の通りです。
- 違和感や痛みを抱えたまま運動を続ける
- 自己流で強いストレッチやマッサージをする
- 長時間の立ち仕事や歩行を続ける
- 自己判断で運動を再開する
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は、膝の使いすぎによる炎症が主な原因のため、間違った対応をすると症状を長引かせたり再発を招いたりする恐れがあります。
医師の診断を受け、指示された安静期間をしっかり守りましょう。
ジャンパー膝の症状チェックに該当したら医療機関を受診しよう
運動後や階段の上り下りで膝のお皿の下に違和感や痛みを感じた場合は、ジャンパー膝の可能性があります。
痛みを我慢して運動を続けると、炎症が慢性化して膝蓋腱の損傷や腱断裂などの恐れもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
また、早くスポーツ復帰したい方は、早期改善を目指せる再生医療による治療をご検討ください。
再生医療は、患者さま自身の細胞や血液を用いて、損傷した膝蓋腱にアプローチし、自身の修復力をサポートする治療法です。
治療方法について詳しく知りたい方は、ぜひ当院「リペアセルクリニック」へお問い合わせください。
>当院の再生医療による膝関節の症例はこちら

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設