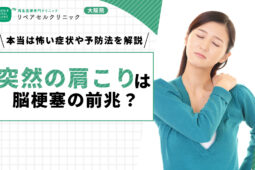- 脳梗塞
- 脳卒中
- 頭部
軽い脳梗塞とは?症状が軽くても油断は禁物!危険性と予防策を解説
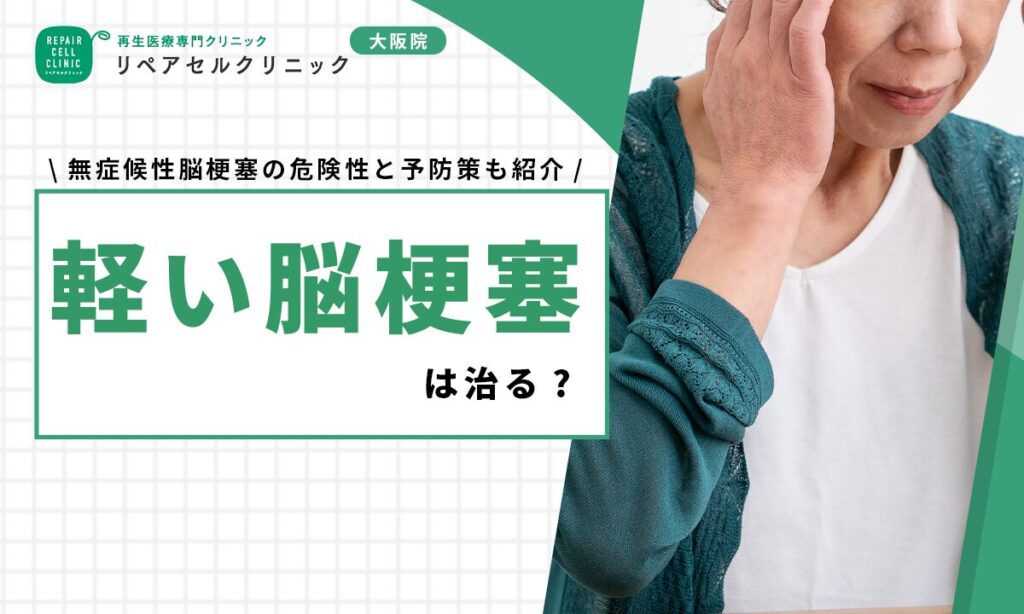
症状が軽い脳梗塞に対して「症状が軽ければ治るのか?」という疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
脳梗塞は軽いから大丈夫と油断できるものではありません。
本記事では、軽い脳梗塞のタイプや症状・予防法、そして根本的な改善を目指せる再生医療の選択肢についてご紹介します。
軽い脳梗塞について疑問や不安がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
以下の動画では、実際に当院リペアセルクリニックで再生医療を受け、脳梗塞の後遺症が改善された患者様の症例を紹介しています。
なお、当院「リペアセルクリニック」では、公式LINEにて脳梗塞(脳卒中)の再発予防に役立つ再生医療を紹介しています。
再生医療について知りたい方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。
目次
軽い脳梗塞とは
脳梗塞の中には症状が軽く、気づきにくいタイプがあります。
このような症状が軽い脳梗塞や自覚症状がないまま進行する脳梗塞を「無症候性脳梗塞」と呼びます。
本章では、軽い脳梗塞について詳しく解説します。
多くの場合は「ラクナ梗塞」
脳梗塞は主に、アテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓症・ラクナ梗塞の3種類に分類されます。
この中で、症状が軽いケースはラクナ梗塞であることが多いです。
ラクナ梗塞は、脳の細い血管(穿通枝)が詰まることで起こる脳梗塞で、脳の深部(基底核や脳幹など)に小さな病変ができるのが特徴です。
症状が軽い傾向にあるラクナ梗塞ですが、繰り返し発症すると次第に認知機能障害や歩行障害、排尿障害などを引き起こす可能性があります。
これは小さな梗塞が積み重なることで、脳の機能に徐々に影響を及ぼすためです。
軽い脳梗塞の重症化を防ぐカギは「早期発見」
軽い脳梗塞は発見された時点では後遺症がないことが多いのですが、放置すると新たな脳梗塞につながる可能性があります。
脳梗塞を繰り返すことで徐々に脳の機能に影響を及ぼし、最終的には認知機能の低下や運動障害などの後遺症につながることもあります。
後遺症を残さないためには早期発見と適切な治療が重要です。
早期発見ができれば、生活習慣の改善などを行い、新たな脳梗塞の発症リスクを大幅に下げることができます。
軽い脳梗塞の前兆・初期症状
軽い脳梗塞は自覚症状がほとんどないため発見が難しいものですが、重度の脳梗塞へと進行する前に何らかの前兆が現れることがあります。
これらの前兆や初期症状を見逃さないことが、深刻な事態を防ぐ鍵となります。
脳梗塞を少しでも早く発見できるよう、前兆や初期症状への理解を深めましょう。
脳梗塞の前兆「一過性脳虚血発作(TIA)」
一過性脳虚血発作(TIA: Transient Ischemic Attack)は、脳梗塞と同じ症状が一時的に起こり、通常は数分から数時間以内、多くは24時間以内に自然消失する状態を指します。
すぐに症状が消失したからといって、決して軽視してはいけません。
一過性脳虚血発作を経験した人の約3割※が、後に本格的な脳梗塞を発症します。
※出典:先進医療.net「脳卒中の前触れ発作『一過性脳虚血発作(TIA)』とは」先進医療.net, 2018年1月5日
一時的な症状であっても、次の発作は軽いとは限らず、重度の脳梗塞になる可能性があります。
脳梗塞の初期症状を見逃さないための「FASTチェック」
脳梗塞が疑われる場合、迅速な行動が必要です。
脳梗塞を含む脳卒中の主な症状を簡単に確認できる方法「FASTチェック」を紹介します。
- F(Face):顔の片側が下がる、または笑うと片側だけ動かない
- A(Arm):片方の腕が上がらない、または力が入らない
- S(Speech):言葉がはっきり話せない、ろれつが回らない
- T(Time):上記のFASの症状が見られたら発症時刻を確認し、すぐに救急車を呼ぶ
「F・A・S」の部分でひとつでも当てはまる症状があれば、脳卒中の可能性が高いと言われています。
脳卒中は症状が出てからの時間経過が治療効果を大きく左右するため、T(Time)が特に重要です。
「様子を見よう」と判断せず、すぐに119番通報し、救急車を呼ぶ行動が命を守ることにつながります。
軽い脳梗塞の主な原因と予防方法
軽い脳梗塞の主な原因は以下の7つです。
予防の第一歩は、原因を理解することです。できることから生活に取り入れていきましょう。
高血圧
高血圧は軽い脳梗塞の最も重要な原因の一つです。
血圧が高い状態が続くと血管に強い圧力がかかり、血管の壁が傷つきやすくなります。
傷ついた血管には血の塊ができやすく、これが脳の血管を詰まらせる原因となります。
高血圧の予防には、塩分を控えた食事、適度な運動、十分な睡眠が効果的です。
薬による治療が必要な場合もありますが、生活習慣の改善で血圧をコントロールできることも多くあります。
糖尿病
糖尿病は血液中の糖分が多い状態が続く病気で、脳梗塞のリスクを高めます。
高血糖が続くと血管の内側が傷つき、血液がドロドロになって血の塊ができやすくなります。
糖尿病の予防には、バランスの取れた食事と規則正しい生活リズムが重要です。
とくに炭水化物の摂りすぎに注意し、野菜を多く取り入れた食事を心がけましょう。
既に糖尿病と診断されている方は、血糖値をコントロールし、定期的に血液検査を受けて医師と相談しながら治療を続けることが大切です。
脂質異常症
脂質異常症は血液中のコレステロールや中性脂肪が異常に多い、または善玉コレステロールが少ない状態です。
悪玉コレステロールが増えすぎると血管の壁に蓄積し、血管を狭くして血の流れを悪くします。
この状態が続くと血管が詰まりやすくなり、脳梗塞の原因となります。
脂質異常症の予防には、揚げ物や肉の脂身を控え、魚や野菜を多く摂る食生活が効果的です。
青魚に含まれるEPAやDHAは血液をサラサラにする働きがあります。
運動も脂質の改善に重要で、週に3回以上、30分程度のウォーキングから始めることをおすすめします。
肥満
肥満は他の生活習慣病の原因となり、間接的に脳梗塞のリスクを高めます。
体重が増えすぎると高血圧、糖尿病、脂質異常症を引き起こしやすくなり、脳梗塞の危険性が上がります。
肥満の解消には、摂取カロリーを適切にコントロールすることが重要です。
食塩の1日の適正摂取量は、男性7.5g未満・女性6.5g未満・高血圧対策では6.0g未満が推奨※されています。
※出典:厚生労働省「日本における食塩摂取量の現状と減塩推進への課題」
急激なダイエットではなく、月に1〜2kg程度のペースでゆっくり体重を減らしていきましょう。
また、筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、太りにくい体質になります。
飲酒・喫煙
飲酒と喫煙は脳梗塞の危険因子です。
過度の飲酒は血圧を上昇させ、喫煙は血管を収縮させるため、ともに血液の流れを悪くし脳梗塞の危険因子となります。
脳梗塞を防ぐためには、飲酒を控え、禁煙を目指すことが重要です。
禁煙が難しい場合は、禁煙外来や補助薬の活用も検討しましょう。
運動不足
運動不足は血液の流れを悪くし、生活習慣病の原因となって脳梗塞のリスクを高めます。
定期的な運動は血液の流れを良くし、血圧や血糖値、コレステロール値の改善に効果があります。
運動習慣がない方は、まず1日20〜30分程度のウォーキングから始めましょう。
エレベーターを使わず階段を利用したり、一駅分歩いたりするなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことも効果的です。
ストレス
慢性的なストレスは血圧を上げ、血液をドロドロにして脳梗塞のリスクを高める要因となります。
ストレスが続くと体内でストレスホルモンが分泌され、血管を収縮させて血液の流れを悪くします。
ストレス対策には、十分な睡眠時間の確保、趣味の時間を作る、深呼吸や軽いストレッチなどのリラクゼーション方法が効果的です。
また、人との会話や笑うことも自然なストレス解消になります。
ストレスを完全になくすことは難しいですが、上手に付き合っていく方法を身につけることで、脳梗塞の予防に繋がります。
軽い脳梗塞の再発予防に注目されている「再生医療」について
軽い脳梗塞を経験すると気になるのは「再発するのではないか」という点でしょう。
近年では、脳梗塞の再発予防に関して、再生医療という新しい治療選択肢が注目を集めています。
再生医療とは、患者さま自身の幹細胞を利用して損傷した細胞や組織の再生・修復を促す医療技術のことです。
脳梗塞の再発予防や後遺症の改善を目的とした再生医療について、詳しく知りたい方は当院「リペアセルクリニック」の公式LINEにご登録ください。
公式LINEでは、再生医療についての詳細や脳梗塞の改善症例をご確認いただけます。
軽い脳梗塞に関してよくある質問
軽い脳梗塞に関してよくある以下の質問をご紹介します。
正しい知識を持つことで不安を軽減し、適切な対応ができるようになります。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
軽い脳梗塞になったらどうなる?
軽い脳梗塞になると、一時的な手足のしびれ、ろれつが回らない、言葉が出にくい、めまい、ふらつきなどの症状が現れることがあります。
これらの症状は通常24時間以内に改善することが多く、日常生活への影響は比較的軽微です。
しかし、軽い脳梗塞や一過性脳虚血発作は「警告サイン」とも呼ばれ、将来的により大きな脳梗塞を起こすリスクが高まります。
症状が軽いからといって放置せず、必ず医療機関を受診することが大切です。
軽い脳梗塞は治る?
軽い脳梗塞は、適切な治療により症状の改善が期待できる疾患です。
治療には薬物療法、リハビリテーション、生活習慣の改善が組み合わされます。
薬物療法では血液をサラサラにする薬や血圧を下げる薬などが使用され、再発予防に重要な役割を果たします。
軽い脳梗塞でも油断は禁物!早期発見と治療が回復のカギ
軽い脳梗塞は、一時的な手足のしびれや言葉の出にくさ、めまいなどの症状が現れる脳梗塞です。
症状が短時間で改善することが多いため見過ごされがちですが、放置すると将来的により重篤な脳梗塞を起こす可能性があるため油断はできません。
軽い脳梗塞は早期発見・早期治療により良好な回復が期待できます。
予防・治療法としては、高血圧管理や生活習慣の改善、医師の判断による抗血小板薬の服用などがあります。
早期発見できた場合は、適切な対策を講じて将来の重篤な脳梗塞を予防しましょう。
脳梗塞を含む脳卒中の再発予防や後遺症の改善に対しては、再生医療という選択肢もあります。
再生医療は幹細胞を用いる治療法で、傷ついた血管や組織の再生・修復を促す医療技術のことです。
脳梗塞の再発予防や後遺症でお悩みの方は、当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長