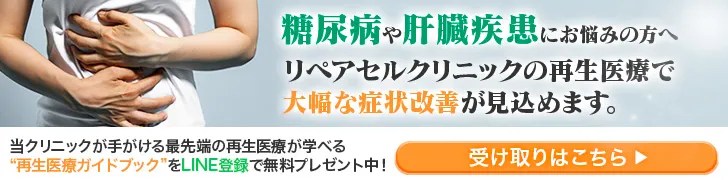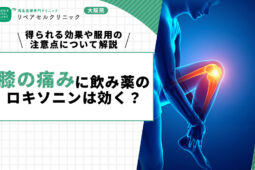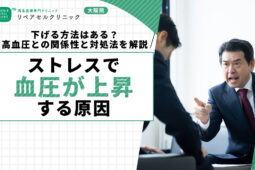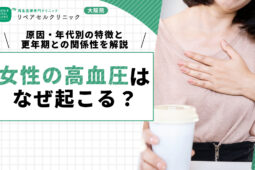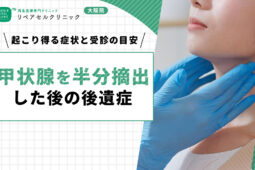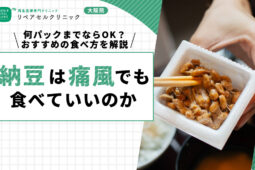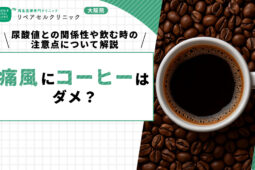- 内科
痛み止めどれがいい?内科医が解説
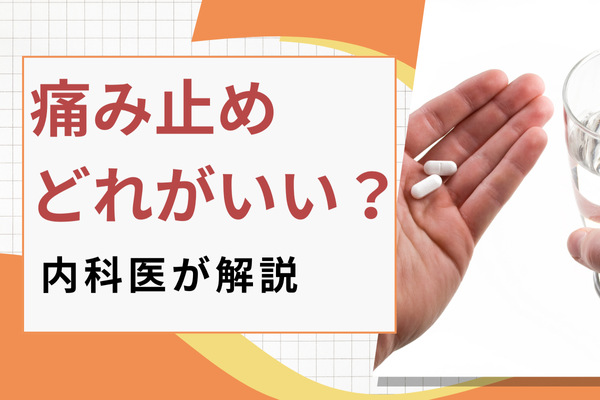
つらい痛み、我慢していませんか?
日常生活を脅かす頭痛、生理痛、神経痛など、痛みは種類も程度も人それぞれ。
市販の痛み止めを飲んでみたけれど効かない、、そんな経験はありませんか?
実は痛み止めには様々な種類があり、その効果や副作用、適切な使い分けを知ることが、痛みを効果的に管理する鍵となります。
この記事では、NSAIDsなどの代表的な痛み止めの種類や効果から、副作用、多剤併用鎮痛法といった一歩進んだ知識まで、医師がわかりやすく解説します。
自分にぴったりの痛み止め選び、そして痛みと賢く付き合う方法を、一緒に探ってみましょう。
痛み止めの種類と効果を知る5つのポイント
痛みは、私たちにとって非常に不快な感覚であり、日常生活に大きな影響を与えます。
痛みを我慢することは、身体的にも精神的にも負担が大きく、生活の質を低下させる可能性があります。
そこで今回は、様々な痛みを和らげる「痛み止め」の種類と効果について、内科専門医がわかりやすく解説します。
年齢や痛みの種類によって適切な薬は異なりますので、この情報を参考に、ご自身に合った痛み止め選びのヒントとして役立ててください。
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の特徴と効果
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は、炎症を抑え、痛みや熱を和らげる効果があります。
「非ステロイド性」とは、ステロイド系の薬ではないことを意味しています。
ステロイド系の薬は強力な抗炎症作用がありますが、副作用も多いため、NSAIDsは比較的安全に使用できる痛み止めとして広く使われています。
よく耳にする「ロキソニン」や「ボルタレン」も、このNSAIDsの一種です。こ
れらの薬は、炎症を起こしている部分に直接作用することで、痛みや腫れ、熱といった症状を改善します。
例えば、ねんざをして足首が腫れて熱を持っている時、NSAIDsを服用すると、炎症が抑えられ、痛みや腫れ、熱が引いていくのです。
| 薬の名前 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| ロキソニン | 筋肉痛、関節痛などに効果を発揮します。 | 腎障害や脳浮腫のリスクがあります。特に、若年者で運動前に服用すると、これらのリスクが高まる可能性があるので注意が必要です。 |
| ボルタレン | 激しい痛みや怪我、捻挫、骨折など急性期の痛みに効果を発揮します。 | 長期間の使用は胃腸への負担となることがあります。 |
| セレコックス | 胃腸への負担が少ない | 他のNSAIDsと比べて高価な場合があります。 |
アセトアミノフェンの特徴と効果
アセトアミノフェンは、比較的副作用が少なく、安全性が高い痛み止めとして知られています。
解熱効果もあるので、風邪などで熱がある時にもよく使われます。「カロナール」という名前で市販されている薬が代表的です。
アセトアミノフェンは、NSAIDsのように炎症を抑える効果は弱いため、強い炎症を伴う痛みにはあまり効果がありません。
しかし、安全性が高いため、子供や高齢者、妊娠中・授乳中の方にも使用できる場合があります。
オピオイド鎮痛薬の特徴と効果
オピオイド鎮痛薬は、他の痛み止めでは効かないような強い痛みに対して使われる、非常に強力な鎮痛薬です。
手術後の痛みや、がんによる痛みなど、激しい痛みに対して効果を発揮します。
しかし、依存性や副作用のリスクがあるため、医師の指示に従って慎重に使用する必要があります。
「トラムセット」のように、アセトアミノフェンとオピオイドを組み合わせた薬もあります。
オピオイド鎮痛薬は、多剤併用鎮痛法の一環として使用されることもあり、パラセタモール(アセトアミノフェンの別名)との併用で相加的または相乗的な効果を発揮し、鎮痛効果を高め、副作用を軽減する可能性が示唆されています。
その他の鎮痛薬(抗うつ薬、抗てんかん薬など)
実は、抗うつ薬や抗てんかん薬といった薬も、特定の痛みに効果を発揮することがあります。
神経痛など、他の痛み止めでは効果が得られないような慢性的な痛みを抱えている方は、医師に相談してみましょう。
これらの薬は、本来の目的とは異なる用途で使用されるため、「適応外使用」と呼ばれます。
痛み止めが効かない時:多剤併用鎮痛法とは
痛みがなかなか取れない、そんな時もあるかもしれません。
痛みの種類や程度、原因は人それぞれ異なるため、一つの痛み止めだけでは効果が不十分な場合があります。
そこで、複数の種類の薬を組み合わせて使う「多剤併用鎮痛法」という方法があります。
それぞれの薬が異なるメカニズムで痛みを抑えるため、単剤よりも高い鎮痛効果が期待できる一方で、薬物相互作用や副作用のリスクも考慮する必要があります。
例えば、NSAIDsとアセトアミノフェンを併用することで、より強い鎮痛効果が得られる場合があります。
また、オピオイド鎮痛薬を使用する場合、パラセタモールとの併用は、オピオイド鎮痛薬の量を減らすことができ、副作用軽減につながる可能性があります。多
剤併用鎮痛法は、特に高齢者で合併症や併用薬が多い場合に、そのメリットが大きくなります。
痛み止めの副作用と注意点6選
痛み止めは、つらい痛みを和らげてくれる頼もしい存在ですが、一方で副作用も存在します。
安全に服用するためには、どのような副作用が起こりうるのか、どのような点に注意すべきなのかを事前に理解しておくことが重要です。
この章では、痛み止めの副作用や注意点、そして副作用が出たときの対処法について、より詳しく解説します。
自分に合った痛み止めを選び、正しく服用することで、痛みを効果的にコントロールし、快適な生活を送れるようにしましょう。
鎮痛薬の種類別の副作用
痛み止めには様々な種類があり、それぞれに特徴的な副作用があります。それぞれの副作用と、その副作用がなぜ起こるのかを理解しておくことが大切です。
-
アセトアミノフェン: 比較的安全性が高い薬として知られていますが、過剰に摂取すると肝臓に負担がかかり、肝機能障害を引き起こす可能性があります。
肝臓は、体内の有害物質を解毒する重要な臓器です。アセトアミノフェンも肝臓で代謝されますが、過剰に摂取すると肝臓の処理能力を超えてしまい、肝細胞がダメージを受けてしまうのです。
決められた服用量を厳守し、用法用量を守ることが非常に大切です。 -
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬): 胃腸障害(吐き気、下痢、胃痛、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)や腎臓への影響(腎機能障害)、まれにですが心血管系への影響(心筋梗塞、脳卒中)などが起こる可能性があります。
NSAIDsは炎症を引き起こす物質の生成を抑えることで効果を発揮しますが、同時に胃腸を守る働きを持つ物質の生成も抑制してしまうため、胃腸障害が起こりやすくなります。
特に、高齢の方や持病のある方は注意が必要です。空腹時の服用を避け、胃腸薬と併用する、あるいはセレコックスのような胃腸への負担が少ないNSAIDsを選択するなどの対策が有効です。
また、腎機能が低下している方は、NSAIDsの服用によって腎機能がさらに悪化する可能性があるため、医師への相談が必要です。
さらに、ロキソニンを運動前に服用すると、腎障害や脳浮腫のリスクを高める可能性があるという報告もあります。これは、運動によって腎血流量が低下している状態でロキソニンを服用すると、腎臓への負担がさらに増大してしまうためと考えられています。 -
オピオイド鎮痛薬: 便秘、眠気、吐き気などが起こりやすいです。
また、長期間使用すると依存性が生じる可能性があり、さらに、呼吸抑制といった重篤な副作用も起こりえます。
医師の指示に従って服用することが非常に重要です。分娩時の疼痛緩和にもオピオイド鎮痛薬が用いられることがありますが、母体と胎児への影響を考慮して慎重に使用する必要があります。
併用禁忌の薬とその理由
一部の痛み止めは、特定の薬と一緒に服用すると、効果が弱まったり、副作用が強まったり、あるいは予期せぬ重篤な副作用が生じる可能性があります。
例えば、ワーファリンなどの抗凝固薬とNSAIDsを併用すると、出血しやすくなる作用が重なってしまい、出血のリスクが高まる可能性があります。
また、一部の抗うつ薬と特定の痛み止めを併用すると、セロトニン症候群という、精神状態の変化、自律神経系の異常、神経筋の異常を特徴とする重篤な副作用が起こる可能性があります。
服用中の薬がある場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
妊娠中・授乳中の服用について
妊娠中や授乳中は、服用できる薬が限られます。胎盤や母乳を通じて薬の成分が胎児や乳児に移行し、影響を与える可能性があるためです。
アセトアミノフェンは、他の鎮痛薬と比較して比較的安全とされていますが、それでも医師や薬剤師に相談してから服用することが推奨されます。
NSAIDsは、妊娠後期に服用すると、胎児の動脈管収縮などを引き起こし、胎児に悪影響を与える可能性があるため、一般的には避けられます。
オピオイド鎮痛薬も、胎児や新生児に影響を与える可能性があります。自己判断で服用せず、必ず医師の指示に従ってください。
分娩時の疼痛緩和には、硬膜外鎮痛法が最も効果的ですが、患者さんの希望や状況によっては、笑気やオピオイド、非オピオイドなどの全身薬物療法が用いられます。
薬剤によって母体や胎児への副作用が異なるため、医師と相談して適切な方法を選択することが重要です。
子供・高齢者の服用時の注意点

子供には、年齢や体重に合わせた適切な用量を服用させることが重要です。
高齢者も、少量から開始し、様子を見ながら徐々に増量していくなどの配慮が必要です。
また、高齢者は複数の薬を併用している場合が多いため、飲み合わせにも注意が必要です。
アセトアミノフェンは、小児や高齢者にも比較的安全に使用できることが多いですが、それでも用量には注意が必要です。
痛み止めの依存性と対策
オピオイド鎮痛薬は、長期間使用すると依存性が生じる可能性があります。
身体的依存と精神的依存があり、身体的依存は、薬を急にやめると離脱症状(吐き気、嘔吐、下痢、発汗、震えなど)が現れる状態です。
精神的依存は、薬がないと不安になったり、薬を求める気持ちが強くなったりする状態です。
依存性を防ぐためには、医師の指示に従って服用し、自己判断で増量したり、長期間服用したりしないことが重要です。
また、痛みが治まったら、医師の指導の下、徐々に減量していくことが必要です。
副作用が出た場合の対処法
痛み止めを服用して、何か異変を感じたら、すぐに服用を中止し、医師や薬剤師に相談しましょう。
自己判断で他の薬を服用したり、症状を我慢したりすることは危険です。適切な対処を受けることで、重篤な事態を防ぐことができます。
自分に合った痛み止めの選び方4つのステップ

痛みを我慢せず、適切な痛み止めを使用して痛みをコントロールすることは、生活の質を向上させる上で非常に重要です。
しかし、痛み止めにも様々な種類があり、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、自分に合った痛み止めを選ぶための4つのステップをご紹介いたします。
痛みの種類(頭痛、生理痛、神経痛など)に合った薬
痛みには、ズキズキとした頭痛、鈍い生理痛、ピリピリとした神経痛など、様々な種類があります。
痛みの種類によって、効果的な痛み止めも異なります。
例えば、頭痛にはアセトアミノフェンやイブプロフェンなどの市販薬が有効ですが、神経痛にはこれらの薬はあまり効かず、プレガバリンやデュロキセチンといった処方薬が必要となることがあります。
医師は、痛みの種類を正確に診断し、最適な薬剤を選択するお手伝いをいたしますので、自己判断で薬を選ぶのではなく、医療機関を受診して適切なアドバイスを受けるようにしてください。
痛みの程度(軽い、中程度、激しい)に合った薬
痛みの程度も、痛み止めの選択において重要な要素です。
軽い痛みであれば、アセトアミノフェンなどの市販薬で十分な場合もありますが、中程度以上の痛みには、より強力な鎮痛効果を持つNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が必要となることもあります。
激しい痛みには、オピオイド系鎮痛薬が用いられることもありますが、これらは依存性や副作用のリスクがあるため、医師の指示に従って慎重に使用する必要があります。
痛みの程度を正確に伝えることは、適切な薬剤を選択する上で非常に重要です。
例えば、「我慢できる程度の痛み」や「耐えられないほどの痛み」といった表現ではなく、「10段階でいうとどの程度の痛みか」といった具体的な表現で医師に伝えることで、より的確な診断と治療を受けることができます。
持病や体質に合った薬
持病がある場合や特定の薬にアレルギーがある場合は、痛み止めの選択にさらに注意が必要です。
例えば、胃腸が弱い方は、NSAIDsによって胃腸障害を起こしやすいため、アセトアミノフェンやセレコキシブなど、胃腸への負担が少ない痛み止めを選択する必要があります。
高齢者や腎機能が低下している方は、薬の代謝が遅くなるため、薬の量を調整する必要があります。また、妊娠中や授乳中の場合は、胎児や乳児への影響を考慮して、医師に相談しながら服用する薬を決めることが重要です。
特に、妊娠後期にNSAIDsを服用すると、胎児の動脈管収縮などを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
分娩時の疼痛緩和には硬膜外鎮痛法が最も効果的ですが、患者さんの希望や状況によっては笑気やオピオイド、非オピオイドなどの全身薬物療法が用いられます。
薬剤によって母体や胎児への副作用が異なるため、医師と相談して適切な方法を選択することが重要です。
市販薬と病院で処方される薬の違い
市販薬と病院で処方される薬は、主成分が同じでも、用量や剤形が異なる場合があります。
市販薬は比較的軽い痛みに対して使用されることが多い一方、病院で処方される薬は、より強い痛みや慢性的な痛みに対して使用されます。
市販薬は手軽に入手できるというメリットがありますが、持病がある場合や複数の薬を服用している場合は、医師の診察を受けて自分に合った薬を処方してもらう方が安全です。
パラセタモールは、単独で使用されることもありますが、他の鎮痛薬、例えばオピオイドと組み合わせて使用されることもあり、その相乗効果で鎮痛効果を高め、副作用を軽減する可能性が示唆されています。
参考文献
- Freo U. “Paracetamol for multimodal analgesia.” Pain management 12, no. 6 (2022): 737-750.
- Zuarez-Easton S, Erez O, Zafran N, Carmeli J, Garmi G, Salim R. “Pharmacologic and nonpharmacologic options for pain relief during labor: an expert review.” American journal of obstetrics and gynecology 228, no. 5S (2023): S1246-S1259.
監修医師 リペアセルクリニック
内科専門医 渡久地 政尚

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長