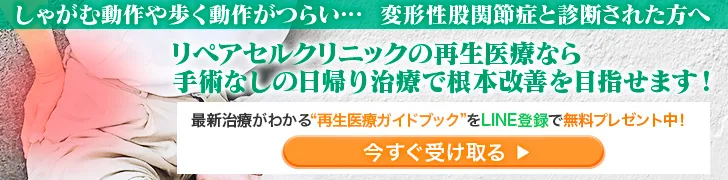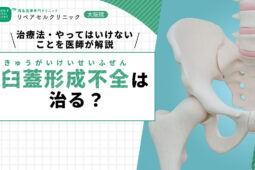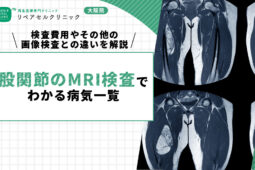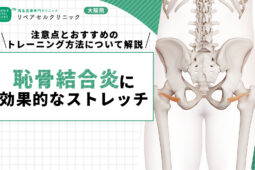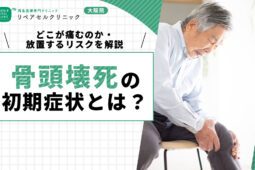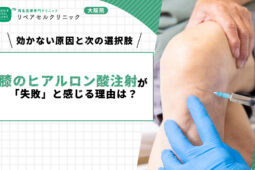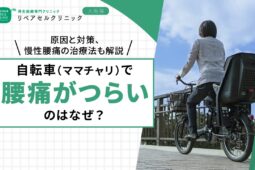- 股関節
- 再生治療
股関節唇損傷はどのくらいで治る?復帰までの期間や予防に効果的なストレッチを解説
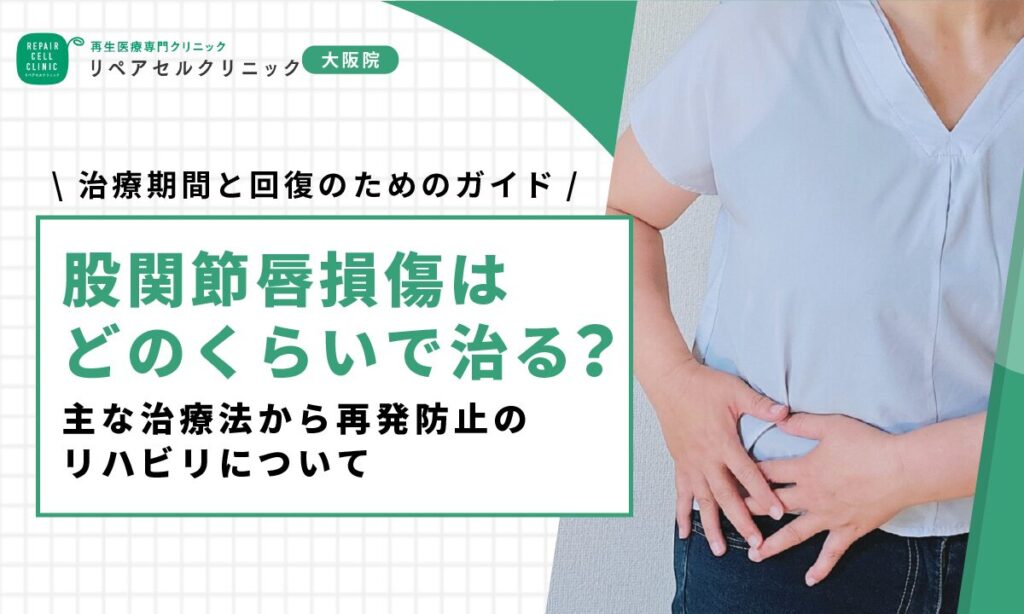
「股関節唇損傷はどのくらいで治る?」
「痛みを早く治す方法はない?」
股関節唇損傷は、股関節の受け皿部分の縁である関節唇が損傷した状態のことです。
日常生活に復帰できるまでの期間は、保存療法で約2〜3カ月、手術した場合は約2〜3週間程度が目安です。
本記事では、股関節唇損傷が治る期間や治療方法について詳しく解説します。
また、股関節唇損傷を早く治したい方は、先端医療である再生医療も選択肢の一つです。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、股関節唇損傷の治療として注目されている再生医療に関する内容や症例を公開中です。
「現在の治療で期待した効果が出ていない方」「股関節唇損傷を早く治したい方」は、ぜひ再生医療について知っておきましょう。
目次
股関節唇損傷はどのくらいで治る?
股関節唇損傷の治療期間を、日常へ復帰する期間とスポーツへ復帰する期間の2つに分けて紹介します。
股関節唇は自然に回復することはほぼない組織なので、適切な治療を受けることが重要です。
治療期間について理解し、治療やリハビリを乗り越えましょう。
日常生活へ復帰するまでの期間
股関節唇損傷から日常生活に復帰できるまでの期間は、保存療法で約2〜3カ月、手術した場合は約2〜3週間程度が目安です。
- 保存療法:約2〜3カ月
- 手術療法:約2〜3週間
手術を行わず、鎮痛薬の内服、関節内注射、リハビリテーションなどで症状の改善を図る保存療法では、おおよそ2〜3カ月が回復の目安とされています。
一方、関節鏡を用いた手術で損傷した関節唇を縫合・修復した場合、約2〜3週間で日常の動作ができます。
関節の可動域や筋力を回復させるために、数カ月間の段階的なリハビリが必要です。
保存療法、手術療法いずれの場合でも、再発や悪化を防ぐためには股関節に過度な負担をかけない生活習慣を身につけることが重要です。
正しい姿勢や歩き方を意識し、股関節に負担の少ない動作を習慣化して、スムーズな回復を目指しましょう。
スポーツへ復帰するまでの期間
股関節唇損傷からスポーツに復帰できるまでの期間は、約4〜6カ月程度です。
競技レベルや股関節唇の損傷程度によって異なりますが、手術した際の回復までの流れの目安は、以下の通りです。
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 術後2〜3週間 | 歩行、関節可動域の改善など基本動作のリハビリ |
| 3カ月頃 | 軽いジョギングの再開が可能になる場合がある |
| 4〜6カ月 | スポーツ復帰を本格的に目指す |
股関節は、スポーツ動作において高い安定性や柔軟性、筋力が求められるため、日常生活に戻るよりも長いリハビリ期間が必要になる傾向にあります。
サッカーやバスケットボール、格闘技などのジャンプ・ダッシュ・深くしゃがむ動作などが含まれる競技では、完全復帰までの時間が長くなるため、長い目で治療に取り組みましょう。
股関節唇損傷の再発や痛みを防ぐためには、股関節をねじる動きや大きく開脚する動作は慎重に行うことが重要です。
股関節唇損傷を早く治すためにやってはいけないこと
股関節唇損傷を早く治すためにやってはいけないことは、以下の通りです。
| やってはいけないこと | 詳細 |
|---|---|
| 深くしゃがみ込む動作 | 床に座る・長時間しゃがむなどは、股関節への圧力が強く、損傷を悪化させる原因になる |
| ジャンプやダッシュなどの急激な運動 | 衝撃や瞬発的な力が股関節に負担をかけ、炎症や再損傷のリスクが高まる |
| 股関節を強くねじる動き | テニス・水泳・ゴルフなどの動作で起こりやすく、関節唇にストレスを与える可能性がある |
| 過剰なスクワットや筋トレ | 深くしゃがむ動きや高負荷のトレーニングは避け、軽度な運動から始める |
| 片脚に偏った姿勢・立ち方 | 体重を片側にかけるクセがあると、股関節に不均等なストレスが加わり回復を妨げる恐れがある |
股関節唇損傷を早く治すには、日常の何気ない動作にも細心の注意が必要です。
上記で紹介している内容は、患部に過度な負担をかけてしまうため意識して避けましょう。
股関節唇損傷は治らない?主な治療方法
股関節唇損傷の治療方法について紹介します。
再生医療は、手術なしで組織の修復や痛みの軽減が期待できる治療法で、新たな選択肢として注目されています。
保存療法
股関節唇損傷の治療では、約3カ月間の保存療法が試みられるのが一般的です。
手術をせずに痛みの緩和や機能改善を目指す方法で、体への負担が少ない点が特徴です。
主な治療内容は、以下のとおりです。
| 治療内容 | 具体例 |
|---|---|
| 安静 | 炎症や痛みが強い時期は、ベッド上で安静にし、関節への負担を抑える |
| 薬物療法 | NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)やステロイド注射などで痛みや炎症をコントロールする |
| 運動療法(リハビリ) | 股関節まわりの筋肉を強化し、骨盤・体幹の柔軟性と安定性を高める |
| 生活動作の見直し | 深くしゃがむ、あぐらをかく、柔らかいソファに沈み込むなど、股関節を深く曲げる動作を避ける |
保存療法は、痛みや症状の緩和を目的としており、股関節唇の損傷の修復はできません。
症状が再発したり、効果が不十分だったりする際は、手術療法が検討されることもあります。
手術療法
保存療法で効果が見られない場合や、痛みが強く日常生活やスポーツ活動に支障をきたしている場合には、手術療法が検討されます。
とくに、アスリートや若年層では、再発防止や競技復帰のために早期の手術が推奨されるケースもあります。
股関節唇損傷の主な手術は、次の2種類です。
| 手術名 | 内容 |
|---|---|
| 股関節唇修復術 | 損傷した関節唇を縫合して、元の位置に固定する |
| 股関節唇再建術 | 損傷部分を切除し、大腿筋膜張筋などから採取した自家組織を移植して補う |
股関節唇損傷の手術では、カメラ付きの器具である関節鏡を用いるのが一般的です。
適切な術後リハビリを経ることで、保存療法よりも早期の回復・痛みの改善が期待できます。
ただし関節鏡手術は、以下のような注意点もあります。
- 高度な技術が必要で、対応できる施設が限られている
- 感染、出血、術後の再発など合併症のリスクがある
医師と十分に相談し、自分の症状や生活スタイルに合った治療方針を立てましょう。
再生医療
幹細胞を活用した再生医療は、近年注目されている股関節唇損傷の新しい治療法です。
患者さまの脂肪組織から採取・培養した幹細胞を患部に注射し、傷ついた組織の修復促進を目指します。
体への負担が少なく、手術や入院の必要がないことから、次のような方に選ばれています。
- 手術を避けたい方
- 保存療法や手術療法で期待した効果が出ていない方
- スポーツへの早期復帰を目指したい方
- 仕事や家庭の都合で長期療養が難しい方
再生医療の治療に興味のある方は、お気軽に当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
股関節の痛みは⼿術しなくても治療できる時代です。
股関節唇損傷の再発予防に効果的なリハビリテーション
股関節唇損傷の再発予防に効果的なリハビリテーションは、以下の通りです。
リハビリテーションでは、股関節の可動域を広げたり、股関節周辺の筋力をアップしたりするトレーニングを行います。
トレーニングの内容は症状によって異なるので、理学療法士や作業療法士の指導に従いましょう。
股関節周辺のストレッチ
股関節唇損傷の治療後に行うリハビリテーションでは、股関節の可動域トレーニングが重要です。
自宅でも簡単に実践できるストレッチは、以下の通りです。
| ストレッチの部位 | 手順 |
|---|---|
| 腸腰筋(腰から足の付け根に渡るインナーマッスル) |
1.仰向けになり片膝を立てる |
| 大臀筋 |
1.仰向けになり片膝を立てる |
ストレッチを毎日の習慣に取り入れることで、股関節の柔軟性が高まり、股関節唇損傷の再発防止につながります。
痛みや違和感がある場合は無理せず、専門家に相談しながら行いましょう。
股関節周辺の筋力トレーニング
股関節唇損傷からの回復後も、再発を防ぐには股関節を支える筋肉を鍛えることが重要です。
筋力が弱いと正しい姿勢を保てず関節に負荷がかかり、股関節唇損傷の再発リスクが高まります。
自宅で無理なくできる基本のトレーニングは、以下の通りです。
| トレーニングの部位 | 手順 |
|---|---|
| 中殿筋(骨盤の外側上部) |
1.横向きに寝て、上体をまっすぐに保つ |
| 大臀筋 |
1.うつ伏せになり、骨盤が浮かないよう意識する |
トレーニングでは、最初は回数を少なめに設定し体調や筋力に応じて少しずつ増やしましょう。
無理のない範囲で行い、痛みが出る場合は中止してください。
股関節唇損傷の治療期間についてよくある質問
股関節唇損傷の治療期間についてよくある質問は、以下の通りです。
疑問を解消して、適切な治療に取り組みましょう。
股関節唇損傷の安静期間は?
股関節唇損傷の安静期間は、約2~3日が望ましい※とされています。
※出典:PubMed
症状が現れた直後は炎症が強く出るため、まずは安静・冷却・圧迫などの応急処置を行いましょう。
手術しないでリハビリや薬物療法などで対応する保存療法を選択した場合は、炎症や痛みが治まるまで関節への負担を避けましょう。
股関節唇損傷の初期症状は?
股関節唇損傷の初期症状では、股関節の痛みを感じたり、股関節が引っかかる感じがしたりします。
- 股関節を曲げたりひねったりすると痛みが出る
- 長時間の立ち仕事や歩行後に違和感が出る
- 股関節に引っかかるような感覚がある
- 股関節を動かしにくくなったように感じる
上記のような症状がある場合、放置すると症状が徐々に悪化し、治るまでにかかる期間も長くなるおそれがあります。
早期に専門医を受診すれば、治療期間を短くできる可能性があります。
股関節唇損傷を放置するとどうなる?
股関節唇損傷を放置すると、痛みや引っかかり感が悪化し、変形性股関節症のリスクが高まる可能性も指摘されています。
症状が進行すると治療期間が長くなり、保存療法だけでなく手術が必要になるケースも増えます。
早期の診断と適切な治療が、回復を早めるために重要です。
変形性股関節症については以下のコラムで詳しく解説しているので参考にしてください。
股関節唇損傷を早く治すなら再生医療をご検討ください
股関節唇損傷が治る期間は症状によって異なります。
保存療法での日常生活の復帰に約2~3カ月、手術を行った場合は約2〜3週間かかります。
スポーツへの復帰には、通常4〜6カ月ほどかかるケースが多いです。
早期回復のためには、深くしゃがむ、ジャンプやダッシュといった股関節に強い負荷をかける動作は控えましょう。
関節唇は自然には再生しない組織のため、痛みが続く場合は早めに整形外科を受診することが重要です。
股関節唇損傷の治療には保存療法や手術だけでなく、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療は手術や入院が不要で、損傷した股関節唇の修復を促すことで根本的な改善を目指す治療法です。
股関節唇損傷を早く治したいとお考えの方は、当院「リペアセルクリニック」までお問い合わせください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設