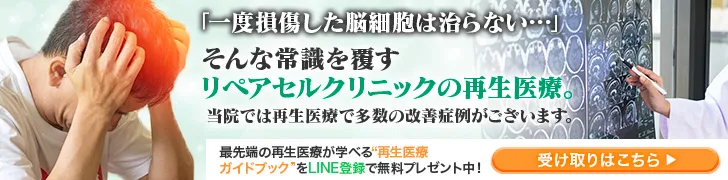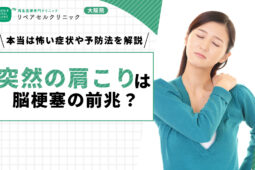- 頭部
- 再生治療
脳挫傷の後遺症はいつまで続く?主な症状と治療も解説
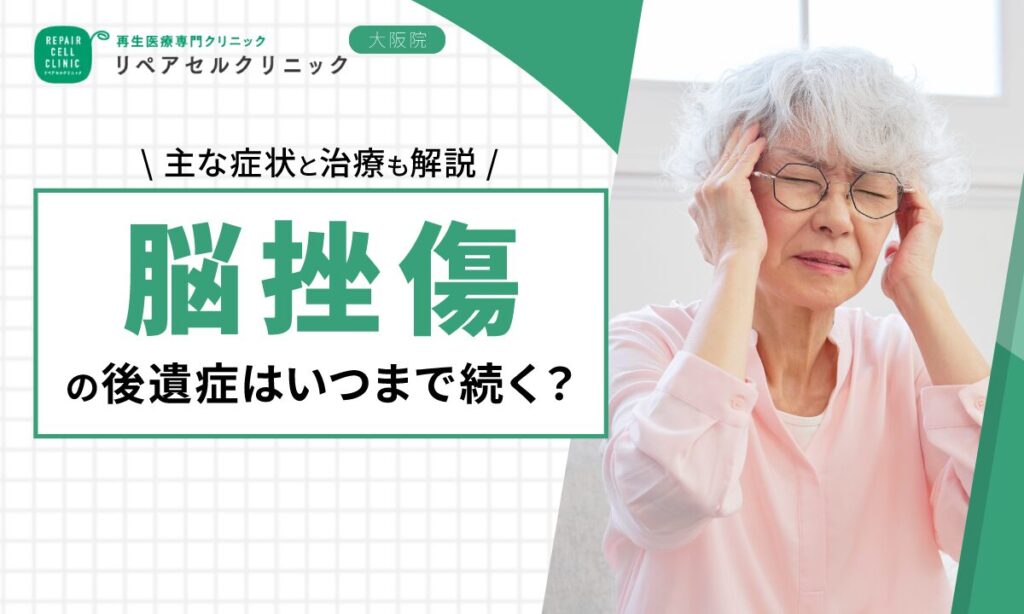
「事故から時間が経ったのに体調が戻らない」「脳挫傷の後遺症はいつまで続く?」「物忘れが増えた気がする」といったお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
脳挫傷の後遺症は、発症直後だけでなく退院後にゆっくり現れることもあり、患者様やご家族が不安を抱えやすい特徴があります。
脳挫傷は、脳に強い衝撃が加わることで起こる外傷性脳損傷のひとつで、損傷部位によって後遺症の出方が大きく異なります。
そこで本記事では、脳挫傷の後遺症として現れやすい症状を分かりやすく整理したうえで、回復までの流れや日常生活でできる工夫、そして後半では再生医療という新しい選択肢についても解説します。
目次
脳挫傷の主な後遺症
脳挫傷の後遺症は、身体・認知・感情・発作など複数の領域に影響が及ぶことがあります。
脳挫傷は損傷部位によって症状の種類が大きく変わるため、「どの後遺症が出るか」には個人差があります。
身体面の症状だけでなく、記憶力や注意力、感情の安定性に影響することもあり、患者様やご家族が「性格が変わったように見える」と感じる場合もあります。
ここからは、それぞれの後遺症を順番に解説していきます。
身体症状:麻痺・しびれ・歩行障害など
脳挫傷では、損傷部位に応じて麻痺やしびれ・歩行のしづらさが現れることがあります。
脳が運動・感覚を司る領域に損傷を受けると、手足の動かしにくさ、細かい作業のしづらさ、しびれなどが続くことがあります。
症状の程度は個人差が大きく、疲れやストレスで症状が強く出ることも珍しくありません。
- 手足の麻痺(動かしづらい・力が入りにくい)
- しびれや感覚の鈍さ
- 歩行のバランスが取りにくい
- 疲れやすさが目立つ
- 細かい動きが難しくなる
身体症状はリハビリにより改善が見られるケースもありますが、無理をすると逆に疲労が強くなることもあるため、適度な休息と段階的な訓練が重要です。
高次脳機能障害:記憶障害・注意障害・感情コントロールの難しさ
脳挫傷では、記憶・注意・感情に関わる領域が影響を受けると「高次脳機能障害」が現れることがあります。
高次脳機能障害は外見から分かりにくいため、周囲に理解されにくい特徴があります。
患者様自身も「なぜできないのか」が分からず戸惑うことがあり、生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。
- 記憶のしづらさ(忘れ物が増える)
- 注意力の低下(集中が続かない)
- 感情コントロールの難しさ
- 段取りや判断力の低下
- 疲れやすさが顕著に現れる
感情の変化や注意力の波は「性格の問題」ではなく、脳機能の障害による影響です。
周囲の理解と環境調整が、生活を支える大きな力になります。
外傷性てんかんや頭痛・めまいなどの症状
脳挫傷では、外傷性てんかんや頭痛・めまいなどの症状が後から現れることがあります。
外傷性てんかんは脳の損傷部位が刺激となり、発作につながる状態です。
また、脳がダメージを受けたあとには頭痛や倦怠感、めまいが続く患者様も多くいます。これらは「後から出てくる後遺症」として注意が必要です。
- 外傷性てんかん(発作の可能性)
- 頭痛や圧迫感
- めまいやふらつき
- 倦怠感が続く
- 睡眠リズムの乱れ
これらの症状は生活の質に大きく影響しやすいため、医療機関と連携しながら適切に管理することが重要です。
次の章では、後遺症がどこまで回復するのか、リハビリの進み方とあわせて整理していきます。
後遺症はどこまで回復する?リハビリと日常生活でできること
脳挫傷の後遺症は、適切なリハビリと生活環境の調整を継続することで改善が期待できる部分があります。
脳挫傷による後遺症は、時間の経過とともに変化していきます。
特に発症直後から数か月は回復が進みやすい時期とされており、その後もリハビリの継続によって生活が安定しやすくなるケースがあります。
ただし、脳の損傷範囲や生活環境などによって回復速度には個人差があります。
それでは、後遺症がどのような過程を経て回復していくのかを詳しく見ていきましょう。
回復のタイムラインの目安(急性期〜回復期〜慢性期)
脳挫傷の回復は急性期・回復期・慢性期の3段階に分かれ、特に最初の数か月が重要とされています。
脳挫傷は外傷のため、脳の腫れや血腫が落ち着くまで時間が必要です。
時間の経過に合わせて脳の状態が変化し、改善が進む時期と落ちつく時期が現れます。これは医学的な自然回復のプロセスに基づいており、期間の長さや改善の度合いには個人差があります。
- 急性期(発症〜約1か月):脳の炎症やむくみが落ち着く時期
- 回復期(1か月〜6か月):自然回復が進みやすい時期
- 慢性期(6か月以降):改善はゆっくりだが継続的な変化が期待できる時期
6か月以降は「改善が止まる」と思われがちですが、実際には環境調整や訓練により日常生活が安定していくケースもあります。
焦らず、患者様に合わせたペースで取り組むことが大切です。
リハビリの役割(PT・OT・ST)と継続の重要性
脳挫傷後のリハビリは、身体・認知・会話の機能を整えるために欠かせない取り組みです。
脳挫傷では、身体機能だけでなく認知やコミュニケーションにも影響が及ぶことがあるため、複数の専門職が協力して支えていく必要があります。
PT・OT・STはそれぞれ役割が異なり、患者様の生活を多面的に支援します。
- PT(理学療法士):歩行・バランスなど身体機能の改善をサポート
- OT(作業療法士):日常生活動作(食事・更衣など)の訓練
- ST(言語聴覚士):言語機能や認知機能のサポート
リハビリは短期間で結果が出るものではなく、継続することで少しずつできることが増えていきます。
また、疲労の影響を受けやすいため、無理な負荷ではなく患者様のペースを尊重することが重要です。
一般的な治療だけでは改善しにくい場合の再生医療という選択肢
脳挫傷の後遺症が長引く場合、再生医療(幹細胞治療)が追加の選択肢として相談されるケースがあります。
脳挫傷による後遺症は、身体・認知・感情・疲労など複数の領域に及ぶため、一般的なリハビリや薬物療法だけでは改善の実感が得られにくい患者様もいらっしゃいます。
そのため、身体が本来持つ力に着目した再生医療が、選択肢のひとつとして検討されることが増えています。
幹細胞を用いた治療は負担の少ないアプローチとして注目が高まっており、「長期化している後遺症に何かできることはないか」と悩む患者様にとって、治療選択肢を広げる一つの方法となることがあります。
- 高次脳機能障害(記憶・注意・感情など)の不調が続く
- しびれや疲労感が長期化している
- 頭痛・めまいが慢性的に続く
- 日常生活動作が回復せず不安が続く
- リハビリだけでは停滞を感じている
- 将来に向けて治療の選択肢を広げたい患者様
リペアセルクリニック大阪院では、再生医療に精通した医師が患者様の状態や生活背景を丁寧にヒアリングし、メリット・デメリットを分かりやすく説明したうえで、適切な方にのみ治療を提案しています。
- 再生医療を専門とする医師が担当
- 丁寧なカウンセリングで不安や疑問に寄り添う
- 後遺症の種類に応じたオーダーメイドの提案
- 無理な治療推奨を行わない誠実な診療体制
- 生活・自主トレのアドバイスも一緒に提供
- プライバシーを守る落ち着いた院内環境
- 相談のみの来院でも歓迎
脳挫傷の後遺症は、患者様とご家族にとって長く不安を抱えやすいものです。
「このままで大丈夫なのか」「治療の選択肢は他にないのか」と感じる場合は、一度専門医に相談することで、より納得感のある方向性を考えやすくなるでしょう。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
後遺症と向き合いながら「今できる最善の一歩」を選ぶことが重要
脳挫傷の後遺症と向き合うには、焦らず現状を整理し、今できる最善の一歩から積み重ねていくことが大切です。
脳挫傷の後遺症は、ご本人もご家族も不安を抱えやすく、「どこまで回復するのか」「いつまで続くのか」と悩むことが少なくありません。
回復はゆっくり進むことも多いため、焦って負荷をかけすぎるよりも、できることから一つずつ取り組む姿勢が生活の安定につながります。
リハビリ・生活リズム・休息・医療機関のサポートを組み合わせることで、改善の可能性が広がるケースもあるため、ひとりで抱え込まず環境を整えることが重要です。
- 症状を正しく理解して焦らず向き合う
- 日常生活の工夫を少しずつ取り入れる
- 専門的なリハビリを継続する
- 不調の変化を医師に相談する
- 選択肢として再生医療を知っておく
- 抱え込まず相談できる環境を整える
脳挫傷の後遺症は、改善までの期間が見えにくいことから、患者様自身が不安を抱え込みやすい状態です。
しかし、「できている部分」「変化が見られた部分」に目を向けることで、前向きな気持ちを保ちやすくなります。
また、一般的な治療やリハビリだけでは不安が残る場合、再生医療のような選択肢を知っておくことで、今後の方針を考えるヒントになります
リペアセルクリニック大阪院では、脳挫傷の後遺症でお悩みの患者様に対して、状態の丁寧なヒアリングと総合的な視点からのサポートを行っています。
生活面・リハビリの方向性・治療の選択肢など、患者様の気持ちに寄り添いながら案内する体制が整っています。
一人で抱え込まず、まずは専門医に相談することで、これからの生活に向けた最善の一歩を一緒に考えていきましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長