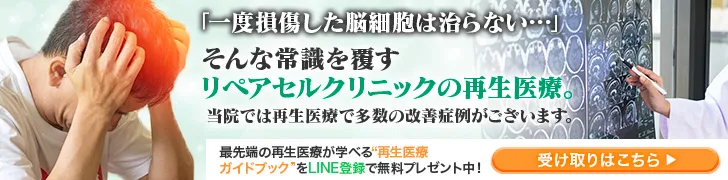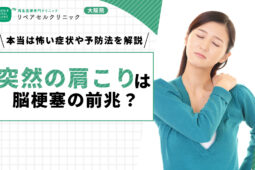- 頭部
高次脳機能障害は治るのか|医学的な回復の限界と改善の可能性を専門的に解説
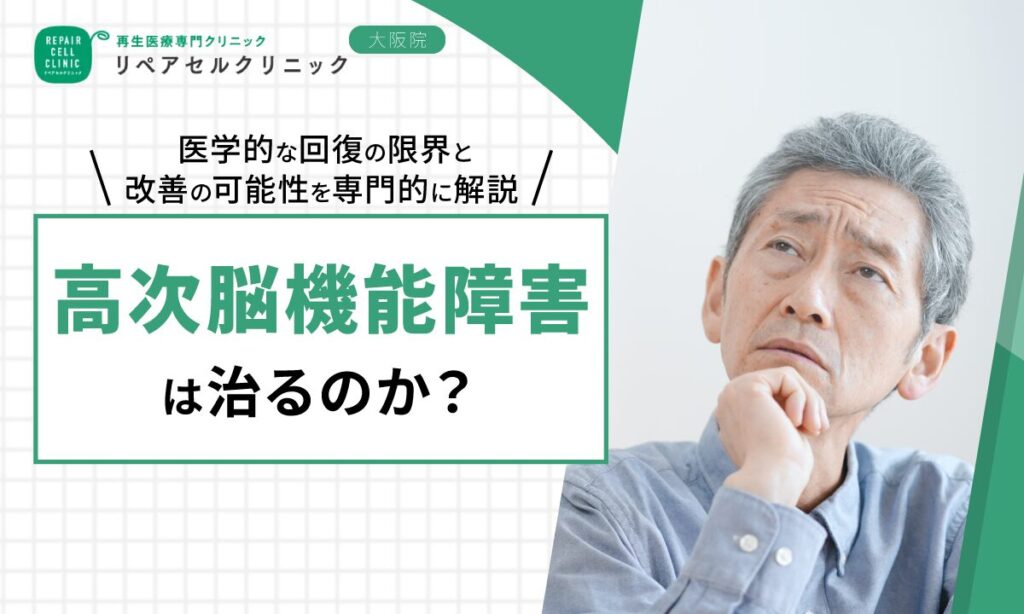
「高次脳機能障害はどこまで治るのか」「この先も改善の余地はあるのか」と不安を抱えている患者様やご家族は多くいらっしゃいます。
記憶力や注意力、感情の調整など、普段の生活に関わる能力が影響を受けるため、将来への心配が大きくなりやすい状態です。
高次脳機能障害は一見すると改善が難しいように思われがちですが、医学的な知見では回復の時期や改善が見込める要素が存在するとされており、適切なケアと環境が重要だと考えられています。
本記事では、高次脳機能障害の仕組みから回復の見通し、改善が期待できるタイミング、症状ごとの傾向、そして後半では再生医療という新しい選択肢まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。
目次
高次脳機能障害は改善するのか?医学的な見解から解説
高次脳機能障害は改善が見られる可能性がありますが、症状や損傷部位により回復の幅が大きく異なるとされています。
脳には「可塑性(かそせい)」と呼ばれる柔軟な仕組みがあり、発症後の一定期間は機能が補われたり、新しい回路が作られたりすることで改善することが確認されています。
ここからは、高次脳機能障害の基本的な理解から、自然回復のタイミング、回復が難しいと言われる背景まで、専門的な内容を分かりやすく整理して解説していきます。
そもそも高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって「記憶・注意・判断・感情のコントロール」などの認知機能が影響を受ける状態を指します。
脳梗塞や頭部外傷などで脳の特定部位がダメージを受けると、身体の麻痺とは異なる“見えにくい障害”として、生活の細かい部分に支障が出る場合があります
。忘れやすい、段取りが難しい、集中が続かない、感情が不安定になるなど、症状は多岐にわたり、個人差が大きいことが特徴です。
- 記憶:新しい情報を覚えにくい
- 注意:集中が続かない・気が散りやすい
- 遂行機能:段取り・計画が立てにくい
- 社会的行動:感情のコントロールが難しい
- 認知:物の意味や状況の理解に時間がかかる
外見では分かりにくいため周囲に理解されにくいことも多く、ご本人だけでなくご家族にとっても負担が大きくなることがあります。
まずは症状の特徴を正しく理解し、必要なサポートや環境調整を行うことが回復の第一歩となります。
自然回復が見込める期間
高次脳機能障害は、発症から数か月〜1年前後までが自然回復の期待できる時期とされています。
脳は損傷を受けても、新しい神経回路を作ったり残った細胞が機能を補い合ったりする「可塑性」という働きを持ちます。
この仕組みが最も活発に働くのが発症後の早い時期であり、集中したリハビリや環境調整で生活動作が整いやすくなることが知られています。
- 発症〜数週間:症状が大きく変化しやすい時期
- 1〜3か月:可塑性が高く改善が期待されやすい
- 6か月前後:改善のスピードが徐々に落ち着く
- 1年前後:自然回復のピークは過ぎることが多い
- 1年以降:改善は緩やかだが工夫で生活は整えられる
自然回復のピークが落ち着いた後も、生活の工夫や継続的な訓練によって日常動作が安定するケースは多くあります
。「もう変わらない」と思い込まず、少しずつ取り組むことで変化が出る可能性を広げることが大切です。
後遺症が残りやすい理由
高次脳機能障害は「脳の高度な機能」を担う部分が損傷するため、後遺症が残りやすいとされています。
記憶・感情・判断・注意などの能力は、脳の複数の領域が連携することで成り立っています。
そのため、どこか1つの部位が損傷しただけでも広い範囲に影響が出る可能性があります。
また、身体機能と異なり損傷の程度が外から見えにくいため、回復のスピードや方向性が人によって大きく異なります。
- 脳の高次機能は複数部位が関係するため影響範囲が広い
- 損傷の部位によって症状が大きく異なる
- 外見で判断しにくいため対応が遅れがち
- 本人の自覚が薄いケースがある
- 改善のスピードがゆっくりで見えにくい
後遺症が続く理由は「治らない」という意味ではなく、脳の複雑な機能が関わっているため変化がゆっくり進むという特徴によるものです。
適切な支援や専門的なケアを組み合わせることで、負担の軽減や生活の改善が期待できるケースもあります。
どこまで改善できる?代表的な症状ごとの回復傾向
高次脳機能障害の回復度合いは症状ごとに異なり、一定の改善が見られるケースがある一方で、長く続く後遺症もあります。
高次脳機能障害は“ひとまとめ”に語られがちですが、実際には記憶・注意・感情の調整・遂行機能など、複数の能力が関係しており、それぞれ回復のスピードや方向性が大きく変わります。
また、患者様の年齢・発症原因・損傷部位・サポート環境などによっても進み方は違うため、「この症状なら必ず治る」「絶対に改善しない」という表現は避けられます。
しかし、医学的には“改善が期待できる領域”と“残存することが多い領域”が存在するとされ、これらを理解しておくことで今後のリハビリ方針や生活の工夫が決めやすくなります。
- 注意障害:比較的改善が見られやすい
- 記憶障害:改善はゆっくり、代償手段の活用が重要
- 遂行機能障害:環境調整と支援で生活が安定しやすい
- 社会的行動障害:周囲の理解とサポートで改善の幅が変わる
- 情緒の不安定:時間と環境調整で落ち着くことが多い
高次脳機能障害は、脳の複数の領域が関わるため回復の進み方に個人差が出やすい障害です。
そのため、「症状そのものを治す」というよりも、「生活のしづらさを減らす」「できる動作を増やす」という視点でアプローチすることが現実的であり、専門医やリハビリスタッフと協力しながら取り組むことで、生活全体の安定が期待できるケースもあります。
次の章では、改善のカギとなる治療やアプローチについて、医学的な観点から整理して解説します。
回復の鍵となる治療
高次脳機能障害の回復には、リハビリ・環境調整・薬物療法を組み合わせた総合的なアプローチが重要です。
高次脳機能障害は、脳の損傷による認知・情緒・思考の変化が複雑に絡み合うため、「この治療だけで改善する」というものではありません。
患者様の症状に合わせて複数の方法を組み合わせることで、日常生活の負担を軽減し、できることを増やすためのサポートが可能になります。
とくにリハビリは脳の可塑性が働く期間に効果が出やすく、発症から時間が経った後であっても、環境調整や代償手段の導入によって生活の安定につながるケースが多く見られます。
- 認知リハビリ:記憶・注意・遂行機能を鍛える訓練
- 作業療法:日常動作の再獲得を支援
- 環境調整:メモ・アラーム・生活導線の工夫
- 薬物療法:不安・情緒の安定、合併症への対応
- 家族支援:周囲が理解することで症状が安定しやすい
- 社会的サポート:職場・学校復帰のための支援制度
治療の中心となるのはリハビリですが、それを支える「環境づくり」が同じくらい重要です。
たとえば、メモやスマホのアラームを活用する、作業手順を1つずつ分かりやすく整理する、といった工夫は、記憶や遂行機能の負担を大きく軽減します。
また、情緒の不安定さや睡眠の乱れが症状に影響することも多く、必要に応じて薬物療法を併用することで、リハビリが進めやすくなるケースも。
複数の視点から支援することで、患者様が生活の中で「できること」を少しずつ増やしていく土台となります。
根本的な改善を目指す治療法|再生医療という新しい選択肢
高次脳機能障害の後遺症に悩む患者様の選択肢として、再生医療(幹細胞治療)が注目されるケースがあります。
高次脳機能障害は、時間とともに自然回復が落ち着いていくため、「これ以上改善が見込めないのではないか」と不安を抱える患者様が多くいらっしゃいます。
従来のリハビリや薬物療法は、生活の負担を軽減し、できることを増やすために欠かせない支援ですが、脳細胞そのものに直接アプローチする治療ではありません。
そのため近年では、身体が本来持っている力に着目した再生医療が、高次脳機能障害のケアにおいて新たな選択肢として相談されることが増えています。
- 集中力の低下や注意力の波が続く
- 記憶のしづらさが生活に影響している
- 感情の不安定さが続いている
- 遂行機能(段取り・判断)の難しさが残っている
- 既存のリハビリでは停滞を感じている
- 治療の選択肢を増やしておきたい患者様
従来のリハビリや環境調整と組み合わせることで、生活全体を安定させるための一つのサポートとして検討されることがあります。
リペアセルクリニック大阪院では、再生医療に精通した医師が、患者様の状態や生活背景を丁寧にヒアリングし、無理のない形で提案を行っています。
高次脳機能障害は改善がゆっくりで、見えにくい変化が多いため、ご本人もご家族も不安を抱えやすい状態です。
気になる症状がある場合は、一度専門医に相談することで、より納得感のある方向性を見つけやすくなるでしょう。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
高次脳機能障害は正しい措置で改善の可能性を広げられる
高次脳機能障害は、適切なケアや環境調整を続けることで改善の可能性を広げられる状態です。
高次脳機能障害の回復はゆっくりで個人差が大きいため、ご本人もご家族も不安を抱えやすい状態です。
しかし、脳の可塑性は発症から時間が経っても働き続けるため、適切な訓練・生活の工夫・支援体制が整うことで日常生活のしづらさが減るケースは多くあります。
「もう改善しない」と決めつけるのではなく、継続的な取り組みが重要です。
- 症状を正しく理解して最適な支援につなげる
- 自主訓練・生活の工夫を無理のない範囲で続ける
- 家族のサポートで安定しやすくなる
- 専門医への相談で不安を軽減し方向性を明確にする
- 再発予防の管理を継続する
- 再生医療という選択肢も必要に応じて検討できる
高次脳機能障害の後遺症が残っている場合や、現在の治療やリハビリだけでは不安を感じている患者様は、選択肢を広げる意味でも再生医療を検討されるケースがあります。
近年は、患者様の身体の状態に合わせた支援ができる医療として注目されており、日常生活の負担を軽減するサポートとして相談されることが増えています。
リペアセルクリニック大阪院では、再生医療の専門的な知識を持つ医師が、患者様一人ひとりの状態を丁寧に確認し、無理のない形で治療の提案や生活指導を行っています。
カウンセリングは丁寧で、患者様の不安や疑問に寄り添いながら進めるため、初めての方でも安心して相談しやすい環境です。
「何から始めればよいか分からない」「今後の見通しを立てたい」という患者様は、一度専門医に相談することで、より納得できる方向性を見つけやすくなります。
焦らず着実に取り組むことで、これからの生活の可能性を少しずつ広げていきましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長