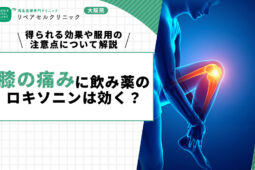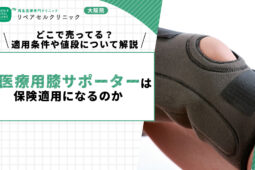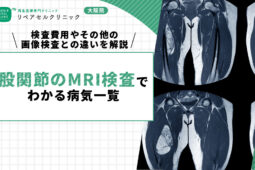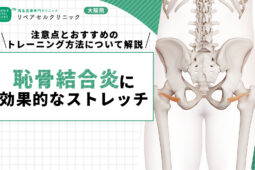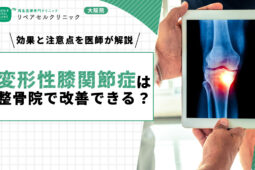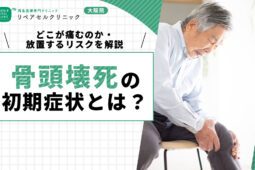- ひざ関節
- 股関節
- 肩
- 再生治療
化膿性関節炎の症状とは?原因・治療法まで医師が解説

化膿性関節炎とは、関節内に細菌が侵入して急激な炎症を起こす感染症です。
数時間から数日で強い痛みや腫れが現れ、放置すると関節の軟骨が破壊される危険性があります。
「朝起きたら関節が腫れて熱を持っている」「痛みが強くて歩けない」「発熱があり不安」など、突然の関節症状に戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、化膿性関節炎の症状・原因・診断方法から治療法・予防法まで、わかりやすく解説します。
化膿性関節炎は緊急で処置が必要な疾患です。
関節に急な痛みや腫れを感じている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
目次
化膿性関節炎とは|関節内に細菌が入り込んで急激な炎症を起こす感染症
化膿性関節炎は、関節液や関節組織に細菌が感染して起こる深刻な感染症です。
原因の多くは細菌ですが、まれにウイルスや真菌が原因となることもあります。
数時間から数日という短期間で急激な痛み・腫れ・発熱が現れることが特徴です。
膝・肩・股関節など大きな関節に多く見られ、放置すると数時間から数日で関節軟骨が損傷する可能性があるため、早期治療が非常に重要です。
以下に該当する方はとくに注意が必要です。
- 高齢者(免疫力の低下)
- 糖尿病患者
- 関節リウマチの患者
- 人工関節置換術後の患者
- 免疫不全状態の患者
- ステロイド使用中の患者
これらの基礎疾患がある方は感染リスクが高いため、関節の痛みや腫れが現れたらすぐに医療機関を受診しましょう。
主な原因菌は黄色ブドウ球菌
黄色ブドウ球菌が最も多い原因菌です。
この細菌は通常、健康な人の皮膚や鼻の中にも存在していますが、免疫力が低下すると感染症を引き起こすことがあります。
皮膚に傷口があると、そこから体内へ侵入、あるいは血液を介して関節に到達するリスクがあるため注意が必要です。
その他の原因菌としては以下があります。
- 連鎖球菌
- 淋菌
- グラム陰性桿菌
検査でどの細菌が原因かを調べることで、その細菌に最も効果が期待できる薬を使った治療ができます。
化膿性関節炎の主な症状|初期症状をチェックしよう
化膿性関節炎は急激に症状が進行するため、初期症状を見逃さないことが重要です。
以下のような症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
- 急激に起こる強い関節痛
- 関節の腫れ・熱感・赤み
- 動かすと激痛が走る
- 発熱・悪寒
- 乳幼児の場合はぐずる・食欲低下・歩かない
症状は非常に急速に悪化し、半日から数日で歩行不能になるほどの強い痛みを呈するケースもあります。
とくに、関節が熱を持って赤く腫れている場合や、38度以上の発熱がある場合は緊急性が高いと考えてください。
乳幼児は症状を言葉で表現できないため、いつもと違う様子(機嫌が悪い、食事を摂らない、足を動かさない)が見られたら注意が必要です。
化膿性関節炎の診断方法|整形外科を受診しよう
化膿性関節炎が疑われる場合、整形外科での診断が必要です。
主な診断方法は以下のとおりです。
- 関節穿刺(関節液検査)
- 血液検査
- 画像検査
関節穿刺では、関節に針を刺して関節液を採取し、白血球数の増加や細菌の有無を調べます。
通常数日以内に原因菌を特定でき、関節液が濁っていたり膿が混じっていたりする場合は化膿性関節炎の可能性が高いと判断されます。
血液検査では、白血球数やCRP(炎症反応の指標)を測定し、感染や炎症の有無を確認。血液培養検査で全身への感染の広がりも評価します。
画像検査では、X線検査で骨の状態を、MRI検査で軟骨や周囲組織の状態を詳しく評価することが可能です。
これらの検査を組み合わせて、感染の有無と原因菌を特定します。
化膿性関節炎の治療期間|基本は6週間前後が目安
化膿性関節炎の治療には、通常6週間前後の期間が目安です。
治療は2段階に分かれます。最初の2週間ほどは病院で点滴による抗菌薬投与を行い、症状が安定したら経口薬に切り替えてさらに4週間ほど継続します。
抗菌薬が効いていれば、通常48時間以内に痛みや腫れが軽減します。
ただし、感染の程度や患者さまの状態によって治療期間は異なるため、医師の指示に従って処方された期間は必ず治療を継続しましょう。
化膿性関節炎の治療法
化膿性関節炎の主な治療法は、以下のとおりです。
早期に適切な治療を開始すれば、関節機能を温存できる可能性が高まります。
抗菌薬療法
抗菌薬療法とは、抗菌薬を使って細菌感染を抑える治療法です。
感染が疑われた時点で、原因菌の特定を待たずにすぐ投与を開始します。
最初は関節に十分な量の薬が届くよう点滴で投与し、症状が安定したら内服薬に切り替えます。
検査で原因菌が判明すれば、その細菌に最も効く抗菌薬へ変更することもあります。
なお、ウイルスが原因の場合は抗菌薬を使用しなくても自然に回復するのが一般的です。
関節ドレナージ(排膿)
関節ドレナージ(排膿)とは、関節内にたまった膿を取り除く処置です。
膿がたまったままだと関節の損傷が進み、薬も効きにくくなるため、早めの対処が欠かせません。
関節の種類や感染の程度に応じて、針を刺して膿を吸引する処置(関節穿刺)、関節鏡(小さなカメラを挿入して関節内を観察・洗浄する器具)を使った手術、または開放手術が選択されます。
膝関節や肩関節では関節鏡手術が行われることが多く、股関節では外科的ドレナージが必要になることが一般的です。
安静とリハビリテーション
感染後の数日間は、痛みを軽減するために副子(固定具)で関節を固定して安静を保ちます。
その後は、筋力の低下や関節のこわばりを防ぐために理学療法(リハビリテーション)を開始します。
適切なリハビリを行わないと、関節の永久的な機能障害が残る可能性があるため、医師や理学療法士の指導のもとで計画的に進めることが大切です。
再生医療
関節の新たな治療法として、再生医療の幹細胞治療があります。
幹細胞治療は、患者さま自身の細胞を採取・培養し、関節内に注入する治療法です。
手術や入院を伴わず、身体への負担が少ないのが特徴です。
ただし、化膿性関節炎そのものの治療には適応されません。感染が完全に治癒した後、関節損傷が残った場合に検討される可能性があります。
関節のさまざまな疾患に対して適応になるため、お悩みの症状がある方は当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。
また、当院の公式LINEでは再生医療に関する情報の提供や、簡易オンライン診断を行っています。
再生医療について詳しく知りたい方は、ぜひご登録ください。
化膿性関節炎を予防する方法
化膿性関節炎を予防するために、日常生活では以下のポイントを意識しましょう。
- 傷口を清潔に保つ習慣をつける
- 免疫力を高める
- 関節に過度な負担をかけないようにする
- こまめなストレッチで関節の柔軟性を維持する
傷口は細菌の侵入経路となるため、小さな傷でも放置せずすぐに洗浄して清潔に保ちましょう。
とくに関節周辺の傷が赤く腫れたり膿が出たりした場合は、早めに医療機関を受診してください。
また、免疫力の維持には、バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動が大切です。
喫煙や過度の飲酒は免疫力を低下させるため控えめにしましょう。
さらに関節への過度な負担は感染リスクを高めます。
スポーツや重労働の際は適切なウォーミングアップやサポーターを活用し、適正体重の維持も心がけてください。
毎日短時間でも関節周りのストレッチを習慣にすることで、関節の柔軟性を保ち感染リスクを減らせます。
化膿性関節炎は早期発見が大切!違和感を覚えたら早めに受診を
化膿性関節炎は、早期に適切な治療を開始すれば関節機能を守れる可能性が高い疾患です。
しかし、治療が遅れると数時間から数日で関節軟骨が破壊され、後遺症が残ることもあります。
関節の急な痛みや腫れ、発熱などの症状が現れたら、「様子を見よう」と考えずにすぐに整形外科を受診してください。
とくに糖尿病や関節リウマチなどの基礎疾患がある方、人工関節の手術を受けた方は、感染リスクが高いため注意が必要です。
早期発見・早期治療が予後を大きく左右します。少しでも関節に異変を感じたら、ためらわずに医療機関に相談しましょう。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設