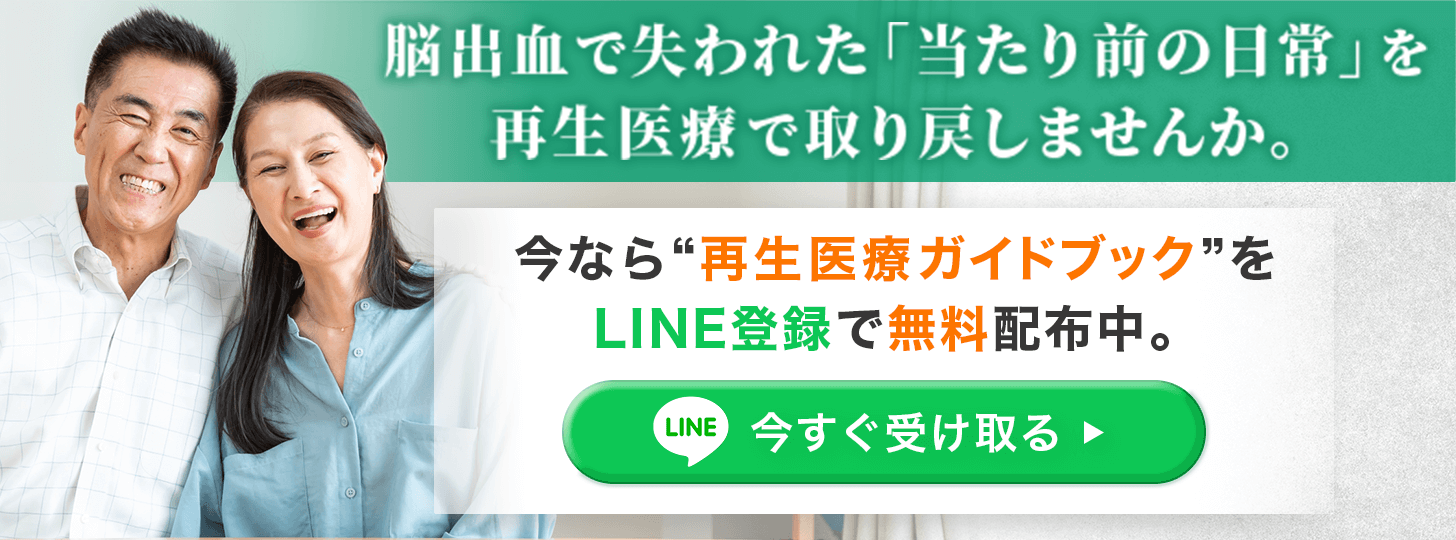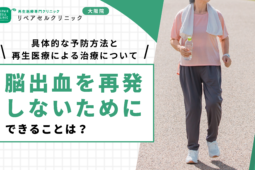- 脳出血
橋出血とは|主な症状、原因、後遺症、治療法について詳しく解説【医師監修】
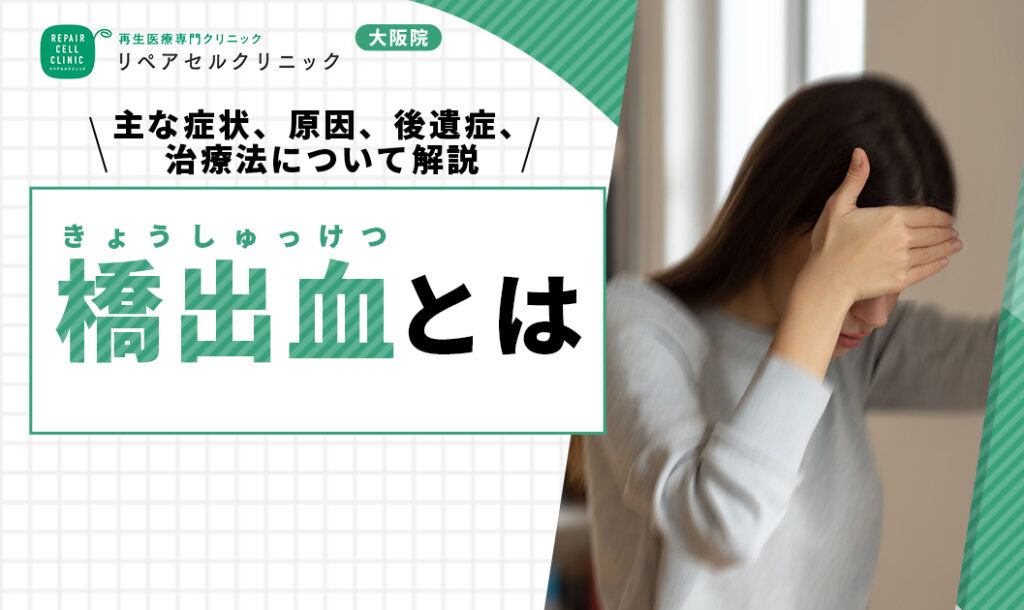
ご家族が突然「橋出血」を発症し、回復の見込みや後遺症など、予後について不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
脳幹の一部である「橋」は生命維持に関わる重要な場所であるため、橋での出血は重篤な症状が出やすい特徴があります。
しかし、決してすべてのケースで希望がないわけではありません。
本記事では、橋出血とはどのような病気か、主な後遺症や治療法についてわかりやすく解説します。
病態を正しく理解し、焦らず治療に向き合うために、ぜひ参考にしてください。
また、近年の脳出血治療に注目されている、後遺症改善や再発予防につながる再生医療についても知っておきましょう。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
以下の動画では、再生医療によって脳出血の後遺症にお悩みだった患者さまの改善症例を紹介しているので、併せてご覧ください。
「脳出血の後遺症について相談したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。
目次
橋出血とは
橋出血とは、脳幹の一部である「橋(きょう)」と呼ばれる部位で出血する脳出血の一つです。
橋は、呼吸・心臓の動き・意識・手足の運動など、生命維持に欠かせない機能を支える重要な場所です。
そのため、橋で出血が起こると、症状が急激に現れやすく、意識の低下、手足の麻痺、呼吸の異常など、命に関わる重い症状が起こることがあります。
脳の中でも生命活動そのものを担う部分で起こる出血であるため、橋出血は脳出血の中でも重症化しやすいタイプとされています。
橋出血の主な症状
橋出血では、以下のような症状が突然現れることがあります。
- 意識障害(突然反応がなくなる、呼びかけに答えない)
- 手足が動かない、急な麻痺
- 呼吸が不安定になる、無呼吸
- 目がうまく動かない(眼球が揺れる・固定する)
- 強いめまい、ふらつき
橋は「脳幹」と呼ばれる生命維持に必要不可欠な部位のため、出血が起きると意識・呼吸・運動の機能が急激に障害されることが特徴です。
また、眼球を動かす神経が通っているため、「目が動かない・左右に揺れる」といった症状も現れやすいとされています。
症状は急速に進むことが多いことから早期治療が重要なので、上記のような症状が見られた場合は、ためらわずに救急要請を行いましょう。
橋出血の主な原因
橋出血の主な原因として、高血圧と血管奇形の2つが挙げられます。
原因によって発症のしやすさや治療方針が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
高血圧
橋出血の主な原因として、高血圧が挙げられます。
高血圧が長期間続くと、脳幹の橋へ向かう細い血管に強い負担がかかり、血管壁が耐えきれずに破れてしまうことで出血が起こります。
橋は小さな範囲に多くの重要な神経が集まっているため、一度出血が広がると短時間で重症化しやすく、意識障害・呼吸の異常・手足の麻痺などが突然現れるのが特徴です。
高血圧が原因の場合、損傷を受けた脳幹の回復を目的とした手術は基本的に行われず、血圧管理・呼吸や循環の安定化など、全身管理が治療の中心となります。
血管奇形
高血圧性よりも比較的若い年代に発症する可能性がある原因として、脳の血管奇形が挙げられます。
代表的なものに「海綿状血管腫」と呼ばれる血管の塊があり、生まれつき異常な毛細血管様の血管が集まって形成されると考えられています。
血管奇形による橋出血は、少量の出血で重症になりにくい一方、再発しやすいことが特徴です。
そのため、出血が落ち着いた時期に手術が検討されるケースもあります。
橋出血で見られる後遺症
橋出血では、以下のような後遺症が残ることがあります。
- 手足の麻痺(四肢麻痺)
手足を動かすための「運動神経の通り道」が橋を通るため、出血によって神経が損傷し、手足が動きにくくなったり、完全に麻痺することがあります。 - 意識障害(覚醒しにくい・反応が乏しい)
意識を保つ役割を担う「網様体」が橋を通っており、障害されると覚醒しにくくなったり、反応が乏しくなることがあります。 - 呼吸障害
呼吸のリズムを調整する中枢が延髄と橋にあるため、出血の影響で呼吸が不安定になり、人工呼吸器が必要になることもあります。 - 眼球運動障害(目が動かない・揺れる)
目の動きをコントロールする神経が橋を通るため、出血でその経路が障害されると、目がうまく動かない・揺れるなどの症状が現れます。
橋出血が起こると複数の機能が同時に障害され、後遺症が重くなりやすいのが特徴です。
ただし、状態や治療経過によっては、リハビリなどを通じて少しずつ改善が見られる場合もあります。
橋出血は回復する?主な治療法
橋出血は、出血範囲や意識状態、治療開始のタイミングによって回復の程度が大きく異なりますが、適切な治療とリハビリによって改善が見られることもあります。
本章では、保存療法と手術療法の2つの治療法について解説します。
橋出血は脳の中心である「脳幹」で起こるため、重症になりやすい病気です。
それぞれどのような治療を行うのか確認し、もしものとき適切に対処できるようにしましょう。
保存療法
橋出血の治療では、多くのケースで出血の拡大を防ぎつつ、全身状態を安定させることを目的とした保存療法が中心となります。
橋は脳の奥深くに位置しており、重要な神経が密集しているため、直接メスを入れて血腫を取り除く手術はリスクが高いからです。
具体的には、以下のような治療・管理を組み合わせて行います。
- 血圧の管理
出血をこれ以上広げないよう、血圧を厳密にコントロールします。 - 呼吸・循環のサポート
脳幹の橋は呼吸中枢に近く、呼吸が不安定になることがあります。
必要に応じて人工呼吸器を使用します。 - 意識・神経症状の管理
意識状態や神経症状を注意深くモニタリングしながら全身管理を行います。
降圧薬を用いて血圧を厳重に管理したり、脳のむくみ(浮腫)を取る薬剤を点滴したりします。
集中治療室などで全身状態を安定させ、自然に血腫が吸収されるのを待つことが、回復への第一歩となります。
また、保存療法と並行して全身状態に注意したうえで早期からリハビリを始めることが重要です。
早期からリハビリを始めることで、長期的な機能回復や後遺症の軽減が期待できます。
手術療法
橋は生命維持の中枢であるため、メスを入れるリスクが高く、原則として血腫を直接取り除く手術(開頭手術)は行われません。
しかし、出血が脳室内に広がり、脳圧が急激に上がる危険な状態(急性水頭症)に陥った場合は、救命のための処置が行われる場合があります。
| 術式 | 目的・特徴 |
|---|---|
| 脳室ドレナージ術 | 脳室にチューブを入れ、溜まった血液や髄液を体外へ排出して脳圧を下げる。 |
| 内視鏡下血腫除去術 | 小さな穴から内視鏡を入れ、脳へのダメージを最小限に抑えつつ血腫を吸引する。 |
上記は、あくまで「二次的な脳への圧迫」を取り除くための手段です。
損傷した神経そのものを修復するわけではないため、適用は慎重に判断されます。
橋出血に関してよくある質問
本章では、橋出血に関してよくある質問について回答します。
以下では、それぞれの質問に対して、簡潔にわかりやすく解説していきます。
橋出血の死亡率は?
橋出血は脳出血の中でも重症化しやすく、死亡率が高い傾向があります。
実際に、国内の臨床研究では退院時の死亡率が61%と報告※されています。
※出典:J-STAGE「脳幹出血患者の予後に関する臨床的検討」
橋には、呼吸・意識・心臓の働きなど生命維持に関わる中枢が集まっているため、出血すると短時間でこれらが障害されるからです。
ただし、年齢・出血量・治療開始の早さなどによって大きく異なります。
脳出血と橋出血の違いは?
「脳出血」は脳の中で起こる出血の総称であり、「橋出血」は脳幹の一部である橋で出血を起こす脳出血の一つです。
橋出血は、脳幹という生命維持の中枢で起こるため、他の部位の出血と比較して重症化しやすく、治療の難易度が高いという特徴があります。
それぞれの関係性と特徴の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 脳出血(脳内出血の総称) | 橋出血(特定部位の脳出血) |
|---|---|---|
| 定義 | 脳内の血管が破れ出血することの総称 | 脳幹の「橋」という部位で出血した病態 |
| 出血部位 | 被殻、視床、小脳など | 橋(脳幹の一部) |
| 重症度 | 部位や出血量により軽度から重度までさまざま | 生命中枢のため重篤になりやすい |
| 主な治療方針 | 部位によっては血腫除去手術が可能 | 手術が難しく、保存療法が中心となる |
つまり、橋出血は「数ある脳出血の中でも、特に注意が必要なタイプ」と理解しておきましょう。
橋出血の初期症状は?
橋出血の初期症状は、下記のように突然現れることが多いです。
- 急な意識障害
- 手足の麻痺
- 呼吸の乱れ
- 眼球の固定・揺れ
- 激しいめまい
橋には、運動・呼吸・意識・眼球運動を司る神経が集まっているため、出血すると短時間で異常が出ることがほとんどです。
特に「急速な意識消失」と「著しい縮瞳(眼の瞳孔が収縮した状態)」は橋出血を疑う際の大きなサインとなります。
命に関わるケースもあるため、異変を感じたら一刻も早く医療機関につながることが大切です。
橋出血の再発予防や後遺症の治療には再生医療をご検討ください
橋出血とは、橋と呼ばれる脳幹の一部で出血する脳出血のタイプの一つです。
橋は、呼吸・心臓の動き・意識・手足の運動など、生命維持に欠かせない機能を支える重要な部位のため、重篤な症状が出やすい特徴があります。
脳出血は再発しやすい病気のため、高血圧の管理や生活習慣の見直しを行い、再発を予防することが重要です。
また、近年の脳出血治療では、後遺症改善や再発予防につながる再生医療が注目されています。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
「脳出血の後遺症について相談したい」「再生医療が自分に合うのか知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長
あわせて読みたいトピックス
-

脳出血の看護ケア|在宅でも家族ができることや注意点・ポイントについて解説
-

脳出血の入院期間|年齢別・重症度別の違い、入院費用について解説【医師監修】
-

高次脳機能障害の平均余命について解説!治療法についても解説
-
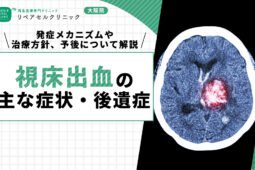
視床出血の主な症状・後遺症|発症メカニズムや治療方針、予後について解説
-
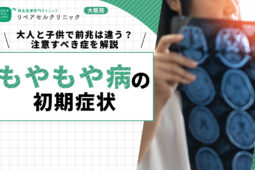
もやもや病の初期症状|大人と子供で前兆は違う?注意すべき症状について解説
-
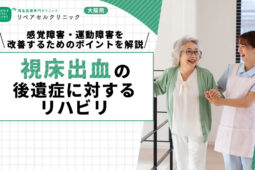
視床出血の後遺症に対するリハビリ|感覚障害・運動障害を改善するためのポイントを解説
-
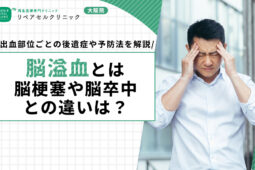
脳溢血とは|脳梗塞や脳卒中との違いは?出血部位ごとの後遺症や予防法を解説【医師監修】
-
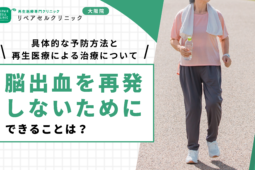
脳出血を再発しないためにできること|年代別の予防法と治療法を解説【医師監修】