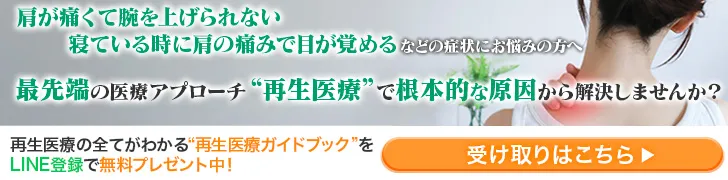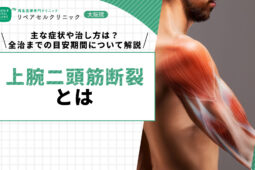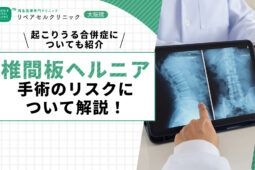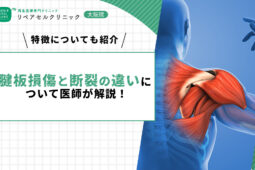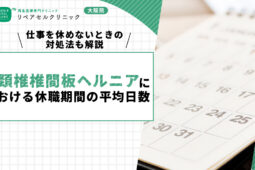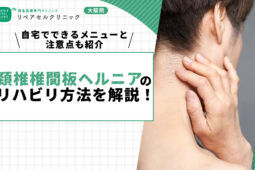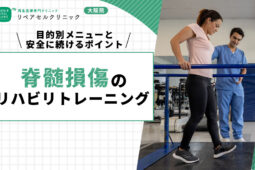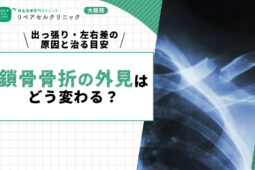- 首
- 肩
胸郭出口症候群の症状チェックリスト|テストのやり方と治療法について解説
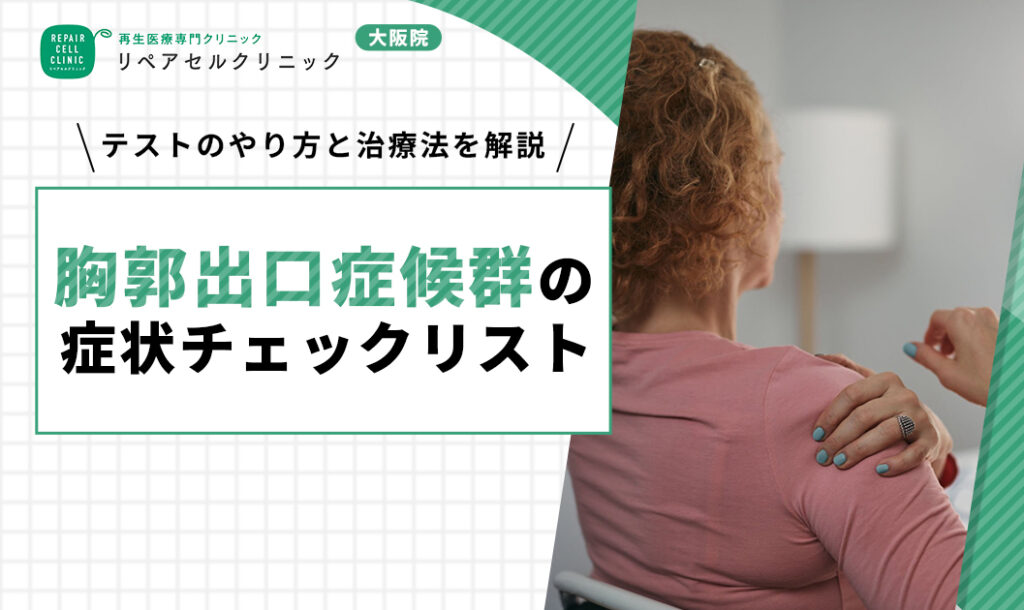
腕や手のしびれ、原因のわからない肩こりに悩まされていませんか。
その症状は「胸郭出口症候群」かもしれません。
一度発症すると、痛みやしびれで仕事や家事に集中できなくなるなど、日常生活に支障をきたす場合があります。
本記事では、胸郭出口症候群の症状チェックリストや自分でできるテスト方法について詳しく解説します。
- 胸郭出口症候群の症状チェックリスト
- 自分でできるテストのやり方
- 主な治療法と症状を放置するリスク
従来の治療法に加えて、近年注目されている再生医療は胸郭出口症候群にも有効な選択肢の一つです。
再生医療は、患者さまご自身の細胞を活用して、圧迫によって傷ついた神経や組織の修復を目指す治療法です。
症例や治療法について、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEで詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
目次
胸郭出口症候群の症状チェックリスト
腕や手のしびれ、原因のわからない肩こりに悩んでいる場合、胸郭出口症候群の症状の可能性があります。
胸郭出口症候群は、首から腕へつながる神経や血管が圧迫されることで起こります。
ご自身の症状が当てはまるか、まずはチェックリストで確認してみましょう。
胸郭出口症候群の症状チェックリスト
- 腕がひんやりと冷たく感じる
- 腕が全体的にパンパンとむくんでいる
- 腕に痛みやしびれを感じる
- 腕の肌の色がいつもより白っぽく見える
- 血管が青紫色に浮き出て見える
- 重いものを持つと肩や首まわりが強くこる
- 腕を上げたときに、腕から背中にかけて痛みやしびれが走る
上記の症状は、頚椎椎間板ヘルニアなど他の疾患と似ているものもあるため、自己判断には注意が必要です。
一つでも当てはまる症状があれば、自己判断せずに専門の医療機関で相談しましょう。
胸郭出口症候群になりやすい人とは
胸郭出口症候群は、特定の身体的な特徴や生活習慣によって発症しやすい傾向があります。
発症しやすい方の主な特徴は、以下のとおりです。
胸郭出口症候群になりやすい人の特徴
- なで肩の人
- 巻き肩や猫背の姿勢が多い人
- 過度な筋トレで筋肉質な人
- 重い物を運ぶ職業の人
- 腕を上げる動作を繰り返すスポーツ選手
特になで肩の方は、鎖骨と肋骨の間のスペースが狭くなりやすく、神経や血管が圧迫されやすいです。
また、デスクワークなどで長時間前かがみの姿勢を続けると、肩が内側に巻いて胸の筋肉が硬くなり、症状を引き起こす原因となります。
胸郭出口症候群の症状が疑われる場合のセルフチェック方法
ご自身の症状が胸郭出口症候群によるものか確かめるために、自宅でできるセルフチェック方法について解説します。
特定の動作で症状が現れるかを確認するもので、あくまで目安ですが、医療機関を受診する際の判断材料にもなります。
テストで陽性の兆候が見られた場合は、自己判断で終わらせず、医療機関を受診しましょう。
一人で行うテストのやり方
一人で行う胸郭出口症候群テストのやり方として、信頼性が高いとされる「ルーステスト」を紹介します。
ルーステストは、神経や血管が圧迫されやすい姿勢をとり、症状が再現されるかを確認する方法です。
具体的な手順は、以下のとおりです。
- 椅子に座るか立った状態で、両腕を横に開いて肩の高さまで上げる
- 肘を90度に曲げ、腕を後ろにひねる(バンザイのような姿勢)
- その姿勢を保ちながら、両手の指を「グー」「パー」と3分間リズミカルに繰り返す
しびれ、前腕のだるさ、指の疲労感やグーパー運動が続けられない場合は、胸郭出口症候群が疑われます。
健常者ではほとんど症状が出ないため、有効なチェック方法といえるでしょう。
二人で行うテストのやり方
二人で行う胸郭出口症候群テストのやり方では、協力者に手首の脈拍を触れてもらいながら行います。
特定の姿勢をとったときに、血流が変化するかどうかで圧迫の有無を確認します。
代表的なテスト方法は、以下のとおりです。
| テスト名 | 手順 | 陽性の判断 |
|---|---|---|
| アドソンテスト | 顎を上げ、症状のある側に顔を向けて首を反らし、深呼吸する | 脈拍が弱くなる、または触れなくなる |
| ライトテスト | 症状のある側の腕を横に開き、肩の高さまで挙上し、さらに肘を90度に曲げる | 脈拍が弱くなる、または触れなくなる |
ライトテストは、健常者でも3〜5割が陽性(偽陽性)の結果になる場合があるため、注意が必要です。
アドソンテストも行い、2つのテストで陽性が出た場合は、胸郭出口症候群が疑われます。
上記のテストは確定診断ではないため、症状が疑われる場合は、必ず医療機関を受診して、適切な検査を受けましょう。
胸郭出口症候群の症状を放置するリスク
胸郭出口症候群の症状は、肩こりや一時的な不調と誤解されがちですが、放置すると深刻な状態に進行するおそれがあります。
適切な治療を受けずに自然治癒することはまれで、多くの場合、慢性化して日常生活に支障をきたします。
初めは一時的だったしびれや痛みが持続的になり、デスクワークや睡眠中にも現れるようになります。
さらに、神経や血管への圧迫が長期間続くと、以下のような回復が難しい状態に至る場合もあるため、注意が必要です。
| 損傷の種類 | 放置した場合のリスク |
|---|---|
| 神経障害 | 手の筋肉が痩せてしまい、握力が低下して細かい作業が困難になる |
| 静脈の圧迫 | 腕に血のかたまり(血栓)ができ、急な腫れや皮膚が青紫色に変色する |
| 動脈の圧迫 | できた血栓が指先まで飛び、動脈を詰まらせて激しい痛みや組織の壊死につながる |
このような深刻な状態を避けるためにも、腕のしびれや痛みといった初期症状を軽視せず、早期に専門医の診断を受け、適切な治療を開始しましょう。
胸郭出口症候群の主な治療法
胸郭出口症候群の治療は、主に「保存療法」と「手術療法」の2つに分けられます。
治療法は症状の重症度や原因に基づいて決定されますが、基本的には身体への負担が少ない保存療法から開始し、症状の改善を目指します。
保存療法で十分な効果が得られない場合や、症状が重い場合に手術療法が検討されるのが基本的な流れです。
保存療法
保存療法は、手術以外の方法で症状の緩和と機能改善を目指す治療法です。
特に、胸郭出口症候群で最も多い神経性のタイプでは、治療の第一選択とされています。
姿勢の改善や筋肉の緊張を和らげることで、神経や血管への圧迫を軽減させます。
具体的な治療法は、以下のとおりです。
| 治療法 | 内容 |
|---|---|
| 理学療法 | ストレッチで硬くなった筋肉を伸ばし、筋力強化で正しい姿勢を保つ |
| 薬物療法 | 消炎鎮痛剤や筋弛緩薬を用いて、痛みや筋肉の過度な緊張を和らげる |
| 注射療法 | 痛みの原因となっている神経の周辺に局所麻酔薬などを注射し、痛みを抑える |
日常生活での姿勢や動作の指導も受け、症状を悪化させない生活習慣を身につけるのも保存療法の一環です。
手術療法
手術療法は、保存療法で改善が見られない場合や、症状が重く日常生活に大きな支障が出ている場合に検討される治療法です。
神経や血管を物理的に圧迫している原因を、手術によって直接取り除きます。
主な手術方法は、以下のとおりです。
- 第一肋骨切除術
- 前斜角筋切除術
- 頚肋切除術
手の筋力低下が進行している場合や、血栓などの合併症が見られる場合は、緊急で手術が選択されるケースもあります。
手術にはリスクも伴いますので、医師と十分に相談したうえで決定しましょう。
胸郭出口症候群の症状に関するよくある質問
胸郭出口症候群について、患者さまから寄せられることの多い質問にお答えします。
ご自身の症状と照らし合わせ、適切な対処法を見つけるための参考にしてください。
胸郭出口症候群はどこが痛い?
胸郭出口症候群の痛みは、圧迫されている神経や血管の場所によって、さまざまな部位に現れます。
主な痛みの部位は、以下のとおりです。
- 首、肩、肩甲骨周り
- 腕の内側から薬指、小指にかけて
- 胸の前面や脇の下
- 鎖骨の周辺
重だるい痛みだけでなく、ビリビリとしたしびれや感覚が鈍くなる状態を伴う場合もあります。
また、血行不良によって腕が白っぽくなったり、冷たく感じたりするのも特徴の一つです。
胸郭出口症候群を自分で治すには?
胸郭出口症候群の症状を緩和するために、自分でできるセルフケアがあります。
主なセルフケアの方法は、以下のとおりです。
| ケアの種類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| ストレッチ | 胸や首の前側の筋肉をゆっくり伸ばし、緊張を和らげる |
| 姿勢改善 | 肩甲骨を背中の中央に寄せる運動で、巻き肩や猫背を矯正する |
| 生活習慣の見直し | 高すぎる枕を避け、入浴で体を温め血行を良くする |
自己判断で無理なケアをすると、かえって症状を悪化させるおそれがあります。
セルフケアを試す際は、まず専門医に相談しましょう。
胸郭出口症候群でやってはいけないことは?
胸郭出口症候群の症状がある場合、特定の動作や習慣は神経や血管への圧迫を強め、症状を悪化させるため避けるべきです。
日常生活で以下の点に注意しましょう。
- 腕を繰り返し高く上げる動作(洗濯物を干す、つり革を持つ)
- 重い荷物を腕で持つ、またはショルダーバッグを片方の肩にかける
- 胸の筋肉を過度に鍛えるトレーニング(ベンチプレスなど)
- 猫背や巻き肩、長時間のデスクワークやスマホ操作
無意識に症状を悪化させる行動をとっていないか、日々の生活を見直してみましょう。
胸郭出口症候群の症状には再生医療もご検討ください
腕や手のつらいしびれ、痛みといった症状は、日常生活の質を大きく下げてしまいます。
治療の基本は、理学療法や薬物療法といった保存療法です。
しかし、これらの治療で改善が見られない場合には手術療法が検討されますが、手術に抵抗がある方も多いでしょう。
近年の治療では、手術せずに胸郭出口症候群を治療する再生医療も選択肢の一つです。
再生医療は、ご自身の脂肪から採取した幹細胞を使い、圧迫によって傷ついた神経や血管、筋肉組織の修復を促す治療法です。
胸郭出口症候群によるつらい症状の根本的な改善を目指したい方は、ぜひ当院リペアセルクリニックにご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設