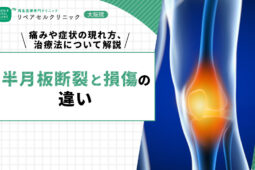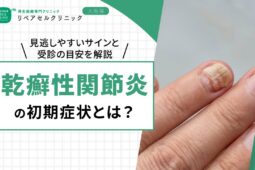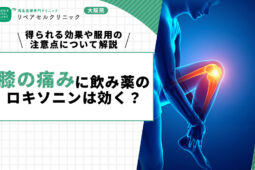- ひざ関節
- 膝部、その他疾患
膝の水を抜く方法|自分で水を抜ける?効果的なストレッチや注意点を解説【医師監修】
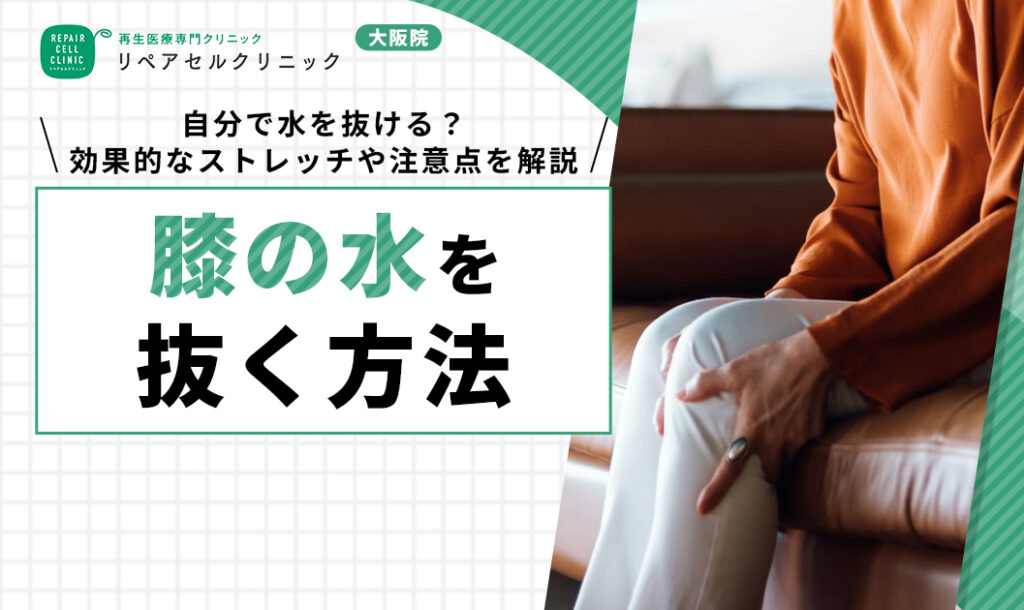
膝に腫れや違和感があり、水が溜まっていると感じる方は多いのではないでしょうか。
膝の水を抜くには、膝関節の近くに注射針を刺して膝に溜まった水を抜く関節穿刺(かんせつせんし)と呼ばれる方法が一般的です。
しかし、原因となっている疾患を治療しなければ再度水が溜まる恐れがあります。
本記事では、病院で膝の水を抜く方法や膝の水を自分で抜く方法があるかどうかを解説します。
また、膝に水が溜まる原因となっている疾患を治療するには、再生医療も選択肢の一つです。
当院リペアセルクリニックの公式LINEでは、再生医療の治療法や症例などの情報を配信しています。
繰り返し溜まる膝の水にお困りの方や、手術以外の治療法を探している方は参考にしてください。
目次
病院で膝の水を抜く方法
病院で膝の水を抜く方法は、以下の通りです。
膝の軟骨や靭帯などの組織に炎症が起こると関節液(滑液)が通常より多く分泌され、膝の腫れや圧迫感、動きにくさなどの症状が現れます。
膝の水が溜まる仕組みや、関連する疾患についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
一般的な方法は「関節穿刺」
膝に水が溜まった場合の処置として、関節内に針を刺して関節液を抜く関節穿刺(かんせつせんし)が挙げられます。
しかし、関節穿刺によって膝の水を抜いた場合でも、膝に水が溜まる原因となっている疾患が治るわけではありません。
原因となっている疾患は、関節穿刺で抜いた膝の水の色や状態が、判断材料となります。
| 水の色 | 状態 |
|---|---|
| 澄んだ黄色で、粘り気がある | 正常 |
| 黄色みが強く、粘り気が少ない | 変形性膝関節症などの疑い |
| 赤もしくは褐色(血液) | 半月板損傷・靱帯損傷などの疑い |
| 濁って見える | 感染症・痛風・関節リウマチなどの疑い |
関節液の色や量に加え、触診や症状の情報をもとに膝の状態を把握して、適切な治療法を決定します。
膝の水を抜く処置の費用やメリットについては、以下の記事を参考にしてください。
ヒアルロン酸注射をするケースもある
症状によっては、膝の水を抜いた後に痛みや炎症を和らげる目的でヒアルロン酸注射が行われる場合があります。
ヒアルロン酸は膝の動きをなめらかにする関節の潤滑油のような成分で、注射によって以下の効果が期待できます。
- 関節液の働きを改善
- 痛みの軽減
- 軟骨のすり減りを抑制
ヒアルロン酸注射の効果はあくまで一時的であり、根本的な原因を治療するものではありません。
とくに、進行した変形性膝関節症には、痛みの緩和が十分でないこともあります。
繰り返し注射を行っても痛みが改善されないときや症状が進行している際には、手術や再生医療など別の治療法を検討する場合もあります。
膝の水を自分で抜く方法は?効果的なストレッチ・マッサージ
結論、膝の水を自分で抜く方法はありません。
しかし、以下のようなストレッチやマッサージによって、症状緩和が期待できます。
膝の水がケガや損傷が原因の場合、自己判断でのマッサージは損傷を悪化させる恐れがあるため、専門医にセルフケア方法を確認しましょう。
また、痛みや違和感がある場合は炎症が起きている可能性があります。
無理に動かしたり、自己流でマッサージやストレッチを行ったりするのは避けましょう。
大腿四頭筋のストレッチ
大腿四頭筋のストレッチの手順は、以下の通りです。
- 1.壁や机の近くに立ち、左手で支える
- 2.右手で右足首を持ち、かかとをお尻に近づけるように膝をゆっくり曲げる
- 3.太ももの前側をゆっくり伸ばす
- 4.余裕があれば、曲げている膝をさらに後方に引く
- 5.伸びている感覚がある状態で30秒キープする
- 6.ゆっくり元に戻し、反対側の足も同様に行う
大腿四頭筋のストレッチは、膝周りの筋肉の柔軟性を保ち関節の負担軽減に役立ちます。
ストレッチの際は、腰が反らないようにしてお腹に軽く力を入れると安定します。
また、膝が前に出ないように注意しましょう。
殿筋群のストレッチ
殿筋群ストレッチの手順は、以下の通りです。
- 1.仰向けに寝て膝を曲げる
- 2.右足を持ち上げ、外側のくるぶしを左膝に重ねる
- 3.手で左足を抱えて下半身を持ち上げる
- 4.右のお尻の伸びを感じながら30秒間キープする
- 5.反対側も同様に行う
殿筋群はお尻の筋肉のことで、柔軟性を高めることで股関節の動きがスムーズになり、膝への負担を軽減する効果が期待できます。
とくにお尻の表層にある大殿筋や中殿筋は膝の安定性にも関わるため、膝の痛みや不安定感の予防にも役立ちます。
ストレッチの際は、背中が丸まらないように意識すると効果的です。
膝周辺のマッサージ
手のひらを使って太ももの筋肉をほぐす膝周辺マッサージの手順は、以下の通りです。
- 1.椅子に座り、太ももの中央またはやや外側に手のひらをあてる
- 2.膝のお皿の上から足の付け根に向かって、手のひらで軽く圧をかけながら少しずつずらす
- 3.痛みを感じるところは、無理せず避ける
マッサージ中に痛みが強くなる場合は、すぐに中止してください。
また、膝の慢性期の痛みを緩和するケアとして取り入れ、急性のケガや炎症があるときは避けましょう。
マッサージは血行を促し筋肉の柔軟性を保つのに役立ちますが、自己判断で行うと症状を悪化させるリスクもあります。
原因に合った治療とあわせて、医師の指導のもとで取り入れましょう。
膝の水を抜く際に注意すべきこと
膝の水を抜く際に注意すべきことは、以下の3つです。
膝に水が溜まった際は、腫れや痛みを軽減するために水を抜く処置を行う場合があります。
処置の目的や注意点を正しく理解して早期の改善につなげましょう。
水を抜くと「クセになる」は誤った知識
水を抜く処置である関節穿刺が水の再発や「クセ」の原因になることはありません。
膝に水が溜まるのは、関節内で炎症が続いているためです。
水を抜く処置は、関節内の圧力を下げて痛みを和らげる一時的な対処法です。
炎症の原因そのものを治すわけではないため、根本的な治療が別に必要です。
変形性膝関節症や半月板損傷などで炎症が持続している場合、水を抜いても再び関節液が溜まる場合があります。
熱感や痛みがある場合は感染症の可能性
膝の水を抜く処置には、まれですが感染症のリスクがあります。
次のような症状が出た際は、感染症の可能性があります。
- 膝が赤くなる
- 膝が腫れる
- 触ると熱を持つ
- 痛みが強くなる
関節内は通常無菌状態ですが、注射の際に皮膚上の細菌が関節内に入り込むことで感染が起こる場合があります。
感染症が進行すると関節の破壊や長期の治療、外科的な手術などが必要になる場合があるため、早期の対応が必要です。
処置後は通常、痛みや腫れは軽度で自然に落ち着きますが、症状が強く続く場合や悪化している場合は速やかに医療機関を受診してください。
水が溜まる原因の根本的な治療が必要
膝に水が溜まる状態を防ぐためには、炎症の根本原因となる疾患の治療が不可欠です。
水が溜まる主な原因は、以下の通りです。
| 原因 | 概要 |
|---|---|
| 変形性膝関節症 | 加齢や過負荷により膝の軟骨がすり減り、関節の変形が起こる |
| 半月板損傷 | 衝撃吸収と関節の安定化に関わる軟骨組織である半月板が、スポーツや加齢による変性で損傷する |
| 靱帯損傷 | 膝の安定性に関わる靭帯が、激しいスポーツや転倒などによって傷つく |
| 関節リウマチ | 自己免疫疾患により関節の滑膜に慢性的な炎症が起こる |
治療はリハビリによる筋力強化や鎮痛薬の使用、場合によっては手術などが行われます。
膝の炎症が落ち着くと、関節液の分泌も自然に減少します。
早めに医療機関で原因を確認し、適切な治療を受けて再発防止につなげましょう。
膝の水を抜く方法についてよくある質問
膝の水を抜く方法についてよくある質問は、以下の通りです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
膝の水を抜く注射は痛い?
痛みの感じ方には個人差がありますが、膝の水を抜く注射は注射針を刺すときの軽い痛みがあるのが一般的です。
穿刺の方法や膝の状態によっては一時的に痛みが強く感じられることもあります。
膝の腫れや痛みが続く場合は、医師に相談して処置を受けましょう。
膝に溜まった水は自然になくなる?
炎症が改善されなければ自然に水がなくなることはほとんどありません。
膝の水を自然に減らすには、炎症を抑えることが重要です。
早めに整形外科を受診して原因を確認し、適切な治療を受けましょう。
膝に水が溜まる原因を根本的に治療しよう
膝の水を抜くには、膝関節近くに注射針を刺して溜まった水を抜く「関節穿刺(かんせつせんし)」が一般的です
水を抜くと一時的に症状は楽になりますが、原因を根本的に治療しないと再び水が溜まる可能性があります。
医療機関を受診して原因を特定し、適切な治療を受けましょう。
また、膝に水が溜まる原因となっている疾患を根本的に治療したい方は、再生医療も選択肢の一つです。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて損傷した組織にアプローチする医療技術です。
膝の慢性的な痛みや腫れを根本から改善したい方や、手術せずに治療したい方に注目されています。
具体的な治療法については、当院「リペアセルクリニック」で無料カウンセリングを行っておりますので、ぜひご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設