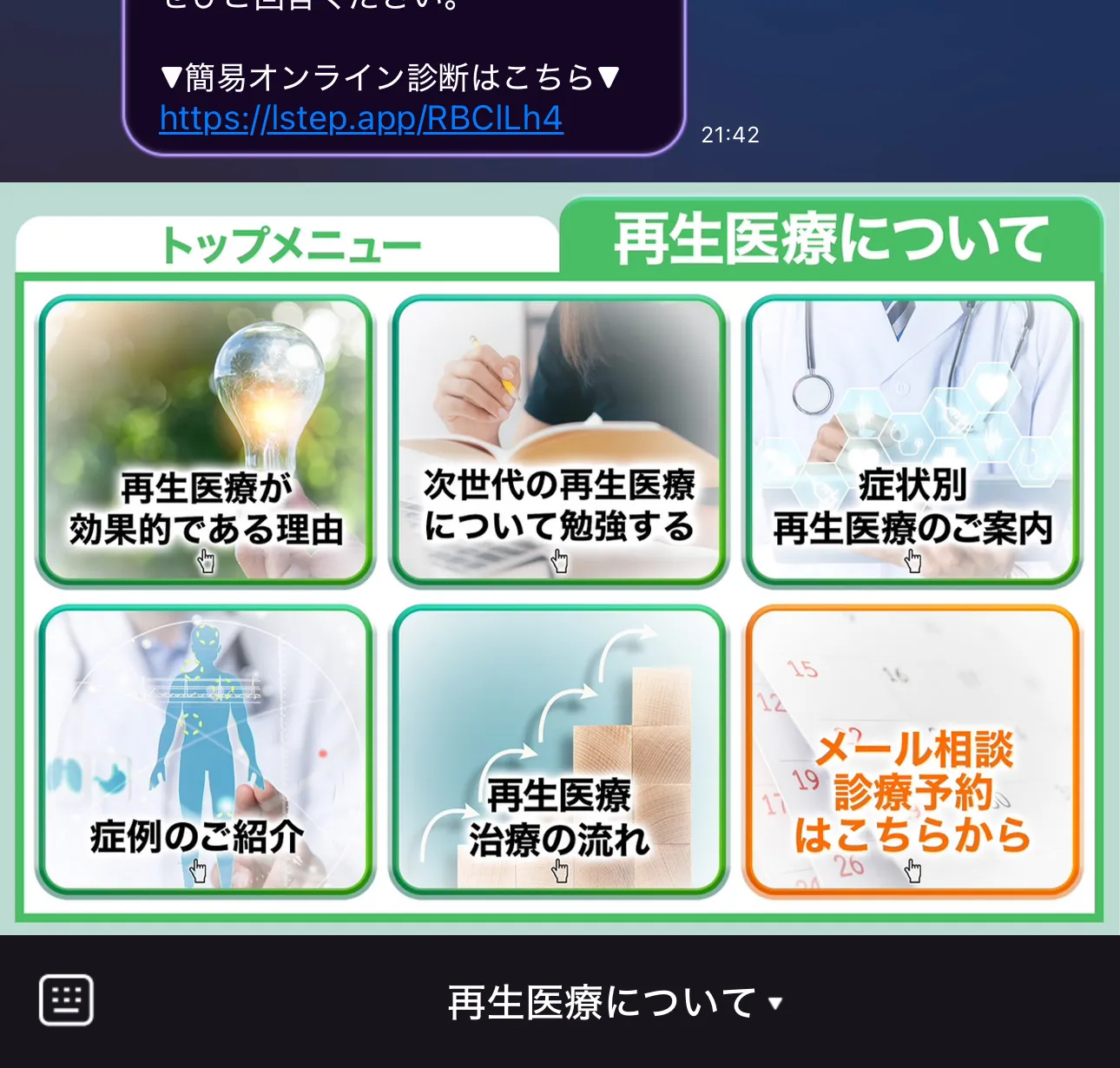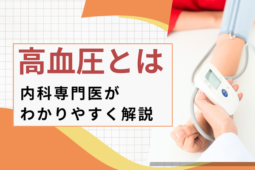血糖値スパイクを起こさない食べ方6つ!糖尿病の予防につながる血糖値を上げにくい食べ物を紹介
公開日: 2019.07.07更新日: 2025.04.30
「血糖値スパイクとは?」「血糖値スパイクにならない食べ方を知りたい」という方はいませんか。
血糖値スパイクとは、食後に急激に血糖値が上昇する現象のことで、身体に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
本記事では、血糖値スパイクの原因や予防方法について、詳しく解説します。
血糖値スパイクにならないように、食事や食べ方などを工夫しましょう。
目次
血糖値スパイクを起こさない食べ方6つ
血糖値スパイクを起こさない食べ方は、以下の6つです。
食後の血糖値が上がりにくい食べ物を選んで食べると、食後の血糖値の上昇が穏やかになります。血糖値スパイクを防ぐポイントをみていきましょう。
食間を2〜3時間以上あける
血糖値スパイクを起こさないためには、食間を2~3時間以上あけることが大切です。
一般的に、血糖値は食後に徐々に上昇し、2~3時間かけて元の値に戻ります。
血糖値が高い状態で、さらに食事を摂取すると、血糖値が急激に上がる可能性があるため注意しましょう。
朝食を抜かない
朝食を抜かないように心がけると、血糖値スパイクの予防につながります。
朝食を抜くことで空腹の時間が長くなるため、昼と夜の食後の血糖値が急上昇しやすくなります。
血糖値の急激な変動を防ぐために、3食規則正しく食べましょう。
野菜から食べ始める
野菜から食べはじめると、血糖値の急上昇を抑えられるため、血糖値スパイクのリスクが低減します。
食事の際は、以下の順番で食べるのがおすすめです。
1.野菜や海藻類などのビタミン類
2.肉や魚などのたんぱく質
3. ご飯や麺類などの炭水化物
野菜に多く含まれる食物繊維は腸の壁をコーティングし、食事の吸収速度を緩やかにする役割があります。
肉・魚に含まれる脂質やたんぱく質は、胃から腸に運ばれる際に、インクレチンと呼ばれるホルモンの分泌を促します。
インクレチンは、胃の内容物が腸に排出されるスピードを遅くする作用があるため、炭水化物の前に肉や魚を摂取するのが効果的です。
早食いせずにゆっくり食べる
血糖値スパイクを防ぐには、食べる順番だけでなく、ゆっくりと食べることも大切です。
早食いをすると、血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働きが追いつかず、食後の血糖値を急激に上昇させてしまいます。
早食いの習慣がある場合は、一口食べたら箸を置くことを意識しましょう。
食後に軽い運動をする
食後に軽い運動をすると、血糖値スパイクの予防につながります。
血糖値が上昇する食後30分~1時間後の運動は、血糖値の上昇を穏やかにする効果があります。
運動習慣がない場合は、無理に散歩やウォーキングを行うのではなく、軽い体操や家事で身体を動かしましょう。
過度な食事制限はしない
血糖値スパイクを予防するには、過度な食事制限はしないことが大切です。
過度な食事制限は、ストレスが溜まり、長続きしない場合があります。
血糖値が上がりやすい炭水化物は、身体にとって必要な栄養素です。
食事の食べる順番や栄養バランスを考え、適度に炭水化物を摂取しましょう。
血糖値スパイクの基礎知識|主な原因について
血糖値スパイクは、食後に急激に上昇した血糖値が急降下する状態のことです。
血糖値スパイクが起こる原因を確認し、自身の食生活を見直しましょう。
血糖値スパイクの基礎知識
食後の短時間に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する状態を「血糖値スパイク」といいます。
スパイクとは「とがったもの」を意味し、急上昇急降下を繰り返した血糖値のグラフが鋭いトゲのような形状になることから、血糖値スパイクと呼ばれます。
食事で摂取したブドウ糖は、エネルギー源として体内で利用されるため、腸で吸収されたあと、血液中に入ります。
健康な人の場合は、血糖値がゆっくりと上昇し、徐々に下降するのが一般的です。
一方で、血糖値スパイクが起こっている場合は、急激な血糖変動から、血糖値のグラフが「M」字になります。
糖尿病では血糖値が常に高い状態が続きますが、血糖値スパイクの場合は、空腹時の血糖値が低いことが特徴です。
血糖値スパイクが起こる原因
血糖値スパイクは、主に以下の原因で起こります。
- 加齢
- 肥満
- 運動不足
- 炭水化物中心の食事
- 朝食を抜く習慣
インスリンが適切に分泌されなかったり、分泌のタイミングがずれてしまったりすると、血糖値スパイクが起こる原因になります。
インスリンは、血糖値を低下させる働きをもつホルモンです。
食後、急激に上昇した血糖値を抑えるために、インスリンが過剰に分泌され、血糖値が急降下します。
乱れた食生活や運動不足などは、血糖値スパイクのリスクになるため注意が必要です。
血糖値スパイクを起こさないための食生活
血糖値スパイクを起こさないために、以下のポイントを押さえて規則正しい食生活を送りましょう。
自身の食生活を見直し、血糖値を上げにくい食べ物を摂取するよう心がけることが大切です。
血糖値を上げにくい食べ物
血糖値スパイクを起こさないために、血糖値を上げにくい食べ物を摂取しましょう。
血糖値が上がりにくい食べ物の例は、以下のとおりです。
- 野菜類(玉ねぎ・オクラ・トマト・レタス・キャベツ など)
- キノコ類
- 海藻類
- 食物繊維を含む食べ物(発芽玄米・大麦・オートミール など)
- 酢
- 柑橘類
- 大豆製品
- 乳製品
野菜類はビタミンやミネラルを豊富に含むため、生活習慣病を予防したい方にもおすすめです。
血糖値が急激に上がりやすい食べ物
血糖値が急激に上がりやすい食べ物を食べると、血糖値スパイクが起こりやすくなる可能性があります。
血糖値を上げやすい食品は、以下のとおりです。
- ご飯
- パン
- 麺類(うどん・そば・パスタ など)
- イモ類(里芋・ジャガイモ など)
- 大豆以外の豆類(おたふく豆・インゲン豆 など)
- 甘いもの(和菓子・洋菓子・スナック菓子 など)
- ジュース
ごはんや麺類、イモ類などの炭水化物は、血糖値が上がりやすい食品です。
野菜は血糖値を上げにくい食品ですが、とうもろこしやかぼちゃなどのデンプン質の野菜は、血糖値を上げやすいため注意しましょう。
血糖値スパイクに潜むリスク
血糖値スパイクには、以下の病気が潜んでいる可能性があります。
空腹時血糖の上昇がみられない血糖値スパイクは、健康診断で見逃される可能性があります。
自覚がないまま血糖値スパイクの症状が進行すると、さまざまな病気になる可能性があるため、早期発見が重要です。
糖尿病のリスク
血糖値スパイクに潜むリスクに、糖尿病があります。
血糖値スパイクは、インスリンの働きや分泌量の低下によって引き起こされます。
インスリンの分泌が低下した状態が続くと、糖尿病の発症リスクが高まるため注意が必要です。
糖尿病の診断には、過去1〜2カ月間の血糖値の平均を示すHbA1cや空腹時血糖の値が用いられます。
認知症のリスク
血糖値スパイクの背後には、認知症のリスクが潜んでいるため注意が必要です。
インスリンが極度に多い状態は、記憶力が低下する原因になります。
血糖値スパイクが起こりインスリンが極度に多い状態が続くと、アルツハイマー型認知症の原因であるアミロイドベータと呼ばれる物質が脳に蓄積します。
インスリンはアルツハイマー型認知症だけでなく、ほかの記憶障害にも影響するホルモンです。
脳に届くインスリン量が極端に少なくなった場合は、記憶力が低下する恐れがあるため、血糖コントロールを十分におこなうことが大切です。
がんのリスク
血糖値スパイクは、がんの発症リスクを高めます。
過度なインスリンは、細胞のがん化やがん細胞の増殖を引き起こすといわれています。
糖尿病によって起こる高インスリン血症や慢性炎症なども、がんを招く原因になるため注意しましょう。
以下の記事では、がん予防に期待できる治療法について、詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
心筋梗塞や脳卒中のリスク
血糖値スパイクによる耐糖能異常で動脈硬化が起こった場合は、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性があります。
血糖値スパイクでは、インスリンの分泌量や働きが低下しているため、上昇した血糖値を正常値に戻しにくくなります。
食後の高血糖によって血管に炎症が起こると、心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。
以下の記事では、脳卒中の1つである脳梗塞になりやすい人の特徴について、詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
血糖値スパイクを起こしているか調べる方法
血糖値スパイクを起こしているか調べる際は、以下の3つの方法で血糖測定を行います。
| 血糖測定の種類 | 検査方法 |
|---|---|
| OGTT(経口糖負荷試験) |
10時間以上絶食した状態で空腹時血糖を測定した後、ブドウ糖液を飲み指定時間に採血する |
| SMBG(血糖自己測定) | 指に穿刺し、専用のセンサーで血液を吸い取る |
| CGM(持続グルコース測定) | 専用のセンサーを装着した状態で過ごす |
血糖値スパイクでは、食後の血糖値が高くなりますが、空腹時は正常値を示す場合が大半です。
OGTTやSMBCは、患者様の食事のタイミングに合わせて検査できるため、正確な糖代謝を確認できます。
CGMはセンサーを装着し、皮下のグルコース濃度を測定する方法です。
グルコース濃度は血糖値とは異なりますが、近い動きをするため、持続的に測定することで血糖コントロール不良を発見できる可能性があります。
【まとめ】血糖値スパイクによる糖尿病が疑われる場合は医療機関を受診しよう
血糖値スパイクによる糖尿病が疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
血糖値スパイクでは、食後に急激な血糖変動が起こります。
血糖値の急上昇・急降下は、身体へ大きなダメージを与え、糖尿病や脳卒中などの病気を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
食事管理や運動習慣などによる血糖コントロールが困難となり、血糖値スパイクによる糖尿病になった場合は、医療機関を受診し治療を受けましょう。
糖尿病を治療せずに放置していると、症状が悪化したり、合併症になったりする恐れがあります。
以下では、糖尿病の再生医療について、詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
血糖値スパイクの予防のためには、血糖値を上げにくい野菜から食べ始めることや、食後に運動を行うことが重要です。
過度な食事制限を避け、無理のない範囲で規則正しい食生活を心がけましょう。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長