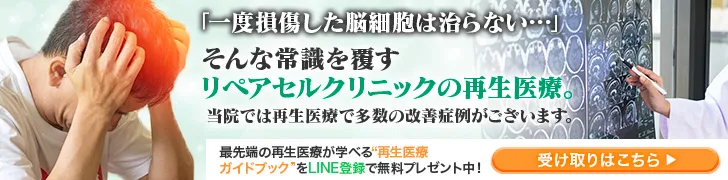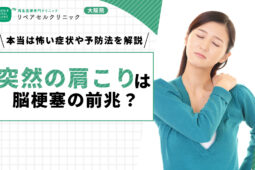- 頭部
高次脳機能障害の「対応の仕方」とは?今日からできる方法と治療の選択肢を解説

高次脳機能障害に向き合うご家族が最初に直面するのは対応の難しさです。
外見では分かりにくい症状が多いため、周囲に理解されにくく、対応に悩んだり不安を抱えたりする患者様・ご家族が少なくありません。
しかし、高次脳機能障害の特徴を知ることで、今日からできる工夫や、接し方のポイントが見つかります。
また、対応の仕方だけでなく、適切なリハビリや治療を組み合わせることで、生活のしやすさを高めていくことも可能です。
本記事では、高次脳機能障害の基本から、家族ができる具体的な対応方法、そして後半では再生医療を含めた治療の選択肢まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。
対応の難しさを一人で抱え込まないための情報を、順を追って紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。。
目次
高次脳機能障害とは?性格の問題ではなく「脳の障害」
高次脳機能障害は「性格」ではなく、脳の損傷によって起こる医学的な障害です。
記憶・注意・判断力・感情のコントロールなど、生活の基盤となる認知機能は、脳の複数の領域が連携して働いています。
そのため、脳梗塞・脳出血・事故による頭部外傷などで脳の一部が損傷すると、性格の変化のように見える行動が生じることがあります。
「わざとやっている」「怠けている」と誤解されやすいのは、高次脳機能障害の大きな特徴のひとつです。ま
ずは“脳の機能の障害”であることを正しく理解することが、対応の仕方を考える最初のステップになります。
- 外見で分かりにくいため周囲に伝わりにくい
- 記憶・注意・感情などの変化が「性格」に見える
- 本人に自覚が乏しいことが多く説明が難しい
- 疲れや環境で症状の波が大きく変わる
- 行動の背景が理解されず誤解が生まれやすい
高次脳機能障害は、周囲の理解が得られるだけで患者様自身も落ち着きやすくなります。
知っておきたい基本的な「対応の仕方」
高次脳機能障害への対応で大切なのは、症状の背景を理解し、感情ではなく「医学的な視点」で向き合うことです。
高次脳機能障害は、脳の損傷によって認知・注意・感情コントロールなどに変化が起きるため、行動の理由が外から分かりにくいことが特徴です。
そのため、ご家族が「なぜこんな言動をするのか」と迷ってしまう場面が多くあります。
ここからは、ご家族が今日から実践できる具体的な対応の仕方を紹介します。
焦らず、できることから取り入れていきましょう。
病気と性格を切り分けて考える
高次脳機能障害の対応では「症状」と「性格」を分けて考えることがとても重要です。
感情の波が大きくなったり、忘れやすくなったり、段取りが難しくなったりするのは、患者様の性格が変わったのではなく、脳の機能が影響を受けているために起こる行動です。
この視点を持つだけで、接し方が大きく変わり、ご家族のストレスも軽減しやすくなります。
- できない行動は「脳の症状」と捉える
- 注意や記憶は疲れや環境によって大きく変動する
- 本人に悪気はない場合がほとんど
- 行動の背景にある理由を探る
- できた部分を見つけて伝える
「わざとではない」という前提で向き合うことで、患者様も安心しやすくなり、関係性が落ち着くケースは多くあります。
まずは理解の姿勢を持つことが、対応の第一歩となります。
家族の日常生活の声かけ・接し方のコツ
家族の関わり方は、患者様の安心感や症状の安定に大きく影響します。
高次脳機能障害では、情報処理や感情の調整が難しくなるため、声かけの仕方や説明の順番を工夫するだけで生活がスムーズになる場面が多くあります。
また、焦らせる言葉や急な環境変化は症状を悪化させることがあるため、できるだけ負担の少ない関わり方を選ぶことが大切です。
- ゆっくり・短く・分かりやすく伝える
- 一度に複数の指示を出さない
- 環境を整える(物の位置・音・光)
- できた行動を肯定的に伝える
- 急がせない・責めないことを意識する
- 疲れのサインに気づき、休息を確保する
声かけや環境の整え方は、患者様の安心感に直結します。
「どこまで手伝うべき?」と迷う場面もありますが、少しずつ一緒に生活リズムを作っていくことで、お互いの負担も軽くなっていきます。
症状別にみる、家族にできる具体的な工夫
高次脳機能障害は症状ごとに対応方法が異なるため、特徴に合わせた工夫がとても大切です。
高次脳機能障害では、記憶・注意・感情・遂行機能など複数の能力が影響を受けるため、症状の種類によって関わり方を変える必要があります。
ご家族が特徴を理解し、無理なく続けられる工夫を取り入れることで、患者様の日常生活が安定しやすくなります。
- 記憶障害:メモ・写真・スマホのアラームを活用する
- 注意障害:刺激を減らした落ち着く環境をつくる
- 遂行機能障害:作業を「小さな手順」に分けて一つずつ伝える
- 感情の不安定:否定せず、落ち着ける空間を用意する
- 社会的行動の変化:予定やルールを明確に伝えて混乱を避ける
- 疲労の出やすさ:こまめに休息を入れ、予定を詰め込みすぎない
症状への理解が深まると「なぜその行動が起きるのか」が見えやすくなり、対応のストレスが大きく減っていきます。
また、小さな工夫でも継続することで生活のしやすさが変わるため、完璧を目指す必要はなく、できる範囲から取り組むことが大切です。
患者様とご家族双方が無理なく続けられるペースを保ちながら、少しずつ生活を整えていきましょう。
対応の工夫だけでなく、「専門的な治療・リハビリ」も大切
高次脳機能障害は家庭での工夫だけでは限界があるため、専門的な治療やリハビリを併用することが非常に重要です。
ご家族による日常的な対応は、患者様の安心感を支えるうえで欠かせません。
しかし、記憶・注意・遂行機能・感情調整などの高度な機能は専門的なアプローチが必要になることが多く、医療機関やリハビリ専門職の支援が組み合わされてこそ、生活の質が安定しやすくなります。
また、患者様自身が「できない自分」を責める気持ちを抱えることもあり、専門家が介入することで心のケアにもつながりやすくなります。
家族だけで抱え込まず、必要な支援を取り入れることが改善への大切な一歩です。
- 専門的な訓練で認知機能の改善が期待できる
- 生活動作の評価から適切な訓練を提案してもらえる
- 感情面のケアも包括的にサポートされる
- 家族の負担軽減につながる
- 状態の変化を専門家がチェックできる
- 進行の防止や再発予防にも役立つ
高次脳機能障害は、症状が見えにくく複雑であるため「家族だけで何とかしよう」とすると、精神的にも身体的にも負担が大きくなってしまいます。
専門職による評価や訓練を受けることで、これまで気づけなかった改善ポイントが見つかることもあります。
また、医療機関と家族が協力してケアに取り組むことで、患者様はより安定して日常生活を送りやすくなります。
専門的な治療は「特別なもの」ではなく、改善の可能性を広げるための大切なサポートといえるでしょう。
次の章では、従来の治療では補いきれない部分に対して、新たな選択肢として注目される再生医療について詳しく解説します。
リペアセルクリニック大阪院で行う再生医療という選択肢
高次脳機能障害の後遺症に対して、再生医療(幹細胞治療)という新しい選択肢が相談されるケースがあります。
高次脳機能障害は、記憶・注意・感情の調整などが複雑に影響し合うため、従来のリハビリだけでは改善のスピードが緩やかになる時期が訪れます。
そのような中で、身体が本来持つ力に着目した再生医療が「選択肢のひとつ」として注目されています。
- 注意力の波が強い
- 記憶のしづらさが残っている
- 感情のコントロールが難しい時期が続く
- 遂行機能(段取り)の負担が大きい
- 生活のしづらさが慢性的に続いている
- 治療の選択肢を広げておきたい患者様
再生医療は、「これまでの治療でできることは続けつつ、別の角度からサポートしたい」という方に選ばれやすい方法です。
患者様の状態や生活背景を丁寧に評価して進めるため、無理な負担をかけず検討できることも特徴のひとつです。
ご家族だけで悩み続けてしまうと、対応の負担も精神的ストレスも大きくなりがちです。
「どの治療が合っているのか知りたい」「後遺症の今後が不安」と感じている場合は、専門医に相談することで選択肢が広がり、より安心して今後の方針を考えやすくなります。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
高次脳機能障害は一人で抱え込まず、「対応」と「治療」を両輪で考えていくことが大切
高次脳機能障害と向き合うには、家庭での対応だけでなく、専門的な治療や支援を同時に活用することが大切です。
高次脳機能障害は外見では分かりづらく、ご家族が負担を抱え込みやすい障害でもあります。
しかし、対応の工夫・生活の調整・リハビリ・医療的支援などを組み合わせることで、患者様の生活のしやすさが徐々に安定していくケースは少なくありません。
「家族だけでどうにかしなければ」という考えから離れ、専門職と一緒に支えていく姿勢がとても重要です。
- 症状を正しく理解して関わり方を整える
- 家庭内の対応は無理なくできる範囲で続ける
- 専門的な治療やリハビリを併用する
- 感情面のケアも大切にする
- 家族だけで抱え込まない環境づくりを意識する
- 必要に応じて再生医療という選択肢も検討しておく
高次脳機能障害は、患者様・ご家族ともに不安が大きくなりやすい障害ですが、正しい知識と支援体制が整うことで、日常生活が落ち着いていくケースが多くあります。
「できていない部分」ではなく、「できている部分」や「進んだ部分」に目を向けることも、前向きなケアにつながります。
もし「今の治療だけで十分なのか」「別の選択肢も知りたい」と感じている場合は、医療機関に相談することで、より納得して今後の方針を決めやすくなります。
リペアセルクリニック大阪院では、再生医療に精通した医師が、患者様の状態・生活環境・現在の治療状況を丁寧に確認したうえで、必要なサポートを総合的に提案しています。
治療の押しつけはせず、患者様とご家族の気持ちに寄り添う姿勢を大切にしているため、初めての方でも相談しやすい環境が整っています。
不安を抱え込む前に、まずは一度専門医に相談することで、これからの生活に向けた選択肢を増やしていきましょう。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長