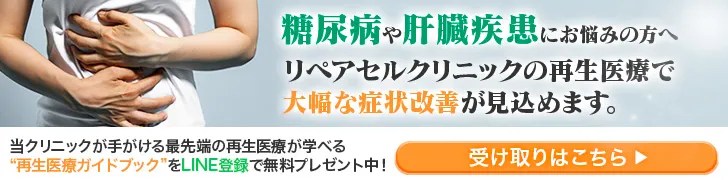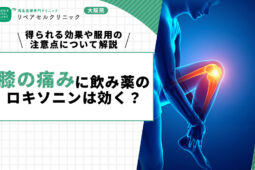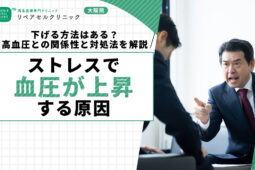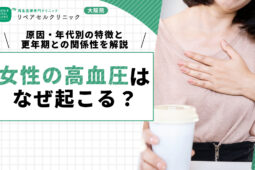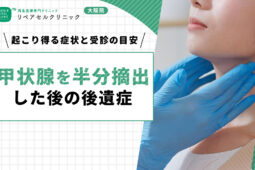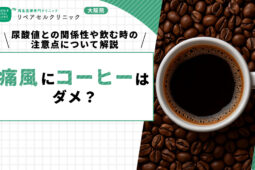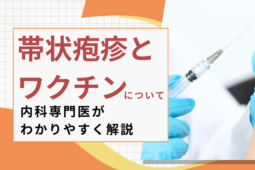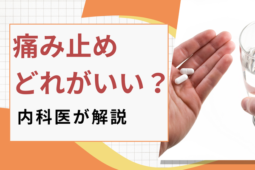- 内科
- その他
納豆は痛風でも食べていいのか|何パックまでならOK?おすすめの食べ方を解説
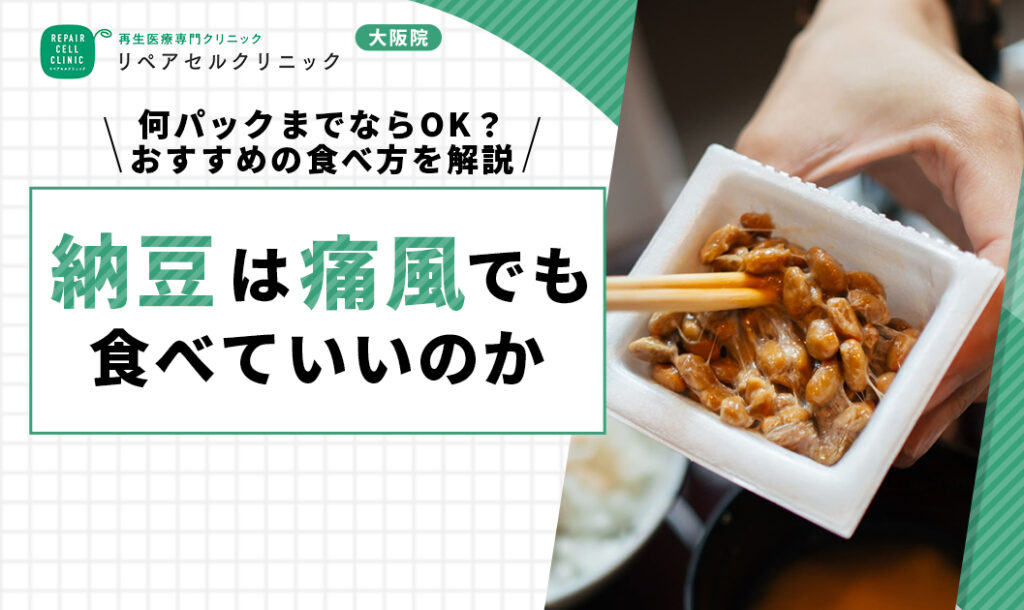
「納豆は痛風でも食べていい?」
「健康に良い納豆を食べたいけれど、痛風への影響が心配」
痛風と診断され、上記のような疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
プリン体が多いとされる大豆製品の中でも、納豆は特に身近な食品であるため、その摂取量や頻度について気になることでしょう。
本記事では、痛風の方が納豆を食べる際の適切な目安量や、尿酸値を上げにくい食べ方について解説します。
- 納豆は痛風でも食べていいのか
- 痛風で納豆を食べるときの注意点
- 痛風患者向けの納豆のおすすめの食べ方
正しい知識を取り入れ、安心して食卓に納豆を並べられるための参考にしてください。
目次
納豆は痛風でも食べていいのか
痛風や尿酸値が高めの方であっても、適量であれば納豆を食べても問題ありません。
本章では、納豆と痛風の関係について、以下の2つのポイントについて解説します。
納豆はプリン体を含んでいますが、極端に多いわけではなく、目安量を守ることで健康的な食生活の一部として取り入れることができます。
過度な心配をせずに納豆を食べるためにも、納豆と痛風の関係性について理解しておきましょう。
プリン体含有量は比較的少ないため適量ならOK
納豆のプリン含有量は、他の高プリン体食品と比較するとそれほど多くはないため、適量であれば痛風の方が食べても問題ありません。
市販納豆に含まれるプリン体総量は「56.6mg/100g」と報告※されており、納豆1パック(40〜50g)あたり約28mgです。
※出典:J-STAGE「納豆摂取習慣による尿酸代謝への影響」
これは、高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインで注意されている「極めて多い(300mg以上)」に該当していません。
高プリン体の食品と納豆のプリン体含有量の比較は、以下のとおりです。
| 食品名 | プリン体含有量(100gあたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 納豆 | 56.6mg | 少ない |
| 鶏レバー | 312.2mg | 極めて多い |
| 白子(イサキ) | 305.5mg | 極めて多い |
| カツオ | 211.4mg | 多い |
上記のように、レバーや白子などの内臓類と比べれば納豆のプリン体は少ないです。
一般的な肉や魚と比較しても低い部類に該当するため、過剰摂取さえ避ければ、日常的に食べても尿酸値への影響は限定的といえるでしょう。
納豆を食べる場合は「1日1パックまで」が目安
痛風の患者さまが納豆を食べる場合、「1日1パック(40〜50g)」を目安にすることをおすすめします。
高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインでは、1日のプリン体摂取量を「400mg以下」に抑えることが推奨されています。
納豆1パックに含まれるプリン体は約28mg程度ですので、これだけで制限を超えることはありません。
しかし、私たちは納豆以外の食事(肉や魚、主食など)からもプリン体を摂取しているため、他の食材とのバランスを考慮すると、納豆は1日1パックに留めておくと良いでしょう。
朝食や夕食のどちらかに一回食事に取り入れる程度が、無理なく続けられる適量です。
納豆を食べると「痛風になる」って嘘?本当?
「納豆を食べると痛風になる」という噂を耳にすることがありますが、過剰摂取していない限り「誤解」といえます。
納豆が痛風の直接的な引き金になる可能性は低く、過剰に恐れる必要はありません。
むしろ、納豆をはじめとする豆類を食事に取り入れることで、血清尿酸値が低下したという研究結果が報告※されています。
※出典:高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版
食事に豆類を取り入れる際は、豆の種類や加工方法によって異なるプリン体含有量に注意しましょう。
| 食品名 | プリン体含有量(100gあたり) |
|---|---|
| 納豆 | 56.6mg |
| 乾燥大豆 | 172.5mg |
| 味噌(白味噌) | 63.5mg |
| ピーナッツ | 49.1mg |
| 枝豆 | 47.9mg |
| 醤油 | 45.2mg |
| そら豆 | 35.5mg |
| 豆腐(冷奴) | 31.1mg |
| 豆乳 | 22.0mg |
「納豆=痛風の原因」と決めつけるのではなく、食事全体のバランスや生活習慣を見直すことが重要といえるでしょう。
痛風で納豆を食べるときの注意点
納豆はプリン体含有量が比較的少なめで痛風の方でも食べられる食品ですが、無条件にどれだけでも食べていいわけではありません。
痛風の方が納豆を食事に取り入れるために注意したい点は、以下の3つです。
これらを守ることで、納豆を食べながら痛風リスクをコントロールできるでしょう。
納豆の食べ過ぎに注意する
納豆のプリン体含有量は少なめとはいえ、食べ過ぎれば摂取量は積み重なり、尿酸値を上げる原因となります。
先述のとおり、1日1パック(約40~50g)であればプリン体摂取量は約28mg程度に収まりますが、これが2パック、3パックとなれば話は別です。
健康に良いからといって極端に摂取量を増やすのではなく、「適量を守ることが重要」と考えましょう。
プリン体は納豆以外の食品からも摂取することになるため、納豆は1日1パック食べる習慣をつけることをおすすめします。
他の食材のプリン体含有量も考慮する
納豆を食べる際は、その日の食事全体のプリン体総量を意識し、一緒に食べるおかずの選び方に工夫が必要です。
納豆自体に一定量のプリン体が含まれているため、メインのおかずにプリン体が多い食品(レバー、干物、カツオなど)を選ぶときは注意しましょう。
高プリン体の食品を一食でも取り入れるだけで、一日のプリン体摂取量の「400mg以下」ギリギリになってしまう可能性があります。
納豆を食べる日は、主菜をプリン体の少ない卵料理や野菜中心のメニューにするなど、プリン体総量のバランスを整えると良いでしょう。
アルコール摂取は控える
納豆を食べるときに限った話ではありませんが、痛風ケアの観点からはアルコールの摂取には注意が必要です。
アルコールは、尿酸の生成を促進するだけでなく、体外への排泄を妨げるという二重のリスクを持っています。
「プリン体ゼロ」の発泡酒であっても、アルコール成分そのものが尿酸値を上げる働きをするため、アルコール摂取は控えた方が賢明です。
納豆を食べる際は、できるだけお酒を控えるか、休肝日を設けるなどして、肝臓への負担を減らすよう心がけましょう。
痛風患者向けの納豆のおすすめの食べ方
痛風で納豆を食べるなら、単体で食べるよりも「尿酸の排泄を助ける食材」や「尿をアルカリ化する食材」と組み合わせるのがおすすめです。
本章では、納豆と相乗効果を狙えるおすすめの食べ方について紹介します。
これらを日々の食事に取り入れ、美味しく効率的な対策を続けていきましょう。
納豆におすすめの食品の組み合わせ
納豆を食べるときは、尿をアルカリ性に傾けるアルカリ性食品や、代謝を助けるビタミン類を含む食品との組み合わせが効果的です。
特におすすめしたい食品は、以下のとおりです。
- 海藻類(わかめ・ひじき)
- ほうれん草・トマト・大根
- きのこ類
- 大豆製品(豆腐)
- いも類
など
これらの食品は納豆との相性も良く、手軽に料理に追加できるものばかりなので、痛風対策に効果的な食事法のためにも、ぜひ取り入れましょう。
おすすめの納豆レシピ
手軽に作れて、痛風対策としての栄養価も高いおすすめレシピを紹介します。
材料を混ぜるだけの簡単なメニューなので、忙しい朝食などに取り入れてみてください。
| レシピ | めかぶ納豆 |
|---|---|
| 材料 | ・めかぶ:2パック(約80g) ・納豆:1パック(約40g) ・醤油:大さじ1/2 |
| 作り方 | ①めかぶと納豆をボウルに入れ、醤油を加えて和える |
| 期待できる効果 | ・尿のアルカリ化をサポートし、尿酸の排出を促す ・めかぶと納豆の相乗効果で腸内環境の改善につながる |
上記はあくまで一例ですが、納豆の持つ栄養価を活かしつつ、痛風に気を付けた組み合わせを工夫することで、痛風の方でも納豆を美味しく食べられるでしょう。
納豆は痛風でも1日1パックはOK!食べ合わせにも注意しよう
痛風だからといって、あれもこれもダメと制限しすぎると、食事の楽しみが減ってしまうものです。
納豆はプリン体含有量が比較的少なめなので、痛風の方でも1日1パックを目安として食べることができます。
食べる際は、「納豆の食べ過ぎ」「他の食材のプリン体含有量も考慮」「アルコールは控える」などの注意点を守りましょう。
痛風と向き合うためにも正しい知識を持ち、適量を守って食べることで健康的な毎日を維持していくことが大切です。

監修者
渡久地 政尚
Masanao Toguchi
医師
略歴
1991年3月琉球大学 医学部 卒業
1991年4月医師免許取得
1992年沖縄協同病院 研修医
2000年癌研究会附属病院 消化器外科 勤務
2008年沖縄協同病院 内科 勤務
2012年老健施設 かりゆしの里 勤務
2013年6月医療法人美喜有会 ふたこクリニック 院長
2014年9月医療法人美喜有会 こまがわホームクリニック 院長
2017年8月医療法人美喜有会 訪問診療部 医局長
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 院長