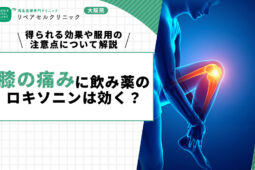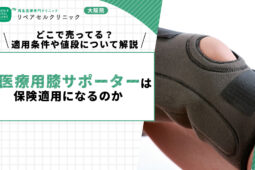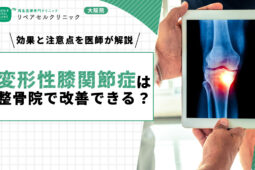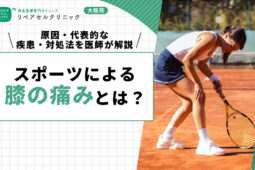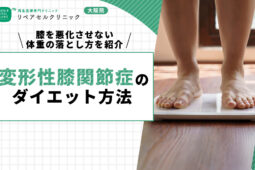- 半月板損傷
- ひざ関節
半月板損傷を早く治す方法|早期回復を目指すリハビリテーション内容を解説
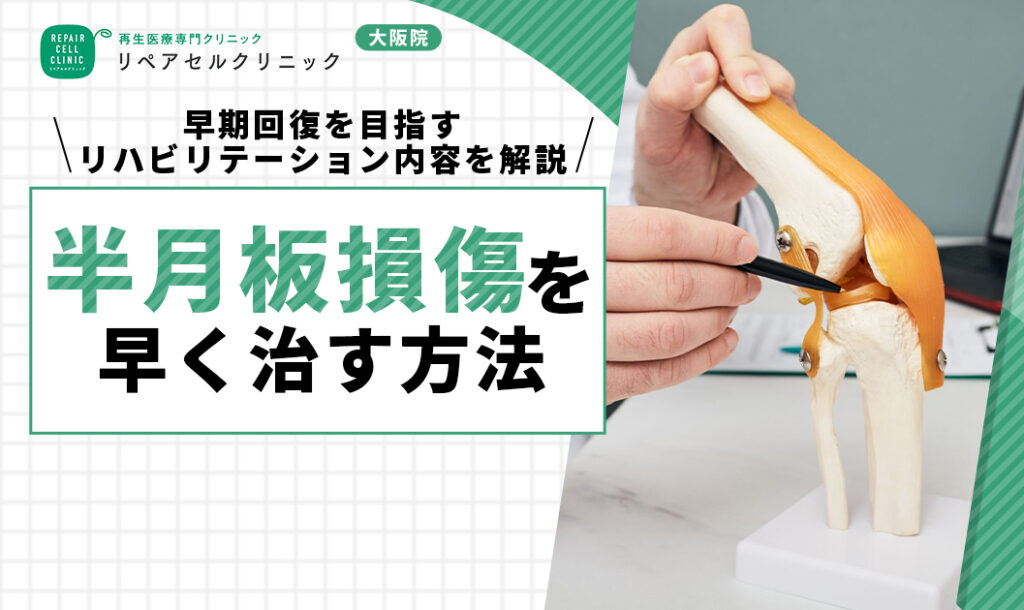
「半月板損傷を早く治す方法は?」
スポーツ中の怪我や日常生活のふとした動作で「半月板損傷」が起こり、早く治す方法を探している方も多いのではないでしょうか。
結論、半月板損傷の早期改善を目指すなら、損傷の状態に合わせた「適切な治療法の選択」と「早期からのリハビリ」が重要となります。
半月板は血流が乏しく自然治癒しにくい組織であるため、ただ安静にしているだけでは、かえって膝周辺の筋力が落ちて回復が遅れることも考えられます。
本記事では、半月板損傷を早く治す方法として、3つの治療法と効果的なリハビリテーションについて解説します。
焦る気持ちを正しい行動に変え、日常生活やスポーツへの早期復帰を目指すためのガイドとしてお役立てください。
また、半月板損傷を一日でも早く治したい方は、再生医療による治療も選択肢の一つです。
再生医療とは、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した半月板の再生・修復を促すことで症状改善を目指す治療法です。
以下の動画では、当院リペアセルクリニックで再生医療の治療を受け、「治らない」と診断された半月板損傷が改善した症例を紹介しています。
「手術せずに半月板損傷を治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院の無料カウンセリングにてご相談ください。
目次
半月板損傷を早く治すために基本情報をチェック
半月板損傷を早く治すには「膝の中で何が起きているのか」を正しく理解し、状態に合わせた適切な対処を選択することが重要です。
早期回復への第一歩として、半月板損傷の基本情報を確認していきましょう。
以下では、半月板損傷の症状や原因についてそれぞれ詳しく解説します。
半月板損傷の症状
半月板損傷の症状は、膝の痛みに加えて膝の引っかかり感があったり、曲げ伸ばしができなくなったりする特徴があります。
具体的な症状の例は、以下のとおりです。
【半月板損傷の主な症状】
- 歩行時に膝が痛くなる
- 膝に引っかかり感がある(キャッチング)
- 膝の力が急に抜ける感覚がある
- 膝の曲げ伸ばしができなくなる(ロッキング)
- 膝に腫れや熱感がある
- 膝を動かすとパキパキ音が鳴る
半月板は膝関節のクッション役を担っているため、亀裂が入ったり、断裂した破片が関節に挟まったりするとスムーズな動きが妨げられてしまいます。
膝の曲げ伸ばしができなくなる「ロッキング」は、激しい痛みを伴い、歩行が困難になることもあるため、早急に医療機関を受診しましょう。
半月板損傷の原因
半月板損傷の原因は、スポーツなどの強い衝撃によって損傷する「外傷性」と、外傷以外の原因から損傷する「非外傷性」の2つに分かれます。
外傷性と非外傷性の特徴は、以下のとおりです。
| 原因 | 特徴 |
| 外傷性 | ・スポーツ中の急激な方向転換などで膝をひねる動作 ・ジャンプの着地時などの衝撃 ・前十字靭帯損傷などと同時に起こるケースもある |
| 非外傷性 | ・加齢による半月板の水分量低下や摩耗によってもろくなる ・膝を深く曲げる、立ち上がるなどの日常的な動作がきっかけとなる |
外傷性の半月板損傷は、サッカーやバスケットボール、バレーボールなどの膝をひねる動作や、強い衝撃が加わりやすいスポーツで発生しやすいです。
一方、非外傷性では、加齢によって半月板がもろくなることで、日常生活のささいな動作が半月板損傷のきっかけとなる場合があります。
半月板損傷を早く治す方法|主な治療法
半月板損傷を早く治すには、ご自身の膝の状態だけでなく、年齢や活動レベルに合った治療を受けることが重要です。
本章では、従来の保存療法や手術療法だけでなく、先端医療である再生医療について解説します。
それぞれの治療法の特徴について詳しく確認していきましょう。
保存療法
保存療法は、手術をせずに痛みや炎症を抑え、膝の機能回復を目指す治療法です。
まずは痛みや炎症が落ち着くまで、膝の負担を避けて安静にし、徐々に膝周辺の筋力や柔軟性向上を目的としたリハビリテーションを行います。
強い痛みを伴う場合は、痛み止め(消炎鎮痛剤)や湿布などで痛みや炎症をコントロールする治療が実施されます。
また、ヒアルロン酸の関節内注射を行う場合があります。
保存療法は対症療法であり、手術を避けられるものの半月板損傷を根本的に治すための治療ではない点に注意しましょう。
手術療法
手術療法は、保存療法で症状が改善しない場合や、ロッキング(膝が動かない状態)などの重度な症状がある場合に検討されます。
手術には、大きく分けて以下の2種類があります。
| 手術法 | 詳細 |
| 半月板縫合術 | ・損傷、または断裂した半月板を縫い合わせる ・半月板の機能を温存できる反面、治癒に時間がかかる |
| 半月板切除術 | ・損傷、または断裂した半月板を切除する ・術後の回復が比較的早い ・クッションが減るため、将来的な変形性関節症リスクが高まる |
現在の手術療法は、膝に小さな穴を開けて内視鏡(関節鏡)を挿入して行うため、今までの手術に比べて体への負担は大幅に軽減されています。
しかし、術後の入院や中長期的なリハビリテーションが必須になる点には注意が必要です。
競技復帰を急ぐスポーツ選手などは、損傷の状態と復帰までの期間について理解したうえで手術を受けるか決めましょう。
再生医療
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて、炎症抑制や損傷した半月板の再生・修復を促す治療法です。
「手術はしたくないが、保存療法だけでは痛みが取れない」という方にとって、手術・入院不要で受けられる選択肢として注目されています。
代表的な治療法は、以下のとおりです。
| 治療法 | 詳細 |
| PRP療法 | 患者さま自身の血液から、組織修復を促す成分(多血小板血漿)を抽出し、膝に注射する。 |
| 幹細胞治療 | 脂肪などから幹細胞を採取・培養し、数を増やしてから膝関節内に投与する。 |
先端医療のため、公的保険が適用されず自由診療となるため費用は高額になりますが、手術を避けて半月板損傷の根本的な改善を目指せます。
半月板損傷の早期回復を目指すリハビリテーション内容
半月板損傷の早期回復の鍵は、患部の炎症を抑えつつ、膝周りの筋力と関節の動きを「痛みのない範囲で」維持・向上させることにあります。
本章では、半月板損傷の早期回復を目指すリハビリテーションについて解説します。
安静にしすぎると筋力が低下して膝への負担が増す悪循環に陥るため、医師や理学療法士の指導のもと、段階的にリハビリテーションを進めていくことが推奨されます。
それぞれの内容について、詳しく確認していきましょう。
下半身の筋力トレーニング
半月板損傷の早期回復・再発予防には、下半身(主に膝周辺)の筋力トレーニングが欠かせません。
膝の安定性を高めるための「大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)」と「ハムストリングス(太ももの裏の筋肉)」を重点的に鍛えましょう。
初期段階では、体重をかけずに行う膝への負担が少ないトレーニングが効果的です。
【パテラセッティング】
- 仰向けに寝て、膝の下にタオルを置く
- タオルを潰すように膝を床に押し付ける
- 1セット10回を目安に行う
【レッグレイズ】
- 両脚を揃えて仰向けに寝る
- 両手を体の横に置き、両脚を90度まで上げる
- かかとが床につくギリギリまでゆっくりと両脚を落とす
- 1セット5〜10回を目安に行う
上記のような筋力トレーニングをできる限り、毎日継続しましょう。
しかし、膝の痛みや違和感がある場合は、トレーニングを中止して安静にすることを優先してください。
膝関節の可動域訓練
半月板損傷の早期回復・再発予防のためにも膝関節の可動域訓練を行い、膝の柔軟性を向上・維持することが重要です。
痛みや腫れの影響で膝を動かさない状態が続くと、膝周辺の筋肉が硬くなり、動きが制限されやすくなってしまいます。
以下の可動域訓練を実践し、膝関節の柔軟性を向上させましょう。
【ヒールスライド】
- 膝を伸ばした状態で仰向けに寝る
- かかとを滑らせてお尻に近づけるように膝をゆっくり曲げる
- 元の位置に戻すように膝をゆっくり伸ばす
- 1セット10回を目安に行う
お風呂上がりなど、体が温まって筋肉が緩んでいるタイミングで行うと、よりスムーズに動かせるでしょう。
膝を曲げ伸ばしする際に、膝が内側に入らないように真っ直ぐ動かすことが重要です。
有酸素運動
有酸素運動によって、全身の血行を良くして組織の修復を促すことで半月板損傷の早期改善につながります。
ジョギングなどの地面からの衝撃がある運動は半月板へのダメージが大きいため、膝への負担が少ない種目から始めましょう。
【膝に負担の少ない有酸素運動】
- エアロバイク
- 水中ウォーキング
有酸素運動によって心肺機能を維持することは、スポーツ復帰後のパフォーマンス低下を防ぐ上でも大きなメリットとなります。
また、体重増加による膝への負担増加を防げるため、再発予防にも効果的です。
バランストレーニング
半月板損傷のリハビリテーションでは、膝関節を安定させ、歩行能力を改善するためのバランストレーニングも重要です。
【おすすめのバランストレーニング】
- 片足立ち
- バランスボードの活用
- バランスディスクの活用
怪我をした後は、無意識のうちに患部をかばった歩き方になり、バランス能力が低下していることが多いため、再発予防の観点からも必要なトレーニングです。
バランストレーニングをする際は、短時間かつ安定した場所から始め、慣れてきたら時間や難易度を上げましょう。
半月板損傷を早く治す方法についてよくある質問
本章では、半月板損傷を早く治す方法についてよくある質問について回答します。
回復を早めるためには、リハビリ以外の時間である「日常生活」の過ごし方も非常に重要です。
それぞれ詳しく確認していきましょう。
半月板損傷を早く治す食べ物はある?
食べただけで半月板が再生するような「特効薬」となる食材はありませんが、組織の修復材料となる栄養素を積極的に摂ることは回復を後押しします。
以下の栄養素を意識して、バランスの取れた食事を心がけましょう。
| 積極的に摂りたい栄養素 | 主な食材 | 主な役割 |
| タンパク質 | 肉、魚、大豆製品、卵 など |
筋肉や靭帯、軟骨のベースとなる重要な栄養素 |
| ビタミンC | ピーマン、ブロッコリー、柑橘類 など |
関節組織の主成分であるコラーゲンの生成を助ける |
| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、玄米 など |
代謝を促し、神経の働きを正常に保つのに役立つ |
コラーゲンやグルコサミンなどのサプリメントも販売されていますが、あくまで補助的なものと考え、まずは毎日の食事を整えることが先決です。
半月板損傷でやってはいけないことは?
半月板損傷でやってはいけないことは、以下のとおりです。
- 痛みを我慢して歩行や運動の継続
- 膝を深く曲げる動作
- 自己流のストレッチやマッサージ
- 肥満・急激な体重増加
- 不適切なサポーターの装着
上記のように膝を深く曲げたり、体重をかけた状態でひねったりする動作は、損傷部分を広げてしまう危険性が高いため厳禁です。
「痛くないから大丈夫」と油断してこれらの動作を行うと、症状の悪化や長引く原因となります。
日常生活の中で「膝への負担」を減らす工夫をすることが、半月板損傷の早期改善を目指すうえで重要なポイントです。
半月板損傷を早く治すには手術不要の再生医療をご検討ください
膝の状態、年齢、活動レベルに合った治療を受けることが、結果的に半月板損傷の早期改善につながります。
まずは、安静・薬物療法・リハビリテーションなどの「保存療法」によって半月板を温存して、症状の改善を目指すことが一般的です。
従来の治療では、保存療法を3〜6ヶ月継続しても改善しない場合や、ロッキング(膝が動かせなくなる)などの重症例では、手術療法が検討されていました。
しかし、近年の治療では、半月板損傷を手術せずに根本的な改善を目指せる再生医療が注目されています。
再生医療とは、患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した半月板の再生・修復を促すことで症状改善を目指す治療法です。
以下のページでは、当院リペアセルクリニックで再生医療の治療を受け、半月板損傷の痛みレベルが改善した症例を紹介しています。
>半月板損傷の痛み改善で手術を回避した症例(60代女性)はこちら
「手術せずに半月板損傷を治したい」「再生医療について詳しく知りたい」という方は、ぜひ当院の無料カウンセリングにてご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設