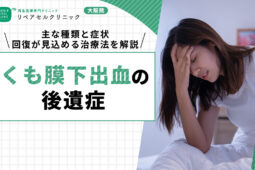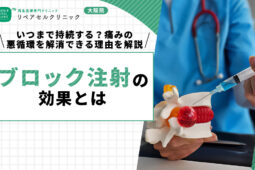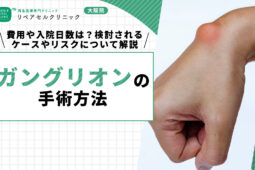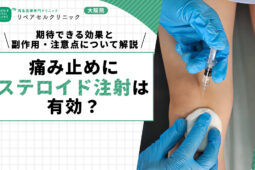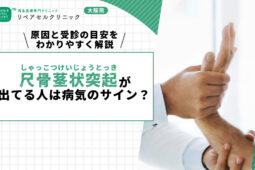- その他
水頭症の寿命はどのくらい?手術しないとどうなるのか、放置リスクと治療法について解説
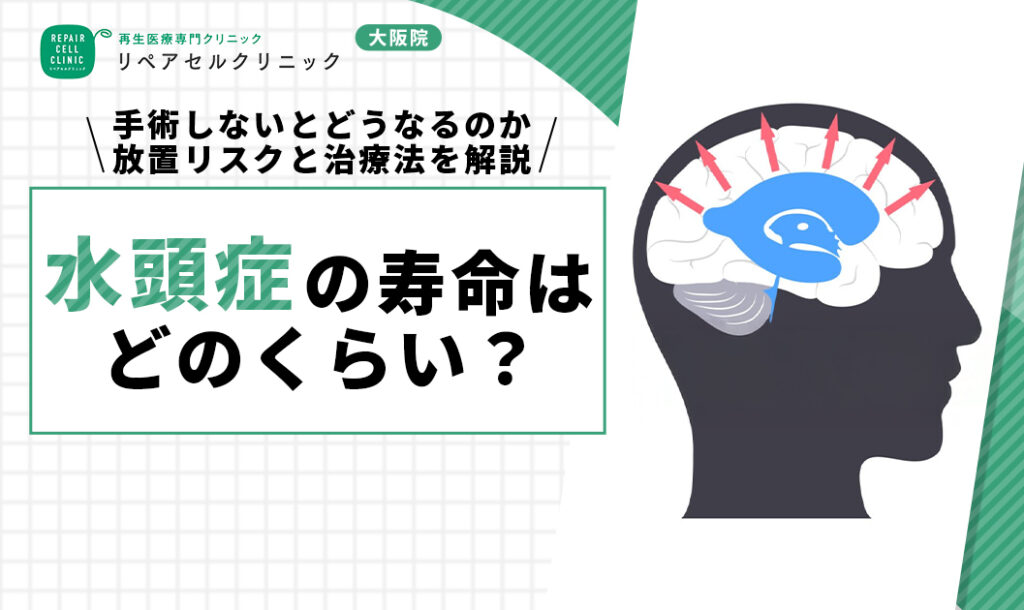
水頭症とは、脳の中にある脳脊髄液という液体がたまりすぎてしまう病気で、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で発症します。
放置すると歩行障害や認知機能の低下など、生活に大きな影響を及ぼす深刻な症状が現れる可能性があります。
水頭症と診断されて「寿命はどのくらいなのか」「手術をしないとどうなるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、水頭症の寿命や治療法、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。
水頭症でお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、水頭症の原因となるくも膜下出血や脳出血については、再発予防の観点から再生医療という治療選択肢もあります。
当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでも、再生医療に関する情報の提供やオンライン診断を実施しておりますので、併せてご覧ください。
「再生医療について詳しく知りたい」という方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。
目次
水頭症の寿命はどのくらい?
水頭症の寿命・予後は、発症年齢、原因(先天性・後天性)、治療開始の時期などによって異なります。
しかし、水頭症は適切な治療を受けることで良好な予後が期待でき、直接寿命に影響する可能性は低いと考えられています。
特に小児の場合、シャント手術を受けた方の80%以上が長期生存できるといわれています。
早期に適切な手術治療を受けることで、症状が改善し、日常生活を自立して送れる可能性が高い※とされています。
※出典:PubMed
健康的な生活を長く送るためにも水頭症の症状を理解し、発症が疑われる場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
水頭症とは|2つのタイプと主な症状
水頭症について正しく理解するためには、その種類と症状を知ることが大切です。
水頭症には大きく分けて以下の2つのタイプがあります。
これらの違いを理解することで、ご自身やご家族の症状に応じた適切な治療を選択できるようになります。
非交通性水頭症
非交通性水頭症は、脳脊髄液の流れる通路のどこかが塞がれてしまう状態です。
脳には脳脊髄液という液体が流れる通り道があり、この通路が脳腫瘍や先天的な異常などによって塞がれると、液体がせき止められて脳を圧迫します。
主な症状は、以下のとおりです。
- 頭痛
- 吐き気
- 視力の低下
- 乳幼児の場合は頭が異常に大きくなる
子どもに起こりやすいタイプですが、成人でも脳腫瘍などが原因で発症する場合があります。
主な原因は、生まれつきの脳の構造異常、脳腫瘍による通路の閉塞、脳の感染症などです。
通路が塞がれることで、脳脊髄液が正常に流れなくなり、脳室という脳の中の部屋が大きく膨らんでしまいます。
進行すると意識障害を引き起こす可能性もあります。
交通性水頭症
交通性水頭症は、脳脊髄液の流れる通路に問題はないものの、液体が吸収されにくくなる状態です。
高齢者に多く見られるタイプで、脳脊髄液の循環量が増えすぎてしまいます。
交通性水頭症の代表的な症状には、以下の3つがあります。
- 歩行障害(小刻みな歩き方、足が上がりにくい、転びやすいなど)
- 認知機能の低下(物忘れ、判断力の低下、反応が鈍くなるなど)
- 尿失禁(トイレが間に合わない、頻尿など)
これらの症状は認知症と似ているため見逃されやすいですが、適切な治療で改善できる可能性があるため、早期に治療を行うことが大切です。
交通性水頭症には、くも膜下出血や頭部外傷、髄膜炎などの病気が原因の「続発性」と、はっきりとした原因がわからない「特発性」があります。
くも膜下出血などの脳の病気を経験された方は、その後も症状の変化に注意することが大切です。
水頭症は回復する?主な治療法
水頭症の治療について、薬で治すことは難しく、基本的には以下の手術療法が必要です。
それぞれの手術方法には特徴があり、患者さまの状態に応じて適切な治療法が選択されます。
脳室ドレナージ術
脳室ドレナージ術は、急激に悪化した水頭症に対して緊急的に行われる一時的な処置です。
この手術では、脳室内にチューブを挿入して、たまった脳脊髄液を体の外に排出させます。
脳の圧力が急激に高まり、意識障害を起こしているような命に関わる状態で行われる救命処置です。
ただし、あくまで一時的な処置であるため、その後の状態に応じて恒久的な治療法であるシャント手術などが検討されます。
シャント手術
シャント手術は、水頭症の根本的な治療として一般的に行われる手術です。
この手術では、体の中にチューブを通して、脳にたまった余分な脳脊髄液をお腹の中(腹腔)に流します。
最も多く行われるのは「V-Pシャント」と呼ばれる方法で、頭とお腹をつなぐチューブを皮膚の下に埋め込みます。
また、背骨の周りを流れる脳脊髄液から直接お腹へチューブをつなぐ「L-Pシャント」という方法もあります。
これらの手術は、脳脊髄液の出口を新しく作ることで、たまりすぎた液体を排出し、症状を改善させることを目的としています。
シャント手術を受けることで、歩行障害や認知機能の低下、尿失禁などの症状が改善される可能性があります。
水頭症を手術しないとどうなる?放置するリスク
水頭症を治療せずに放置すると、以下の症状が悪化するリスクがあります。
- 歩行障害が進み、転倒のリスクが高まって自力で歩けなくなる可能性がある
- 認知機能が低下し、物忘れや判断力の低下が著しくなる
- 尿失禁が頻繁になり、日常生活に支障をきたす
先天性水頭症を放置した場合には、さらに深刻な問題が生じる可能性があります。
考えられるリスクは、以下のとおりです。
- 新生児や乳児では頭が異常に大きくなる
- 症状が進行すると黒目が下の方に寄る「落陽現象」や吐き気、けいれんが現れる
- 年長の子どもでは頭痛や吐き気が早い段階から見られる
- 脳の圧力が高い状態が続くと視力低下や失明につながる恐れがある
- 意識障害が現れ、生命に危険が及ぶリスクも高まる
水頭症は、早期に適切な治療を受けることで症状の改善が期待できる病気です。
手術を避けて様子を見るのではなく、医師と相談しながら治療時期を見極めましょう。
水頭症の寿命についてよくある質問
水頭症の寿命や治療について、よくある質問を紹介します。
これらの疑問を解消して、適切な治療選択の参考にしてください。
水頭症になっても長生きできる?
水頭症と診断されても、適切な治療を受けることで長生きできる可能性は十分にあります。
特に小児の場合、早期にシャント手術などの適切な治療を受けた場合、80%以上の方が長期生存できるとされています。
重要なのは、症状が現れた段階で早めに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることです。
水頭症の死亡率は?
水頭症を放置した場合の死亡率は約50%※に達するといわれています。
※出典:東邦大学医療センター「水頭症」
しかし、適切な治療を受けた場合は、水頭症が寿命に影響を与える可能性は低いため、早期発見・治療開始が重要です。
高齢者でも水頭症は回復する?
高齢者の水頭症でも、適切な手術治療を受けることで症状の回復が期待できます。
一般的に、水頭症の改善率は「歩行障害:58〜90%」、「認知障害:29〜80%」、「排尿障害:20〜82.5%」程度になると報告※されています。
※出典:厚生労働省「特発性正常圧水頭症」
高齢だからといって手術を諦める必要はありません。
ただし、症状が長期間続いていたり、他の病気を併発していたりする場合は、回復の程度に個人差があります。
水頭症の回復には適切な治療を受けることが重要
水頭症は、適切な治療を受けることで症状の改善が期待できる病気です。
特に小児の場合、シャント手術などの治療により、80%以上の方が長期生存できるとされており、歩行障害や認知機能の低下などの症状も改善される可能性があります。
また、水頭症の原因がくも膜下出血や脳出血である場合、これらの脳血管障害の再発予防も重要です。
脳内出血を防ぐための治療選択肢として、再生医療という方法があります。
再生医療は、患者さまの細胞や血液を用いて自然治癒力を高めることで、損傷した脳血管の再生・修復を促す医療技術です。
▼くも膜下出血に対する再生医療の症例動画
くも膜下出血や脳出血などの再発を予防したい方や脳出血による後遺症にお悩みの方は、当院リペアセルクリニックへご相談ください。

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師