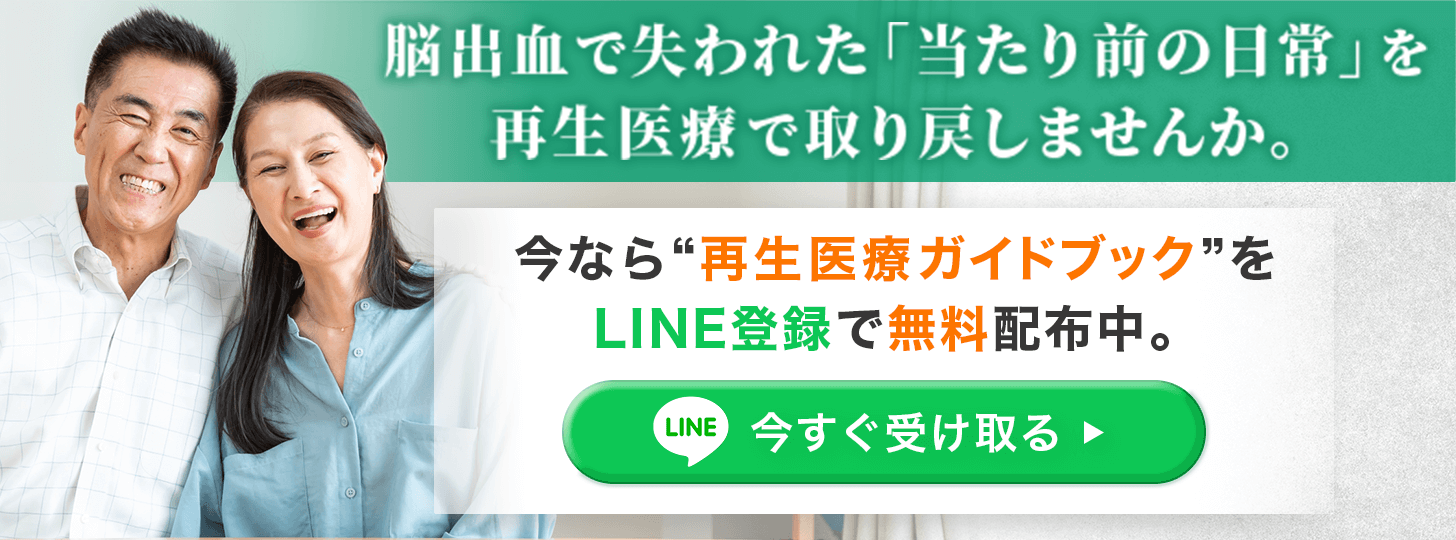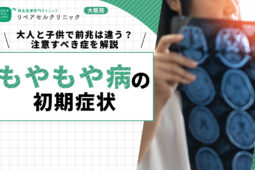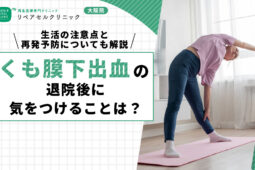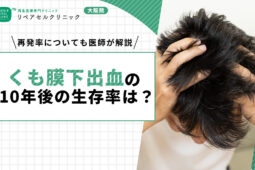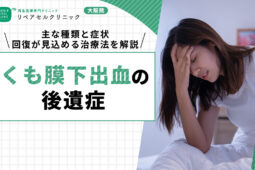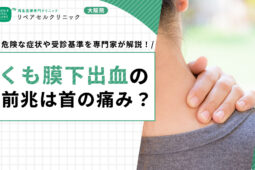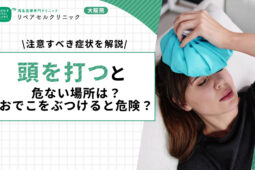- くも膜下出血
- 再生治療
くも膜下出血はなぜ女性に多い原因とは?放置リスクや回復への道を詳しく紹介
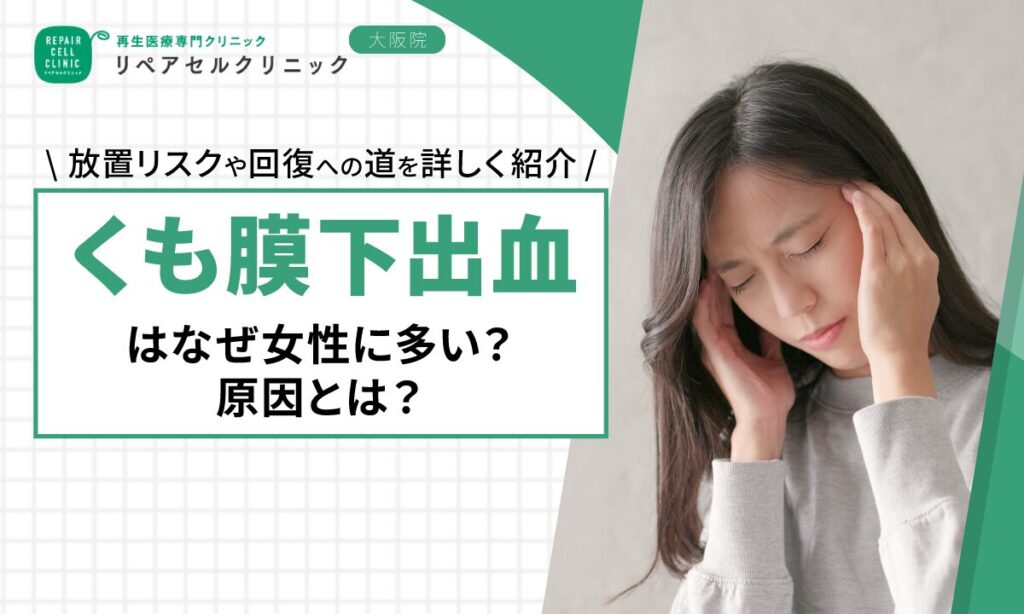
くも膜下出血は女性に多い疾患であり、頭痛や吐き気などの前兆があらわれます。
「最近頭痛が増えたけど、くも膜下出血の前兆なのかな?」と不安に感じていませんか?
くも膜下出血は死亡率が高く、助かった場合でも後遺症を引き起こす恐れがあるため、早急な検査が必要です。
しかし、単なる頭痛との違いがわからず、検査するかどうか迷っている方も少なくありません。
本記事では、くも膜下出血が女性に多い原因や、適切な治療方法などをわかりやすく解説します。
治療には手術が必要といわれた方は、切らずに改善を目指せる「再生医療」も参考にしてみてください。
目次
くも膜下出血はなぜ女性に多い原因
くも膜下出血はなぜ女性に多いのか、実は以下の原因があるためです。
閉経は女性特有のものですが、生活習慣がくも膜下出血を引き起こす可能性もあります。
ここからは、くも膜下出血が喫煙や遺伝とどう関係するのか、詳しい原因をみていきましょう。
閉経によるエストロゲン低下が血管を脆くする
閉経を迎えた女性は血管が脆くなってしまい、くも膜下出血を引き起こす可能性があります。
女性ホルモンのエストロゲンは血管をしなやかに保っていますが、閉経後は保護作用が失われるため、血管壁の柔軟性が低下します。
硬くなった血管は脳動脈瘤を形成しやすいので、膨らんだ部分が破裂すると、くも膜下出血の原因となる恐れも。
閉経の時期は更年期と重なる場合が多く、頭痛や吐き気などがあっても、「更年期障害が原因だろう」と考えがちです。
手足の麻痺やめまいなどの症状もあらわれ、くも膜下出血が疑われる場合は、早めに医療機関の検査を受けましょう。
喫煙・高血圧・大量飲酒がリスクを増幅
喫煙や大量飲酒は高血圧になりやすく、くも膜下出血のリスクを増幅させます。
タバコを吸うと、ニコチンなどの有害物質が血管の炎症を引き起こし、脳動脈瘤が形成されやすくなるため、血圧上昇の原因となります。
大量飲酒も高血圧につながってしまい、脳動脈瘤の形成や、破裂リスクを高めるので要注意です。
喫煙や飲酒の生活習慣がある方は、タバコの本数やお酒の摂取量を減らし、定期的に血圧を測ってみましょう。
家族歴・遺伝性疾患(多発性嚢胞腎など)にも注意
くも膜下出血は遺伝する疾患ではありませんが、 脳動脈瘤には遺伝的要因が考えられます。
3親等内の家族(父母・兄弟姉妹・子ども)が以下に該当する場合は、ご自身もくも膜下出血の発症リスクが高くなります。
- 糖尿病
- 高血圧
- 多発性嚢胞腎
糖尿病や高血圧は脳動脈瘤を引き起こす場合があるため、家族の体質にも要注意です。
多発性嚢胞腎は親から子に遺伝するケースが多く、症状が悪化すると腎不全につながりますが、脳動脈瘤などの合併症を引き起こす場合もあります。
家族にくも膜下出血や脳動脈瘤の病歴があり、ご自身も頭痛や吐き気に悩んでいる場合は、早めに検査を受けておきましょう。
くも膜下出血とは?突然の激しい頭痛に潜むリスク
くも膜下出血とは、脳動脈瘤が破裂し、脳全体に血液が広がる症状です。
外傷による脳へのダメージや、脳腫瘍などもくも膜下出血を引き起こしますが、主な原因は脳動脈瘤の破裂です。
脳動脈瘤の破裂は脳にかかる圧を高くし、脳内に血液が行き届かなくなるため、意識を失ってしまうケースもあります。
くも膜下出血の発症率は男性よりも女性が高く、死亡率も高い疾患です。
後遺症を引き起こす可能性や、再発リスクもあるため、命が助かっても安心はできません。
激しい頭痛に突然襲われたときは、頭部CTなどの検査を受けておきましょう。
くも膜下出血の前兆と早期発見のポイント
くも膜下出血には以下の前兆があるため、頭痛やめまいには注意が必要です。
ここからは、くも膜下出血の特徴的な症状や、早期発見のポイントを解説します。
「突然の激しい頭痛」は要注意
くも膜下出血には警告頭痛と呼ばれる前兆があるため、突然の激しい頭痛は要注意です。
頭痛がすぐに収まった場合でも、今までにない激痛であれば、くも膜下出血の警告サインになっている可能性があります。
激しい頭痛が続くときは痛み止めで我慢せず、すぐに医療機関の診察を受けましょう。
救急受診が早ければ、命を守れる確率が高くなります。
めまい・吐き気・視覚異常が続く場合も早めの受診を
くも膜下出血の前兆には、急なめまいや吐き気、視覚異常もあります。
脳動脈瘤の破裂によって出血すると、平衡感覚を調整する小脳や脳幹に悪影響を及ぼすため、めまいや吐き気を引き起こします。
また、脳動脈瘤が大きくなると、周辺の神経を圧迫し、ものが二重に見える視覚障害を引き起こす恐れも。
軽い症状でも「未破裂動脈瘤」の可能性があるため、急なめまいや視覚障害などが起きたときは、脳神経外科の診察を受けておきましょう。
くも膜下出血の治療方法
くも膜下出血になった場合は、以下の方法で治療できます。
どの治療方法もくも膜下出血の原因を除去できますが、体への負担や感染症リスクなどを考慮する必要があります。
手術は頭部に傷が残ってしまうので、以下を参考に自分に合った治療方法を検討してみましょう。
開頭クリッピング術
開頭クリッピング術とは、手術によって頭蓋骨を開き、脳動脈瘤の根元を金属クリップで閉じる治療方法です。
くも膜下出血の代表的な治療方法ですが、以下のメリット・デメリットを考慮する必要があります。
| 開頭クリッピング術のメリット |
・脳動脈瘤を直接見るため、血液の流れを確実に止められる ・手術中に脳動脈瘤が破裂してもすぐに対処できる ・再発リスクが低い |
| 開頭クリッピング術のデメリット |
・頭部に手術痕が残る ・感染症や合併症のリスクがある ・体にかかる負担が大きい ・顎の動きに不快感が残りやすい ・術後は1~2週間程度の入院が必要 |
開頭クリッピング術は体にかかる負担が大きいため、再発リスクが高い症例や、体力がある若年層に用いられるケースが一般的です。
手術の際にはこめかみの近くを切開するので、顎の動きに不快感が残ってしまう恐れも。
開頭クリッピング術を検討する際は、ほかに選択肢があるかどうかも考えておきましょう。
血管内コイル塞栓術
血管内コイル塞栓術とは、カテーテルを使って動脈瘤内部にコイルを詰め、血流を遮断する低侵襲治療です。
体力が低下している方や高齢者に向いていますが、以下のメリット・デメリットがあるため、十分な検討が必要です。
| 血管内コイル塞栓術のメリット |
・体への負担を軽減できる ・入院期間が短い ・手術の傷が残らない |
| 血管内コイル塞栓術のデメリット |
・くも膜下出血の再発リスクが高い ・脳梗塞などの合併症リスクがある ・脳動脈瘤の状態により、コイルを詰められないケースがある |
血管内コイル塞栓術は頭部を切開しないため、開頭クリッピング術よりも体にかかる負担は軽くなります。
手術の傷も残りませんが、脳動脈瘤の膨らみが再発する場合があります。
合併症のリスクもあるので、血管内コイル塞栓術を受けるかどうかは、医師とじっくり相談して決めましょう。
再生医療
再生医療とは、幹細胞の働きを活用し、損傷した血管や脳組織を修復する治療方法です。
比較的新しい治療方法となるため、ご存じない方もいらっしゃいますが、国内外で臨床研究が進んでおり、回復の可能性も広がっています。
治療の際には自己脂肪から幹細胞を抽出し、体外培養して患部に注射するため、手術や入院は必要ありません。
自分の幹細胞を活用すると、アレルギー反応などのリスクも低減できます。
再生医療についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひリペアセルクリニック大阪院にご相談ください。
リペアセルクリニック大阪院には再生医療の専門医が在籍し、くも膜下出血や脳梗塞などの治療に成果を上げています。
自分の体を守るためにくも膜下出血のサインを見逃さないようにしよう
くも膜下出血は女性に多く、死亡率も高いため、頭痛などのサインを見逃さないように注意しましょう。
早めに原因を特定し、適切な治療を受けると、完治の可能性が十分にあります。
ただし、外科手術は合併症や再発のリスクがあり、一定期間の入院も必要です。
頭部の切開に抵抗がある方や、元どおりの健康体を取り戻したい方は、ぜひリペアセルクリニック大阪院の無料相談をご活用ください。

監修者
圓尾 知之
Tomoyuki Maruo
医師
略歴
2002年3月京都府立医科大学 医学部 医学科 卒業
2002年4月医師免許取得
2002年4月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2002年6月関西労災病院 脳神経外科 勤務
2003年6月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2003年12月大阪母子医療センター 脳神経外科 勤務
2004年6月大阪労災病院 脳神経外科 勤務
2005年11月大手前病院 脳神経外科 勤務
2007年12月大阪大学医学部附属病院 脳神経外科 勤務
2012年3月大阪大学大学院 医学系研究科 修了(医学博士)
2012年4月大阪大学医学部 脳神経外科 特任助教
2014年4月大手前病院 脳神経外科 部長