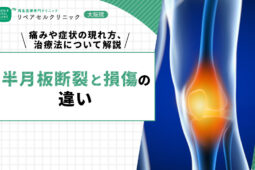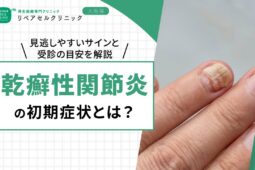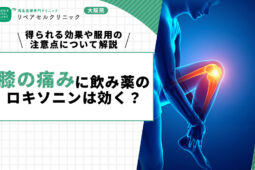- 靭帯損傷
- ひざ関節
外側側副靭帯損傷とは|主な症状、原因、チェック方法について解説【医師監修】
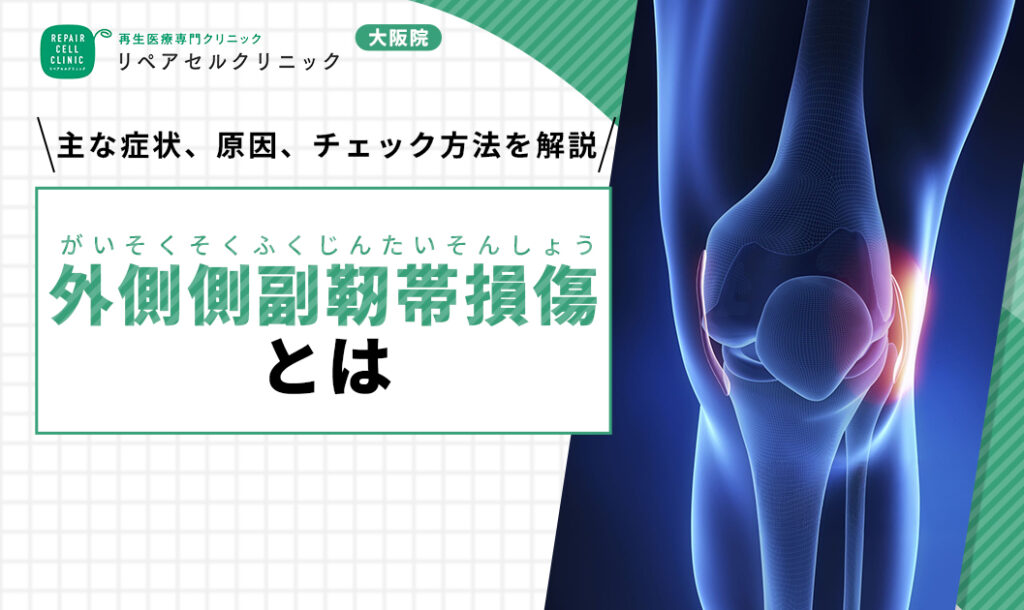
外側側副靭帯損傷とは、膝の外側にある靭帯が傷つくケガで、スポーツや転倒などで発症します。
放置すると膝の不安定感が続き、日常生活に支障をきたすことがあります。
膝の外側が痛む、腫れる、不安定な感じがするなどの症状で困っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外側側副靭帯損傷の症状や原因、セルフチェック方法について詳しく解説します。
膝の痛みや不安定感で悩まれている方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは靭帯損傷に対する治療として注目されている再生医療に関する情報を公式LINEで発信しております。
早期回復を目指したい方や手術を避けたい方は、ぜひ公式LINEをご登録いただき、再生医療についてご確認ください。
目次
外側側副靭帯損傷とは
外側側副靭帯損傷とは、膝の外側にある靭帯が伸びたり切れたりして、膝関節が不安定になるケガです。
ここでは、外側側副靭帯損傷について以下の内容を解説します。
これらの正しい知識を身につけて、適切な治療を選択しましょう。
外側側副靭帯損傷の症状
外側側副靭帯損傷では、膝の外側に特徴的な症状が現れます。
主な症状は以下の通りです。
- 膝の外側の痛み
- 膝の外側の腫れ
- 膝の不安定感
- 膝から下のしびれや感覚の異常
これらの症状が複数当てはまる場合は、外側側副靭帯損傷の可能性があります。
とくに膝下のしびれを伴う場合は、腓骨神経損傷を合併している可能性があるため、早期発見と早期治療が重要です
膝の不安定感も日常生活やスポーツに大きな支障をきたすため、痛みだけでなく違和感があれば医療機関を受診しましょう。
外側側副靭帯損傷の主な原因
外側側副靭帯損傷は、膝の外側に強い力が加わることで発症します。
主な原因は以下の通りです。
- スポーツでの接触
- 転倒や事故
- 急激な方向転換
- 膝の過度な内反
外側側副靭帯損傷は、他の膝の靭帯損傷と比べて発生頻度は低いとされています。
靭帯や半月板などの他の組織も同時に損傷するケースや、腓骨神経損傷によってしびれなどの症状が起こることもあります。
外側側副靭帯損傷の検査・診断方法
外側側副靭帯損傷の診断には、医師による徒手検査と画像検査が行われます。
医師が膝を特定の方向に動かして靭帯の状態を確認します。
代表的な検査として、膝を伸ばした状態と軽く曲げた状態で外側に力を加える「外反ストレステスト」があります。
画像検査の中でも、MRI検査が有効です。
MRIは靭帯の損傷の程度や部分的な断裂、完全断裂などを詳細に確認できます。
また、レントゲン検査では骨折の有無を確認し、超音波検査で靭帯の連続性を調べることもあります。
これらの検査を組み合わせることで、損傷の重症度を正確に判断し、適切な治療方針を決定できます。
外側側副靭帯損傷かどうかセルフチェックする方法
ご自身の症状が外側側副靭帯損傷に該当するか、以下のポイントを確認してみましょう。
- 膝の外側に痛みがある
- 膝の外側に腫れが見られる
- あぐらをかくような動作で膝が不安定に感じる
- スポーツなどでの素早い方向転換時に膝がグラつく
- 膝から下にしびれや感覚の異常がある
- 膝の外側を押すと強い痛みがある
これらの項目に複数当てはまる場合は、外側側副靭帯損傷の可能性があります。
とくに痛みや腫れ、不安定感が強い場合は、早めに整形外科を受診することをおすすめします。
ただし、上記のセルフチェックはあくまで目安であり、正確な診断には医療機関での専門的な検査が必要です。
症状が軽い場合でも、放置すると症状が悪化したり慢性化したりする可能性があるため、症状がある方は医療機関を受診しましょう。
外側側副靭帯損傷の主な治療法
外側側副靭帯損傷の主な治療法は、以下のとおりです。
損傷の程度や患者さまの活動レベルに合わせて、適切な治療法が選択されます。
保存療法
軽度から中等度の靭帯損傷では多くの場合、保存療法が第一選択となります。
保存療法は、手術を行わずに損傷した靭帯の改善、症状の緩和を目指す治療法です。
治療の初期段階では、安静にして患部を冷やし、圧迫して腫れを抑え、心臓より高い位置に足を上げます。
痛みや腫れが落ち着いたら、膝の装具やサポーターを使用し、徐々にリハビリを開始します。
リハビリは膝周りの筋力を強化し、膝の安定性を高めることを目的として行われます。
保存療法での回復期間は、損傷の程度によって異なりますが、通常6週間から3カ月程度とされています。
手術療法
手術療法は、靭帯が完全に断裂している場合や、保存療法で改善が見られない場合に検討されます。
損傷した靭帯を修復したり、必要に応じて別の組織を使って再建したりする手術が行われます。
手術後は装具を着用して膝を保護し、段階的にリハビリを進めます。
手術後のリハビリ期間は通常3〜6カ月程度で、スポーツへの完全復帰にはさらに時間がかかることがあります。
外側側副靭帯損傷の治療に注目されている再生医療
近年、外側側副靭帯損傷の治療において再生医療が注目を集めています。
従来の治療法とは異なるアプローチを行う再生医療について、以下の2つを紹介します。
新しい治療選択肢として、再生医療についての理解を深めましょう。
再生医療とは
再生医療とは、人間が持っている自然治癒力を高めることで、損傷した組織の再生・修復を促す医療技術です。
膝の靭帯損傷に対する再生医療では、患者さま自身の幹細胞を採取・培養し、損傷部位に投与します。
再生医療は手術のように大きく切開する必要がないため、身体への負担が少ない治療法です。
また、自分自身の細胞や血液を使用するため、拒絶反応やアレルギーなどのリスクが低いのも特徴です。
リペアセルクリニックの再生医療
当院「リペアセルクリニック」では、外側側副靭帯損傷に対する再生医療を提供しています。
採取した幹細胞を冷凍せずに新鮮な状態で培養できる独自の培養技術を持っている点が特徴の一つです。
幹細胞を培養した際に冷凍保存すると、治療に使うときの解凍によって活動力が低下する可能性があります。
当院では、幹細胞を冷凍せず新鮮な状態で培養し、高い活動力を持ったまま患部に投与するため、高い治療効果が期待できます。
治療後は定期的なフォローアップを行い、回復状況を確認しながら適切なリハビリを進めていきます。
具体的な治療の流れや症例について詳しく知りたい方は、当院リペアセルクリニックにお問い合わせください。
>当院の再生医療による膝関節の症例はこちら
スポーツ外傷は⼿術しなくても治療できる時代です。
外側側副靭帯損傷に関するよくある質問
外側側副靭帯損傷について、よくある質問を紹介します。
外側側副靭帯損傷への理解を深めて、治療に臨みましょう。
外側側副靭帯の痛みの原因は?
外側側副靭帯の痛みの主な原因は、スポーツや事故などによる靭帯の損傷です。
膝の内側から外側へ強い力が加わると、外側側副靭帯に過度な負担がかかります。
損傷の程度によって痛みの強さも異なり、重度の場合は歩行困難になることもあります。
外側側副靭帯はどれくらいで治る?
外側側副靭帯の回復期間は、損傷の程度によって大きく異なります。
軽度の損傷では、2週間から4週間ほどで日常生活に支障がない程度まで回復します。
中等度の損傷では、6週間から8週間程度の治療とリハビリが必要です。
重度の損傷や完全断裂の場合は、保存療法で3カ月以上、手術を行った場合は6カ月程度の回復期間が必要となります。
ただし、これらはあくまで目安です。
回復速度は年齢、損傷の程度、リハビリへの取り組み方、全身の健康状態などによって個人差があります。
外側側副靭帯損傷を早く治したい方は再生医療をご検討ください
外側側副靭帯損傷は、膝の外側にある靭帯が傷つくケガで、痛みや腫れ、不安定感などの症状が現れます。
スポーツでの接触や転倒などが主な原因で、損傷の程度に応じて保存療法や手術療法が選択されます。
セルフチェックで該当する症状がある場合は、早めに整形外科を受診して正確な診断を受けることが大切です。
適切な治療とリハビリを行えば、多くの場合で良好な回復が見込めます。
早期回復を目指したい方や手術を避けたい方には、再生医療という治療法もあります。
再生医療とは、人間が持っている自然治癒力を高めることで、損傷した組織の再生・修復を促す新しい治療法です。
外側側副靭帯損傷を早く治したい方は、当院「リペアセルクリニック」へご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設