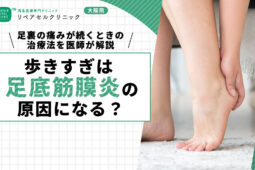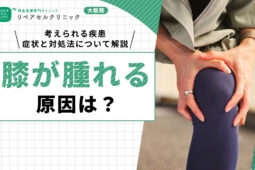- 靭帯損傷
- 足底腱膜炎
- 再生治療
後十字靭帯損傷のリハビリの「禁忌動作」とは?やってはいけない理由を解説
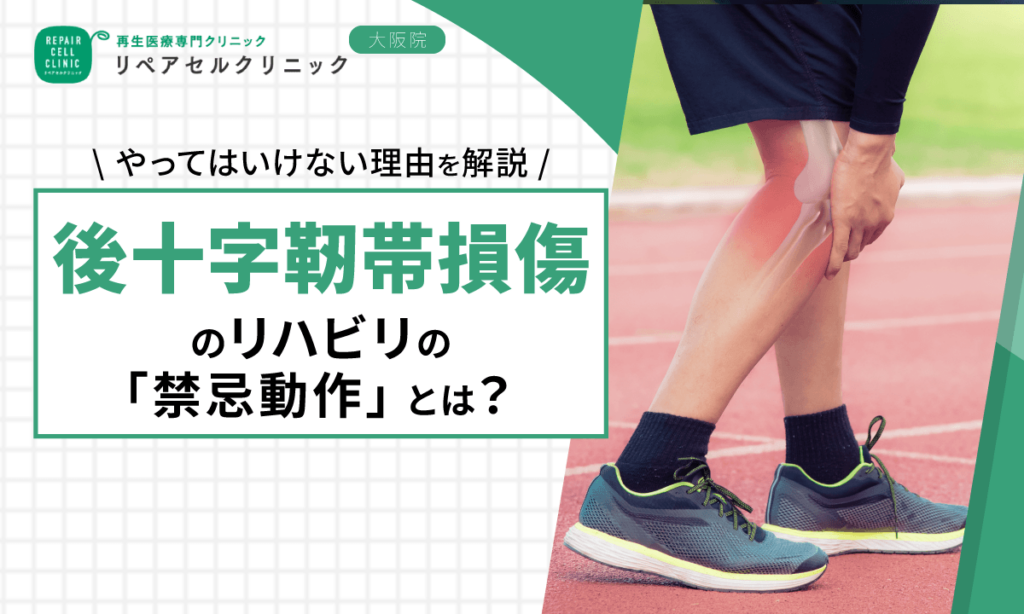
後十字靭帯損傷は、前十字靭帯損傷と比べて痛みが軽度で済むことが多く、「これくらいなら大丈夫」と軽視してしまいがちな怪我です。
しかし、この油断こそが、リハビリにおける最大の落とし穴となります。
特に、靭帯に強い負担をかける禁忌動作を破ってしまうと、回復が大幅に遅れたり、関節の不安定性が残ってしまう危険性があります。
「早く治したいのに、なぜか膝の調子が悪い…」と感じる方は、知らず知らずのうちに禁忌動作をしているかもしれません。
この記事では、後十字靭帯損傷のリハビリにおける「やってはいけない禁忌動作」とその理由を時期別に詳しく解説します。
さらに、安全に回復を進めるための具体的なステップも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
後十字靭帯損傷リハビリの禁忌動作一覧
後十字靭帯損傷後のリハビリにおける禁止動作を、時期別に解説していきます。
具体的な内容と、再生医療による新たな回復アプローチについて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
初期(0〜4週)固定・保護期に避けるべきこと
この時期は、損傷した後十字靭帯の治癒と保護を最優先とし、安静を保つことが求められます。
特に、以下の動作は靭帯に大きな負担をかけるため厳禁です。
- ハムストリングス(太もも裏)の単独収縮
- 膝の過伸展(反りすぎ)
- 深い屈曲(しゃがみ込み、正座など)
- 装具を外しての歩行・荷重
特に避けるべきは、膝関節の過度なストレスにつながる動作です。
具体的な禁忌動作として、ハムストリングス(太ももの裏の筋肉)を単独で強く収縮させる運動があります。
これは、ハムストリングスが脛骨を後方に引き、後十字靭帯に直接的な張力をかけるためです。
また、膝の過伸展(反りすぎ)や、深い屈曲(しゃがみ込みや正座など)も、靭帯への負担が大きいため厳禁です。
医師の指示する装具を外しての歩行や荷重も、靭帯の安定性を損ない治癒を妨げるため行ってはいけません。
再損傷を防ぐため、装具を正しく装着し、部分的な荷重に留める必要があります。
中期(4〜12週)可動域拡大期の注意点
徐々に関節の可動域を拡大していく期間ですが、後十字靭帯への負担を考慮し、段階的なリハビリが必要です。
特に以下の動作は禁止、または注意が必要です。
- 強いハムストリングス運動
- 後方荷重動作
- 無理なストレッチや過屈曲
強いハムストリングスの収縮を伴う運動(レッグカールなど)は、後十字靭帯に強いストレスをかけるため、禁止です。
また、階段下りや坂道歩行など、脛骨が後方にずれる力(後方荷重)がかかる動作も避けましょう。
リハビリの進行に合わせて可動域を広げる際も、無理なストレッチはせず、痛みのない範囲で慎重に行う必要があります。
自転車漕ぎをする場合も、サドルの設定に注意し、膝の過度な屈曲を避けることが重要です。
後期(3〜6か月)筋力回復期に気をつけたいこと
筋力回復とスポーツ復帰に向けた準備期間ですが、後十字靭帯の強度はまだ完全ではありません。
以下の点に、細心の注意を払いましょう。
- 高負荷・衝撃動作の制限
- 異常のサインを見逃さない
- 「痛みがない=完治」ではない
ジョギング、ジャンプ、急な方向転換といった、膝に高い衝撃やねじれを生じさせる動作は、必ず医師や理学療法士の許可が出てから段階的に行いましょう。
もしリハビリ中に膝の腫れや不安定感を感じた場合は、すぐにその動作を中止し、専門家に相談してください。
最も重要なのは、「痛みがないこと=完治」ではないという認識を持つことです。
見た目では治っていても、靭帯の強度や関節の安定性はまだ完全ではない可能性が高いです。
指定されたプログラムを最後までやり遂げることが、再損傷の予防と完全な社会復帰への鍵となります。
後十字靭帯損傷とは?見落とされがちなリハビリの落とし穴
後十字靭帯は、膝関節の中心にあり、脛骨(すねの骨)が後方にずれるのを防ぐ主要なストッパーの役割を担っています。
後十字靭帯の損傷は、スポーツ中の衝突や、膝を曲げた状態で強く地面にぶつける事故などで発生します。
前十字靭帯損傷と比べて初期の症状が軽いことが多く、見落とされがちです。
リハビリにおいて「禁忌動作」が特に重要となるのは、ハムストリングスの強い収縮や後方への荷重などが加わると、容易に再損傷したり、関節の不安定性が残存したりするためです。
この不安定感が、将来的な変形性膝関節症につながる落とし穴となります。
そのため医師の指示に基づき、後十字靭帯に負担をかけない動作を厳守し、段階的に機能回復を目指すことが不可欠です。
時期別リハビリの進め方と安全なステップ
時期別のリハビリの進め方と安全なステップは、以下の通りです。
リハビリの各段階における具体的な注意点と安全な進め方を詳しく解説します。
0〜4週:安静・四頭筋の軽い運動
リハビリ初期の目標は、患部の保護と腫れの軽減、そして膝関節を支える大腿四頭筋の機能維持です。
この時期の最適な運動は、以下の通りです。
- 安静と固定
- 大腿四頭筋の軽い収縮運動
- 歩行練習
医師の指示する装具を正しく装着して、日常生活における膝関節の安定化を図ります。
運動としては、膝を完全に伸ばした状態での大腿四頭筋の軽い収縮を積極的に行い、筋力低下を防ぎます。
歩行は理学療法士の指導のもと、部分荷重から開始します。
特に荷重制限を厳守し、杖や松葉杖を使用して後十字靭帯への負担を徹底的に避けることが、再損傷を予防し、その後の治癒過程をスムーズにするための鍵となります。
4〜8週:可動域の改善とバランス練習
この時期は、関節の拘縮を防ぎ、可動域を段階的に改善することが中心となります。
靭帯へのストレスは最小限に抑えつつ、以下のリハビリを行います。
- 可動域拡大
- プールでの歩行や軽い体重移動の練習
- 禁忌の維持
目標は屈曲60〜90度程度までの可動域拡大であり、決して無理はせず、痛みのない範囲で慎重に行います。
また、全身の協調性やバランス感覚を養うために、プールでの歩行や軽い体重移動の練習など、重力が軽減された状態での安全な負荷トレーニングを導入します。
最も重要なのは、引き続きハムストリングスの強い収縮を伴う運動を厳しく制限することです。
この筋肉は後十字靭帯に強い負担をかけるため、リハビリの進行は慎重にし、運動後に腫れや痛みが増加しないか常に確認することが不可欠です。
8〜12週:筋力強化と歩行の安定化
中期後半に入ると、筋力強化と日常生活動作の安定化に重点を移し、以下を実施する段階になります。
- 安全な筋力強化
- 日常動作の再開
- 自己管理
筋力強化ではレッグプレスなどを利用し、軽負荷かつ角度制限を設けた状態で、主に大腿四頭筋を集中的に鍛えます。
安全な筋力強化を通じて、日常生活における膝の機能的な使い方を再学習することが目標です。
同時に、階段昇降や長時間の歩行など、日常動作を段階的に再開していきます。
もし運動中やその後に膝の痛みや腫れ、不安定感を感じた場合は、すぐにその動作を中止し、専門家に相談しましょう。
完全なスポーツ復帰に向けた準備として、基礎的な安定性を着実に築き上げることが求められます。
回復を早める新たな選択肢|再生医療によるアプローチ
後十字靭帯損傷の回復を早める新たな選択肢として、再生医療が注目されています。
リペアセルクリニックでは、患者さんご自身の血液から採取するPRP(多血小板血漿)や幹細胞を損傷部位に注入し、組織の自然治癒力と修復能力を活性化させる治療法を採用しています。
手術を伴う治療法に比べて身体への負担が少なく、早期の炎症を抑え、組織の再生を促す効果が期待されています。
特に、保存療法で不安定感が残る場合や、手術を避けたい患者にとって有効な選択肢です。
リペアセルクリニック大阪院では、後十字靭帯損傷に対するPRP・幹細胞治療の豊富な症例があり、左膝の後十字靭帯を損傷した女性の痛みが軽減した症例もあります。
当院では、専門的な知見に基づき、一人ひとりの状態に合わせた最適な治療で早期回復をサポートします。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
後十字靭帯損傷のリハビリは“禁忌を守る”ことが最短の回復ルート
後十字靭帯損傷のリハビリにおいて、最も重要なのは「何をしないか」を徹底することです。
後十字靭帯損傷は治りにくく、特にハムストリングスの強い収縮や後方荷重といった禁忌動作は、再損傷や不安定性の原因となります。
そのため、時期別に禁忌を正確に理解し、焦らず段階的に進めることが最短の回復ルートとなります。
近年では再生医療をリハビリと組み合わせることで、「治りにくい靭帯を再生へ導く」という新しい治療選択肢も登場しています。
リペアセルクリニック大阪院は、この再生医療により、患者様の自然治癒力を最大化し、「もう一度、動ける膝へ」と導く支援を行っています。
手術を避けたい方や、回復を早めたい方にとって頼れる選択肢です。
気になる方は、当院のメール相談・オンライン診療にてご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設