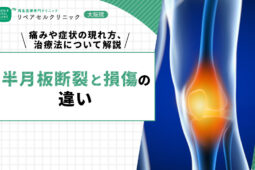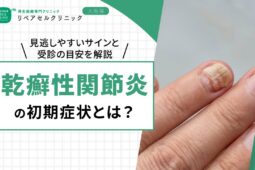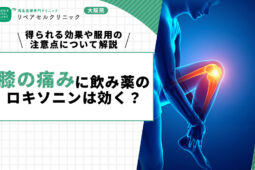- 靭帯損傷
- ひざ関節
腸脛靭帯炎(ランナー膝)に有効なストレッチ4選|ほぐし方のポイントについて解説

腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは、ランニングや繰り返しの運動により膝の外側に痛みが生じる症状で、ランニング愛好家に多く見られる怪我の一つです。
痛みを放置して無理を続けると、歩行時や日常生活でも痛みが出るようになり、運動を続けられなくなってしまう可能性があります。
この記事では、腸脛靭帯炎の症状を和らげる効果的なストレッチ方法と、症状改善のための対処法を詳しく解説します。
腸脛靭帯炎でお悩みの方は、ぜひ最後まで読んで適切な対処法を見つけましょう。
また、現在リペアセルクリニックでは手術なしで根本的な改善が期待できる再生医療に関する情報をLINEで発信しております。
膝の痛みに関する改善症例も紹介しているため、合わせてご覧ください。
目次
腸脛靭帯炎(ランナー膝)とは|基礎知識をチェック
腸脛靭帯炎は、別名「ランナー膝」と呼ばれるほど、ランニング愛好家に多く見られる怪我です。
適切な対処のためには、以下の症状や原因を正しく理解することが大切です。
これらの正しい知識を身につけて、ご自身の症状を確認してみましょう。
腸脛靭帯炎の症状
腸脛靭帯炎の初期症状は、運動後に膝の外側に生じる痛みです。
痛みは安静にすれば徐々に収まりますが、炎症がひどい場合や無理に運動を続けた場合、歩いたり膝を曲げ伸ばししただけでも痛みが出ることがあります。
久しぶりにランニングやジョギング、ウォーキングを行うときによくみられる症状です。
腸脛靭帯炎の原因
腸脛靭帯炎は、膝の外側にある腸脛靭帯が太ももの骨と擦れることで炎症を起こします。
発症の主な原因は、ランニングやサイクリングなどの反復的な運動、もしくは運動に対する筋力不足です。
ただし以下の要因でも発症する可能性があります。
- O脚、扁平足などのアライメント異常
- 股関節周囲の筋力や柔軟性の低下
腸脛靭帯炎はランナーの方に多い疾患ですが、自転車、バスケットボール、階段の昇降など、膝の屈伸を繰り返す動作を行う方にも発症します。
腸脛靭帯炎の診断方法
腸脛靭帯炎は、問診や触診である程度診断できますが、炎症の状態や他の疾患と見分けるために、レントゲンやMRI、エコー検査を行うこともあります。
また、腸脛靭帯炎かどうかチェックする方法として「グラスピングテスト」があるので、ぜひお試しください。
- 膝を90度ほど曲げる
- 膝の外側上部2〜3cm上を親指で圧迫する
- その状態で膝をゆっくり伸ばしていく
- 痛みが出れば、腸脛靭帯炎が疑われる
ただし、痛みの原因が半月板損傷など他の疾患の可能性もあるため、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
腸脛靭帯炎に有効なストレッチ・ほぐし方4選
腸脛靭帯炎の痛みが落ち着いたら、徐々にストレッチを開始します。
ここでは、腸脛靭帯と関連する筋肉をほぐす効果的なストレッチとして以下の4つをご紹介します。
各ストレッチは無理をせず、痛くなりすぎない範囲で行いましょう。
①フォワードフォールド・ストレッチ(前屈)
太ももの外側から膝の外側まで、脚の外側全体を伸ばすストレッチです。
- 直立した状態から、左足を右足の後ろに引いて交差させる
- 腰を曲げて手を床につき、左わき腹をよく伸ばす
- その体勢を2〜3秒キープしたら、元の姿勢に戻る
- 左右それぞれ10〜15回ずつ繰り返す
運動後に行う場合は、膝から股関節まで脚の外側全体が伸びるように意識しながら、手を下に伸ばした状態で30秒ほどキープしましょう。
②ラテラルストレッチ
太ももの上部から股関節にかけての腸脛靭帯を伸ばすストレッチです。
- 壁または椅子に片手をつき、身体を安定させる
- 壁側の足を後方に引いて、反対の足と交差させる
- その状態で壁に対して腰を近づけ、壁側の腰の部分を伸ばす
- 再び元の姿勢に戻り、同じ動作を繰り返す
壁や椅子でしっかり身体を支えながら、股関節周辺を伸ばしてください。
③4の字ストレッチ
太ももの上部から股関節にかけての張りを和らげる、仰向けの姿勢で行うストレッチです。
- 腰幅より少し両足を開き、仰向けに寝て、両膝を立てる
- 右足首を左膝の上に乗せ、「4の字」の形を作る
- 上げた足の力でもう片足の膝を床に向けて押し下げていく
- 元の姿勢へと戻る
身体が傾かないよう逆側の手で床を支えながら、じっくりと伸ばしましょう。
④タオルやヨガストラップを活用したストレッチ
タオルまたはヨガ用ストラップを使って行うストレッチは、足を伸ばし切った状態で腸脛靭帯に効果的にストレッチをかけられます。
タオルを使用する場合は、ねじって紐状にして使いましょう。
- 床に座った体勢で、タオルまたはヨガストラップを片足に巻く
- そのまま仰向けになり、タオルを巻いた方の足を天井に向け、できるだけまっすぐに伸ばす
- もう片方の足のかかとが、しっかりと床についていることを確認する
- 突き上げた足を身体の反対側に向けて伸ばす
身体が傾かないように、伸ばした足とは逆の手で床をしっかり支えましょう。
日常的にランニングをしている方は、ぜひ取り入れてみてください。
腸脛靭帯炎の症状に対してストレッチ以外にできる対処法
腸脛靭帯炎の症状を改善するためには、ストレッチだけでなくさまざまな対処法を組み合わせることが効果的です。
ここでは、以下の日常生活で実践できる3つの対処法をご紹介します。
これらの対処法を適切に組み合わせることで、症状の改善と再発予防につながります。
マッサージなどのセルフケア
腸脛靭帯炎の症状を緩和するためには、大腿筋膜張筋や腸脛靭帯自体のマッサージが有効です。
大腿筋膜張筋のセルフマッサージを以下の手順で実施しましょう。
- 座った状態で、太ももの外側上部(股関節の横)を探す
- 親指または手のひらで、円を描くように優しくマッサージする
- 硬い部分や圧痛点があれば、30秒程度軽く圧迫する
ただし、発症直後の急性期に自己判断でマッサージをすると逆効果になることもあるため、安静が優先されます。
患部をアイシング、または湿布を貼って、患部に負担をかけないように安静に保ちましょう。
テーピングやサポーターの活用
テーピングやサポーターを活用することで、膝への負担を軽減し、症状の悪化を防げます。
テーピングやサポーターは、腸脛靭帯にかかる摩擦を減らし、膝の安定性を高める効果が期待できます。
テーピングが難しい場合は、手軽に装着できるサポーターがおすすめです。
ご自身の症状や活動レベルに合わせて、適切なものを選びましょう。
シューズの見直し
シューズが足に合っていない場合、膝への負担が増加し、腸脛靭帯炎を引き起こす原因となります。
以下のポイントを確認して、シューズの見直しを検討しましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| サイズ | つま先に適度な余裕があり、かかとがしっかり固定されているか |
| クッション性 | 衝撃を十分に吸収できる適切なクッション性があるか |
| 摩耗状態 | 靴底がすり減っていたり、変形していないか |
| 足の形状 | 扁平足やO脚など、ご自身の足の特徴に合っているか |
シューズの見直しは、腸脛靭帯炎の予防と改善に大きく役立ちます。
腸脛靭帯炎がストレッチで改善しないときは再生医療をご検討ください
腸脛靭帯炎は、適切なストレッチやセルフケアにより症状の緩和を目指せます。
しかし、長期間に渡って症状が続く場合や、保存療法で十分な効果が得られない場合は、他の治療法を検討する必要があります。
ストレッチや保存療法を続けても症状が改善しない場合には、再生医療による治療も選択肢の一つです。
再生医療は患者さまの細胞や血液を用いて、損傷した組織の修復・再生を促す医療技術です。
症状が長引いている方や、より積極的な治療を希望される方は、再生医療を専門とする当院「リペアセルクリニック」にご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設