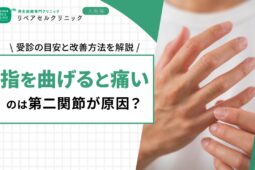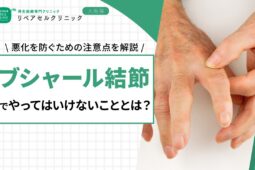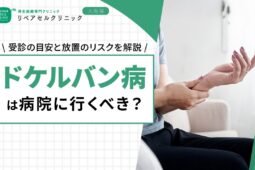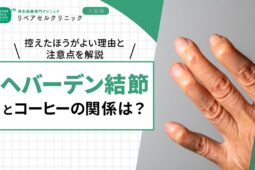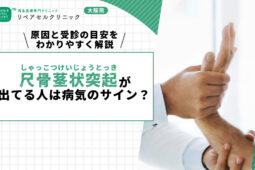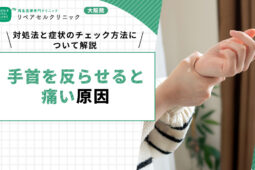- 手
- 再生治療
手根管症候群で「やってはいけない事」とは?悪化を防ぐための正しい対処法を紹介
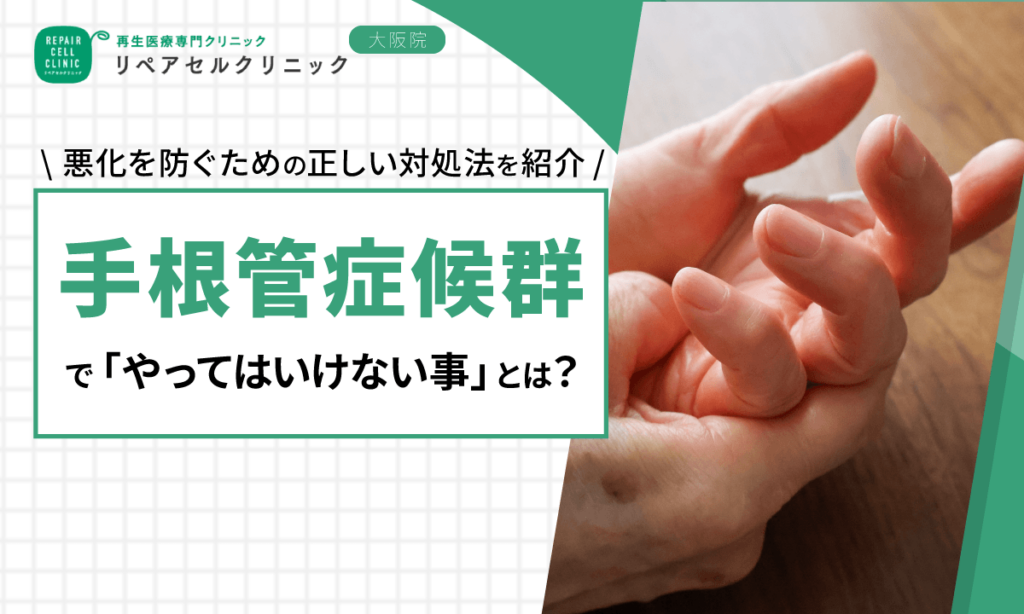
手根管症候群は、指のしびれや痛み、特に夜間の激しい症状によって日常生活に大きな影響を及ぼします。
そのつらい症状を悪化させないためには、「やってはいけない事」を正しく理解し、日常生活から手首への負担を減らすことが何よりも重要です。
この記事では、手根管症候群の症状を進行させてしまう「やってはいけない事」一覧と、それを防ぐための正しいセルフケア方法を詳しく解説します。
さらに、セルフケアで改善しない場合に検討すべき、手術に頼らない再生医療という新しい治療の選択肢についても紹介しています。
手根管症候群を根本から改善し、再発を防ぐための正しい知識と対処法を知り、快適な生活を取り戻しましょう。
目次
手根管症候群で「やってはいけない事」一覧
手根管症候群でやってはいけない事は、以下の通りです。
上記を繰り返すことで症状が悪化し、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
手首を深く曲げたままの長時間作業
手根管症候群の症状がある場合、手首を深く曲げた状態での長時間の作業は避けましょう。
手首を曲げた状態が長く続くと、手根管内の正中神経への圧迫が強まり、しびれや痛みが悪化する原因となります。
特に、キーボード操作や細かい手作業などで手首が極端に曲がってしまう姿勢に注意が必要です。
作業中は手首をできるだけまっすぐな状態に保ち、適度に休憩を取り、ストレッチを行いましょう。
無理な姿勢を避け、手首への負担を軽減する工夫をしてください。
強く握る・重い物を持つ動作を繰り返す
物を強く握り続けたり、重い物を繰り返し持ち上げたりする動作は、手根管内の圧力を高め、症状を悪化させる一因となります。
こうした動作は、手や手首周りの筋肉に過度な緊張を生じさせ、正中神経への刺激を強めてしまいます。
買い物袋や工具などを長時間強く握る必要がある場合は、可能な限り力を抜いて作業するか、補助具の使用を検討してください。
また重い物を運ぶ際は、腕全体を使うように意識し、手首への集中した負担を減らすように心がけましょう。
寝るときに手首を曲げる姿勢
就寝中に手首を極端に曲げたまま寝てしまう姿勢は、手根管症候群の夜間の症状、特につらい「しびれ」や「痛み」を引き起こす大きな要因です。
寝ている間は意識的に姿勢をコントロールできないため、手首が曲がった状態で長時間固定され、神経への圧迫が強くなります。
これを防ぐためには、手首をまっすぐな状態に保つための装具(サポーターやスプリント)を装着して就寝することが非常に有効です。
また横向きで寝る際に、手首が枕の下などに入り込まないように注意しましょう。
長時間スマホやパソコンを続ける
長時間にわたってスマートフォンやパソコンの操作を続けることは、手根管症候群の症状を悪化させる可能性が高いです。
特にスマホ操作では、指や手首に負担のかかる姿勢になりやすく、またパソコンでのタイピングやマウス操作でも、手首が不自然に曲がった状態や、指先に力が入りすぎた状態が続きがちです。
スマホやパソコンは連続使用を避け、30分に一度など時間を決めて休憩を取り、手首や指を休ませるストレッチを行いましょう。
痛みを我慢して作業を続ける
手根管症候群による手や指の痛みやしびれを感じながらも、我慢して作業を続けることは、症状を慢性化・重症化させる最も危険な行為の一つです。
痛みは体が発する「休息が必要」というサインです。
このサインを無視して負荷をかけ続けると、炎症がさらに悪化し、正中神経へのダメージが深刻化する可能性があります。
少しでも症状を感じたら、すぐに作業を中断し、手首を休ませてください。
痛みが続く場合は、自己判断せずに整形外科などの専門医に相談し、適切な治療や生活指導を受けましょう。
手根管症候群とは?原因とメカニズムを簡単に理解
手根管症候群は、手首の付け根にある手根管というトンネルの中を通っている正中神経が圧迫されて起こる病気です。
この神経が圧迫される主な原因は、以下の通りです。
- 反復動作
- ホルモンの変化
- 病気や怪我
パソコン作業や家事、育児(抱っこ)、スマートフォンの操作など、手首を酷使したり、指を頻繁に動かしたりする反復動作を長時間・継続的に行うことで、手根管内の腱が炎症を起こし、むくんで神経を圧迫します。
また、特に妊娠・出産期や更年期の女性に多く見られるように、ホルモン変化に伴う体のむくみや腫れも、手根管内の圧力を高める要因の一つです。
さらに、糖尿病や関節リウマチといった基礎疾患、あるいは手首の骨折やねんざによる変形なども、手根管内の容積を狭めたり、滑膜炎を引き起こしたりして、発症のリスクを高めます。
これらの要因が複合的に作用し、正中神経が圧迫されることで、指のしびれや痛みといった症状が現れます。
手根管症候群の悪化を防ぐセルフケア
手根管症候群の悪化を防ぐセルフケアは、以下の通りです。
日々のちょっとした工夫を取り入れることで悪化を防ぎ、再発のリスクも低くなります。
姿勢と環境の見直し
手根管症候群の悪化を防ぐには、日常生活における手首への負担を最小限に抑えることが必要です。
パソコンでタイピングを行う際は、手首の曲がりを防ぎ、手のひらを支えるためにパームレストを積極的に使用しましょう。
また、スマートフォンを使用する際は、片手で無理な姿勢を取るのではなく、両手で持つようにしたり、スマホスタンドを活用したりして、手首や指への局所的な負担を軽減してください。
さらに、家事を行う際には、手首の負担が少ない軽量器具や電動アイテムに置き換えるなど、作業環境を工夫することが症状の進行を防ぐ鍵となります。
就寝時の工夫
手根管症候群の症状は、就寝中に悪化することが多いため、夜間の手首の姿勢を管理することが重要です。
寝ている間に手首が曲がってしまうのを防ぐため、手首をまっすぐ保つようにタオルを軽く巻いたり、サポーターを使用したりして固定しましょう。
これにより、手根管内での神経圧迫を和らげ、夜間のしびれや痛みの発生を抑える効果が期待できます。
また、うつ伏せ寝や、枕の下などに手や手首を入れ込んでしまう姿勢は、手首を極端に曲げたり、体重で圧迫したりすることになるため、極力避けましょう。
手首に負担をかけずに自然な姿勢で休むことが、症状の改善につながります。
セルフケアで改善しない場合は早期受診が重要
手根管症候群の初期段階では、生活習慣の改善やセルフケアによって症状が軽減することがあります。
しかし、症状が持続したり悪化したりする場合は、放置せずに早期に整形外科などの専門医を受診しましょう。
進行すると、手術が必要になる場合や、神経の回復が難しくなるリスクがあるためです。
特に以下のようなサインが見られたら、速やかに医療機関を受診することを検討してください。
- しびれや痛みが数週間続いている
- 親指の付け根の筋肉が痩せている
- 夜の痛みやしびれで眠れない日が続いている
上記のサインは症状の進行を示しており、医師による正確な診断と、装具療法や薬物療法、あるいは手術といった適切な治療が必要となります。
早期の受診が回復を早め、症状の固定化を防ぐ鍵となります。
手術に頼らない新しい選択肢|再生医療というアプローチ
手根管症候群の治療において、症状が重度の場合や保存療法で改善が見られない場合、従来は手術が選択されてきました。
しかし、近年では、体への負担が少ない再生医療という新たなアプローチが登場しています。
リペアセルクリニックでは、手根管症候群に対して、患者様ご自身の細胞を活用した再生医療を提供しています。
この治療法は、患者様自身の脂肪組織などから採取した幹細胞を患部に注入することで、損傷した正中神経の炎症を抑え、本来持つ神経組織の修復や再生を促すことを目指します。
リペアセルクリニック大阪院では、左変形性手関節症に悩む患者様に幹細胞治療を行い、症状を軽減させた実績があります。
手術をしない新しい治療「再生医療」を提供しております。
手根管症候群はやってはいけない事と正しい治療選びで再発を防げる
手根管症候群のつらい症状から解放され、再発を防ぐためには、悪化させる原因を排除し、適切な治療を選ぶことが重要です。
まず日常生活で、手首を深く曲げたままの長時間作業や、重い物を持つ動作などを避け、手首への過度な負担を軽減することが基本となります。
それに加えて、一時的な症状緩和に留まらず、損傷した神経の修復・再生を促す再生医療などの根本改善を目指す治療を選択することで、再発の可能性を低く抑えることが可能になります。
慢性的なしびれや痛みに悩んでいる方は、リペアセルクリニックのメール相談・オンライン診療にてご相談ください。

監修者
坂本 貞範
Sadanori Sakamoto
医療法人美喜有会 理事長
「できなくなったことを、再びできるように。」
人生100年時代、皆様がより楽しく毎日を過ごせることの
お手伝いができれば幸甚の至りでございます。
略歴
1997年3月関西医科大学 医学部卒
1997年4月医師免許取得
1997年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)医学部附属病院 勤務
1998年5月大阪社会医療センター附属病院 勤務
1998年9月大阪府立中河内救命救急センター 勤務
1999年2月国立大阪南病院 勤務
2000年3月野上病院 勤務
2003年3月大野記念病院 勤務
2005年5月さかもとクリニック 開設
2006年12月医療法人美喜有会設立 理事長就任
2019年9月リペアセルクリニック大阪院 開設
2021年5月リペアセルクリニック東京院 開設
2023年12月リペアセルクリニック札幌院 開設