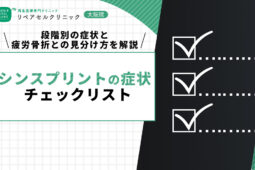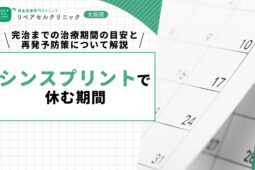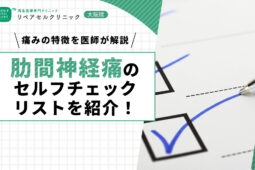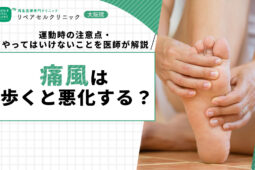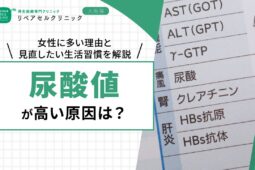- その他
関西だしと関東だしの塩分量の違いは?過剰摂取による健康リスクも解説
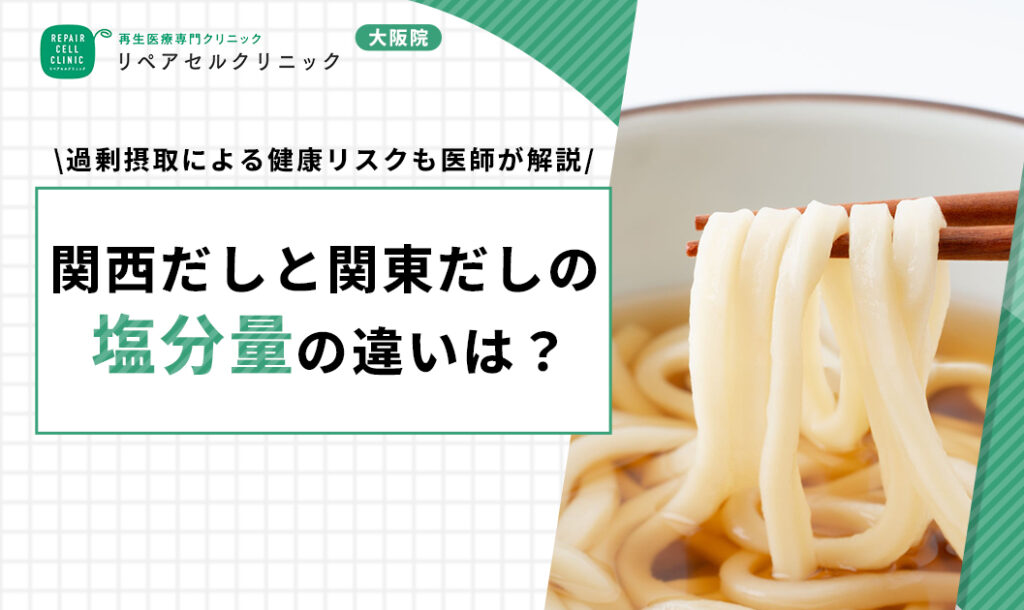
健康のために減塩を心がけている方にとって、日々の調理で使うだしの塩分量は気になるポイントです。
関西だしと関東だしは色や味付けが異なりますが、実際の塩分量の違いについて理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、関西だしと関東だしの塩分濃度の違いと、塩分の摂りすぎによる健康リスク、無理なく減塩する方法を解説します。
日々の食事で塩分が気になっている方は、ぜひ最後まで読んで適切な減塩方法を見つけましょう。
目次
関西だしと関東だしの塩分濃度はどちらが高い?違いも紹介
関西だしと関東だしの塩分濃度について、多くの方が誤解しています。
色の違いから塩分量も大きく異なると思われがちですが、実際の塩分量は使用する調味料全体のバランスによって決まります。
そのため、関西だし・関東だしのどちらの塩分濃度が高いとは、一概には言えません。
関西だしと関東だしの違いは以下のとおりです。
| 関西だし | 関東だし | |
|---|---|---|
| 使用する醤油 | 色の薄い薄口醤油 | 色の濃い濃口醤油 |
| だしの種類 | 昆布だしを効かせることが多い | かつおだしと組み合わせることが多い |
| 調理の特徴 | 素材の味を大切にする調理法が特徴 | 濃い色と強い味付けが好まれる傾向 |
| 特徴 |
|
|
減塩を意識するなら、醤油の種類だけでなく、調味料全体の使用量に注目しましょう。
塩分の摂りすぎで起こる健康リスク
食塩の摂りすぎは、高血圧をはじめとした以下の生活習慣病に深く関わってきます。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」※では、成人男性は9g未満、女性は7.5g未満が一日あたりの食塩摂取目標量です。
※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
しかし、多くの日本人が目標値よりも多く食塩を摂取している現状があります。
これらの正しい知識を身につけて、健康維持のための適切な食生活を心がけましょう。
高血圧・心血管疾患(脳卒中、心筋梗塞など)
血液中の塩分濃度が高くなると、体は水分を保持して濃度を薄めようとするため、血液量が増えて血管に強い圧力がかかり、高血圧になります。
- 塩分過多により血液量が増加
- 血管への圧力が高まり高血圧に
- 動脈硬化から脳卒中・心筋梗塞のリスク増大
高血圧で治療している人は、一日6g未満の食塩摂取がすすめられています。
腎臓病
長期間にわたって塩分を摂りすぎると腎臓に大きな負担がかかり、腎臓の機能が低下します。
- 塩分過多で腎臓に負担
- 機能低下により老廃物が体内に蓄積
- 重症化すると人工透析が必要に
腎臓は一度機能が低下すると回復が難しい臓器です。
日頃から塩分を控えめにして、腎臓の負担を減らしましょう。
胃がん
塩分の多い食事で胃の粘膜が繰り返し傷つくと炎症が慢性化し、胃がんの発生リスクを高める要因となります。
- 塩分で胃の粘膜が傷つく
- 慢性炎症から胃がんのリスク増大
- 漬物・塩蔵品の摂りすぎに注意
減塩と合わせて野菜や果物を多く摂ることで、胃の健康を守れます。
骨粗鬆症
塩分を摂りすぎると、尿と一緒にカルシウムも排出されてしまい、骨粗鬆症の要因になります。
- 塩分過多でカルシウムが尿と一緒に排出
- 骨密度が低下し骨粗鬆症のリスク増大
- 高齢者・閉経後の女性はとくに注意
カルシウムを含む食品を積極的に摂りながら、減塩を心がけることで骨の健康を維持できます。
健康維持のために無理なく減塩する方法
減塩は健康維持に欠かせませんが、急に味付けを変えると食事が楽しめなくなってしまいます。
無理なく減塩するには段階的に薄味に慣れていくことがポイントです。
以下の方法を実践して、おいしく無理なく減塩を続けましょう。
| 方法 | 具体的な実践内容 |
|---|---|
| だしや香辛料を活かす | 昆布やかつお節でしっかりだしを取り、生姜・にんにく・七味唐辛子などの香辛料や、レモン・酢などの酸味を活用する |
| 少しずつ薄味に慣れる | 醤油を小皿に少量取り分ける、味噌汁の味噌を少し減らすなど、2週間ほど続けると味覚が変化する |
| 野菜や果物を多く摂る | カリウムを含む海藻類・イモ類・果物を摂取し、体内の余分な塩分排出を助ける(男性3,000mg以上、女性2,600mg以上が目安) |
| 副菜をしっかり食べる | 野菜の煮物・おひたし・サラダなどで品数を増やし、各料理の塩分を控えめにしても満足感を得る |
| 市販食品のチェック | 栄養成分表示の食塩相当量を確認し、減塩タイプの商品を選ぶ(おでん約3.8g、かけうどん約5.6gの塩分) |
これらの工夫を組み合わせることで、塩分を控えながらおいしい食事を楽しめます。
塩分過多による病気は、進行すると薬や生活改善だけでは難しい
塩分の摂りすぎは、高血圧や腎臓病、心血管疾患、胃がん、骨粗鬆症などの生活習慣病のリスクを高めます。
これらの病気を予防するためには、日々の食事で塩分量に気を配ることが大切です。
だしや香辛料を活かす、段階的に薄味に慣れる、野菜や果物を積極的に摂るなど、無理なく減塩する方法を実践しましょう。
ただし、生活習慣病が進行してしまった場合、薬や食事療法だけでは改善が難しいケースもあります。
そのような場合には、再生医療も治療選択肢の一つとして考えられます。
再生医療とは、体内のさまざまな細胞に変化できる「幹細胞」を用いる治療法です。
当院「リペアセルクリニック」では、再生医療に関する情報をLINEで発信しているので、ぜひご確認ください。

監修者
岩井 俊賢
Toshinobu Iwai
医師